タイムトラベル物だと思っていたのに
突然に半陽陰の女性の半生が始まり
「間違えた?」と軽くパニック。
途中から時空を飛び始め、話が繋がって来て、
なるほどな!と。
勘の良い人ならすぐにわかると思うけど
鈍い私はラストで唸りました。
過酷過ぎる運命だわ。
タイムトラベルの機械が発明されたのが1981年ということは、
元ネタはかなり昔に書かれたんだろうな。
彼女の「身体」も現代なら
もう少し選択肢があるんだろうけど、
世の中に男性と女性しかおらず、
男は男らしくなければならない時代には、
あれしか方法が無かったんだろうな。
だからこそ、ああなるんだな。
SFとしてだけでなく、
ジェーンの孤独さが強く伝わってくるので
ラブストーリー部分も美しい。
彼女の幸せを願わう方へ誘導されので
いろんな事情を知った時、
見ている方はジョンと同じ気持ちになる、
そういう「作り方」が上手いですね。
穴だらけの話なので人にはすすめないけど、
見て良かったです。
穴だらけ、というと語弊があるね。
現代では女性の宇宙飛行士が普通にいるし、
タイムパラドックスを発生させない基準も
なんとなくできちゃっている現代から見ると、
なんで?と思う部分があるんだよね。
見た後に調べたら、原作はハインラインの59年の作品なのね。
だからタイムパラドックスがあそこまで哲学的なんだ。
パラドックスが続くことに意義がある。
まさしく輪廻だったよ。
古典SFに馴染みがあれば楽しめると思います。
サラ・スヌークの演技が実に素晴らしかったです。
突然に半陽陰の女性の半生が始まり
「間違えた?」と軽くパニック。
途中から時空を飛び始め、話が繋がって来て、
なるほどな!と。
勘の良い人ならすぐにわかると思うけど
鈍い私はラストで唸りました。
過酷過ぎる運命だわ。
タイムトラベルの機械が発明されたのが1981年ということは、
元ネタはかなり昔に書かれたんだろうな。
彼女の「身体」も現代なら
もう少し選択肢があるんだろうけど、
世の中に男性と女性しかおらず、
男は男らしくなければならない時代には、
あれしか方法が無かったんだろうな。
だからこそ、ああなるんだな。
SFとしてだけでなく、
ジェーンの孤独さが強く伝わってくるので
ラブストーリー部分も美しい。
彼女の幸せを願わう方へ誘導されので
いろんな事情を知った時、
見ている方はジョンと同じ気持ちになる、
そういう「作り方」が上手いですね。
穴だらけの話なので人にはすすめないけど、
見て良かったです。
穴だらけ、というと語弊があるね。
現代では女性の宇宙飛行士が普通にいるし、
タイムパラドックスを発生させない基準も
なんとなくできちゃっている現代から見ると、
なんで?と思う部分があるんだよね。
見た後に調べたら、原作はハインラインの59年の作品なのね。
だからタイムパラドックスがあそこまで哲学的なんだ。
パラドックスが続くことに意義がある。
まさしく輪廻だったよ。
古典SFに馴染みがあれば楽しめると思います。
サラ・スヌークの演技が実に素晴らしかったです。

























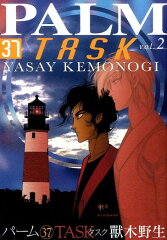

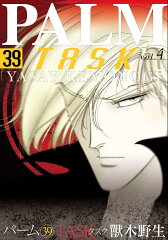
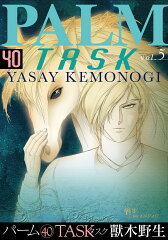
![Wings (ウィングス) 2013年 06月号 特別付録 永久保存版小冊子「プチ・パームブック」[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61in8ViynvL._SL160_.jpg)


