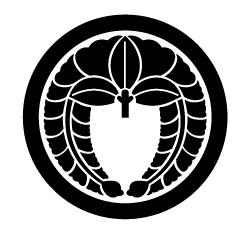今日は大晦日。なにをして過ごしますか?大掃除?紅白歌合戦それともダウンタウンの大晦日SP?
大晦日こそ先祖供養納め日です。
一年間のご先祖の加護に感謝しましょう。
先祖供養は自分の遺伝子のビタミン剤です。
ビタミン不足で直ぐ身体が弱体化することはありませんが、慢性的に不足するとやがて病気になってしまいます。
今の日本は、病気の状態かどうかはわかりませんが、高度経済成長期と比較すると、だいぶ精神的には弱ってきていると思います。いくら小手先でやろうとしても勢いが有りません。
ある学者が、日本の弱体化は学校で道徳を教えなくなってから、家庭で先祖供養しなくなってから・・・と言っていました。
全くやってないわけではないでしょうが、だいぶ薄れてきています。一理あるなと思いました。
日本が元気だった高度経済成長期は偶然に来たのではなく、日本人の頑張りの蓄積です。
その頑張りの根っこに有ったのが、道徳と先祖供養ではないかと思います。
この二つが無い人は根っこの無い人。遺伝子の元気が無くなってしまいます。
家系も元気が失せてきます。結婚運や子宝運が無いとか・・・。
家系も元気が無いとすれば、先祖供養というビタミン剤が足らないのです。
日本家系調査会
大晦日こそ先祖供養納め日です。
一年間のご先祖の加護に感謝しましょう。
先祖供養は自分の遺伝子のビタミン剤です。
ビタミン不足で直ぐ身体が弱体化することはありませんが、慢性的に不足するとやがて病気になってしまいます。
今の日本は、病気の状態かどうかはわかりませんが、高度経済成長期と比較すると、だいぶ精神的には弱ってきていると思います。いくら小手先でやろうとしても勢いが有りません。
ある学者が、日本の弱体化は学校で道徳を教えなくなってから、家庭で先祖供養しなくなってから・・・と言っていました。
全くやってないわけではないでしょうが、だいぶ薄れてきています。一理あるなと思いました。
日本が元気だった高度経済成長期は偶然に来たのではなく、日本人の頑張りの蓄積です。
その頑張りの根っこに有ったのが、道徳と先祖供養ではないかと思います。
この二つが無い人は根っこの無い人。遺伝子の元気が無くなってしまいます。
家系も元気が失せてきます。結婚運や子宝運が無いとか・・・。
家系も元気が無いとすれば、先祖供養というビタミン剤が足らないのです。
日本家系調査会