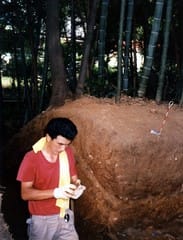(東京都台東区上野)
昭和5年(1930)東京教育博物館から東京科学博物館に改称するのを機に建造された、RC造地上3階(一部4階)地下1階、延床面積7,500�の建物である。
ネオルネッサンス様式を基調とし、飛行機の形状を取り入れた建物は、芸術と科学を併せ持った特徴を持つ。
長く国立科学博物館本館として使用されてきたが、老朽化が進んだことと、展示方式に改善の必要性があったこと等から、2004年の新館(地球館)の完成を待って改修工事を開始し、2007年完了、「日本館」となった。







(関連記事:東京上野2007)