今日の衆議院予算委員会で松野頼久議員の質問の中にとても心配な話があった。質問の大意は、熊本地震の被災に対する政府の支援の姿勢を問うものだったが、その中で松野議員は新町の坪井川に架かる明八橋を例にあげ、個人所有の歴史的建造物についても、歴史的景観を守るという観点から、その補修に政府の支援をお願いしたいという趣旨だったと思う。震災発生以降、新町方面へ行っていないので、被災状況はわからないが、議員の質問から推察するとおそらく個人では補修できないほどの被災状況なのだろう。同じ新町では、吉田松花堂も危ないという話も聞くし、ランドマークともいうべき建造物が消えてしまうのは忍びない。なんとか次の世代まで残してほしいものだ。
▼東京の「日本橋」や皇居の「二重橋」を架設した明治時代の名石工・橋本勘五郎が、熊本へ帰郷後、明治8年に架設した石橋

▼東京の「日本橋」や皇居の「二重橋」を架設した明治時代の名石工・橋本勘五郎が、熊本へ帰郷後、明治8年に架設した石橋












 漱石の「草枕」の十二に次のような一節がある。
漱石の「草枕」の十二に次のような一節がある。







 世界的なシンセサイザー奏者で作曲家の冨田勲さんが、5日、亡くなった。
世界的なシンセサイザー奏者で作曲家の冨田勲さんが、5日、亡くなった。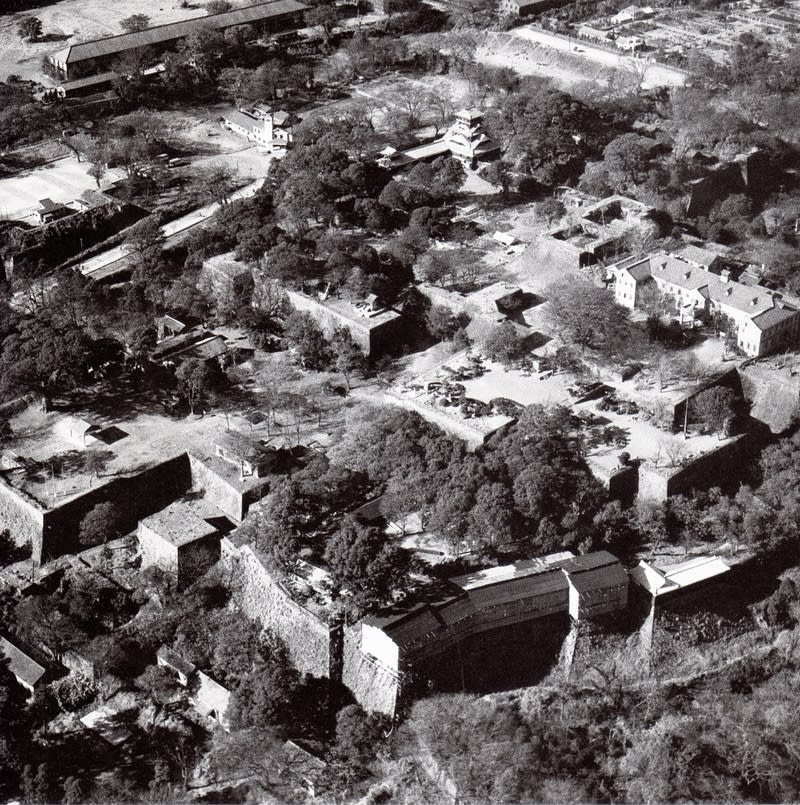

 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が熊本にいた頃、地震に遭ったことがある。日清戦争の戦時下で、八雲が熊本で2番目の坪井西堀端35番地の家に住んでいた明治27年8月のことである。地震の頻発に庭で夜を明かしたことを友人宛の書簡で述べている。この家は現存しないが、数年前までこの家のすぐ近くにあった地蔵堂が残っていた。しかし、今はこれも撤去され、八雲を偲ぶものは何もない。熊本市立図書館「図書館講座・郷土史」資料には次のように書かれている。
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が熊本にいた頃、地震に遭ったことがある。日清戦争の戦時下で、八雲が熊本で2番目の坪井西堀端35番地の家に住んでいた明治27年8月のことである。地震の頻発に庭で夜を明かしたことを友人宛の書簡で述べている。この家は現存しないが、数年前までこの家のすぐ近くにあった地蔵堂が残っていた。しかし、今はこれも撤去され、八雲を偲ぶものは何もない。熊本市立図書館「図書館講座・郷土史」資料には次のように書かれている。








