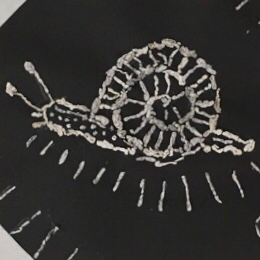前回に続き、鶴見川源流を求めて、谷戸の森を彷徨っています。。。🐌

野中谷戸の径路(地図①〜④)を、南多摩尾根幹線道路の唐木田配水所がある鶴見川流域最高点まで登ってきたのが前回のはなし。。
そして、今回は展望台のある給水塔から、森へと再び降りて、田中谷戸周辺の源流探しに向かってみたいと思います。

因みにこちらは150年ほど前の江戸から明治へと移った頃の周辺地図ですが、上の地理院地図と比べてみても、今回歩いた2つの谷戸群周辺の等高線だけが、ほとんど変わっていないのは、びっくりですよね。。
それだけで、この鶴見川源流の森を守り続ける方々のチカラの強さが窺えるような気がしました。

給水塔から急な斜面を降りて、再び谷戸を目指します。

ここは源流の森の奥の奥。。
クヌギもかなりの貫禄があります。
頭上からはキレイな野鳥の声が聞こえていますが、モノマネ上手なガビチョウでしょうっ。

少し登り返して、平坦な場所に出ました。(地図⑤)
どうやら2つの谷戸群に挟まれた尾根に乗ったようです。
またここは鶴見川源流の分水界にも当たる場所。
歩きやすさからも、ずっと昔からの里道だったりするのかもしれません。

しばらく、下草に覆われた作業道を行くと、暗い植林の森の先には再び案内板が見えてきました。(地図⑥)

ここが田中谷戸。。。
なんだか先程の野中谷戸とは様相、、いや林相がずいぶん違うようですが、この谷戸から奥へは草木に阻まれているため、谷を詰めることは無理なようです。

周囲は、じめじめとした湿地帯ですが、下手に踏み込む気にはなれないような雰囲気がここにはあります。

ついつい足早に下りてきてしまいましたが💧、その先の畑のある場所から、田中谷戸を振り返ってみます(地図⑦)

山から里におりてきました。(地図⑧)

麓の道路脇の鶴見川源流の泉(地図⑨)とその広場を通りかかります👀
親切な説明板も、年月のせいで判読がしにくくなっていますが、どうやら、この池は谷戸から流れ落ちて溜まったものでも、まったくの天然の湧き水でもなさそうな気がしました。
ま、都会の暗渠もそうだが、この川も見た目よりは、なんだかいろいろな事情がありそうです。。

せっかくなので、泉の広場の脇道を上がった谷戸の湧水で出来た小さな池まで足を伸ばしてみました。
この溜池は畑で利用しているようですね(地図⑩)

そんな小径で「道水界」の標石を見つけます👀
こーいう標石は初めて見ましたが、ちょうどこの先で先程の分水界尾根へと続くことから、どうやらここは山からの水と人里との結界だと伝えているようですね。

改めて、今日は源流を探して、あの峰々をがっつり歩きました💧
もし源流を探しながらのひとり歩きをするならば、地理院地図かGPSで地形を読みながらあるく方が、何かと良いかもしれません。参考までに。

帰りは小山田バス停から町田駅行きのバスを利用。
「小山田」には以前から一度は来て見てみたいと思っていましたが、すれ違うヒトも全く皆無な野路山路の侘び具合には、ホント想像以上に驚かされた鶴見川源流歩きになりました。
帰りのバスの本数もかなり少なく、所要時間も町田駅まで30分はかかりますので、冬場のひとり歩きはお気をつけ下さいね。
しかしここは東京都町田市ですよ、、、すごいっ❗️