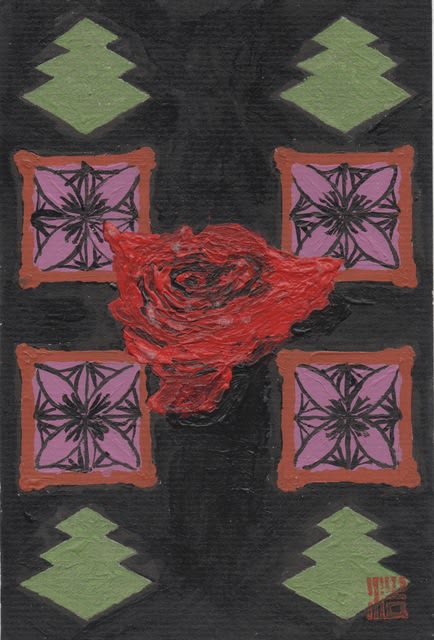ヴェルデュラン家の社交界(サロン)に出入りするスワン。ヴェルデュラン家は新興ブルジョワ階級であり、大貴族階級のゲルマント家とは直接なんの交流=交通もない。だがしかしスワンは両方の家から多少なりとも歓迎されている。それがスワンの強み。またスワンがヴェルデュラン家のサロンをうろうろする理由は、そこに行けばオデットに会えるという下心ゆえである。とはいえただオデットに会いたいがためだけに出かけるわけではなく、そこそこ上流階級化してきたヴェルデュラン家の社交界(サロン)には、大貴族の社交界では見ることのできない文学・芸術関連の品々が豊富に揃っていたことが上げられる。もともとスワン自身の嗜好性が文学・芸術へ向いていた。なのでしばしば出かける。ヴェルデュラン家の館には芸術家肌のスワンを心地よく刺激する空気がいつも横溢していた。それは習慣・制度化される前の<或る感じ>としてしか気づくことができないような微妙な感覚、「感覚器官や神経組織」のレベル、<感受性>の段階で俊敏に気づくことしかできない<スタイル>がすでに取り入れられていたからに違いない。
「スワンからすると、オデットの存在ゆえに、たしかにこの家にはほかのどの家に招待されても得られないものが備わっていた。どの部屋にも感覚器官や神経組織のようなものが張りめぐらされ、スワンの心をたえず刺激するのだ」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.105」岩波文庫 二〇一一年)
もっとも、ヴェルデュラン夫妻は二人とも何のどこがどう「芸術」なのか、よくわかっていない人たちである。短期間でどれほど大きく成長した新興ブルジョワ一家であっても、この種の感性は始めからア・プリオリに備わっているものでは全然ない。しかし注目すべきは音楽家のヴァントゥイユの作品、とりわけピアノ・ソナタと室内楽が何度も繰り返し演奏される点にある。ヴァントゥイユの音楽の特徴として「べつの世界、べつの秩序に属する、闇におおわれた未知の想念で、知性には計り知れない想念であるが、それでもやはりたがいに完全に区別でき、それぞれに価値や意味も異なる想念である」とプルーストは述べる。日頃のスワンが所属している<或る価値体系>からヴァントゥイユの音楽を通して<別の価値体系>へと跳躍することができる。ある意味、「麻薬的陶酔」に浸ることができる。ニーチェのいう「官能」に近い。この種の官能をうまく処理できない場合、大規模な暴力事件や戦争となって視覚化されるというのはニーチェ哲学の特徴の一つ。
次の箇所にこうある。「べつの夜会ではじめてこのソナタを聴いたときに察知した不可思議な実体の代わりに知性に便利なように単純化された等価物にもとづくものだからだとわかっていた」。単純化すれば等価交換可能なものだ。商品交換できるだけでなく、商品交換が可能な限りでどこまでも売買され得る。昨今の社会でネットを通してCDやDVDが大々的に流通しているのと同じことだ。
「小楽節がその魅力を表現した形式は、たしかに理屈に変換できないものだった。しかしスワンは、自分の力にひそむ数多くの富を明るみに出してくれる音楽への愛が一年以上も前からしばしばわが身のうちに芽生えてからというもの、音楽のさまざまなモチーフこそ正真正銘の想念だと考えていた。といってもべつの世界、べつの秩序に属する、闇におおわれた未知の想念で、知性には計り知れない想念であるが、それでもやはりたがいに完全に区別でき、それぞれに価値や意味も異なる想念である。ヴェルデュラン家の夜会のあと、スワンが小楽節をくり返い弾かせてはそれがいかに香水や愛撫のようにわが身を籠絡(ろうらく)し包みこんでしまうかを解明しようとしたとき、小楽節を構成する五音のあいだにわずかな隙間ができ、おまけにそのうちの二音がたえずくり返されるところから、あの寒さに身を縮めるような甘美な印象が生じることが理解できた。しかし実のところ自分にそのような理屈が言えるのは、小楽節それ自体にもとづくからではなく、ヴェルデュラン夫妻と知り合う前にべつの夜会ではじめてこのソナタを聴いたときに察知した不可思議な実体の代わりに知性に便利なように単純化された等価物にもとづくものだからだとわかっていた」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.356」岩波文庫 二〇一一年)
だが大事なのは音楽という形式でなら、普段はまるで共感し合えない人々がなぜか共感し合える事態が出現する、それもたびたび出現するということだろう。人間は放っておけば幾らでも好き勝手なことが言えてしまう。だからしょっちゅう衝突し合っている。しかし音楽を通した場合に限るとしても、いつもは敵同士の間柄であってもなお共感できてしまう。なぜだろうか。こうある。
「無限の鍵盤を形づくるのは、愛情や情念や勇気や平穏からなる無数のキーであり、そのうち、探査もされたことのない多くの深い闇に隔てられあちこちに散らばるいくつかのキーだけが、何人かの偉大な芸術家によって発見されたのにすぎない。ありがたいことにそうして芸術家たちは、各自が発見したテーマに相当するものをわれわれの心に呼び醒ますことにより、空虚な無とみなされ、とうてい入りこめず意気阻喪させられるわれわれの魂という巨大な闇が、いかに豊かで多様な富を知らず知らずのうちに宿しているかを示してくれるのである」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.357」岩波文庫 二〇一一年)
<私>という身体の中で、まだ見出されていないもの。もっと見出されることが期待できるもの。それを発掘することが芸術にはできる。これは驚くべき事態である。戦争では不可能なことが芸術にはできてしまう。かつて「ペンは剣より強し」と言われたが反故化して久しい。にもかかわらずかつて以上に複雑化した昨今ではなぜか「芸術(言語含む)は原爆より強い」こともあるとわかってきた。ネット社会の逆説の一つなのだが説明し出すと長くなるため、ここでは差し当たり次のことに明確な位置付けを与えておこう。ガタリはいう。「彼」はプルーストを、「トランス」はトランス・ジェンダーという時のトランスを、指して用いられている。後者は「横断的」ともいう。
「彼の分析そのものは彼をトランス-主体的およびトランス-客体的抽象的諸機械装置の収集へと向かわしめ、彼はわれわれにそれらの綿密な描写、それも言うまでもなく絶妙の筆致を伴った描写を見せている」(ガタリ「機械状無意識・第2部・第1章・P.259」法政大学出版局 一九九〇年)
もっとも、ヴァントゥイユの「小楽節」がいつもスワンの頭の中にあるわけでない。そしてまたヴァントゥイユの「小楽節」だけがスワンにとっての<至高性>だというわけでもない。しかし「それは光や音や立体感や肉体的官能などほかに同じものがない概念と同じ資格で、スワンの頭のなかに潜在していた」。
「たとえ小楽節について考えないときでも、それは光や音や立体感や肉体的官能などほかに同じものがない概念と同じ資格で、スワンの頭のなかに潜在していた」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.358」岩波文庫 二〇一一年)
ヴァントゥイユの「小楽節」はスワンにとって<他者>として出現するのだ。それ以前はまるで何一つ見えないし共鳴したり共振したりもしたことのない<他者>。レヴィナスに言わせればこうなる。
「<他者>はただたんにその顔のうちに《あらわれるのではない》。<他者>のあらわれは、行動と自由の支配のもとに従属した現象とはことなる。じぶんがとりむすぶ関係そのものから無限に遠ざかりながら、<他者>は絶対的なものとしてこの関係のうちでひといきに現前する。《私》は関係から、とはいえ絶対的に分離された存在との関係のただなかで、その関係から身を引き剥がす。他者が私にふり向くときのその顔は、顔の表象のうちに吸収されれしまうことがない。正義を叫ぶ他者の悲惨さを聴きとることは、あるイメージを表象することではなく、責任あるものとして自己を定立することであり、顔のうちに現前する存在よりも過剰であると同時に過少なものとしてみずからを定立することである。過少なものであるのは、顔が私にじぶん自身の義務を思いおこさせ、私を裁くからである。顔のうちで現前する存在は高さの次元から、超越の次元から到来する。当の存在はそこで異邦人として現前しうるけれども、障害物や敵対者のように、私に対立することがない。他方、過剰なものとして自己を定立するのは、《私》としての私の定立が他者の本質的な悲惨に応答しうることであり、じぶんでそのための資源を見出すことであるからだ。その超越において私を支配する<他者>は、同時に異邦人、寡婦、孤児であり、かれらに対して私は義務を負っているのである」(レヴィナス「全体性と無限・下・第3部・P.78~79」岩波文庫 二〇〇六年)
日常生活のごく平板な意味で使われている言葉ではまるで何一つ伝達できず到達もできない<他なるもの>。それを芸術家は見出し可視化し出現させ問いかける。あるいは共鳴・共振させる。ヴァントゥイユの音楽はスワンの前でそのような<他者>として出現する。それはそのとき初めて可視化された<問い>なのだ。<他者=他なるもの>を「目に見えるようにしてくれる」技術者。それがヴァントゥイユやエルスチールといった芸術家である。
「会話では伝えることのできないこの現実的な残滓のすべて、つまり各人が感じたものを質的に区別してくれるが、ことばで他人と意思を通じあおうとすれば万人共通の些細な上っ面に話を限定するほかない以上、ことばの入口で置き去りにせざるをえないこの言いあらわしがたいもの、それをこそ芸術は、エルスチールの芸術と同じくヴァントゥイユの芸術は、われわれが個人と呼んではいるが芸術なくしてはけっして知ることのないさまざまな世界の内密な組成をスペクトルの色彩として顕在化することによって、目に見えるようにしてくれるのではなかろうか?もしもわれわれが翼を備え、べつの呼吸器官を身につけ、広大無辺の宇宙を飛行できるようになったとしても、そんなことはわれわれにはなんの役にも立つまい。というのも、たとえ火星や金星へ行ったとしても、われわれが同じ感覚を持ちつづけるかぎり、その感覚はわれわれが目にするあらゆるものに地球上のものと同じ外観をまとわせるにちがいないからである。ただひとつ正真正銘の旅、若返りのための唯一の水浴は、新たな風景を求めて旅立つことではなく、ほかの多くの目をもつこと、ひとりの他者の目で、いや数多くの他者の目で世界を見ること、それぞれの他者が見ている数多くの世界、その他者が構成している数多くの世界を見ることであろう。エルスチールを供にすれば、ヴァントゥイユを供にすれば、それと同等の芸術家たちを供にすれば、われわれにはそれが可能になり、文字どおり星から星へと飛行できるのである」(プルースト「失われた時を求めて11・第五篇・二・P.154~155」岩波文庫 二〇一七年)
<他者>と出会うこと。<ない>と思い込んでいた仕切りが実は<ある>と教えてくれるばかりか「目に見えるようにしてくれる」人々。見ているのに見えていなかったものを可視化してくれたエルスチールの絵画のように、ヴァントゥイユの音楽はそれまでまるで理解できていなかった事情について、<私>の眼前へ贈り寄越し、間違う余地なく光り輝く明るみへ引き出す。
BGM1
BGM2
BGM3

「スワンからすると、オデットの存在ゆえに、たしかにこの家にはほかのどの家に招待されても得られないものが備わっていた。どの部屋にも感覚器官や神経組織のようなものが張りめぐらされ、スワンの心をたえず刺激するのだ」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.105」岩波文庫 二〇一一年)
もっとも、ヴェルデュラン夫妻は二人とも何のどこがどう「芸術」なのか、よくわかっていない人たちである。短期間でどれほど大きく成長した新興ブルジョワ一家であっても、この種の感性は始めからア・プリオリに備わっているものでは全然ない。しかし注目すべきは音楽家のヴァントゥイユの作品、とりわけピアノ・ソナタと室内楽が何度も繰り返し演奏される点にある。ヴァントゥイユの音楽の特徴として「べつの世界、べつの秩序に属する、闇におおわれた未知の想念で、知性には計り知れない想念であるが、それでもやはりたがいに完全に区別でき、それぞれに価値や意味も異なる想念である」とプルーストは述べる。日頃のスワンが所属している<或る価値体系>からヴァントゥイユの音楽を通して<別の価値体系>へと跳躍することができる。ある意味、「麻薬的陶酔」に浸ることができる。ニーチェのいう「官能」に近い。この種の官能をうまく処理できない場合、大規模な暴力事件や戦争となって視覚化されるというのはニーチェ哲学の特徴の一つ。
次の箇所にこうある。「べつの夜会ではじめてこのソナタを聴いたときに察知した不可思議な実体の代わりに知性に便利なように単純化された等価物にもとづくものだからだとわかっていた」。単純化すれば等価交換可能なものだ。商品交換できるだけでなく、商品交換が可能な限りでどこまでも売買され得る。昨今の社会でネットを通してCDやDVDが大々的に流通しているのと同じことだ。
「小楽節がその魅力を表現した形式は、たしかに理屈に変換できないものだった。しかしスワンは、自分の力にひそむ数多くの富を明るみに出してくれる音楽への愛が一年以上も前からしばしばわが身のうちに芽生えてからというもの、音楽のさまざまなモチーフこそ正真正銘の想念だと考えていた。といってもべつの世界、べつの秩序に属する、闇におおわれた未知の想念で、知性には計り知れない想念であるが、それでもやはりたがいに完全に区別でき、それぞれに価値や意味も異なる想念である。ヴェルデュラン家の夜会のあと、スワンが小楽節をくり返い弾かせてはそれがいかに香水や愛撫のようにわが身を籠絡(ろうらく)し包みこんでしまうかを解明しようとしたとき、小楽節を構成する五音のあいだにわずかな隙間ができ、おまけにそのうちの二音がたえずくり返されるところから、あの寒さに身を縮めるような甘美な印象が生じることが理解できた。しかし実のところ自分にそのような理屈が言えるのは、小楽節それ自体にもとづくからではなく、ヴェルデュラン夫妻と知り合う前にべつの夜会ではじめてこのソナタを聴いたときに察知した不可思議な実体の代わりに知性に便利なように単純化された等価物にもとづくものだからだとわかっていた」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.356」岩波文庫 二〇一一年)
だが大事なのは音楽という形式でなら、普段はまるで共感し合えない人々がなぜか共感し合える事態が出現する、それもたびたび出現するということだろう。人間は放っておけば幾らでも好き勝手なことが言えてしまう。だからしょっちゅう衝突し合っている。しかし音楽を通した場合に限るとしても、いつもは敵同士の間柄であってもなお共感できてしまう。なぜだろうか。こうある。
「無限の鍵盤を形づくるのは、愛情や情念や勇気や平穏からなる無数のキーであり、そのうち、探査もされたことのない多くの深い闇に隔てられあちこちに散らばるいくつかのキーだけが、何人かの偉大な芸術家によって発見されたのにすぎない。ありがたいことにそうして芸術家たちは、各自が発見したテーマに相当するものをわれわれの心に呼び醒ますことにより、空虚な無とみなされ、とうてい入りこめず意気阻喪させられるわれわれの魂という巨大な闇が、いかに豊かで多様な富を知らず知らずのうちに宿しているかを示してくれるのである」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.357」岩波文庫 二〇一一年)
<私>という身体の中で、まだ見出されていないもの。もっと見出されることが期待できるもの。それを発掘することが芸術にはできる。これは驚くべき事態である。戦争では不可能なことが芸術にはできてしまう。かつて「ペンは剣より強し」と言われたが反故化して久しい。にもかかわらずかつて以上に複雑化した昨今ではなぜか「芸術(言語含む)は原爆より強い」こともあるとわかってきた。ネット社会の逆説の一つなのだが説明し出すと長くなるため、ここでは差し当たり次のことに明確な位置付けを与えておこう。ガタリはいう。「彼」はプルーストを、「トランス」はトランス・ジェンダーという時のトランスを、指して用いられている。後者は「横断的」ともいう。
「彼の分析そのものは彼をトランス-主体的およびトランス-客体的抽象的諸機械装置の収集へと向かわしめ、彼はわれわれにそれらの綿密な描写、それも言うまでもなく絶妙の筆致を伴った描写を見せている」(ガタリ「機械状無意識・第2部・第1章・P.259」法政大学出版局 一九九〇年)
もっとも、ヴァントゥイユの「小楽節」がいつもスワンの頭の中にあるわけでない。そしてまたヴァントゥイユの「小楽節」だけがスワンにとっての<至高性>だというわけでもない。しかし「それは光や音や立体感や肉体的官能などほかに同じものがない概念と同じ資格で、スワンの頭のなかに潜在していた」。
「たとえ小楽節について考えないときでも、それは光や音や立体感や肉体的官能などほかに同じものがない概念と同じ資格で、スワンの頭のなかに潜在していた」(プルースト「失われた時を求めて2・第一篇・二・二・P.358」岩波文庫 二〇一一年)
ヴァントゥイユの「小楽節」はスワンにとって<他者>として出現するのだ。それ以前はまるで何一つ見えないし共鳴したり共振したりもしたことのない<他者>。レヴィナスに言わせればこうなる。
「<他者>はただたんにその顔のうちに《あらわれるのではない》。<他者>のあらわれは、行動と自由の支配のもとに従属した現象とはことなる。じぶんがとりむすぶ関係そのものから無限に遠ざかりながら、<他者>は絶対的なものとしてこの関係のうちでひといきに現前する。《私》は関係から、とはいえ絶対的に分離された存在との関係のただなかで、その関係から身を引き剥がす。他者が私にふり向くときのその顔は、顔の表象のうちに吸収されれしまうことがない。正義を叫ぶ他者の悲惨さを聴きとることは、あるイメージを表象することではなく、責任あるものとして自己を定立することであり、顔のうちに現前する存在よりも過剰であると同時に過少なものとしてみずからを定立することである。過少なものであるのは、顔が私にじぶん自身の義務を思いおこさせ、私を裁くからである。顔のうちで現前する存在は高さの次元から、超越の次元から到来する。当の存在はそこで異邦人として現前しうるけれども、障害物や敵対者のように、私に対立することがない。他方、過剰なものとして自己を定立するのは、《私》としての私の定立が他者の本質的な悲惨に応答しうることであり、じぶんでそのための資源を見出すことであるからだ。その超越において私を支配する<他者>は、同時に異邦人、寡婦、孤児であり、かれらに対して私は義務を負っているのである」(レヴィナス「全体性と無限・下・第3部・P.78~79」岩波文庫 二〇〇六年)
日常生活のごく平板な意味で使われている言葉ではまるで何一つ伝達できず到達もできない<他なるもの>。それを芸術家は見出し可視化し出現させ問いかける。あるいは共鳴・共振させる。ヴァントゥイユの音楽はスワンの前でそのような<他者>として出現する。それはそのとき初めて可視化された<問い>なのだ。<他者=他なるもの>を「目に見えるようにしてくれる」技術者。それがヴァントゥイユやエルスチールといった芸術家である。
「会話では伝えることのできないこの現実的な残滓のすべて、つまり各人が感じたものを質的に区別してくれるが、ことばで他人と意思を通じあおうとすれば万人共通の些細な上っ面に話を限定するほかない以上、ことばの入口で置き去りにせざるをえないこの言いあらわしがたいもの、それをこそ芸術は、エルスチールの芸術と同じくヴァントゥイユの芸術は、われわれが個人と呼んではいるが芸術なくしてはけっして知ることのないさまざまな世界の内密な組成をスペクトルの色彩として顕在化することによって、目に見えるようにしてくれるのではなかろうか?もしもわれわれが翼を備え、べつの呼吸器官を身につけ、広大無辺の宇宙を飛行できるようになったとしても、そんなことはわれわれにはなんの役にも立つまい。というのも、たとえ火星や金星へ行ったとしても、われわれが同じ感覚を持ちつづけるかぎり、その感覚はわれわれが目にするあらゆるものに地球上のものと同じ外観をまとわせるにちがいないからである。ただひとつ正真正銘の旅、若返りのための唯一の水浴は、新たな風景を求めて旅立つことではなく、ほかの多くの目をもつこと、ひとりの他者の目で、いや数多くの他者の目で世界を見ること、それぞれの他者が見ている数多くの世界、その他者が構成している数多くの世界を見ることであろう。エルスチールを供にすれば、ヴァントゥイユを供にすれば、それと同等の芸術家たちを供にすれば、われわれにはそれが可能になり、文字どおり星から星へと飛行できるのである」(プルースト「失われた時を求めて11・第五篇・二・P.154~155」岩波文庫 二〇一七年)
<他者>と出会うこと。<ない>と思い込んでいた仕切りが実は<ある>と教えてくれるばかりか「目に見えるようにしてくれる」人々。見ているのに見えていなかったものを可視化してくれたエルスチールの絵画のように、ヴァントゥイユの音楽はそれまでまるで理解できていなかった事情について、<私>の眼前へ贈り寄越し、間違う余地なく光り輝く明るみへ引き出す。
BGM1
BGM2
BGM3