新坂川の残桜を見に行きました。好天で暖かいせいもありましたが、近距離とはいえ、腰痛を抱える身で、買い物以外に出かけようという気になったのは久しぶりです。
ソメイヨシノに較べると白っぽい山桜(?)。

満開からほぼ一週間。桜はまだ見ごたえがありました。
近くに寄ってみると、ほとんど葉桜でした。
風に吹かれて舞い落ちる無数の花びらも、花いかだをつくるまでにはなかなかまとまらぬようで……。
鳩も花いかだができるのを待っているようです。
地面にはたくさんの花びらが落ちて、吹き溜まりができていましたが、流れる川に落ちてしまうと大した量ではないのでしょうか。
近くのゆりのき通りではユリノキの芽吹きが始まっていました。
東京で桜が満開となったのは四日。我が地方はその手の報道がないので、いつ満開を迎えたのか知るすべがありませんが、気温でいうと、いつも東京よりちょっぴり低いことが多いので、一日遅れの五日ということにしておきましょうか。毎年のことながら、桜の季節は花曇りが多くて、気分も晴れません。
ずっと曇りだった空、午後になると、陽射しが出たので、買い物ついでに、近くのさざんか公園の桜を愛でに行きました。
カメラに収めてみると、あまりパッとしませんでしたが、数本ある桜の樹は満開でした。

晴れたとはいっても雲が多く、陽射しの遮られることも多かったものの、こんな青空が拡がるとは思ってもみませんでした。
スーパーでは缶酎ハイを買って帰りましたが、相手もいない独りでは意気も上がらず、花見酒とも行かず、虚しく持ち帰りました。

一昨年十一月、火事のもらい火に遭い、一駅隣りの街に引っ越して迎える二年目の夏です。
引っ越す前は毎月二十七日がくると、東漸寺という浄土宗のお寺に欠かさず参拝に出向いていたのですが、引っ越したあと、新しい住処から東漸寺まで歩いて行くと、所要時間は二十六~七分……。往復一時間近く。
遠くなってしまったのと、去年九月には脊柱菅狭窄症という病に見舞われてしまったので、歩いて行くことはとてもできぬ。電車で行くとしても、歩く距離はあまり変わらぬ。よって、毎月行くことは叶わぬかもしれぬが、七月二十七日だけは万難を排して行かねばならぬ、と決意を固めていました。
昨年の七月二十七日は病に見舞われる前であったので、無事参拝を終えています。
なぜ二十七日、とりわけ七月二十七日なのか……というと、七月二十七日は私の誕生日、毎月二十七日というのは月命日ならぬ月誕生日だからです。
我が干支の守り本尊は阿弥陀如来。いくつか持病を抱えながらも、曲がりなりにも日々健康で暮らせるのは、阿弥陀様のご加護があるから……。そのように考えるので、二十七日は阿弥陀様を本尊としている東漸寺にお礼参りに行こうと決めたのです。
ところが、万難を排してでも行かねばならぬはずの、先月二十七日の我が地方は最高気温37・2度という猛暑日。日中を避け、夕方に参拝に出る、という策がなかったわけではないが、日中の暑さに耐えているだけで体力を消耗してしまっていたので、わずかひと駅といえど電車に乗って出かけようという気力が湧かず、已む無く参拝を諦めたのでした。
それなら翌日……と考えましたが、翌二十八日も35・0度という猛暑日。二十九日(34・4度)、三十日(35・2度)、三十一日(34・5度)と揺るぎない暑さが続いて、身体も気力も日増しに衰弱。
昨八月朔日は七月九日以来、二十三日ぶりという雨が降って、ほんのちょっとだけ涼しくなりました。そして今日二日、午前中は気のせいか、涼しさが尾を曳いています。
で、遅ればせながら腰を上げました。
じつは毎月通うかかりつけの内科の病院が東漸寺のすぐ近くにあって、薬が切れるので、腰を上げなければならなかったのです。
診察を終えたあと、勇躍東漸寺へ……。
旧水戸街道に面する東漸寺の入口です。
門前に掲げられた標語。
総門。
涼し気な参道の彼方に山門。阿吽の仁王尊が睨みを効かせています。
中雀門。これより本堂。
本堂手前左には観音堂。
そして本堂です。本尊・金色の阿弥陀如来坐像が祀られています。
持病は多々あって、この日の通院を含め、通う病院・クリニックは三つもあれど、曲がりなりにも健康な生活を送れるよう、お守りくださっているのは、私の干支の守り本尊である阿弥陀様のお陰であろうと改めて感じるので、感謝のお賽銭をあげて参拝します。
本堂参拝のあとは開山の経譽愚底上人(?-1517年)の墓所に参拝します。
その墓所のあちこちにあるのがショウジョウソウ(猩々草)です。誕生日のお礼参りで楽しみにしているのは、この紅色の葉。ポインセチアの仲間です。
紅い花が開いたように見えますが、紅いのは葉っぱ。真ん中に開きかけの花があります。

手持ちの野草図鑑には草丈50~100センチとありますが、東漸寺のショウジョウソウはせいぜい15~20センチ程度です。秋になると、花が黒い実に姿を変えます。今秋、もしくることができたら、実をいただいて、我が庭に播こうか、と。
今日七日は二十四節気のうち大雪、そして今日から十一日までは大雪の初候・閉塞成冬です。
「成冬」というのは確かに「ふゆとなる」と読めますが、「閉塞」=「そらさむく」というのはなかなかそうとは読めません。そういうことを別にすると、年に七十二ある「候」の中で、実際の季節とは少し違うという「候」が多かったりする中、ピンとくる「候」の一つです。
そしてやはり、大雪の次候、十二月十二日から十六日まではどうかというと、熊蟄穴(くまあなにこもる)、さらにその次、十七日から二十一日の鱖魚群(さけのうおむらがる)などは、私が棲む地域ではそのさまを見ることができないので、そんなことを示されたりいわれたところで、まったくピンときません。
これらは日本の略本暦ですが、中国の長慶宣明暦でそれぞれに当たるのは虎始交(虎が交尾を始める)、茘挺出(捩菖蒲が芽を出し始める)とあって、虎などは動物園へ行かなければ見れないし、その虎の交尾となると、つがいがいる動物園でなければならない。ますます現実感がなくなります。
その点、我が地方では今日こそ好天に恵まれて暖かかったものの、昨日までは雨に見舞われ、一昨日昨日と最高気温は10度に届かないという寒さで、まさに「成冬」でした。
昨日までの雨がちの天気は「さざんか梅雨」と呼ぶようです。
秋から冬にかけて、移動性高気圧が北に偏ることがある、すると本州南海上に前線が停滞、ちょうど梅雨どきのような気圧配置になって雨をもたらす。ちょうどさざんかの咲く季節なので、そう呼ぶのだそうですが、俳句の季語なのかと思って、講談社版「日本大歳時記」を引っ張り出してみたものの、該当するものはありませんでした。
季語などではなく、気象庁か気象関係者の造語であれば、私は信用しないことにしています。
なぜならば、台風や豪雨の季節に、「これまで経験したことのない」とか「大切な人の命を守る行動」などという、けったいな日本語をつくったのは気象庁であろうと思われるからです。用いられている単語そのものは、中国語や韓国語ではなく、確かに日本語には違いないけれども、普通こういう使い方をするか? ということばです。
気象庁は日本語の専門家ではないので、勝手にやっているぶんには、まァいいかと思っても、正しい日本語を使わなければならぬはずの放送局まで気象庁のいうままにけったいなことばを使っているのかけしからん、というなるのではないかと思います。さらに台風などの中継のときには「身の安全を云々……した上で中継しています」と、バラエティ番組ではないのだから、いわなくてもいい、当然のことを敢えていう、という余計なことまでやっています。
重箱の隅をつつくようなことはこのへんにして、確かに季節はさざんかの咲くころです。
サザンカ(山茶花)。花の尠ない時期に咲いてくれるので、貴重です。
我が庵の近くにこんな名の公園があり、周囲を取り囲んでいるのは文字どおり山茶花の樹です。
ぐずついて寒々としていた日々が去ってくれて、雲一つない快晴の一日になりました。

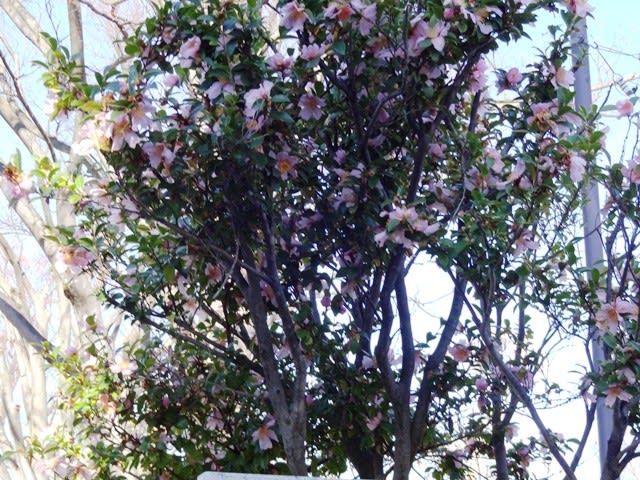
一本だけピンク色した花の樹がありました。
※「さけ」はブラウザによっては表示されないかもしれません。魚偏に厥と書きます。
江戸川堤へ菜の花を見に行こうと思い立ちました。
我が庵を出て西の方角を目指します。五分ほどで中央分離帯に夾竹桃(キョウチクトウ)が植えられている、きょうちくとう通りを横断します。
きょうちくとう通りと十字に交差するけやき通りに出ました。まだケヤキ(欅)の芽吹きはありません。
けやき通りが坂川に架かる橋(欅通り橋)を渡ります。
欅通り橋から十分ほど歩くと、道は神明堀に突き当たって行き止まり。坂川に較べると細い川(排水路?)なのに、橋の数は坂川の半分しかありません。
流山街道に出ました。
まだ暑い季節ではないので飲料は必須ではありませんが、念のため買って、トートバッグに忍ばせておこうと思っているのに、大型衣料品店や電気店はあっても、コンビニや自販機が見当たりません。
ツクシ(土筆)がたくさん顔をのぞかせていました。
途中、立ち止まって写真を撮ったりしていたので、庵を出てから四十分近くかかりましたが、観音寺に着きました。まっすぐ向かっていたら三十分少々で着く距離です。私には馴染みの深いムクロジ(無患子)のあった(いまはありません)お寺なので、かつてはよくきていました。
観音寺周辺は様変わりしていました。今日現在のグーグルマップを開き、地図を航空写真に変えると、いつ撮影した画像を使っているのか、空き地があるのがわかりますが、実際は家が建て込んで、空き地はほとんど見当たりません。
観音寺の横には香取神社があるのは変わりませんでしたが、公園ができたりして、ここも様変わりです。
江戸川の堤防に着きました。
江戸川土手から観音寺を遠望。


望遠レンズを装着したカメラを携帯してきたので、ここぞとばかりシャッターを切りました。
観音寺先で江戸川堤防に上り、上流に向かって五分ほど歩いたところにこんな標識がありました。
幸房(こうぼう)とは対岸・三郷市の地名です。「岩野木の渡し」「七右衛門新田の渡し」とも呼ばれたようです。岩野木はやはり三郷市の地名、七右衛門新田はこちら側松戸市の地名ですが、いわずもがな、木柱が建てられているところは流山市で、七右衛門新田は少し下流です。
この堤防も以前はよく歩いたものですが、この標識は前はなかったような……。
すっかり歩き疲れてしまったので、南流山駅まで歩き、一駅だけ電車に乗って帰ります。
今年も彼岸花が顔を覗かせました。お彼岸が近くなると、毎年毎年律儀に姿を現わします。
紅葉シーズンにはまだ間があるので、観光客の姿もなく、物静かな本土寺の参道です。

参道のところどころにヒョロヒョロと……。昨日か一昨日顔を出したばかりなので、まだ弱々しく、頼りなげです。
離れたところに一株だけ慌てもの。明日にでも花開きそうです。競合する相手がないので、土の養分を独り占めできるからでしょうか。
慶林寺の彼岸花(白)は鉢植えですが、こちらもすくすくと育っています。
雨がちの天気がつづいたので、しばらく富士川沿いの散策を控えていたら、稲刈りの真っ盛りを迎えていました。
すでに刈り取りが終わった田んぼも多く見られました。
十五日は阿弥陀様の縁日です。
いくつか持病がありながら、先月の十五日にお参りしてから一か月の間は、曲がりなりにも大禍なく過ごせたのも阿弥陀様のご加護があったからであろう。いつからかそういうふうに考えるようになったので、毎月この日は阿弥陀如来を本尊にお祀りしている東漸寺へお礼参りに出向くのです。
我が庵は平賀中台と呼ばれる台地の上にありますが、東漸寺に向かうときは途中で台地の端っこを通ります。目に入る遠くのマンションやクリーンセンターのものらしき煙突などを目安にして地図を見てみると、船橋あたりの方角が望めるようです。
この日はその東南東から南南東にかけての方角に、雷雲らしき雲があるのが見えました。夕方のTVのニュースでは、千葉市内のざんざん降り(一時間で22ミリ)の様子が映し出されていましたが、船橋も同様だったようで、アメダスによると、15ミリという雨量が記録されました。ところが、私が暮らす松戸では雨は降りませんでした。
東漸寺には涼し気な緑陰が拡がっていました。
この日の我が地方の最高気温は29・8度でしたが、松戸には観測施設がないので、これも船橋にあるアメダスの記録です。体感温度ではとても30度を切ったとは思えない一日でしたが、千葉市内に雷雨があったころ、船橋でも雨が降って、気温が下がったのだろうと思われます。
本堂へのお参りを終えると墓所へ向かいます。本尊に阿弥陀様を迎えてくださったのは開山の経譽愚底さんだと考えるので、そのお墓にもお礼参りをするためです。
歴住の墓所に向かうと……。 ? なんという花だろうと思ってカメラに収めましたが、紅いのは花ではなく、葉っぱです。
グーグルレンズで検索するために、スマートフォンのカメラで撮り直し、検索してみたら、ショウジョウソウと出ました。漢字では「猩々草」と書きます。
「猩々」とは、中国で考えられ、猿に似た架空の動物です。転じて酒の好きな人、すなわちいつも顔を真っ赤にしている大酒呑みのこと。
あとでポインセチアの変種だと知って、なるほどそういえばよく似ているワイと感じました。
よく見ると、一般の人の墓石の前にもありました。
東漸寺歴住の墓所です。
東漸寺の本堂や観音堂だけでなく、本堂左手にある歴住の墓所に参拝するのは毎月十五日と二十七日です。中央にあって一基だけ竿(四角い石)があり、一段高いのが開山・經譽愚底(きょうよ・ぐてい)上人の卵塔です。
ショウジョウソウはこの墓所の入口あたりにありました。
墓所から本堂の屋根越しに眺めた空。
この日の夕方になって、明日には関東地方も梅雨明けか、とTVの天気予報はいっていましたが、巨大な入道雲も顔を覗かせて、すでに完全な夏空です。
日課の慶林寺参拝は午後になりました。
今日のハス(蓮)はピンク。咲いたらしいのはこの一輪だけでした。
ガマ(蒲)。山野ではなく、街中で育っているためか、なんとなく繊細さを伺わせる面立ちです。
梅雨の中休みです。しかし、本当に梅雨入りしたのかどうか疑わしい。レーダーや数値など、科学的根拠に基づいているはずの気象情報、と思っていた(それなのに当たらない)のに、梅雨入りしたかどうかはその日が当番の気象士の主観次第であるということを初めて知りました。もちろんその人が一人で勝手に決めるのではないようですが……。
八時過ぎ、ごみ出しに出たら、梅雨空などどこ吹く風、というような夏空が拡がっていました。
お昼が近づくのにつれて暑くなりましたが、朝のうちは湿度も低そうでサッパリした陽気でした。
昨日の朝の段階の天気予報では、台風5号の影響で関東地方南部は恐るべき大雨ということでした。ところが、なかなか雨の降りそうな気配はない。
インターネットで天気情報を視ると、雨は午後になってからとなっていました。そしてまた、ところが、昼を過ぎても雨は降らない。雨雲レーダーを視て動かしてみると、雨は夜八時ごろからのよう。
暗くなったのでカーテンを締めましたが、雨の降る音はしません。雨雲レーダーを視ていた限りでは、雨雲は千葉市や成田市を北限として北東へ流れて行き、結局、我が地方にかかることはなかったと見えます。


慶林寺の牡丹臭木(ボタンクサギ)はどの株も満開近い状態になってきました。
ひと足早く満開状態になっていた参道入口のオタフクアジサイはひと足早く後退期に入っています。
この時期、私の愉しみの一つは半夏生です。草花の半夏生と二十四節気七十二候の半夏生。季節のほうの半夏生は四日後の七月二日です。
北小金の駅から常磐線の線路づたいに南柏方向へ550メートルほど歩いたところ。右手は常磐線の土盛り。折しも水戸方面に向かう特急電車が轟音を轟かせて走り去って行くところでした。
この先、江戸川の支流の支流の支流・平賀川を渡る窪地があります。富士川に合流して、さらに坂川に合流し、最後は江戸川に合流して東京湾に流れる川で、橋ともいえぬか細い橋が架かっています。
余談ながら、「自転車は下りてお通り下さい。」と書かれた標識が出ていますが、自転車を下りる人ほぼ100%ありません。自転車を下りろ、というのですから、バイクはもってのほか、と普通の人なら考えると思うのに、バイクを下りろとは書いてないのだからいいのだろうとばかりに、郵便局員も100%エンジンを噴かせて通り過ぎて行きます。
いまだ目撃したことはありませんが、バイクに乗って通りかかる警察官はどうするだろう。是非見てみたいものだと思います。
そもそも私が暮らしているあたりは広い道に恵まれていないので、国道6号をくぐる隧道や北小金駅前付近など、「自転車云々」と書かれた標識が結構あります。もちろんそれに従って自転車を下りる人はまず皆無。そこが歩道であれば、バイクが通るのは交通違反になるので、さすがにバイクの知らんぷりはいませんが……。
一番窪んだところに半夏生(ハンゲショウ)の群生地があります。川は流れているはずですが、どこを流れているのか、川面は見当たりません。
今年に限らず、毎年毎年、もしかして、と思うのは、この窪地に降りられるような細工がなされて、半夏生を間近に見られぬか、ということなのです。
半夏生の別名は片白草(カタシログサ)。
片一方 ― 陽の当たる表 ― だけが白くなるので、この名があります。あるいは半分だけ白粉(おしろい)を塗るので、半化粧、とも……。しかし、本当に裏は緑色のままなのか、見てみたいと思うのですが、鉄のフェンスで遮られて、間近まで降りられそうもないので、橋の上から表を眺めるだけです。

去年のいまごろは葉っぱに緑の残ったところがありましたが、今年は見たところ、すべて真っ白に化粧をしているようです。

かたわらには凌霄花(ノウゼンカズラ)の花。

散歩道のあちこちではブッドレアの花もほころび始めていました。
四日前の十五日からあまり陽射しがありません。おまけに昨日今日とまるで嵐のような風が吹きます。去年と較べると、5キロも軽くなった私の身体は、強い風にもてあそばれてどこかへ飛んで行きそうです。
週末まではずっと雨模様。梅雨入り宣言こそ出されていませんが、まるで梅雨です。
今日十八日は観音菩薩の縁日なので、観音さまをお祀りしている東漸寺と慶林寺をハシゴです。

東漸寺観音堂(上)と慶林寺の観音像。

慶林寺では梅の実が大きくなってきました。
散歩道ではところどころで白いアジサイ(紫陽花)が咲き始めたのを目にします。慶林寺ではカシワバアジサイが咲き始めました。

参道ではハナモモ(花桃)の実も。
七年ぶりに梅酒をつくろうかという気になりましたが、例年だとそろそろ青梅が出る無人の野菜直売所にはまだその兆しがありません。

ウツギ(空木)の花を見ました。もう少し季節が過ぎると、クサギ(臭木)が咲き始める斜面に一本だけ幹がありました。
♪卯の花の、匂う垣根に
時鳥、早も来鳴きて
忍音もらす、夏は来ぬ
♪さみだれの、そそぐ山田に
早乙女が、裳裾ぬらして
玉苗植うる、夏は来ぬ
♪橘の、薫るのきばの
窓近く、蛍飛びかい
おこたり諌むる、夏は来ぬ
♪楝ちる、川べの宿の
門遠く、水鶏声して
夕月すずしき、夏は来ぬ
♪五月やみ、蛍飛びかい
水鶏鳴き、卯の花咲きて
早苗植えわたす、夏は来ぬ
歌詞が五番まであったとは知りませんでした。
ナツグミ(夏茱萸)の実も色づき始めていました。
五月になりました。
空だけを見ていると、いかにも薫風薫る五月、という明るさですが、地上はとても薫風とは呼べないような風が荒れ狂っています。
慶林寺参道のハナモモ(花桃)の樹です。

濃い緑の木陰なので、注意して見ないことには見過ごしてしまいがちですが、小さな実をつけ始めました。
午後、遅めの散歩は慶林寺とは反対方向へ。とちのき通りです。

栃の葉はすっかり大きくなりました。
あまり歩くことのない径に足を向けてみました。とちのき通りを少し外れたところにある市営住宅です。
あまり歩くことはないので、こんな高木があったとは憶えがありません。もう少し早いか遅いか、別の季節に歩いていたら、この樹々があったことすら記憶には刻まれなかったのに違いありません。
通り過ぎて行くと、目の前に大きな花がありました。富士川に向かって下る斜面を均した土地に建てられているので、私が歩いている道路は市営住宅の二階から三階に当たる高さを走っています。市営住宅の庭は数メートル下です。普通なら真横に花を見ることなどできないでしょう。
見たときはなんという樹なのかわかりませんでした。庵に帰ったあとで調べて、北米中部原産の樹木で、ユリノキというのだと知りました。英名はアメリカン・チューリップ・ツリー。手許にある樹木図鑑には秋の黄葉が見事、と紹介されています。
二年間だけ棲んだことのある新松戸のマンション近くに、ゆりのき通りという名のつけられた並木道があります。棲んでいたのが十年以上も前なのと、当時は樹木などに関心もなかったからかどうか、並木道の光景は思い浮かびません。
秋になったら……と、忘れぬようメモを残しました。
歩いているうちに、右手の甲をひやりと冷たいものがかすめました。なんだろうと思って空を見上げると、いつの間にかこんな黒雲が空を覆っていました。西に傾きかけた太陽に照らされているので、周辺は明るいのです。空だけ真っ暗。狐の嫁入りのようです。

百八十度身体を捻ると田んぼ。こちらは陽射しがあります。例年なら田植え風景を見るのは二日後のこどもの日です。梅も桜も早かった今年は田植えも早いのか。
昨日、西日本ではかなりの大雨。東日本は晴れたり曇ったりでしたが、追っつけ雨になるのは必至。
ところが、西日本の大雨はどこ吹く風、というような、午前中はこんな青空でした。
ただ、いずれ雨をもたらすらしい低気圧の影響で風は強い。十一日前、今月二日の桜吹雪は染井吉野(ソメイヨシノ)でしたが、今日の花吹雪は八重桜。

日課の慶林寺参拝に赴く途中に二本の八重桜があります。
慶林寺の参道にはピンク色の花を咲かせる若木。

「りんごつがる」という札が提げられていました。

これから咲こうという蕾もありますからまだ咲き始めたばかり。多少強い風が吹いても、散らされたりしません。
♪林檎の花びらが、風に散ったよな、となるのは例年であれば五月。何もかも早い今年は今月中か。
桐の樹も若葉を芽吹いています。 
青空に釣られて、栃の若葉を愛でてみようかと、とちのき通りへ足を延ばしました。
市がきちんと管理しているのだから、まさかとは思うけれど、ひょっとして枯死(?)と思ったら……。
人間の顔にたとえると、両目の真ん中、鼻のように見えるのが若葉です。
かと思えば、もうこんなに葉を繁らせている幹もありました。
昨日、たまたま九年前、三月の自分のブログを視ていました。この年の慶林寺の河津桜が満開を迎えたのは三月二十七日。それなのに今年の満開は三月朔日。およそ一か月も早かったのだから、改めて愕いてしまいました。
連れて枝垂れ桜もソメイヨシノも早い。周辺にある枝垂れ桜はすでに散り、ソメイヨシノも散り始めです。
流山・鰭ヶ崎にある東福寺へ残桜を観に行ったのは2010年が四月十日、11年が同十五日。今年は開花が半月ほど早いので、すでに散り始めているのに違いない。すわ……というわけで、残桜見物に出かけることにしました。
最近は長い距離を歩くことができなくなっていました。しかし、このところは身体が軽く感じるようになっていたので、東福寺まで歩くのは少しホネがあるのですが、歩いて行ってみることにしたのです。ついでに新松戸と馬橋の間で観られる新坂川の残桜もハシゴします。
身体が軽いと感じるようになったことに何か思い当たるところがあるのかというとおおありで、大酒飲みだった私が今月三日・雛祭りの夜を最後に断酒生活に入っていたのです。今日でまだ二十五日目なので、どこまでつづけられるものかわかりませんが、アルコールを絶って一週間ぐらいしたころから、会う人ごとに「顔色がよくなった、背中がシャンとして姿勢がよくなった」といわれるようになりました。体重も3キロほど落ちて、身が軽くなったような気がします。
日々の散歩でも、長いことやる気にならなかった五百歩の速歩き兼大股歩きを、一回の散歩につき一度だけですが、試みようという気になりました。再開直後は大腿直筋が痛んだものですが、最近はそれほど痛まなくなりました。そんなことから、久々に長距離歩きに挑戦してみようと考えたのです。
毎日のお勤めである慶林寺参拝を終えて、東福寺に向かいます。グーグルマップで計測すると三十分かかる距離です。
慶林寺をあとにして十五分で新坂川に到達しました。このころから急に暑くなってきました。
横須賀橋という橋を渡ります。東福寺の桜を観たあと、この川の下流にある桜を観に行くことになります。
新坂川から八分で坂川の本流。ここで渡るのは新横須賀橋。ここから流山市です。
慶林寺から三十三分歩いて東福寺に着きましたが、久しぶりだったので、曲がるべき道を間違えて、山門前に出てしまいました。本当はもっと手前で曲がって、庫裏に通じる裏の石段(山門前とは違って、緩い上に短いのです)を上ろうと思っていたのです。
ただ、間違えた代わりにもう一つの実験を思いつきました。高所恐怖症の私なのに、この石段を上ってみようと思ったのです。
とはいえ、颯爽と上る、などという芸当は夢のまた夢 ― へっぴり腰で、上れば上るほど足を滑らせるのではないかという恐怖感と戦いつつ、手すりを唯一の頼りにしながら、ただひたすら足許の石段だけを見て、なんとか上り終えることができました。
ずっと避けてきた石段上りに挑戦するなど、少し前なら考えられないことです。これもアルコールを絶った功徳でしょうか。ただ、下りは前(というか下)が目に入ってしまうので、まだ無理だろうと思います。
東福寺本堂です。真言宗豊山派の寺院。
弘法大師が巡錫のおり、当地で薬師如来像を彫り、それを祀るために堂庵を建立したと伝えられています。また天慶の乱のときには藤原秀郷がこの寺で平將門征伐を祈願したとされています。
薬師詣でを自分の勤めの一つとしている私にとってはしばしばお参りしたいお寺ですが、將門贔屓の私にとっては敬遠したい寺でもあります。



カメラでは捕らえられませんが、境内の到るところで桜がハラハラと空を舞っています。
長袖のラグビージャージを着ていましたが、暑さもあって腕まくり。腕に花びらが舞い落ちてくればカメラに……と待ち構えていましたが、そうは問屋が卸さない。
帰りは当初上ろうと考えていた、庫裏の裏にある石段を下ります。
東福寺をあとに三分で流鉄の鰭ヶ崎駅へ。ここから終点の馬橋まで電車に乗って、新坂川の残桜を観に行きます。
鰭ヶ崎~馬橋間は営業キロ3・6キロ、運賃は¥170。JRだと新松戸~南柏間(3・8キロ=¥160、スイカなら¥157)に等しいので、もうちょっと高くてもいい(ローカルの私鉄なので)と思うのですが、意外と儲かっているのかもしれません。ただし、流鉄はスイカは使えません。
喉が乾いていたこともあり、ちょっとでも流鉄に利益があるようにと思って、自販機で伊右衛門を購入しました。ここもスイカは使えないみたいです。
やってきたのはこんな電車。西武鉄道のお下がりです。画像では小さくて見えませんが、「さくら」というヘッドマークをつけています。
吊り革にはハート型と最近私が手に入れたばかりのオレンジリング型(赤く写っていますが、これはカメラのせい)。オレンジリングとは認知症高齢者をサポートするボランティアの印。
馬橋駅西口に出ました。左に見える跨線橋は新坂川をまたいでいます。
馬橋駅西口清水広場。そこそこに見応えのある桜でした。

馬橋駅をあとにして歩き始めてから三分ほどで視界に桜並木が入ってくるようになります。ここも盛んに舞い散る花びらです。
かつて ― と、いっても十年以上前 ― 平気で上り下りしていた流鉄&常磐線をまたぐ跨線橋です。今日の体調と東福寺での勢いなら上ることもできるかもしれませんが、向こうへ行く用があるのならともかく、上るためだけに上るという無駄なことはやめておきます。

桜通りと呼ばれる新坂川沿いの径。花びらの舞い散る傍らを流鉄が走り抜けて行きます。こちらは「流星」号。
鳩も花見と洒落たか。
川岸の径はこのまま新松戸駅近くまでつづいていますが、桜並木はこのあたりでおしまいです。
昨日は久しぶりの雨……と思ったら、結構強い雨。風も強く、持っていた傘を差すことができないような悪天候でした。
今朝は一転して、快晴です。ただ、風はかなり冷たい。
慶林寺の河津桜も満開から散り始めへ……。
空には雲一つありません。

境内にある河津桜は葉っぱが目立つようになっていました。
枝垂れ梅が河津桜との選手交代を告げています。
慶林寺裏にある民家の小窓にこんな雛飾りがありました。
ごく普通の民家で、店舗ではありませんが、手づくりのマスクも売っていて、「ピンポンしてください」と書かれているので、チャイムを鳴らせば応対してくれるようです。
明後日は啓蟄。虫たちがモゾモゾと動き始めるように、私も暗闇から這い出さなければなりません。
今日は例年より一日早く訪れた節分です。二月二日が節分に当たるのは1890年(明治三十年)以来、百二十四年ぶりだそうです。
昨日、最高気温を記録したのは夜中の十一時半過ぎという異常。
そして今日は払暁から日の出の時刻にかけて、かなり強い雨。豪雨とか台風頻発という異常気象ではないとしても、こういうプチ異常が多くなってきているように思います。
雨が上がって陽射しは出たものの、北西の空にはこんな不気味な雨雲が残っていました。
日課の慶林寺参拝。毎年立春のころには律儀に花を開く河津桜。参道入口に一本。中ほどに一本。そして境内に一本とありますが、今年はまだだろうと思いながら、境内に足を踏み入れました。
境内の河津桜です。

見上げて眺め回したところ、一輪……そしてもう一輪。やっぱり今年も律儀に咲いてくれていました。
あまり通ることのない径へ遠回りして帰ったら、菜の花畑がありました。春なんですね。











