関東には数少ない一遍さんのお寺を訪ねました。北松戸にある本福寺というお寺です。
お寺があるのは台地の上で、中世の城館・上本郷城があったと考えられているところです。で、お寺巡りの前に城趾の探索。
北松戸駅で降りて国道6号線沿いを歩き、上本郷交差点で左に折れて坂を上ります。この坂は「寮の坂」と呼ばれていますが、名の由来は不明です。
坂を上り切ったところ、スイッチバックする形でさらに坂を上ると、本覚寺という日蓮宗の寺がありました。元禄十二年(1699年)の創建と伝えられ、松戸ではもっとも標高の高いところにある寺だそうです。
この寺が建つのは台地の先端部です。ここが上本郷城の主郭部だったのではないかと想像されていますが、周辺は宅地化されて、城があったことを偲ぶことのできるものは何もありません。
例によって千野原靖方著「東葛の中世城郭」をひもときましたが、城の由来もはっきりしていません。
建武期、千葉家十一代・貞胤(さだたね)が築き、戦国期には大谷口城の高城氏の支配下に置かれたようですが、城主が誰であったのか、どのように機能したのかは不明です。
台地の端っこにあるので、さすがに境内からの眺望は利きます。
スイッチバックした場所に戻って道なりに進むと、本福寺門前に到りました。本覚寺~本福寺の道にも城趾を偲ばせるものは何もありません。
本福寺は鎌倉時代の嘉元元年(1303年)、ないしは元応元年(1319年)の開山。開基は一遍さんの一番弟子・他阿(たあ)上人。
境内に建つ開祖・一遍上人の銅像。
「一遍聖絵」にある肖像画や総本山・清浄光寺にある像より若々しいお顔をしています。
遊女たちを連れて全国を遊行されたという脚は、肖像画ではもっと丈の短い着物を着て、臑もゴツゴツしていますが、この銅像はどちらかといえば、ふっくらとしています。
一遍さんに関してはいろいろ物語りたいものがありますが、いずれ機会を見て……。
同じく本福寺境内にある切られ地蔵。
伝説によると、昔、近くの寺で盆踊りがあったとき、このあたりでは見かけぬ若者がきて、巧みな踊りを見せたそうです。なかなかの男前にも見えたので、娘たちは夢中になってしまいました。
すると、おもしろくないのは村の若い衆です。若い衆の一人が刀で切りつけると、カーンという金属音がして、若者は忽然と姿を消してしまいました。
翌朝、若い衆が境内へ行ってみると、石地蔵の胸に生々しい刀傷があって、驚くとともに恐れ入ったという話です。
上本郷七不思議という言い伝えがあって、この伝説はそのうちの一つです。
http://www33.ocn.ne.jp/~maty/ensen/kirare/kirare1.html
お地蔵様には顔から腹にかけて刀で切ったような傷があるのですが、つたない私のテクニックとコンパクトデジカメでは確認できないかもしれません。
門前にある「吉田松陰脱藩の道」の碑。
嘉永四年(1851年)、吉田松陰が江戸藩邸を抜け出して(脱藩して)、東北遊歴に出たとき、この道を通ったという記念碑です。
格別松陰を評価しない(というか、したくない)私としては、一人の人間が通ったというだけで伝説になるのか、と呆れるような思いですが、まあ、通ったのは事実らしい。通っただけでなく、本福寺で一夜の宿を借りたようで、境内には松陰が泊まったという説明板までありました。
その松陰が上ってきたのであろう山道を下りました。いまは石段に換わり、手すりもつけてありますが、江戸末期は樹木の鬱蒼と茂った暗い山道だったのではないでしょうか。

石段を下り切ったところにカンスケ井戸がありました。
「カンスケ」というのは屋号らしいのですが、その家が絶えてしまったいまとなっては、どんな家であったのかはっきりしないそうです。

そこからしばらく歩くと、上本郷第二小学校脇に宮ノ下湧水がありました。宮ノ下の「宮」とは台地の上にある風早神社のことです。
遠くにいても、流れ出た水が下水溝に落ちるゴボゴボという音が聞こえます。見た限りでは水量も豊かで清涼そうなのに、下水に流してしまうだけというのはいかにももったいない。
このあと上本郷の駅前を抜け、天神山古墳前を通って、またスーパー銭湯・湯楽の里(ゆらのさと)へ行ってきました。
湯楽の里前にある工務店。
店主か? 不況の影響なのか、随分寝苦しそうな格好で昼寝をしていたので、断わりもせず失礼してカシャリと一枚。
到着したのが午後二時と早かったせいか、スーパー銭湯は空いていました。ほんの数分間ですが、私が露天に入っていたときは、広い露天風呂を私が独りで占領、という状態だったほどです。
001番の下足箱は空いていなかったので、私の誕生日の番号を使いました。
この日、これまで入ったことがなかった露天の泡風呂に入りました。前四回はいつも入っている人があって、空かなかったのです。
さらに壷湯(二つ並んでいます)も一人で占領。
前回は前に入っていた人の体格がよかったため、満々と貯まったお湯をザバーッと溢れさせることができませんでしたが、今回は矢継ぎ早に二つをハシゴして、ザバーッ、ザバーッ……と。
この壺湯はとくに子どもにはうれしいようで、空くとサッとばかり走って行くので、いつも先を越されてしまいます。子どもと争ってもなぁ、と自重するので、なかなか入ることができません。
これでサウナを除いてすべての湯を体験しました。入浴時間は四十分。
↓この日歩いたところ。
http://chizuz.com/map/map63441.html
※一月二十四日(日曜日)の残念。
ラグビートップリーグプレーオフ準決勝・トヨタ自動車は対三洋電機戦。
相手司令塔・ブラウンが前試合の暴力行為で出場停止。小憎らしい奴がいないのだから、絶好のチャンスでしたが、さすがに三洋電機の壁は厚い。後半追い上げて、21対25と4点差まで迫りましたが、そこまで。あえなく終了のホイッスルを聞くこととなりにけり。










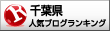


































 を注文。
を注文。






























