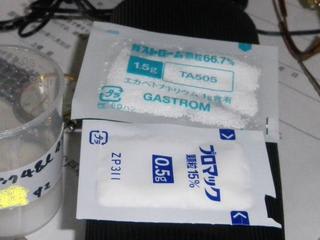今日大晦日。
一年の垢を落としに湯楽の里(ゆらのさと)というスーパー銭湯に行ってきました。
我が庵は古いマンションの一室で、しかも六階のせいか、水量が乏しいので、お風呂の湯が溜まるまで半端でない時間がかかります。
休日ならともかく、勤めから帰ってきてお風呂に入ろうと思っても、湯を張り終えるまで待つ時間を考えると苛々するだけなので、シャワーで汚れを落とすだけ、ということになりがちです。そのシャワーも水量が乏しい。
というわけで、湯船に浸かって身体を温める、という極楽には長らくご無沙汰でした。

新松戸の隣駅・新八柱で新京成電鉄に乗り換えて一つ目、みのり台という駅で降りました。
スーパー銭湯はみのり台駅からおよそ1キロ。歩いて十数分と、いささか距離があります。
強い向かい風に吹きっさらしになりながら、身体が冷えてしまったころにようやく到着しました。

これまで利用したこともないのに、見ずてんで十枚綴り4900円也の回数券を買いました。
入浴料は平日だと620円、今日大晦日と正月三が日は特定日とやらで750円になるところ、回数券があれば一回490円で入れるのです。
お買い得、と思って衝動買いしてしまいましたが、行きたくもないのに、券を無駄にしたくないばかりに行くハメになるのか、電車賃を使ってまで行くのは莫迦らしいと棄ててしまうことになるのか。入ってみないことには決まりません。
私と同じように、帰ろうにも帰る故郷のない人が多いのか、ロビーの長椅子は空席のない情況でした。
浴室に入ると、入口に近いほうから、高温のサウナ、低温のサウナの二つ。浴槽は水風呂、薬湯、普通の湯(白湯)、ジャグジーの四つ。窓の外には露天、と並んでいますが、想像していた以上に狭く、狭いのは我慢するとしても、江戸ッ子には湯温の低いのが物足りない。
とはいえ、私はそろそろ一か月が経とうとはいうものの、退院直後ではあるし、輸血後でもあります。のぼせがくるようなら即座に上がるべし、と自分に言い聞かせて、恐る恐る湯船に身体を沈めました。
しばらく浸かっていると、ほんわかとした気分になってきました。子どもたちもいましたが、騒いだりはしゃいだりする子がいないのがいい。ゆったりと身体を伸ばしてリラックスできました。
普通の湯に浸かったあと、身体と髪を洗って、今度はジャグジーに……。
西伊豆、草津、四万、箱根、湯河原、熱海、房総と近場ばかりながらも、温泉体験は豊富なほうですが、血の巡りが悪い体質なのか、身体の芯から温まったという思い出はほとんどありません。その上、せっかちという気質なので、腰湯で長時間入浴するのも苦手です。
草津でも熱海の駅前でも、足湯だけで身体がポカポカ温まる、という人がいますが、私にはそういう体質の人がいる、ということが信じられません。
熱い湯にザブッと浸かって、実際は身体の芯まで温まっているのかどうかわからないけれども、肌だけは真っ赤にして出てくる、という風呂の入り方が理想なのですが、ジャグジーもぬるめでした。
それでも脚を伸ばして入れる風呂はさすがにリラックスします。
お湯の中で自転車を漕ぐ真似をしたり、エイエイッと身体をひねってみたり……。お風呂、とくに寒い季節のお風呂は極楽です。

胃潰瘍をやっていなければ、湯上がりはビールというところですが、子どものころを思い出して、コーヒー牛乳を飲みました。
いつの間にかガラス瓶ではなく、プラスチックの容器に変わっています。蓋も専用の針をブチュッと刺して開けるタイプではなく、プルトップ型に変わっていました。
何よりも変わったのは量が少なくなっていること。
売っているのは自販機です。自分で冷蔵ケースから取り出し、番台にお金を払って飲む、というシステムが懐かしい。
一度上がって休憩し、もう一度入ろうと思っていましたが、さすがに湯中りしたものか、疲れてしまったので、三十分強で帰ることにしました。
往きは強い風が吹いていましたが、帰りは風も収まって、それほど寒いとは感じません。
新松戸まで戻って、明日元旦の雑煮用に小松菜と鶏肉を買おうとダイエーに行きました。が、小松菜のコーナーだけ空っぽでした。
師走のどん詰まりとはいえ、まだ七時前という早い時間です。ほうれん草と青梗菜はたっぷりとありましたが、青菜であればいいというものぢゃあ、お雑煮はない。
何も買わずにさっさと退散して、近くにある地元スーパーに行ってみました。見落としたのかもしれませんが、ここには小松菜のコーナーがなかった。仕方がないので、野菜類は買わないと決めている新松戸駅前の某スーパーに戻る形になりました。
この店は、たとえば私の好物のじゃが芋を買うと、一袋に一つか二つは芯の部分が腐ったものが混じっています。ほかには取り立てて不具合(見た目の)はないので、駅前という便利さもあってちょくちょく買い物をしますが、野菜だけは買わないと決めているのです。
行ってみると、案の定というか、ありがたいというか、小松菜は払底していました。これで、明日雑煮をつくるのはサッパリと諦めがつきました。しかし、普段なら絶対にしない無駄歩きをしたせいで、身体はすっかり冷え切ってしまって、折角温まったあとだったのに、くしゃみをしながら帰ることとなりました。