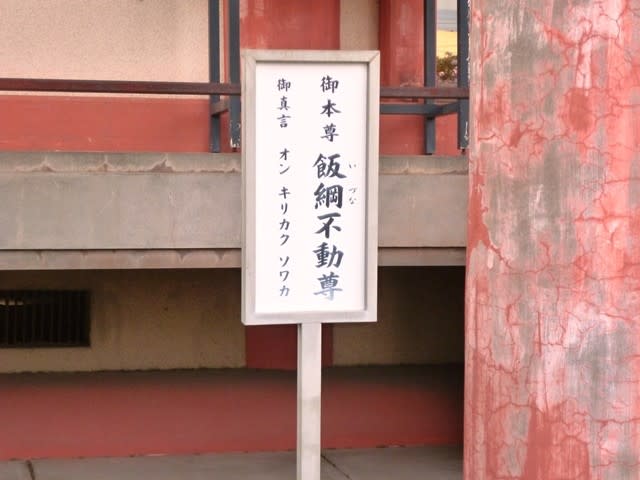坂川は流山市から市川市まで16キロ。昔は逆川といって、文字どおり逆流することがあったので、その名がつけられたそうです。
北小金に棲んでいたときに比べて、散歩に出ることが尠なくなりました。新しく引っ越した新松戸の街は、田畑や野原の多かった北小金とは違い、マンションばかりで、歩いていても味気ないからです。自然に触れようとすると、坂川まで行かなくてはなりません。
我が庵から一番近い坂川河畔は関の橋という橋が架かっているあたりです。我が庵からは800メートルほど、歩いて八分で着きますが、その間は住宅街なので、刺激が乏しい。
坂川周辺を中心に歩いていたら、これまで特段気にしなかったことが気になるようになりました。それは橋名板=橋の名や渡る川や鉄道などに一定の決まりがあるということでした。そこで関の橋を渡って河口まで橋名板をチェックしながら、坂川放水路の右岸を歩いてみることにしました。

スタート地点・橋を渡る前の関の橋の橋名板=上流側(画像上)と下流側です。

橋を渡ると、下流側に橋の名(漢字表記)と橋が架けられた年月(上流側)。
必ずしも決まりはないようですが、その道路の起点に当たる側の左に橋名(漢字表記)、右に交差する河川や鉄道、道路など。橋を渡ると(道路の終点側から見ることになります)、左に竣工年月、右にひらがな表記の橋名、というのが多いようです。
関の橋の場合は、漢字表記とひらがな表記の橋名が逆でした。
中央に見えるのは排水機場。川の流れは変わりませんが、坂川本流はこの排水機場で左手に曲がり、川自体はゆるくカーヴを描くだけで、何一つ変わりはないのに、坂川放水路と名を変えます。
正面から眺めた排水機場です。

排水機場を過ぎると、かねぎりばし(金切橋)。

なかみちばし(仲道橋)。

いなりおおはし(稲荷大橋)。
十六日前に訪れた金蔵院を再訪。今日は境内にはお邪魔せず、山門前で拝礼するだけで通り過ぎます。

金蔵院の西側を流れ、坂川放水路に注ぐ神明堀の水門としんめいおおはし(神明大橋)の橋名板。金切橋から十分。
雨の降る心配はなさそうなものの、青空が顔を覗かせているのは一か所だけで、あとは分厚い雲に覆われていました。
神明大橋から二分。流山街道を横切ります。橋はもんとおおはし(主水大橋)。
流山街道はこの地域一番の主要道路なので、交通量が多い。にもかかわらず信号がないので、渡るチャンスはなかなかやってきません。
流山街道を渡り終えると二分。もんとなかはし(主水中橋)です。
河口が近づいてきて、松戸排水機場も大きく見えるようになってきました。
坂川と坂川放水路の水を江戸川に排水する施設です。最大排水量は毎秒100立方メートル。平均的な25メートルプール(600立方メートル換算)を六秒で満たしてしまう計算になりますが、この計算でいいのでしょうか。
水門です。
主水中橋から二分。もんとはし(主水橋)。この橋までくると、川沿いの径は突き当りになってなくなります。
ほとんど人も通らないようなところに自販機がありました。素人目には売れそうもないと思えますが、撤去されないところをみれば、それなりに売れるのでしょう。
江戸川堤防に上がることのできる道がありました。

堤防を上り切ったところに河畔へと下る径がありました。その先に先ほどは後ろから見た水門。
画像の右手から左手に流れ下って行く江戸川と坂川放水路が合流するところです。坂川放水路はここでおしまい。
こういう標識があるのに、バイクを走らせるスットコドッコイがいました。
東京湾の江戸川河口から25キロ地点。遠望できる鉄橋はつくばエクスプレスです。