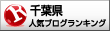今日も慶林寺にお参りに出ます。
本尊の薬師如来に、私と繋がりがある人々の無事息災を祈ります。
参道では著莪(シャガ・射干とも)が咲き始めていました。中国原産、アヤメ属アヤメ科の植物。
本来は四月が開花期。季節はほぼ四月ではありますが、まだ三月。桜と同じように、この花も今年は開花が早い。
参道の中ほどにある御衣黄(ギョイコウ)桜です。
例年なら開花は四月中旬から下旬ですが、蕾のふくらみ具合を見ると、この花も今年は早そうです。
慶林寺の河津桜はすっかり葉桜になってしまいました。
慶林寺をあとに、今日は常磐線に沿って歩きます。あまりにも桜の開花が早かったので、香取神社の桜を見ていなかったからです。
慶林寺前から北小金駅を過ぎ、常磐線の線路伝いに歩くと、径は富士川が形づくる谷に向かって下り坂。渡るところでは富士川は暗渠になっているので、川は見えません。
見えない富士川を渡ると、流山市です。今度は径は上り坂。途中から梨畑が拡がります。
梨畑が見えてくると、目に入ってくるとは想像していなかった白いものが見えました。
こちらも早い。
この時点では例年の梨の花の開花がいつごろであったのか、わかっていませんでしたが、白いものが目に飛び込んできた瞬間、とっさに早ッ! と感じてしまいました。
どの樹を見ても、花が咲くのは下と先端の部分の花が先で、枝の中ほどはまだ蕾です。
高台を上り切ったあと、見下ろしてみました。
同じ畑ですが、種類が異なるのでしょうか。こちらはまったく花がありません。
毎年、梨の花が咲き出すころに見にきているわけではありませんが、たまたま六年前、花が咲き始めたころをブログに載せていました。この年の開花は今年よりおよそ二週間も遅い四月十二日でした。
梨の花が咲いたよ
この高台にきた目的の香取神社の桜です。この花を見て、今日の散策は終了です。