関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ Kalafina の teaser?
■ Kalafina Anniversary LIVE 2025 teaser 3
どういう意図でUPされたかわからないが、これがオフィシャルだとすると、ふたたびKalafina&梶浦由記さんのタッグが復活するかもしれぬ。
■『Break out of your bubble』 - Little Glee Monster 10th Anniversary Live(2024.10.20)
リトグリのこの曲はかなりいいと思う。
でも、梶浦サウンドとはあきらかに違う。とくにコーラスワーク。
やはり、日本の女性ヴォーカルの質を保っていくには梶浦サウンドは不可欠だと思う。
■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance
深みのあるKEIKOの中低音、音域広くきらびやかなJoelleの声質。
KAORIはふつうのユニットだったら楽勝でソプラノリードとれるが、その上をいく貝田さんのスーパーハイトーン。
4人のことなる個性を、ひとつにまとめあげられる梶浦さんの楽曲。
■ Revo(Sound Horizon)&梶浦由記(FictionJunction) - 砂塵の彼方へ....
FictionJunction&Sound Horizonの奇跡のコラボ。
世界に誇っていいレベルだと思う。
■ into the world - kalafina
おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。
完璧な女神降臨状態。
FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。
メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。
そして、完璧なステージング。
音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。
このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。
■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来
どうしてこんな音像を生み出せるのか。
知名度低くてもメガヒットなくても、邦楽の至宝であることまちがいなし!
【関連記事】
■ 伝説のユニットkalafina
どういう意図でUPされたかわからないが、これがオフィシャルだとすると、ふたたびKalafina&梶浦由記さんのタッグが復活するかもしれぬ。
■『Break out of your bubble』 - Little Glee Monster 10th Anniversary Live(2024.10.20)
リトグリのこの曲はかなりいいと思う。
でも、梶浦サウンドとはあきらかに違う。とくにコーラスワーク。
やはり、日本の女性ヴォーカルの質を保っていくには梶浦サウンドは不可欠だと思う。
■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance
深みのあるKEIKOの中低音、音域広くきらびやかなJoelleの声質。
KAORIはふつうのユニットだったら楽勝でソプラノリードとれるが、その上をいく貝田さんのスーパーハイトーン。
4人のことなる個性を、ひとつにまとめあげられる梶浦さんの楽曲。
■ Revo(Sound Horizon)&梶浦由記(FictionJunction) - 砂塵の彼方へ....
FictionJunction&Sound Horizonの奇跡のコラボ。
世界に誇っていいレベルだと思う。
■ into the world - kalafina
おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。
完璧な女神降臨状態。
FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。
メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。
そして、完璧なステージング。
音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。
このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。
■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来
どうしてこんな音像を生み出せるのか。
知名度低くてもメガヒットなくても、邦楽の至宝であることまちがいなし!
【関連記事】
■ 伝説のユニットkalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)
■ 同-21 (C.極楽寺口-4)
■ 同-22 (C.極楽寺口-5)から。
62.龍護山 満福寺(まんぷくじ)
公式Web
鎌倉市腰越2-4-8
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
司元別当:
札所:新四国東国八十八ヶ所霊場第84番、相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番
稲村ヶ崎~七里ヶ浜周辺に寺社は少なく、霊光寺(日蓮宗)は参拝していますが御首題はいただけず、顕証寺(本門佛立宗)の御首題はWeb検索でヒットしません。
よって腰越にエリアを進めます。
満福寺は源義経公・武蔵坊辨慶ゆかりの寺院です。
公式Web、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
天平十六年(744年)行基の開山と伝わる古刹で、古義真言宗手広村青蓮寺末といいます。
御本尊は行基御作の薬師如来、弘法大師御作の不動尊を安ずるとあります。
史料の多くは義経公とのゆかりに紙面をさいています。
源義経公(1159-1189年)は、鎌倉幕府初代将軍源頼朝公の異母弟で、日本史上もっとも著名とみられるその生涯については、ここではふかくなぞりません。
当山に関連ある事柄のみ、簡単に追ってみます。
治承八年(1184年)2月、摂津一ノ谷で平氏を破った義経公は京に凱旋すると後白河法皇から厚遇を受け、頼朝公の許可を得ずして法皇から検非違使・左衛門少尉の任官を受けました。
頼朝公はこれを怒り、義経公の平氏追討の任を解きました。
しかし、義経公解任後の戦況は思わしくなく、元暦二年(1185年)再び義経公を平氏追討に起用するや、義経公は讃岐屋島で見事な勝ち戦をおさめ、同年3月、長門壇ノ浦で平氏を滅ぼしました。
しかし同年4月、頼朝公は朝廷から勝手に任官を受けた義経公麾下の東国武者らを罵り、東国への帰還を禁じました。
平氏追討で義経公を補佐した梶原景時からは、義経公が平家追討の功を誇るあり様が書状で頼朝公に伝えられました。
軍監・景時の意見を聞かず独断専行で軍を進めたこと、兄の範頼公の所轄である九州へ無断で進出したことなども伝えられ、頼朝公の不興を買ったともいわれます。
同年5月、義経公は壇ノ浦で捕らえた平宗盛・清宗父子を護送して京を立ち、鎌倉に凱旋しようとしました。
しかし義経公のあり様に不審を抱く頼朝公は鎌倉入りを許さず、宗盛父子のみを鎌倉に入れ、義経公は腰越の満福寺に留め置かれました。
5月24日、義経公は満福寺で頼朝公に対し叛意のないことを切々と示す書状をしたため、頼朝公の側近大江広元に託しました。
これが有名な「腰越状」で、義経公の側近・辨慶が筆を執ったという説もあります。
頼朝公は義経公を弟として正当に処遇し、その実力も認めていましたが、義経公の神がかった武略と声望の高まり、そして法皇との個人的な結びつきは、東国での武家政権樹立をめざす頼朝公にとって脅威となったことは想像に難くありません。
また、義経公が京で平氏の捕虜である平時忠の娘(蕨姫)を娶ったことも、頼朝公の疑念を深めたという見方もあります。
6月9日、頼朝公が義経公に宗盛父子と平重衡を伴わせて帰京を命じると、鎌倉入りを果たせなかった義経公はこれを恨み、「関東に怨みを成す輩は、義経に属くべき」と言い放ち、これを聞いた頼朝公は義経公の所領を没収したと伝わります。
なお、『愚管抄』、延慶本『平家物語』などは、義経公はじつは鎌倉入りを果たし頼朝公と対面している旨記しているようで、「腰越状」も後世の偽作との見方があります。
8月16日の除目で義経公は頼朝公の推挙により伊予守を拝任したといい、この時点では頼朝公と義経公の決裂は決定的ではなかったという見方があります。
しかし、義経公は伊予守拝任後も朝廷から頼朝公に無断で受けた検非違使・左衛門少尉を離任せず、これにより頼朝公との関係はついに破綻したという説もあります。
頼朝公は義経公の動向を監視すべく梶原景時の嫡男・景季を京に遣わすと同時に、木曽義仲に与力した叔父・源行家の追討を要請しました。
10月、義経公の行家同心を断じた頼朝公は義経公討伐を決意し、刺客として京へ送られた土佐坊昌俊らは堀川の義経邸を襲いました。(堀川夜討)
しかし義経公に行家勢が加勢して襲撃は失敗。
義経公は捕らえた土佐坊から頼朝公の命による襲撃と聞き及ぶと、行家と謀って頼朝公打倒の兵を挙げ、後白河法皇より頼朝公追討の院宣を得ています。
しかし、義経公への与力は思うように集まらず勢いなしとみるや、今度は法皇は義経公追討の院宣を出しています。
このあたりの前後関係や頼朝公の関与については諸説ありますが、義経公が政治に長けた法皇の動きに翻弄されている姿がうかがわれます。
11月1日、頼朝公率いる義経公追討軍が駿河国黄瀬川に達すると、義経公らは京を落ち船で九州へと向うも、暴風で難破して摂津に押し戻されました。
7日には伊予守、検非違使・左衛門尉などの官職を解任され、義経公と行家捕縛の院宣が下されました。
義経公は郎党や愛妾の静御前を連れて吉野に身を隠しましたが、ここでも追討を受け京に潜伏。
文治二年(1186年)になると叔父・行家、佐藤忠信、伊勢義盛などの郎党もつぎつぎと討ち取られました。
義経公の関東での後見人として義父の河越重頼がいましたが、重頼と嫡男重房も殺害され関東での後ろ盾も失いました。
文治三年(1187年)京に潜み切れなくなった義経公は、藤原秀衡を頼り奥州・平泉へと赴きました。
藤原秀衡は義経公を盛り立てる意思をもっていましたが文治三年(1187年)10月に病没。
後継の泰衡は義経公を守り抜くことができず、文治五年(1189年)閏4月ついに義経公が拠る衣川館を襲撃、義経公や辨慶などの郎党は奮戦しましたがことごとく討死し、義経公はここに自害しました。(衣川の戦い)
享年31と伝わります。
義経公の首は鎌倉に送られ、和田義盛、梶原景時らによって首実検が腰越の浦で行われたといいます。
このことからも、腰越は義経公とゆかりをもつ地といえます。
満福寺には辨慶が書いたという「腰越状」の下書きとされる書状が所蔵され、山内には辨慶の腰掛石や手玉石など、義経公・辨慶ゆかりの品が遺ります。
寺前の池は、辨慶が「腰越状」を書く時に墨摺りの水を汲んだことから「硯池」と呼ばれ現存しています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
満福寺
満福寺は、腰越村の中にあり、龍護山と号す。眞言宗なり。
開山行基、本尊薬師 行基作・不動 弘法作
此寺地は、昔源義経、宿せられし所なりと云ふ。【東鑑】に、元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、如思に朝敵を平げ訖ぬ。剰へ前内府平宗盛を相具して参上す。其賞兼て不疑處に、日来不儀の聞へ有るに依て、忽御気色を蒙り、鎌倉中に入られず。腰越の驛に於て、徒に日を捗るの間、愁鬱の余に、因幡前司廣元に付して、一通の疑状を頼朝へ奉つるとあり。其状の下書也とて、今寺にあり。辨慶が筆跡と云。状中の文字、【東鑑】に載たるとは所々異なり。或人云、新筆なり。辨慶が筆には非ずと。
硯池
寺の前にあり。相伝ふ義経の命にて、辨慶疑状を書し時、硯水を汲たる池なりと。池の端に辨慶が腰懸石とてあり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
萬福寺
腰越村の内なり。龍護山と号す。古義眞言宗、同國手廣青蓮寺末なり。
開山行基、本尊薬師如来 行基作。弘法大師作の不動尊を安ず。
此寺、義経の宿陣せられし事をいひ伝ふ。元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、思ひの如く朝敵を平げ、剰へ屋島の内府平宗盛を相具して参り、其賞兼て疑はざる處に、不儀の聞へ有に依て、忽御気色を蒙り、鎌倉へ入られず、腰越の驛に於て徒に日を捗るの間、愁鬱の余り、因幡前司廣元に附して、一通の疑状を幕府え奉るといふ。其状の下書なりとて、今も此寺にあり。辨慶が筆なりといひ伝ふ。文書中【東鑑】に見えしとは異なる所もあり。辨慶が書けること覚束なし。
硯池
寺の前庭にあり。寺伝に、義経の仰に依て、辨慶が疑状を書たる時、硯水を汲し池といふ。又池の端に辨慶腰かけ松と名附るもあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(腰越村)満福寺
龍護山醫王院と号す。古義眞言宗手廣村青蓮寺末。
開山は行基、中興は高範(承安三年(1173年)三月十六日寂す)
本尊は薬師なり 長三尺三寸、行基作、同作の日月光、十二神もありしが、寛文中、回禄に烏有せしとぞ。
不動 弘法作長八寸
十一面観音 同作、長二尺五寸
彌陀 定朝作、長一尺五寸 等を安ず。
文治元年五月延尉義経頼朝の不審を蒙りて鎌倉へ入られず、当所に滞留す。
当時●止宿の所なりと云ふ
此時大江廣元に就て呈せし疑状の草案なりとて今に蔵せり。古文書部に詳載す、世に腰越状と称す是なり、辨慶が書記せしと伝ふれどおぼつかなし
【寺宝】(抜粋)
薬師書像一幅 弘法筆
地蔵堂 天神社 辨天社
硯池
本堂の前にあり。是辨慶疑状を書し時、池水を汲て硯池に滴す故に此名ありと云ふ、池辺に腰掛石といふあり、辨慶が腰を掛し所といふ。
■ 山内掲示
龍護山満福寺と号し、開山は行基(668-749)と伝えられ、本尊は薬師如来像です。源義経(1159-89)が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を汲んだといわれる硯池、腰掛石があります。-古義真言宗-
■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会・鎌倉文学館)
源義経と腰越
鎌倉時代前期の武将、源義経は、幼名牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。
治承四年(1180)兄頼朝の挙兵に参じ、元暦元年(1184)兄範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。帰洛後、洛中の警備にあたり、後白河法皇の信任を得、頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉となったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、讃岐屋島、長門壇ノ浦に平氏を壊滅させた。
しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの、鎌倉入りを拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため大江広元にとりなしを依頼する手紙(腰越状)を送った。
「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。
さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあひ具して、関東へ下向せられけるとき、腰越に関を据ゑて、鎌倉へは入れらるまじきにてありしかば、判官、本意なきことに思ひて、「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ゐられざれば、判官力におよばず。
その申し状に曰く、
源義経、恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに選ばれね勅宣の御使として朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)
しかし、頼朝の勘気は解けず、かえって義経への迫害が続いた。義経の没後、数奇な運命と悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。
中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。
■ 現地掲示(義経宿陣之趾/鎌倉市青年団)
文治元年(皇紀一八四五年) 五月
源義経朝敵ヲ平ラゲ 降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ凱旋セシニ
頼朝ノ不審ヲ蒙リ 鎌倉二入ルコトヲ許サレズ
腰越ノ驛二滞在シ 鬱憤ノ餘
因幡前司大江廣元ニ付シテ一通ノ歎状ヲ呈セシコト東鑑ニ見ユ
世ニ言フ腰越状ハ 即チコレニシテ
其ノ下書ト傳ヘラルルモノ満福寺二存ス
-------------------------
江ノ電「腰越」駅からもほど近く、駅前通りを南東に進んだところが参道入口。
ここにサイン類と「義経腰越状旧跡 満福寺」の寺号標があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口のサイン類
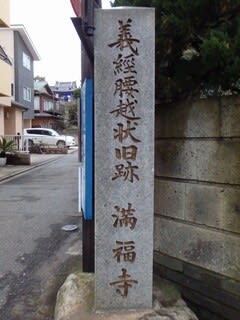

【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 江ノ電と参道階段
ここから、江ノ電の踏切の向こうに山門と鐘楼、そして本堂の屋根が見えます。
踏切遮断機のすぐ脇から山門階段。江ノ電の線路に至近で、撮り鉄さんにはたまらないスポットでは?


【写真 上(左)】 幟
【写真 下(右)】 参道階段
階段脇に「義経腰越状旧跡 満福寺」の幟がはためき、雰囲気が高まります。


【写真 上(左)】 参道階段すぐ下に江ノ電
【写真 下(右)】 山門
階段の先に構える山門はおそらく入母屋屋根銅版葺の四脚門で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、梁上に四連の斗栱、軒に二軒の垂木を備えた豪壮なもの。
見上げに山号扁額、大棟には清和源氏の紋「笹龍胆」を掲げています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門の寺号標


【写真 上(左)】 「義経宿陣之趾」の石碑
【写真 下(右)】 鐘楼
山門右手には、鎌倉市青年団建立の「義経宿陣之趾」の石碑。左手には鐘楼。
山門そばにある「笛供養」の碑は、笛を愛した義経公にちなむものと思われます。
「笛供養」の碑のよこには、ぼけ封じ祈願仏(おそらく地蔵尊と思われる)が御座します。
さほどの階段ではないのにかなり高低差を稼いでいるらしく、山内からは相模湾が見渡せます。


【写真 上(左)】 「笛供養」の碑とぼけ封じ祈願仏
【写真 下(右)】 山内からの相模湾


【写真 上(左)】 大師堂と札所碑
【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-1
山内には大師堂があり、こちらが弘法大師霊場の拝所とみられます。
山内には相州二十一ヶ所霊場の札所を示す碑や板がいくつかあります。この霊場の札所標はあまり目にることがないので、これは貴重です。


【写真 上(左)】 相州霊場札所碑-2
【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-3
山門くぐって正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。向拝上に端正な軒唐破風をおこしています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、頭貫から中備にかけて、じつに8つの斗を置いています。
身舎側に海老虹梁、中備の彫刻は「腰越状」書き上げの構図と思われます。


【写真 上(左)】 中備と兎の毛通しの彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額

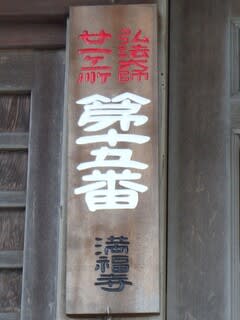
【写真 上(左)】 相州霊場札所板-1
【写真 下(右)】 相州霊場札所板-2
その上兎の毛通しは朱雀の彫刻か、さらに唐破風上の鬼飾りには「笹竜胆」の紋が輝いています。
向拝正面桟唐戸の上には寺号扁額や相州二十一ヶ所霊場の札所板が掲げられ、見どころの多い本堂てす。


【写真 上(左)】 腰越状の石像と本堂
【写真 下(右)】 腰越状の石像
本堂向かって左には、義経公と辨慶の石像。辨慶が筆を執っているので、おそらく腰越状をしたためている場面と思われます。
その横に「弁慶の腰掛石」。
訪れたときは、マスコット?のおネコちゃんが石のうえに座り込んでいました。
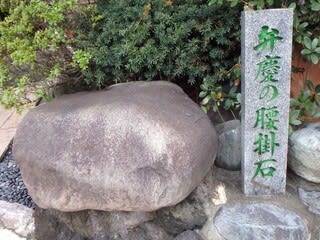

【写真 上(左)】 弁慶の腰掛石
【写真 下(右)】 おネコちゃん
本堂向かって右には慈悲観音立像と「弁慶の手玉石」。
本堂を拝観(有料)すると、腰越状(の下書き?)、義経公や静御前の襖絵、弁慶仁王立ちの絵などが間近で拝せるようですが、筆者は拝観しておりません。


【写真 上(左)】 弁慶の手玉石
【写真 下(右)】 硯の池(右)と義経公手洗の井戸(左)
本堂右手の山側には鎌倉七里ヶ浜霊園へ向かうトンネルがあり、その右手に「硯の池」、左手には義経公手洗の井戸があります。
「腰越」駅にも案内看板があり、道すがらもいくつかの案内サイン、参道まわりの幟、さらには腰越状の石像を置かれるなどサービス精神?が感じられるお寺さまです。


【写真 上(左)】 サイン-1
【写真 下(右)】 サイン-2
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。
こちらはかなり渋めの霊場札所を兼務されています。
相模国準四国八十八ヶ所霊場は湘南エリアの弘法大師霊場で文政四年(1821年)開創と伝わる歴史ある霊場ですが、現況は廃寺や札所異動も多く、御朱印はいただきにくい霊場となっています。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
小田急武相三十三観音霊場は小田急電鉄が主導して沿線の寺院を札所選定した観音霊場です。
この霊場の札所印はなかなかレアですが、他霊場を兼務される札所が多く、御朱印じたいの拝受は比較的容易です。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
〔 満福寺の御朱印 〕
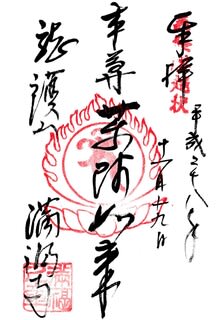
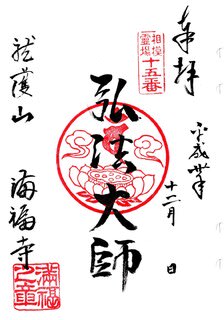
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
これまでに拝受している御朱印は以上の2点ですが、Web上では「千手観音」(新四国東国八十八ヶ所霊場第84番)、「十一面観音」(おそらく小田急武相三十三観音霊場第33番)の御朱印もヒットします。
63.小動神社(こゆるぎじんじゃ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
神奈川県神社庁Web
鎌倉市腰越2ー9ー12
御祭神:健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊、歳徳神
旧社格:村社、旧腰越村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:浄泉寺(鎌倉市腰越、真言宗大覚寺(青蓮寺)末)
小動神社は八王子宮(はちおうじのみや)とも呼ばれ、源頼朝公の側近・佐々木左兵衛尉盛綱の勧請と伝わります。
鎌倉公式観光ガイドWeb、神奈川県神社庁Web、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
佐々木盛綱(1151年-)は、近江国佐々木庄に拠った宇多源氏の棟梁・佐々木秀義の三男です。
秀義は平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公に従うも敗れ、一門は関東へ落ちのび渋谷重国の庇護を受けました。
秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。
三男盛綱は16歳で伊豆國に配流された頼朝公に仕えました。
頼朝公の信任篤く、治承四年(1180年)8月、平氏打倒を決意した頼朝公に挙兵の計画を告げられたとも。
治承四年(1180年)8月の山木館襲撃に加わり、加藤景廉とともに山木兼隆の首を獲ったといいます。
石橋山の戦いののちは渋谷重国の館に逃れ、頼朝公が兵を集めて鎌倉に入ると再び頼朝公の麾下に参じ、富士川の戦いでも戦功をあげています。
元暦元年(1184年)、盛綱は平氏追討のため備前國児島に入り、平行盛ら五百余騎が籠もる城郭をわずか六騎で攻め落としたといいます。(藤戸の戦い)
平家滅亡後も頼朝公の側に仕え、公の寺社参詣や儀式、あるいは上洛の随兵としてその名が多くみえます。
頼朝公没後の建久十年(1199年)3月に出家して西念と号しました。
なお、群馬県安中市磯部の松岸寺には佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があります。
詳細は→こちらの記事(■「鎌倉殿の13人」と御朱印-4)をご覧ください。
小動(こゆるぎ)の岬は江ノ島をのぞむ風光明媚な地で、この地に聳える「小動の松」は風もないのに枝葉が揺れ、常に妙音を琴瑟の如く発していたためこの銘木にちなみ「小動」を地名にしたといいます。
『八王子宮縁起』「鎌倉公式観光ガイドWeb」によると、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱は江の島弁財天への参詣の途中に当山に詣で、「小動の松」のあたりを散策して佳景を楽しみ、まことに神徳の地と詠嘆したそうです。
「当山に詣で」とあるので、当地にはすでに寺社が存在していた可能性があります。
現地掲示の『由緒略記』には「相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり」とあります。
弘法大師ゆかりの奇瑞の地とあっては、霊地として崇められのは自然な成り行きでは。
盛綱は平家追討中備州児島の戦で霊夢を感じて大勝し、その報賽のため故郷・近江國から八王子宮を勧請したのが当社の草創といいます。
盛綱の小動来訪は文治年中(1185-1190年)、児島の戦(藤戸の戦い)は元暦元年(1184年)なので時系列が合いませんが、おそらく以前から小動のパワスポぶりは知っていたのでは。
『吾妻鑑』には、盛綱が尊崇する近江國の八王子宮を勧請する地を探していたとあるので、小動のパワスポぶりを知り、藤戸の戦いの戦捷もあってこの地に八王子宮を勧請したとみられます。
元弘三年(1333年)5月、新田義貞が鎌倉攻めの際に当社に戦勝を祈願し、建武年間(1334-1338年)に社殿を再建したといい、義貞を中興とする史料もあります。
この戦勝祈願は稲村ヶ崎の戦いの際とみられ、小動は稲村ヶ崎より手前なので、あるいは進路の潮が引く奇跡は八王子宮の霊験あってのことかもしれず、これを報賽して社殿再建がなされたのでは。
社殿再建は義貞寄進の太刀と黄金をもってなされたといい、黄金の太刀を海中に投じたという稲村ヶ崎の戦いを彷彿とさせます。
当社は明治維新までは、八王子宮(社)、八王子大権現、三神社などと称せられ、腰越の浄泉寺が別当でした。
旧腰越村の鎮守と伝わり、小田原藩7代藩主・大久保忠真(1778-1837年)が「三神社」の扁額を揮毫奉納しているので、大名層の尊崇も集めていたとみられます。
明治元年、神仏分離を受け地名の小動をとって小動神社と改称しています。
以前は本地佛として銅造長四寸の十一面観世音菩薩を安じ、八王子大権現と称されているので、神仏習合色が強かったのでは。
明治6年村社に列格。明治42年字神戸の鎮守・諏訪社を合祀し、昭和13年には神饌幣帛料供進神社に指定されています。
浄泉寺による管理は、神仏分離以降も大正6年7月までつづいていました。
『鎌倉市史 社寺編』には「当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。」とあり、なにか委細があったのかもしれません。
関東大震災で文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊しましたが、昭和4年に新築しています。
毎年7月に催される天王祭は江ノ島の八坂神社と共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わうそうです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
小動 附八王子宮
小動はも七里濱を西へ行、腰越へ入左の方、離れたる巌山あり。此所をこゆるぎと云ふ。山上に八王子の宮あり。又山の端に、海邊へ指出たる松あり。風波に常に動くゆへに、こゆるぎの松と云と也。
土御門内大臣の歌に、「こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」。
又北條氏康の歌に、「きのふたちけうこゆるぎの磯の波、いそひでゆかん夕暮の道」。
此等の歌、此所とも云ひ、或は大磯の濱とも云ふ。相模の名所こゆるぎの歌多し。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
小動
『新編鎌倉志』とほぼ同様のため略。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
八王子社
守鎮とす、幣殿・拝殿あり、社地を小動(古由留義)と云ふ。按ずるに【鎌倉志】に此地を当國の名所、小余呂伎磯となし、證歌を引用し、或は大磯の濱を詠とも記したるは、謬と云ふべし、彼名所は、淘綾郡大磯の属なること論を挨ず
本地佛 十一面観音 銅造長四寸を安ず
牛頭天王歳德神を合祀し、神社の額を扁す 今の領主の筆
縁起に拠るに文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱の勧請と云ふ。毎年正月十六日を祭期とし、六月十四日には天王の祭事を行へり
境内社後に至れば翠岩丹壁峙立して海中に突出し頗勝地たり
別当は村内浄泉寺兼管す、神木銀杏樹あり
神寶
劔一振 元弘三年(1333年)新田義貞鎌倉を攻るの時当社に祈誓し、成功の後報賽として、奉納せし物と云ふ
末社 稲荷 金毘羅 天神 船玉 第六天 山王 十羅刹 辨天 宇賀神
■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
祭神 健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊 相殿に歳徳神を祀る。
境内社 海神社 稲荷社 琴平社 第六天社
神事と芸能 例祭日・湯花神楽 七月十四日・天王祭の神輿渡御
社殿 本殿(流造) 幣殿 拝殿(入母屋造・唐破風付)以上権現造 銅板葺 三棟一宇
境内坪数 630.21坪
由緒沿革
『八王子宮縁起』(弘治二年(1556年銘))によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱当山に詣で、松樹の辺を徘徊、佳景を愛す。殊に小動の松は平日無風なるに枝葉摩動し、妙音琴瑟の如く、正に天女遊戯の霊木なり。誠に神徳永昌の奇峰なりと感じ、平家追討中備州児島の戦に霊夢を感じて大勝した報賽のため、年来尊崇の八王子宮を勧請し奉る、これ当社の草創なり」という。
又、元弘三年(1333年)五月新田義貞が鎌倉攻めの時、当社に戦勝を祈願し社殿を再建したという。
社号は八王子宮、八王子大権現などと称せられ、常泉寺が別当あったが、明治維新、神仏分離により独立し地名の小動をとって小動神社と改称した。
明治六年十二月村社に列格。
大正十四年の関東大震災に、文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊したが昭和四年十二月復興工事か完成した。
昭和十三年七月神饌幣帛料供進神社に指定された。
腰越区の氏神社である。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
小動神社
もと八王子宮、三神社などと称したが明治の神仏分離に際し地名の小動をとって小動神社と改めた。
祭神は健速須佐之男命・建御名方神・日本武尊。『風土記稿』には本地十一面観音銅像長四寸を安んじ、牛頭天王・歳徳神を合祀すとある。(中略)
元指定村社。境内地630.21坪
本殿・拝殿・末社四(海神社 稲荷社 琴平社 第六天社)・社務所・倉庫(中略)
腰越の鎮守。
勧請年月未詳。
弘治二年(1556年)、浄泉寺中興の元秀法印が書写した八王子宮縁起によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱が勧請し、建武年間(1334-1336年)新田義貞が中興したという。
明治四十二年三月九日、諏訪神社を合併。
文化十四年(1817年)四月建立の本殿は震災により破損した。拝殿は昭和四年に新築したものである。
当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。
■ 境内掲示(小動神社由緒略記)
祭神 日本武尊 素戔嗚尊 建御名方神 歳徳神
伝承
相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり、この松を小動の松と云うとあり。新編鎌倉史に、土御門内大臣の歌『こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」の歌は、此所の事とも云ひ、或いは、大磯の浜を詠うとも云う。相模の名所「こゆるぎ」の歌、多しとある。
社号は、古くは八王子宮、八王子大権現などと称された。相模風土記には、八王子社を鎮守とし、社地を社地を小動(古由留義)と云うとあり。
明治初年、現在の『小動神社』と改称した。
明治42年当地字、神戸の鎮守であった諏訪神社を合祀した。
由緒
文治年中(1185年)佐々木盛綱の創建と考えられる。
盛綱は、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた武将で、源平合戦の時に、神恩報賽のため守護神である父祖伝来の領国、近江の八王子宮を新たに勧請すべく、その地を探し求めていたが、ある日、江の島弁財天に参詣の途次、小動山に登り、大いにその風光を賞せられ勧請の地と定められた。
新田義貞が、鎌倉攻めの戦勝を祈願され、後に『報 賽』として『剣一振に黄金』を添えて寄進され、社殿は再興された。
八王子宮縁起によれば、新田義貞を中興の祖と称している。
江戸時代、小田原城主、大久保忠真公(113,000石)は【三神社】の扁額を揮毫し奉納された。三神社とは、三柱の祭神を尊称したものである。
社殿(前半略)・祭礼(略)
境内社として、海(わたつみ)神社(海上安全の神様)・稲荷社・金刀比羅宮・第六天社をお祠りしています。
■ 境内掲示(鎌倉市)
主祭神 健速須佐之男命 建御名方神 日本武尊
小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということに由来します。
縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。
元弘三年(1333年)五月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。
七月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。
-------------------------
「腰越」駅からもほど近い小動の岬に御鎮座です。
西側は腰越漁港。現在の主力魚種はしらすで、周辺には名物「しらす丼」の店がいくつかあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
社頭は国道134号に面しています。
参道すぐに石造明神鳥居と右手に社号標。
海際の神社は境内が狭い例も多いですが、こちらは鳥居から長々と参道が伸びています。
道幅が広くスケール感のある参道です。


【写真 上(左)】 神宝殿
【写真 下(右)】 参道階段手前
しばらく進むと両脇に一対の石灯籠。
その先から参道階段が始まります。
海側に向かっているのにのぼり階段とは、当地のパワスポぶりを物語っています。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水鉢
位置関係が定かではないのですが(おそらく参道階段の手前)、立派な手水舎のなかの手水鉢は黄褐色に変色し、これは井水使用かと思います。
階段の先に石造の明神鳥居(二の鳥居)で、社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 二の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居の扁額


【写真 上(左)】 小動神社
【写真 下(右)】 小動神社の向拝-1
小動神社社殿は参道右手に御鎮座。
拝殿前に狛犬一対。
拝殿は入母屋銅板葺で流れ向拝。軒唐破風とその上に千鳥破風を起こす重厚な意匠です。
水引虹梁両端に獅子獏の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、その上に兎の毛通し、唐破風の鬼飾、千鳥破風の懸魚と鬼飾を立体的に連ねて見応えがあります。
向拝正面桟唐戸のうえには社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 小動神社の向拝-2
【写真 下(右)】 向拝の扁額
史料に載る境内社がいまも趣ふかく御鎮座される、パワスポ的空気感の境内です。
小動神社の向かって右手の奥には石の鳥居の先に、海(わたつみ)神社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 綿津見神 別名 船玉神とも云う」「漁業の神・航海の神」とありました。


【写真 上(左)】 海神社
【写真 下(右)】 稲荷社(右)と金刀比羅宮(左)
参道階段の正面にあたる位置には覆屋があり、向かって右手の朱い鳥居の先に、稲荷社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 宇迦之御魂神 併神 佐田彦神=猿田彦神 大宮能売神=天鈿女命」「商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神」とありました。
向かって左手の石の鳥居の先に、金刀比羅宮が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 大物主神 別名 大国主命」「海神竜王ともいい、航海安全 海難救助を司る神」とありました。
境内右手奥の石の鳥居には六天王の扁額が掲げられています。
ここからくの字に曲がった参道階段がつづき、大(第)六天社が切妻造銅板葺妻入りのお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 第六天神 別名 淤母陀琉神(おもたるのかみ)」「諸願成就の神」とありました。
淤母陀琉神(おもだる)は神世七代の第六代の神とされ、中世には神仏習合により第六天王の垂迹であるとされました。


【写真 上(左)】 第六天社
【写真 下(右)】 腰越漁港と江ノ島
境内からは腰越漁港を見下ろし、その先には江ノ島が望めます。
御朱印はたしか社務所でご神職から拝受できました。
〔 小動神社の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)へつづく。
【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-2)
■ 素顔で踊らせて
■ ラチエン通りのシスター
■ 旅姿六人衆
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)
■ 同-21 (C.極楽寺口-4)
■ 同-22 (C.極楽寺口-5)から。
62.龍護山 満福寺(まんぷくじ)
公式Web
鎌倉市腰越2-4-8
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
司元別当:
札所:新四国東国八十八ヶ所霊場第84番、相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番
稲村ヶ崎~七里ヶ浜周辺に寺社は少なく、霊光寺(日蓮宗)は参拝していますが御首題はいただけず、顕証寺(本門佛立宗)の御首題はWeb検索でヒットしません。
よって腰越にエリアを進めます。
満福寺は源義経公・武蔵坊辨慶ゆかりの寺院です。
公式Web、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
天平十六年(744年)行基の開山と伝わる古刹で、古義真言宗手広村青蓮寺末といいます。
御本尊は行基御作の薬師如来、弘法大師御作の不動尊を安ずるとあります。
史料の多くは義経公とのゆかりに紙面をさいています。
源義経公(1159-1189年)は、鎌倉幕府初代将軍源頼朝公の異母弟で、日本史上もっとも著名とみられるその生涯については、ここではふかくなぞりません。
当山に関連ある事柄のみ、簡単に追ってみます。
治承八年(1184年)2月、摂津一ノ谷で平氏を破った義経公は京に凱旋すると後白河法皇から厚遇を受け、頼朝公の許可を得ずして法皇から検非違使・左衛門少尉の任官を受けました。
頼朝公はこれを怒り、義経公の平氏追討の任を解きました。
しかし、義経公解任後の戦況は思わしくなく、元暦二年(1185年)再び義経公を平氏追討に起用するや、義経公は讃岐屋島で見事な勝ち戦をおさめ、同年3月、長門壇ノ浦で平氏を滅ぼしました。
しかし同年4月、頼朝公は朝廷から勝手に任官を受けた義経公麾下の東国武者らを罵り、東国への帰還を禁じました。
平氏追討で義経公を補佐した梶原景時からは、義経公が平家追討の功を誇るあり様が書状で頼朝公に伝えられました。
軍監・景時の意見を聞かず独断専行で軍を進めたこと、兄の範頼公の所轄である九州へ無断で進出したことなども伝えられ、頼朝公の不興を買ったともいわれます。
同年5月、義経公は壇ノ浦で捕らえた平宗盛・清宗父子を護送して京を立ち、鎌倉に凱旋しようとしました。
しかし義経公のあり様に不審を抱く頼朝公は鎌倉入りを許さず、宗盛父子のみを鎌倉に入れ、義経公は腰越の満福寺に留め置かれました。
5月24日、義経公は満福寺で頼朝公に対し叛意のないことを切々と示す書状をしたため、頼朝公の側近大江広元に託しました。
これが有名な「腰越状」で、義経公の側近・辨慶が筆を執ったという説もあります。
頼朝公は義経公を弟として正当に処遇し、その実力も認めていましたが、義経公の神がかった武略と声望の高まり、そして法皇との個人的な結びつきは、東国での武家政権樹立をめざす頼朝公にとって脅威となったことは想像に難くありません。
また、義経公が京で平氏の捕虜である平時忠の娘(蕨姫)を娶ったことも、頼朝公の疑念を深めたという見方もあります。
6月9日、頼朝公が義経公に宗盛父子と平重衡を伴わせて帰京を命じると、鎌倉入りを果たせなかった義経公はこれを恨み、「関東に怨みを成す輩は、義経に属くべき」と言い放ち、これを聞いた頼朝公は義経公の所領を没収したと伝わります。
なお、『愚管抄』、延慶本『平家物語』などは、義経公はじつは鎌倉入りを果たし頼朝公と対面している旨記しているようで、「腰越状」も後世の偽作との見方があります。
8月16日の除目で義経公は頼朝公の推挙により伊予守を拝任したといい、この時点では頼朝公と義経公の決裂は決定的ではなかったという見方があります。
しかし、義経公は伊予守拝任後も朝廷から頼朝公に無断で受けた検非違使・左衛門少尉を離任せず、これにより頼朝公との関係はついに破綻したという説もあります。
頼朝公は義経公の動向を監視すべく梶原景時の嫡男・景季を京に遣わすと同時に、木曽義仲に与力した叔父・源行家の追討を要請しました。
10月、義経公の行家同心を断じた頼朝公は義経公討伐を決意し、刺客として京へ送られた土佐坊昌俊らは堀川の義経邸を襲いました。(堀川夜討)
しかし義経公に行家勢が加勢して襲撃は失敗。
義経公は捕らえた土佐坊から頼朝公の命による襲撃と聞き及ぶと、行家と謀って頼朝公打倒の兵を挙げ、後白河法皇より頼朝公追討の院宣を得ています。
しかし、義経公への与力は思うように集まらず勢いなしとみるや、今度は法皇は義経公追討の院宣を出しています。
このあたりの前後関係や頼朝公の関与については諸説ありますが、義経公が政治に長けた法皇の動きに翻弄されている姿がうかがわれます。
11月1日、頼朝公率いる義経公追討軍が駿河国黄瀬川に達すると、義経公らは京を落ち船で九州へと向うも、暴風で難破して摂津に押し戻されました。
7日には伊予守、検非違使・左衛門尉などの官職を解任され、義経公と行家捕縛の院宣が下されました。
義経公は郎党や愛妾の静御前を連れて吉野に身を隠しましたが、ここでも追討を受け京に潜伏。
文治二年(1186年)になると叔父・行家、佐藤忠信、伊勢義盛などの郎党もつぎつぎと討ち取られました。
義経公の関東での後見人として義父の河越重頼がいましたが、重頼と嫡男重房も殺害され関東での後ろ盾も失いました。
文治三年(1187年)京に潜み切れなくなった義経公は、藤原秀衡を頼り奥州・平泉へと赴きました。
藤原秀衡は義経公を盛り立てる意思をもっていましたが文治三年(1187年)10月に病没。
後継の泰衡は義経公を守り抜くことができず、文治五年(1189年)閏4月ついに義経公が拠る衣川館を襲撃、義経公や辨慶などの郎党は奮戦しましたがことごとく討死し、義経公はここに自害しました。(衣川の戦い)
享年31と伝わります。
義経公の首は鎌倉に送られ、和田義盛、梶原景時らによって首実検が腰越の浦で行われたといいます。
このことからも、腰越は義経公とゆかりをもつ地といえます。
満福寺には辨慶が書いたという「腰越状」の下書きとされる書状が所蔵され、山内には辨慶の腰掛石や手玉石など、義経公・辨慶ゆかりの品が遺ります。
寺前の池は、辨慶が「腰越状」を書く時に墨摺りの水を汲んだことから「硯池」と呼ばれ現存しています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
満福寺
満福寺は、腰越村の中にあり、龍護山と号す。眞言宗なり。
開山行基、本尊薬師 行基作・不動 弘法作
此寺地は、昔源義経、宿せられし所なりと云ふ。【東鑑】に、元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、如思に朝敵を平げ訖ぬ。剰へ前内府平宗盛を相具して参上す。其賞兼て不疑處に、日来不儀の聞へ有るに依て、忽御気色を蒙り、鎌倉中に入られず。腰越の驛に於て、徒に日を捗るの間、愁鬱の余に、因幡前司廣元に付して、一通の疑状を頼朝へ奉つるとあり。其状の下書也とて、今寺にあり。辨慶が筆跡と云。状中の文字、【東鑑】に載たるとは所々異なり。或人云、新筆なり。辨慶が筆には非ずと。
硯池
寺の前にあり。相伝ふ義経の命にて、辨慶疑状を書し時、硯水を汲たる池なりと。池の端に辨慶が腰懸石とてあり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
萬福寺
腰越村の内なり。龍護山と号す。古義眞言宗、同國手廣青蓮寺末なり。
開山行基、本尊薬師如来 行基作。弘法大師作の不動尊を安ず。
此寺、義経の宿陣せられし事をいひ伝ふ。元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、思ひの如く朝敵を平げ、剰へ屋島の内府平宗盛を相具して参り、其賞兼て疑はざる處に、不儀の聞へ有に依て、忽御気色を蒙り、鎌倉へ入られず、腰越の驛に於て徒に日を捗るの間、愁鬱の余り、因幡前司廣元に附して、一通の疑状を幕府え奉るといふ。其状の下書なりとて、今も此寺にあり。辨慶が筆なりといひ伝ふ。文書中【東鑑】に見えしとは異なる所もあり。辨慶が書けること覚束なし。
硯池
寺の前庭にあり。寺伝に、義経の仰に依て、辨慶が疑状を書たる時、硯水を汲し池といふ。又池の端に辨慶腰かけ松と名附るもあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(腰越村)満福寺
龍護山醫王院と号す。古義眞言宗手廣村青蓮寺末。
開山は行基、中興は高範(承安三年(1173年)三月十六日寂す)
本尊は薬師なり 長三尺三寸、行基作、同作の日月光、十二神もありしが、寛文中、回禄に烏有せしとぞ。
不動 弘法作長八寸
十一面観音 同作、長二尺五寸
彌陀 定朝作、長一尺五寸 等を安ず。
文治元年五月延尉義経頼朝の不審を蒙りて鎌倉へ入られず、当所に滞留す。
当時●止宿の所なりと云ふ
此時大江廣元に就て呈せし疑状の草案なりとて今に蔵せり。古文書部に詳載す、世に腰越状と称す是なり、辨慶が書記せしと伝ふれどおぼつかなし
【寺宝】(抜粋)
薬師書像一幅 弘法筆
地蔵堂 天神社 辨天社
硯池
本堂の前にあり。是辨慶疑状を書し時、池水を汲て硯池に滴す故に此名ありと云ふ、池辺に腰掛石といふあり、辨慶が腰を掛し所といふ。
■ 山内掲示
龍護山満福寺と号し、開山は行基(668-749)と伝えられ、本尊は薬師如来像です。源義経(1159-89)が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を汲んだといわれる硯池、腰掛石があります。-古義真言宗-
■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会・鎌倉文学館)
源義経と腰越
鎌倉時代前期の武将、源義経は、幼名牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。
治承四年(1180)兄頼朝の挙兵に参じ、元暦元年(1184)兄範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。帰洛後、洛中の警備にあたり、後白河法皇の信任を得、頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉となったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、讃岐屋島、長門壇ノ浦に平氏を壊滅させた。
しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの、鎌倉入りを拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため大江広元にとりなしを依頼する手紙(腰越状)を送った。
「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。
さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあひ具して、関東へ下向せられけるとき、腰越に関を据ゑて、鎌倉へは入れらるまじきにてありしかば、判官、本意なきことに思ひて、「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ゐられざれば、判官力におよばず。
その申し状に曰く、
源義経、恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに選ばれね勅宣の御使として朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)
しかし、頼朝の勘気は解けず、かえって義経への迫害が続いた。義経の没後、数奇な運命と悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。
中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。
■ 現地掲示(義経宿陣之趾/鎌倉市青年団)
文治元年(皇紀一八四五年) 五月
源義経朝敵ヲ平ラゲ 降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ凱旋セシニ
頼朝ノ不審ヲ蒙リ 鎌倉二入ルコトヲ許サレズ
腰越ノ驛二滞在シ 鬱憤ノ餘
因幡前司大江廣元ニ付シテ一通ノ歎状ヲ呈セシコト東鑑ニ見ユ
世ニ言フ腰越状ハ 即チコレニシテ
其ノ下書ト傳ヘラルルモノ満福寺二存ス
-------------------------
江ノ電「腰越」駅からもほど近く、駅前通りを南東に進んだところが参道入口。
ここにサイン類と「義経腰越状旧跡 満福寺」の寺号標があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口のサイン類
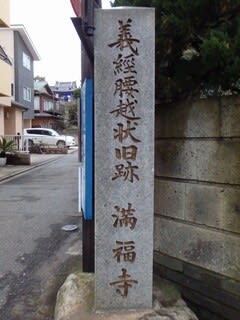

【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 江ノ電と参道階段
ここから、江ノ電の踏切の向こうに山門と鐘楼、そして本堂の屋根が見えます。
踏切遮断機のすぐ脇から山門階段。江ノ電の線路に至近で、撮り鉄さんにはたまらないスポットでは?


【写真 上(左)】 幟
【写真 下(右)】 参道階段
階段脇に「義経腰越状旧跡 満福寺」の幟がはためき、雰囲気が高まります。


【写真 上(左)】 参道階段すぐ下に江ノ電
【写真 下(右)】 山門
階段の先に構える山門はおそらく入母屋屋根銅版葺の四脚門で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、梁上に四連の斗栱、軒に二軒の垂木を備えた豪壮なもの。
見上げに山号扁額、大棟には清和源氏の紋「笹龍胆」を掲げています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門の寺号標


【写真 上(左)】 「義経宿陣之趾」の石碑
【写真 下(右)】 鐘楼
山門右手には、鎌倉市青年団建立の「義経宿陣之趾」の石碑。左手には鐘楼。
山門そばにある「笛供養」の碑は、笛を愛した義経公にちなむものと思われます。
「笛供養」の碑のよこには、ぼけ封じ祈願仏(おそらく地蔵尊と思われる)が御座します。
さほどの階段ではないのにかなり高低差を稼いでいるらしく、山内からは相模湾が見渡せます。


【写真 上(左)】 「笛供養」の碑とぼけ封じ祈願仏
【写真 下(右)】 山内からの相模湾


【写真 上(左)】 大師堂と札所碑
【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-1
山内には大師堂があり、こちらが弘法大師霊場の拝所とみられます。
山内には相州二十一ヶ所霊場の札所を示す碑や板がいくつかあります。この霊場の札所標はあまり目にることがないので、これは貴重です。


【写真 上(左)】 相州霊場札所碑-2
【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-3
山門くぐって正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。向拝上に端正な軒唐破風をおこしています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、頭貫から中備にかけて、じつに8つの斗を置いています。
身舎側に海老虹梁、中備の彫刻は「腰越状」書き上げの構図と思われます。


【写真 上(左)】 中備と兎の毛通しの彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額

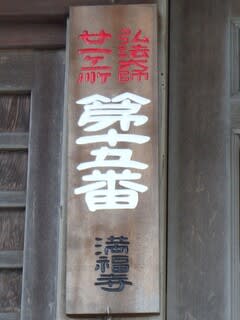
【写真 上(左)】 相州霊場札所板-1
【写真 下(右)】 相州霊場札所板-2
その上兎の毛通しは朱雀の彫刻か、さらに唐破風上の鬼飾りには「笹竜胆」の紋が輝いています。
向拝正面桟唐戸の上には寺号扁額や相州二十一ヶ所霊場の札所板が掲げられ、見どころの多い本堂てす。


【写真 上(左)】 腰越状の石像と本堂
【写真 下(右)】 腰越状の石像
本堂向かって左には、義経公と辨慶の石像。辨慶が筆を執っているので、おそらく腰越状をしたためている場面と思われます。
その横に「弁慶の腰掛石」。
訪れたときは、マスコット?のおネコちゃんが石のうえに座り込んでいました。
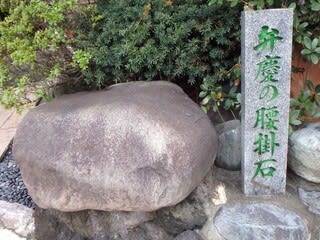

【写真 上(左)】 弁慶の腰掛石
【写真 下(右)】 おネコちゃん
本堂向かって右には慈悲観音立像と「弁慶の手玉石」。
本堂を拝観(有料)すると、腰越状(の下書き?)、義経公や静御前の襖絵、弁慶仁王立ちの絵などが間近で拝せるようですが、筆者は拝観しておりません。


【写真 上(左)】 弁慶の手玉石
【写真 下(右)】 硯の池(右)と義経公手洗の井戸(左)
本堂右手の山側には鎌倉七里ヶ浜霊園へ向かうトンネルがあり、その右手に「硯の池」、左手には義経公手洗の井戸があります。
「腰越」駅にも案内看板があり、道すがらもいくつかの案内サイン、参道まわりの幟、さらには腰越状の石像を置かれるなどサービス精神?が感じられるお寺さまです。


【写真 上(左)】 サイン-1
【写真 下(右)】 サイン-2
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。
こちらはかなり渋めの霊場札所を兼務されています。
相模国準四国八十八ヶ所霊場は湘南エリアの弘法大師霊場で文政四年(1821年)開創と伝わる歴史ある霊場ですが、現況は廃寺や札所異動も多く、御朱印はいただきにくい霊場となっています。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
小田急武相三十三観音霊場は小田急電鉄が主導して沿線の寺院を札所選定した観音霊場です。
この霊場の札所印はなかなかレアですが、他霊場を兼務される札所が多く、御朱印じたいの拝受は比較的容易です。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
〔 満福寺の御朱印 〕
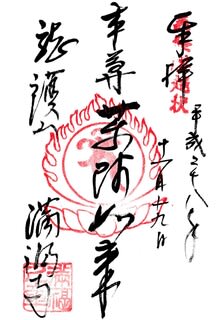
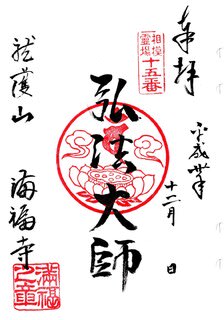
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
これまでに拝受している御朱印は以上の2点ですが、Web上では「千手観音」(新四国東国八十八ヶ所霊場第84番)、「十一面観音」(おそらく小田急武相三十三観音霊場第33番)の御朱印もヒットします。
63.小動神社(こゆるぎじんじゃ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
神奈川県神社庁Web
鎌倉市腰越2ー9ー12
御祭神:健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊、歳徳神
旧社格:村社、旧腰越村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:浄泉寺(鎌倉市腰越、真言宗大覚寺(青蓮寺)末)
小動神社は八王子宮(はちおうじのみや)とも呼ばれ、源頼朝公の側近・佐々木左兵衛尉盛綱の勧請と伝わります。
鎌倉公式観光ガイドWeb、神奈川県神社庁Web、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
佐々木盛綱(1151年-)は、近江国佐々木庄に拠った宇多源氏の棟梁・佐々木秀義の三男です。
秀義は平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公に従うも敗れ、一門は関東へ落ちのび渋谷重国の庇護を受けました。
秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。
三男盛綱は16歳で伊豆國に配流された頼朝公に仕えました。
頼朝公の信任篤く、治承四年(1180年)8月、平氏打倒を決意した頼朝公に挙兵の計画を告げられたとも。
治承四年(1180年)8月の山木館襲撃に加わり、加藤景廉とともに山木兼隆の首を獲ったといいます。
石橋山の戦いののちは渋谷重国の館に逃れ、頼朝公が兵を集めて鎌倉に入ると再び頼朝公の麾下に参じ、富士川の戦いでも戦功をあげています。
元暦元年(1184年)、盛綱は平氏追討のため備前國児島に入り、平行盛ら五百余騎が籠もる城郭をわずか六騎で攻め落としたといいます。(藤戸の戦い)
平家滅亡後も頼朝公の側に仕え、公の寺社参詣や儀式、あるいは上洛の随兵としてその名が多くみえます。
頼朝公没後の建久十年(1199年)3月に出家して西念と号しました。
なお、群馬県安中市磯部の松岸寺には佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があります。
詳細は→こちらの記事(■「鎌倉殿の13人」と御朱印-4)をご覧ください。
小動(こゆるぎ)の岬は江ノ島をのぞむ風光明媚な地で、この地に聳える「小動の松」は風もないのに枝葉が揺れ、常に妙音を琴瑟の如く発していたためこの銘木にちなみ「小動」を地名にしたといいます。
『八王子宮縁起』「鎌倉公式観光ガイドWeb」によると、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱は江の島弁財天への参詣の途中に当山に詣で、「小動の松」のあたりを散策して佳景を楽しみ、まことに神徳の地と詠嘆したそうです。
「当山に詣で」とあるので、当地にはすでに寺社が存在していた可能性があります。
現地掲示の『由緒略記』には「相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり」とあります。
弘法大師ゆかりの奇瑞の地とあっては、霊地として崇められのは自然な成り行きでは。
盛綱は平家追討中備州児島の戦で霊夢を感じて大勝し、その報賽のため故郷・近江國から八王子宮を勧請したのが当社の草創といいます。
盛綱の小動来訪は文治年中(1185-1190年)、児島の戦(藤戸の戦い)は元暦元年(1184年)なので時系列が合いませんが、おそらく以前から小動のパワスポぶりは知っていたのでは。
『吾妻鑑』には、盛綱が尊崇する近江國の八王子宮を勧請する地を探していたとあるので、小動のパワスポぶりを知り、藤戸の戦いの戦捷もあってこの地に八王子宮を勧請したとみられます。
元弘三年(1333年)5月、新田義貞が鎌倉攻めの際に当社に戦勝を祈願し、建武年間(1334-1338年)に社殿を再建したといい、義貞を中興とする史料もあります。
この戦勝祈願は稲村ヶ崎の戦いの際とみられ、小動は稲村ヶ崎より手前なので、あるいは進路の潮が引く奇跡は八王子宮の霊験あってのことかもしれず、これを報賽して社殿再建がなされたのでは。
社殿再建は義貞寄進の太刀と黄金をもってなされたといい、黄金の太刀を海中に投じたという稲村ヶ崎の戦いを彷彿とさせます。
当社は明治維新までは、八王子宮(社)、八王子大権現、三神社などと称せられ、腰越の浄泉寺が別当でした。
旧腰越村の鎮守と伝わり、小田原藩7代藩主・大久保忠真(1778-1837年)が「三神社」の扁額を揮毫奉納しているので、大名層の尊崇も集めていたとみられます。
明治元年、神仏分離を受け地名の小動をとって小動神社と改称しています。
以前は本地佛として銅造長四寸の十一面観世音菩薩を安じ、八王子大権現と称されているので、神仏習合色が強かったのでは。
明治6年村社に列格。明治42年字神戸の鎮守・諏訪社を合祀し、昭和13年には神饌幣帛料供進神社に指定されています。
浄泉寺による管理は、神仏分離以降も大正6年7月までつづいていました。
『鎌倉市史 社寺編』には「当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。」とあり、なにか委細があったのかもしれません。
関東大震災で文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊しましたが、昭和4年に新築しています。
毎年7月に催される天王祭は江ノ島の八坂神社と共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わうそうです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
小動 附八王子宮
小動はも七里濱を西へ行、腰越へ入左の方、離れたる巌山あり。此所をこゆるぎと云ふ。山上に八王子の宮あり。又山の端に、海邊へ指出たる松あり。風波に常に動くゆへに、こゆるぎの松と云と也。
土御門内大臣の歌に、「こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」。
又北條氏康の歌に、「きのふたちけうこゆるぎの磯の波、いそひでゆかん夕暮の道」。
此等の歌、此所とも云ひ、或は大磯の濱とも云ふ。相模の名所こゆるぎの歌多し。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
小動
『新編鎌倉志』とほぼ同様のため略。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
八王子社
守鎮とす、幣殿・拝殿あり、社地を小動(古由留義)と云ふ。按ずるに【鎌倉志】に此地を当國の名所、小余呂伎磯となし、證歌を引用し、或は大磯の濱を詠とも記したるは、謬と云ふべし、彼名所は、淘綾郡大磯の属なること論を挨ず
本地佛 十一面観音 銅造長四寸を安ず
牛頭天王歳德神を合祀し、神社の額を扁す 今の領主の筆
縁起に拠るに文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱の勧請と云ふ。毎年正月十六日を祭期とし、六月十四日には天王の祭事を行へり
境内社後に至れば翠岩丹壁峙立して海中に突出し頗勝地たり
別当は村内浄泉寺兼管す、神木銀杏樹あり
神寶
劔一振 元弘三年(1333年)新田義貞鎌倉を攻るの時当社に祈誓し、成功の後報賽として、奉納せし物と云ふ
末社 稲荷 金毘羅 天神 船玉 第六天 山王 十羅刹 辨天 宇賀神
■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
祭神 健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊 相殿に歳徳神を祀る。
境内社 海神社 稲荷社 琴平社 第六天社
神事と芸能 例祭日・湯花神楽 七月十四日・天王祭の神輿渡御
社殿 本殿(流造) 幣殿 拝殿(入母屋造・唐破風付)以上権現造 銅板葺 三棟一宇
境内坪数 630.21坪
由緒沿革
『八王子宮縁起』(弘治二年(1556年銘))によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱当山に詣で、松樹の辺を徘徊、佳景を愛す。殊に小動の松は平日無風なるに枝葉摩動し、妙音琴瑟の如く、正に天女遊戯の霊木なり。誠に神徳永昌の奇峰なりと感じ、平家追討中備州児島の戦に霊夢を感じて大勝した報賽のため、年来尊崇の八王子宮を勧請し奉る、これ当社の草創なり」という。
又、元弘三年(1333年)五月新田義貞が鎌倉攻めの時、当社に戦勝を祈願し社殿を再建したという。
社号は八王子宮、八王子大権現などと称せられ、常泉寺が別当あったが、明治維新、神仏分離により独立し地名の小動をとって小動神社と改称した。
明治六年十二月村社に列格。
大正十四年の関東大震災に、文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊したが昭和四年十二月復興工事か完成した。
昭和十三年七月神饌幣帛料供進神社に指定された。
腰越区の氏神社である。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
小動神社
もと八王子宮、三神社などと称したが明治の神仏分離に際し地名の小動をとって小動神社と改めた。
祭神は健速須佐之男命・建御名方神・日本武尊。『風土記稿』には本地十一面観音銅像長四寸を安んじ、牛頭天王・歳徳神を合祀すとある。(中略)
元指定村社。境内地630.21坪
本殿・拝殿・末社四(海神社 稲荷社 琴平社 第六天社)・社務所・倉庫(中略)
腰越の鎮守。
勧請年月未詳。
弘治二年(1556年)、浄泉寺中興の元秀法印が書写した八王子宮縁起によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱が勧請し、建武年間(1334-1336年)新田義貞が中興したという。
明治四十二年三月九日、諏訪神社を合併。
文化十四年(1817年)四月建立の本殿は震災により破損した。拝殿は昭和四年に新築したものである。
当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。
■ 境内掲示(小動神社由緒略記)
祭神 日本武尊 素戔嗚尊 建御名方神 歳徳神
伝承
相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり、この松を小動の松と云うとあり。新編鎌倉史に、土御門内大臣の歌『こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」の歌は、此所の事とも云ひ、或いは、大磯の浜を詠うとも云う。相模の名所「こゆるぎ」の歌、多しとある。
社号は、古くは八王子宮、八王子大権現などと称された。相模風土記には、八王子社を鎮守とし、社地を社地を小動(古由留義)と云うとあり。
明治初年、現在の『小動神社』と改称した。
明治42年当地字、神戸の鎮守であった諏訪神社を合祀した。
由緒
文治年中(1185年)佐々木盛綱の創建と考えられる。
盛綱は、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた武将で、源平合戦の時に、神恩報賽のため守護神である父祖伝来の領国、近江の八王子宮を新たに勧請すべく、その地を探し求めていたが、ある日、江の島弁財天に参詣の途次、小動山に登り、大いにその風光を賞せられ勧請の地と定められた。
新田義貞が、鎌倉攻めの戦勝を祈願され、後に『報 賽』として『剣一振に黄金』を添えて寄進され、社殿は再興された。
八王子宮縁起によれば、新田義貞を中興の祖と称している。
江戸時代、小田原城主、大久保忠真公(113,000石)は【三神社】の扁額を揮毫し奉納された。三神社とは、三柱の祭神を尊称したものである。
社殿(前半略)・祭礼(略)
境内社として、海(わたつみ)神社(海上安全の神様)・稲荷社・金刀比羅宮・第六天社をお祠りしています。
■ 境内掲示(鎌倉市)
主祭神 健速須佐之男命 建御名方神 日本武尊
小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということに由来します。
縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。
元弘三年(1333年)五月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。
七月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。
-------------------------
「腰越」駅からもほど近い小動の岬に御鎮座です。
西側は腰越漁港。現在の主力魚種はしらすで、周辺には名物「しらす丼」の店がいくつかあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
社頭は国道134号に面しています。
参道すぐに石造明神鳥居と右手に社号標。
海際の神社は境内が狭い例も多いですが、こちらは鳥居から長々と参道が伸びています。
道幅が広くスケール感のある参道です。


【写真 上(左)】 神宝殿
【写真 下(右)】 参道階段手前
しばらく進むと両脇に一対の石灯籠。
その先から参道階段が始まります。
海側に向かっているのにのぼり階段とは、当地のパワスポぶりを物語っています。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水鉢
位置関係が定かではないのですが(おそらく参道階段の手前)、立派な手水舎のなかの手水鉢は黄褐色に変色し、これは井水使用かと思います。
階段の先に石造の明神鳥居(二の鳥居)で、社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 二の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居の扁額


【写真 上(左)】 小動神社
【写真 下(右)】 小動神社の向拝-1
小動神社社殿は参道右手に御鎮座。
拝殿前に狛犬一対。
拝殿は入母屋銅板葺で流れ向拝。軒唐破風とその上に千鳥破風を起こす重厚な意匠です。
水引虹梁両端に獅子獏の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、その上に兎の毛通し、唐破風の鬼飾、千鳥破風の懸魚と鬼飾を立体的に連ねて見応えがあります。
向拝正面桟唐戸のうえには社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 小動神社の向拝-2
【写真 下(右)】 向拝の扁額
史料に載る境内社がいまも趣ふかく御鎮座される、パワスポ的空気感の境内です。
小動神社の向かって右手の奥には石の鳥居の先に、海(わたつみ)神社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 綿津見神 別名 船玉神とも云う」「漁業の神・航海の神」とありました。


【写真 上(左)】 海神社
【写真 下(右)】 稲荷社(右)と金刀比羅宮(左)
参道階段の正面にあたる位置には覆屋があり、向かって右手の朱い鳥居の先に、稲荷社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 宇迦之御魂神 併神 佐田彦神=猿田彦神 大宮能売神=天鈿女命」「商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神」とありました。
向かって左手の石の鳥居の先に、金刀比羅宮が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 大物主神 別名 大国主命」「海神竜王ともいい、航海安全 海難救助を司る神」とありました。
境内右手奥の石の鳥居には六天王の扁額が掲げられています。
ここからくの字に曲がった参道階段がつづき、大(第)六天社が切妻造銅板葺妻入りのお社を構えられて御鎮座。
掲示には「祭神 第六天神 別名 淤母陀琉神(おもたるのかみ)」「諸願成就の神」とありました。
淤母陀琉神(おもだる)は神世七代の第六代の神とされ、中世には神仏習合により第六天王の垂迹であるとされました。


【写真 上(左)】 第六天社
【写真 下(右)】 腰越漁港と江ノ島
境内からは腰越漁港を見下ろし、その先には江ノ島が望めます。
御朱印はたしか社務所でご神職から拝受できました。
〔 小動神社の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)へつづく。
【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-2)
■ 素顔で踊らせて
■ ラチエン通りのシスター
■ 旅姿六人衆
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)
■ 同-21 (C.極楽寺口-4)から。
60.霊鷲山 感応院 極楽律寺(ごくらくりつじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市極楽寺3-6-7
真言律宗西大寺派
御本尊:釈迦如来
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番、鎌倉十三仏霊場第12番(大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第1番
※鎌倉二十四地蔵霊場第20番導地蔵尊、同第21番月影地蔵尊を護持
極楽律寺は真言律宗の名刹で極楽寺とも呼ばれます。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
極楽寺の開基は北条重時、開山は忍性菩薩(良觀上人)とされますが、草創はそれ以前に遡るとみられています。
Wikipedia等によると『極楽寺縁起』には「深沢(現・鎌倉市西部)に創建された念仏系の寺院(開山正永和尚)」が草創とあるようです。
(『極楽寺由緒沿革書』には永久年間(1113-1118年)、僧勝覚の創建とあるとも。)
また、『元亨釋書』には正嘉(1257-1259年)の頃に一沙門が一宇を建て、丈六の彌陀像を安して極楽寺を号したとあり、極楽寺の草創については諸説あります。
鎌倉幕府2代執権・北条義時の三男で幕府連署であった重時(極楽寺殿)は、この極楽寺が寺域が狭く整備も足りないことから、正元元年(1259年)忍性菩薩(良観上人・良観房)に諮ったところ、西南の「地獄谷」と呼ばれる霊場こそ招提すべき地であるとの教示を得ました。
重時は早速地獄谷の地に極楽寺を遷し、自身が開基となりました。
重時は建長八年(1256年)に出家し、(今の)極楽寺の山庄に隠居しているので、隠居後に極楽寺を開基していることになります。
『吾妻鏡』には、重時は弘長元年(1261年)6月病に倒れるも、鶴岡八幡宮別当隆弁の加持により回復したとあります。
『新編鎌倉志』には「発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終る」とあり、重時は往生まで極楽寺にて念佛三昧で過ごしたことになります。
弘長元年(1261年)11月3日逝去。
重時の子長時(鎌倉幕府6代執権)・業時兄弟は極楽寺を修営したとあり、子院四十九院を擁して伽藍は壮麗をきわめたといいます。
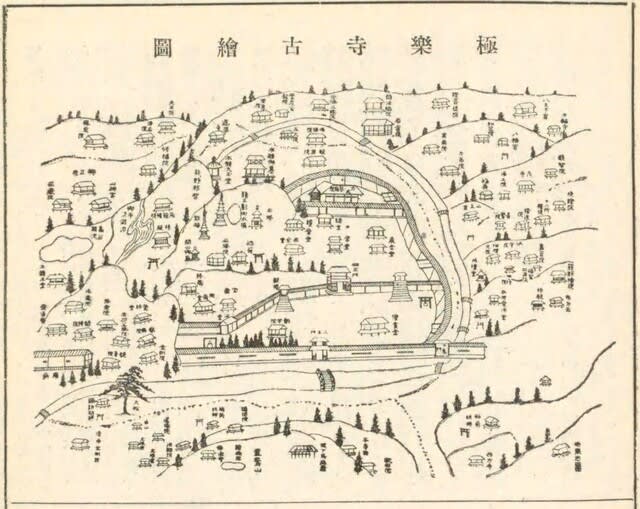
(雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻,雄山閣,昭7-8. 国立国会図書館デジタルコレクションより転載/インターネット公開(保護期間満了))
『新編相模國風土記稿』収録の「極楽寺古繪図」には伽藍が立ち並ぶ山内が描かれ、一大霊地を構成していたことがわかります。
最盛期には現在の極楽寺のみならず、稲村ヶ崎小学校の建つ谷一帯が極楽寺の山内で、現在江ノ電が走る極楽寺川沿いの谷には病者・貧者救済の施設があったとみられます。
(現・立稲村ケ崎小学校が最盛期の中心伽藍の地とみられています。)
『吾妻鏡』には、重時の三回忌法要は弘長三年(1263年)極楽寺で西山浄土宗の宗観房を導師として催行とあり、この時点では極楽寺は浄土教系寺院との見方があります。
しかし文永四年(1267年)8月に忍性菩薩を請して開山とし、当寺に移住した時点では「真言律(宗)」に改めていたとみられます。
忍性(にんしょう、忍性菩薩、1217-1303年)は、通称良観とも呼ばれます。
大和国の生まれで、幼くして文殊菩薩信仰に目覚め、師叡尊から真言密教・戒律受持・聖徳太子信仰を受け継いだといいます。
聖徳太子の「四箇院の制」に感銘を受け、とくに病者に薬を施す施薬院、病者を収容治療する療病院、身寄りのない者や年老いた者を収容する悲田院を重んじ、社会的弱者の救済に尽力したことで知られています。
弘長二年(1262年)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、文永四年(1267年)8月には極楽寺を開山しています。
師の叡尊は、忍性の生来の慈悲心が弱者救済に適していると見抜き、この役割を忍性に託したという見方があります。
実際、忍性が開山した極楽寺山内にも療病院、悲田院、癩宿などが設けられています。
忍性は道路の改修や橋梁の架設などを行い、極楽寺坂切通を拓いたのも忍性と伝わることから、忍性は優れた土木技術を持つ人々を抱えていたとみられています。
忍性の多岐にわたる功績は広く称えられ、嘉元元年(1303年)87歳で示寂の後、後醍醐帝より菩薩号を贈られています。
忍性菩薩、そして極楽寺を語るとき、「真言律(宗)」は外せないのでこれについてまとめてみます。
「真言律(宗)」については、■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9の第28番霊雲寺で整理しているので、ほぼそこからの再掲となります。
真言律(宗)とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。
弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。
叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。
「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。
→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)
真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。
以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。
叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。
叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。
『新編相模國風土記稿』には「弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺(極楽寺)を御願場とす」とあります。
江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。
明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。
真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。
とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。
元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。
もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。
のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。
この点からしても、中世の極楽寺は勅願祈願寺としての性格も強かったとみられます。
なお、鎌倉と律宗との関係をみるとき、願行上人憲静(1215-1295年)の存在は欠かせません。
願行上人は北京律(ほっきょうりつ)の法統とされますが、真言律宗の名刹、金沢の称名寺とも関係があったとみられており、極楽寺ともなんらかの関係があったのかもしれませんが、調べた限りでは詳細不明です。
→ 関係記事(■ 鎌倉市の御朱印-7)
極楽寺に戻ります。
元弘三年(1333年)には後醍醐帝の綸旨を賜り寺領を安堵され後醍醐帝の勅願所となりましたが、その後度重なる戦乱や火災により寺勢は衰微しました。
天正十九年(1591年)、徳川家康公より九貫五百文の朱印地を得たものの、再び荒廃し、一時無住の時期もあったといいます。
天保十二年(1841年)成立の『新編相模国風土記稿』には「塔頭 吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す」とあり、最盛期には49を数えた子院が、天保にはわずか1院となったことがわかります。
そのなかには他地へ移った寺院もあるとみられます。
たとえば、横浜市港北区新羽の西方寺の公式Webには「極楽寺の一院として存在した西方寺は、極楽寺坂切り通しの北側崖上にあり、その付近が古図に示す西方寺の所在と一致し、歴代住侶の墓石十基ほどを残し今も存在し、西方寺跡とされています。」「極楽寺より西方寺が移転されたのは、明応年間(1492)で今から五百年ほど前のこと」とあり、極楽寺の一院であったことを明記しています。


【写真 上(左)】 西方寺
【写真 下(右)】 西方寺の御朱印
栄枯盛衰の歴史を辿った極楽寺ですが近世に復興し、複数の霊場の札所も兼ねて、いまは多くの拝観客が訪れています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
極楽寺
極楽寺、霊山山と号す。眞言律にて、南都西大寺の末寺なり。開山は、忍性菩薩、良觀上人と号す。
当寺は、陸奧守平重時が建立なり。重時を極楽寺と号し、法名觀覺と云。【東鑑】に、弘長元年(1261年)十一月三日、平重時卒す。年六十四、時に極楽寺の別業に住す。発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終るとあり。按ずるに、【元亨釋書】に、初め正嘉(1257-1259年)中に沙門あり。一宇を営で、丈六の彌陀の像を安ず。名て極楽寺と云。未落せずして亡す。平重時、其宇を今の地に遷して齋場とす。重時の子長時・同弟業時、力を戮て修營すとあり【帝王編年記】に、永仁六年(1298年)四月十日、関東の将軍家久明親王、御祈祷の為に、十三箇寺の寺領の違亂を停止、殺生禁断の事あり。相州鎌倉郡の極楽寺、其一つなり。
此寺、昔は四十九院ありしとなり。今吉祥院と云のみあり。寺領九貫五百文あり。又千服茶磨とて、大なる石磨、門を入右の方にあり。昔此寺繁昌なりしを、知らしめんが為なりといふ。
本堂
本尊は釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸したりといふ。十大弟子の像もあり。作者不知。
左に興正菩薩の木像、自作といふ。
右に忍性菩薩の木像、是も自作と云。
又文殊の坐像あり。古への文殊堂の本尊なりと云ふ。(略)
寺寶
九條袈裟 壹頂 乾陀穀子袈裟、東寺第三傳と書付あり。今按ずるに、乾陀穀子袈裟は、弘法大師の伝来にて、八祖相承とて、東寺の寶物なり。今此寺に所有は、其袈裟を摸したる、第三伝と見へたり。(中略)
二十五條袈裟 壹頂 紗なり。八幡大神の所持と云ふ。按ずるに八幡へ調進の物なり。(中略)
千體地藏 弘法作。本尊は、長一寸餘。千體は長五六分ばかり也。今皆紛失して纔に二三百ばかり残れり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
極楽寺
霊山山と号す。眞言・律、南都西大寺末なり。
開山は忍性菩薩良觀上人、開基は陸奧守重時が、法号をば極楽寺觀覺と称す。(中略)
古は谷々に四十九院ありしといふ。今は吉祥院といふ一院ばかり。
本堂
本尊釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸せしといふ。十大弟子の像もあり。作不知。
左に興正菩薩の自作の木像、右に忍性菩薩の是も自作の木像といふ。
文殊の坐像もあり。古への文殊堂の本尊なりといふ。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(山之内庄極楽寺村)極楽寺
霊鷲山感應院と号す。眞言律宗南都西大寺末。
北條陸奧守重時が草創なり、始正嘉(1257-1259年)中に一老衲ありて一宇を営み丈六の彌陀像を安じ、名づけて極楽寺と云ふ。然るに経営の功未だ完かずして老衲尋て寂しぬ
正元(1259-1260年)の初重時寺域の狭小なるを見て地を卜して新に創立せんと欲し僧忍性に議しけるに、性答て是より西南に当り地獄谷と云へる霊場あり、此地こそ招提の境なれと云て即性彼地に到り念誦す、須㬰にして感應あり、重時就て一宇を遷して斎場とす、地獄谷は今の境内なりと云ふ
重時の子武蔵守長時其弟業時等力を戮て修飾し、子院四十九院を構造す、堂宇壮麗に一刹となる
時に性(忍性)を請して開山始祖とす、文永四年(1267年)八月性(忍性)当寺に移住せり
弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺を御願場とす
性(忍性)嘉元元年(1303年)七月十二日寂す 嘉暦三年(1328年)後醍醐帝性(忍性)の行徳を追崇ありて菩薩の号を賜ふ
元弘二年(1332年)六月勅願寺幷寺領安堵の事
其後堂宇漸く衰廃し、今は仏殿一宇塔頭一院のみ残れり
本尊釋迦 大像長六尺余、興正作、十大弟子の像を置く 毘首羯磨作、脇に興正菩薩 坐像自作長三尺及び聖徳太子の像 立像長二尺三寸余、運慶作、又文殊の像あり、古昔域内別堂に安ぜし本尊なりと云ふ
寺寶
乾陀穀子袈裟 一領 東寺第三傳とあり、元は京都東寺にありしに、永仁元年(1293年)十二月八日、当寺に贈りしとなり、今按ずるに、この袈裟は、東寺の寶物にて【元亨釋書】空海の伝に、弘安十四年正月勅以東寺賜空海乃置惠果所付、健陀國袈裟及念珠為寺鎮と載す、文字違へり健陀●は西域の國名なり(中略)
二十五條袈裟 一領 八幡太神の御袈裟と云へど、是は八幡宮へ調進せし物ならんと
北條陸奧守重時墓
寺後の山にあり、重時は左京太夫義時の三男なり、弘長元年(1263年)十一月三日当所別業に在て卒す、法名を觀覺極楽寺と称す
塔頭
吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す、本尊不動を置く 座像二尺五寸智證作
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 真言律宗
山号寺号 霊鷲山感応院極楽律寺
建立 正元元年(1259年)
開山 忍性菩薩
開基 北条重時
開山は良観房忍性。奈良西大寺叡尊門下で戒律を学ぶ。弘長二年(一二六二)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、その後文永四年(一二六七)に極楽寺に開山として迎えられました。
極楽寺は正元元年(一二五九)に深沢に創建され、後に開基となる北条重時が現在地に移転したといわれています。元寇に際しては、幕府の命により異国降伏の祈祷を行い、また、鎌倉幕府滅亡後も勅命により国家安泰を祈る勅願所としての寺格を保ちました。かつての寺域は広大で、中心の七堂伽藍を囲むように多くの子院、そして療病院などの病院施設もあったことが当寺に伝わる絵図からわかります。
-------------------------


【写真 上(左)】 極楽寺駅
【写真 下(右)】 極楽寺駅ホームから
江ノ電「極楽寺」駅至近でホームから見えます。
駅の出口は反対側なので、桜橋で江ノ電の線路を渡って「導地蔵尊」の前を左に折れるとすぐです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標と墓標
少しく引きこんで山門。
手入れの行き届いた植栽、落ち着いたただずまいは鎌倉の名刹ならではのもの。
こちらは以前は境内撮影禁止でしたが、現在は解除されている模様です。
解除後参拝しておらず、山内の写真がまったくないので、↓の動画を参考にご案内します。
■ 極楽寺駅周辺と極楽寺 (鎌倉市極楽寺)
山門手前左に、開山忍性菩薩・開基北条重時の墓標と寺号標。
山門は趣ある茅葺屋根。左右に脇塀を備えた四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を置く堂々たる山門です。
主門は柵で閉ざされているので脇門の木戸から入内します。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
山門から真っ直ぐに桜並木の石畳参道が伸び、正面が本堂。
参道右手に大師堂と転法輪殿(収納庫)。
参道左手には客殿、納経所と本堂よこに資料館があります。


【写真 上(左)】 冬の山内
【写真 下(右)】 山門から本堂
度重なる天災や兵火のため当初の伽藍は失われ、現在は文久三年(1863年)再建の山門、本堂、大師堂、客殿がメインです。
西側山手には忍性塔があり、こちらは奥の院となっています。
忍性塔は高さ3.57メートルの大型の石造五輪塔で、納置品から嘉元三年(1303年)頃の建塔とみられ、国の重要文化財に指定されています。
通常は非公開で、毎年4月8日のみ公開の模様。
塔内納置品は良観房忍性和尚と同二世賢明房慈済和尚の舎利容器であることから、忍性の墓塔ともいわれます。こちらも国の重要文化財に指定されています。
五輪塔(伝・忍公塔、非公開)は忍性塔の右方にある石造五輪塔で、かつては北条重時の墓塔とされ、昭和2年国の史跡に指定されました。
しかし、昭和36年の豪雨で塔が倒れた際、塔内から発見された納置品より当山3世善願坊順忍と比丘尼禅忍の供養塔であることが判明しています。
忍性塔の周囲にある宝篋印塔が北条重時の墓塔とみる説もあります。
大師堂は宝形造銅板瓦棒葺で向拝柱はありません。
鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番の札所板が掲げられ、霊場拝所となっています。

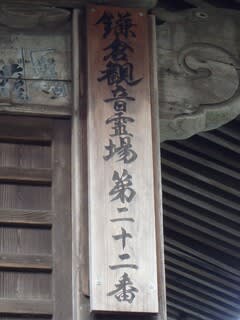
【写真 上(左)】 鎌倉観音霊場札所板
【写真 下(右)】 同 札所標

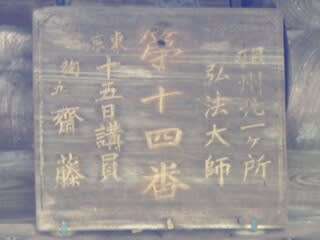
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-1
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-2
鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印には「常磐御前念持佛」の印判がありますが、これを裏付ける史料はみつかりませんでした。
転法輪殿(収納庫)はがっしりとした近代建築で、御本尊である秘仏「清凉寺式釈迦如来」、伝来の木造十大弟子像、木造釈迦如来坐像などが収納されています。
本堂はおそらく宝形造銅板葺流れ向拝で四周に高欄をまわし、屋根勾配が急な特徴ある意匠です。
頂部露盤には北条氏の家紋「三つ鱗紋」とおぼしき紋が刻まれています。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置いています。
Wikipediaによると、
本堂の須弥壇中央に不動明王坐像、向かって右に薬師如来坐像、左に文殊菩薩坐像を安置。右奥には忍性像、左奥には興正菩薩(叡尊)像を安置するとのこと。
文殊菩薩坐像はかつてあった文殊堂の御本尊ゆかりの像とみられ、忍性像、興正菩薩(叡尊)像も史料にあらわれています。
不動明王坐像は平安時代末期の作といい、島根県の勝達寺から大正5年に移されたとの由。
向拝に地蔵尊のご縁日が張り出されているので、地蔵尊も奉安とみられます。
通常本堂内は非公開で、4月7日-9日のみ入堂できるようです。
なお、史料に見える聖徳太子像(伝運慶作)、弘法大師が師の惠果阿闍梨から贈られた乾陀穀子袈裟(東寺蔵)の写し(?)などについては所在の調べがつきませんでした。
あるいは、転法輪殿(収納庫)か資料館に収蔵されているのかもしれません。
本堂前には「不許葷酒肉入山門」と刻した戒壇石。戒律の厳しい真言律宗らしい標石です。
本堂向かって右前には「千眼茶臼」「製茶鉢」。
開山の忍性菩薩が悲田院、施益院などを設置されたときに使用されたものと伝わります。
参道右手、授与所前には子育地蔵尊の露仏が御座、参道山門寄り左手には忍性菩薩が粥を施すために使用したという「極楽寺の井」もあります。
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。
複数の霊場札所を兼務されているので、霊場申告は必須です。
また、鎌倉二十四地蔵霊場第20番の導地蔵尊、同第21番の月影地蔵尊の御朱印もこちらで拝受できますが、当然先にお参りしてからの申告となります。
〔 極楽律寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 東国花の寺霊場の御朱印(御本尊)
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
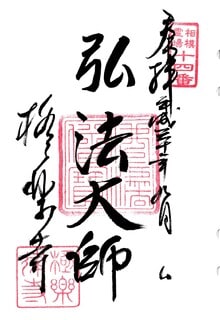

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

鎌倉十三仏霊場の御朱印
61.導地蔵堂(みちびきじぞうどう)
鎌倉市極楽寺2-2-2
真言律宗西大寺派?
御本尊:地蔵菩薩
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第20番
※御朱印は極楽律寺にて授与。
導地蔵堂は導地蔵尊を安する鎌倉二十四地蔵霊場第20番の札所で、極楽寺地蔵尊とも呼ばれます。
『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記の史料などを参考に縁起沿革を追ってみます。
導地蔵堂は文永四年(1267年)、極楽寺の忍性が運慶作の地蔵像を安置したのが創始といわれています。
『新編相模國風土記稿』には「(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二 一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持」とあり、おそらく前者の「運慶の作佛」が導地蔵尊とみられます。
子育てに霊験あらたかで、この地蔵尊の視野の中にいる子どもたちを災難から守るとされることから「導(き)地蔵」と呼ばれます。
幼い子の宮参りの帰りにはこの地蔵尊に赤飯を供え、子の安全成長を祈るのがこのあたりの風習といいます。
鎌倉時代~室町にかけて戦火に遭うも、室町時代に地蔵尊を新たに造立、堂宇に安置されたといいます。
なお、極楽寺の忍性については、60.極楽律寺の記事をご覧ください。
当尊については史料・資料がすこぶる少なく、この程度しかご紹介できません。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二
一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持。
-------------------------
江ノ電「極楽寺」駅至近です。
駅の出口は反対側、桜橋で江ノ電の線路を渡るとすぐに「導地蔵堂」があります。
山肌を背に、寄棟造で朱色の銅板本瓦棒葺の大ぶりな堂宇です。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
屋根は二重で、下の屋根は雨よけになっており、縁側には観光客が座って休んでいました。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
身舎に「導地蔵」の板がかかり、地蔵堂であることがわかります。
扉は開いている場合があり、そのときはお厨子のなかに御座す木立像の導地蔵尊を拝せます。
大きな瞳で前方を見つめられ、子供の安全を見守られているかのようです。


【写真 上(左)】 尊格板
【写真 下(右)】 導地蔵尊
御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。
〔 導地蔵堂(鎌倉二十四地蔵霊場)の御朱印 〕
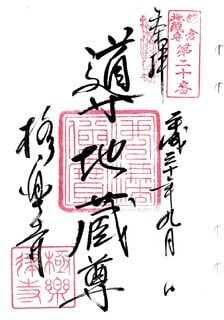
→ ■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)へつづく。
【 BGM 】
■ Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love
〔 From 『Bobby Caldwell』(1978)〕
■ Natalie Cole - Split Decision
〔 From 『Everlasting』(1987)〕
■ King Of Hearts - Don't Call My Name
〔 From 『King Of Hearts』(1994)〕
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)
■ 同-21 (C.極楽寺口-4)から。
60.霊鷲山 感応院 極楽律寺(ごくらくりつじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市極楽寺3-6-7
真言律宗西大寺派
御本尊:釈迦如来
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番、鎌倉十三仏霊場第12番(大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第1番
※鎌倉二十四地蔵霊場第20番導地蔵尊、同第21番月影地蔵尊を護持
極楽律寺は真言律宗の名刹で極楽寺とも呼ばれます。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
極楽寺の開基は北条重時、開山は忍性菩薩(良觀上人)とされますが、草創はそれ以前に遡るとみられています。
Wikipedia等によると『極楽寺縁起』には「深沢(現・鎌倉市西部)に創建された念仏系の寺院(開山正永和尚)」が草創とあるようです。
(『極楽寺由緒沿革書』には永久年間(1113-1118年)、僧勝覚の創建とあるとも。)
また、『元亨釋書』には正嘉(1257-1259年)の頃に一沙門が一宇を建て、丈六の彌陀像を安して極楽寺を号したとあり、極楽寺の草創については諸説あります。
鎌倉幕府2代執権・北条義時の三男で幕府連署であった重時(極楽寺殿)は、この極楽寺が寺域が狭く整備も足りないことから、正元元年(1259年)忍性菩薩(良観上人・良観房)に諮ったところ、西南の「地獄谷」と呼ばれる霊場こそ招提すべき地であるとの教示を得ました。
重時は早速地獄谷の地に極楽寺を遷し、自身が開基となりました。
重時は建長八年(1256年)に出家し、(今の)極楽寺の山庄に隠居しているので、隠居後に極楽寺を開基していることになります。
『吾妻鏡』には、重時は弘長元年(1261年)6月病に倒れるも、鶴岡八幡宮別当隆弁の加持により回復したとあります。
『新編鎌倉志』には「発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終る」とあり、重時は往生まで極楽寺にて念佛三昧で過ごしたことになります。
弘長元年(1261年)11月3日逝去。
重時の子長時(鎌倉幕府6代執権)・業時兄弟は極楽寺を修営したとあり、子院四十九院を擁して伽藍は壮麗をきわめたといいます。
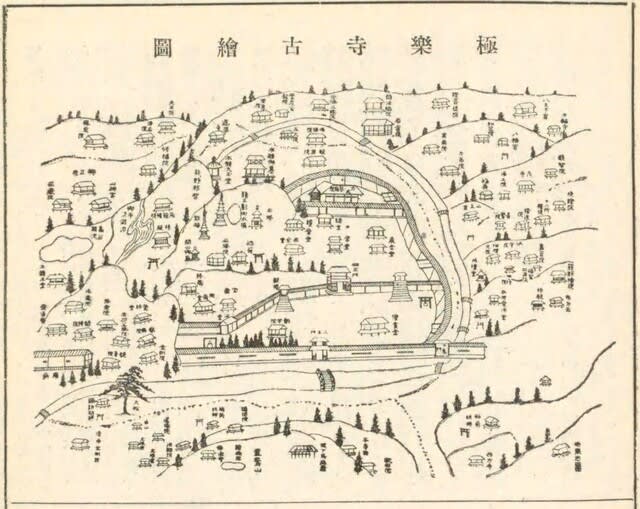
(雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻,雄山閣,昭7-8. 国立国会図書館デジタルコレクションより転載/インターネット公開(保護期間満了))
『新編相模國風土記稿』収録の「極楽寺古繪図」には伽藍が立ち並ぶ山内が描かれ、一大霊地を構成していたことがわかります。
最盛期には現在の極楽寺のみならず、稲村ヶ崎小学校の建つ谷一帯が極楽寺の山内で、現在江ノ電が走る極楽寺川沿いの谷には病者・貧者救済の施設があったとみられます。
(現・立稲村ケ崎小学校が最盛期の中心伽藍の地とみられています。)
『吾妻鏡』には、重時の三回忌法要は弘長三年(1263年)極楽寺で西山浄土宗の宗観房を導師として催行とあり、この時点では極楽寺は浄土教系寺院との見方があります。
しかし文永四年(1267年)8月に忍性菩薩を請して開山とし、当寺に移住した時点では「真言律(宗)」に改めていたとみられます。
忍性(にんしょう、忍性菩薩、1217-1303年)は、通称良観とも呼ばれます。
大和国の生まれで、幼くして文殊菩薩信仰に目覚め、師叡尊から真言密教・戒律受持・聖徳太子信仰を受け継いだといいます。
聖徳太子の「四箇院の制」に感銘を受け、とくに病者に薬を施す施薬院、病者を収容治療する療病院、身寄りのない者や年老いた者を収容する悲田院を重んじ、社会的弱者の救済に尽力したことで知られています。
弘長二年(1262年)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、文永四年(1267年)8月には極楽寺を開山しています。
師の叡尊は、忍性の生来の慈悲心が弱者救済に適していると見抜き、この役割を忍性に託したという見方があります。
実際、忍性が開山した極楽寺山内にも療病院、悲田院、癩宿などが設けられています。
忍性は道路の改修や橋梁の架設などを行い、極楽寺坂切通を拓いたのも忍性と伝わることから、忍性は優れた土木技術を持つ人々を抱えていたとみられています。
忍性の多岐にわたる功績は広く称えられ、嘉元元年(1303年)87歳で示寂の後、後醍醐帝より菩薩号を贈られています。
忍性菩薩、そして極楽寺を語るとき、「真言律(宗)」は外せないのでこれについてまとめてみます。
「真言律(宗)」については、■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9の第28番霊雲寺で整理しているので、ほぼそこからの再掲となります。
真言律(宗)とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。
弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。
叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。
「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。
→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)
真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。
以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。
叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。
叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。
『新編相模國風土記稿』には「弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺(極楽寺)を御願場とす」とあります。
江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。
明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。
真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。
とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。
元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。
もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。
のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。
この点からしても、中世の極楽寺は勅願祈願寺としての性格も強かったとみられます。
なお、鎌倉と律宗との関係をみるとき、願行上人憲静(1215-1295年)の存在は欠かせません。
願行上人は北京律(ほっきょうりつ)の法統とされますが、真言律宗の名刹、金沢の称名寺とも関係があったとみられており、極楽寺ともなんらかの関係があったのかもしれませんが、調べた限りでは詳細不明です。
→ 関係記事(■ 鎌倉市の御朱印-7)
極楽寺に戻ります。
元弘三年(1333年)には後醍醐帝の綸旨を賜り寺領を安堵され後醍醐帝の勅願所となりましたが、その後度重なる戦乱や火災により寺勢は衰微しました。
天正十九年(1591年)、徳川家康公より九貫五百文の朱印地を得たものの、再び荒廃し、一時無住の時期もあったといいます。
天保十二年(1841年)成立の『新編相模国風土記稿』には「塔頭 吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す」とあり、最盛期には49を数えた子院が、天保にはわずか1院となったことがわかります。
そのなかには他地へ移った寺院もあるとみられます。
たとえば、横浜市港北区新羽の西方寺の公式Webには「極楽寺の一院として存在した西方寺は、極楽寺坂切り通しの北側崖上にあり、その付近が古図に示す西方寺の所在と一致し、歴代住侶の墓石十基ほどを残し今も存在し、西方寺跡とされています。」「極楽寺より西方寺が移転されたのは、明応年間(1492)で今から五百年ほど前のこと」とあり、極楽寺の一院であったことを明記しています。


【写真 上(左)】 西方寺
【写真 下(右)】 西方寺の御朱印
栄枯盛衰の歴史を辿った極楽寺ですが近世に復興し、複数の霊場の札所も兼ねて、いまは多くの拝観客が訪れています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
極楽寺
極楽寺、霊山山と号す。眞言律にて、南都西大寺の末寺なり。開山は、忍性菩薩、良觀上人と号す。
当寺は、陸奧守平重時が建立なり。重時を極楽寺と号し、法名觀覺と云。【東鑑】に、弘長元年(1261年)十一月三日、平重時卒す。年六十四、時に極楽寺の別業に住す。発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終るとあり。按ずるに、【元亨釋書】に、初め正嘉(1257-1259年)中に沙門あり。一宇を営で、丈六の彌陀の像を安ず。名て極楽寺と云。未落せずして亡す。平重時、其宇を今の地に遷して齋場とす。重時の子長時・同弟業時、力を戮て修營すとあり【帝王編年記】に、永仁六年(1298年)四月十日、関東の将軍家久明親王、御祈祷の為に、十三箇寺の寺領の違亂を停止、殺生禁断の事あり。相州鎌倉郡の極楽寺、其一つなり。
此寺、昔は四十九院ありしとなり。今吉祥院と云のみあり。寺領九貫五百文あり。又千服茶磨とて、大なる石磨、門を入右の方にあり。昔此寺繁昌なりしを、知らしめんが為なりといふ。
本堂
本尊は釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸したりといふ。十大弟子の像もあり。作者不知。
左に興正菩薩の木像、自作といふ。
右に忍性菩薩の木像、是も自作と云。
又文殊の坐像あり。古への文殊堂の本尊なりと云ふ。(略)
寺寶
九條袈裟 壹頂 乾陀穀子袈裟、東寺第三傳と書付あり。今按ずるに、乾陀穀子袈裟は、弘法大師の伝来にて、八祖相承とて、東寺の寶物なり。今此寺に所有は、其袈裟を摸したる、第三伝と見へたり。(中略)
二十五條袈裟 壹頂 紗なり。八幡大神の所持と云ふ。按ずるに八幡へ調進の物なり。(中略)
千體地藏 弘法作。本尊は、長一寸餘。千體は長五六分ばかり也。今皆紛失して纔に二三百ばかり残れり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
極楽寺
霊山山と号す。眞言・律、南都西大寺末なり。
開山は忍性菩薩良觀上人、開基は陸奧守重時が、法号をば極楽寺觀覺と称す。(中略)
古は谷々に四十九院ありしといふ。今は吉祥院といふ一院ばかり。
本堂
本尊釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸せしといふ。十大弟子の像もあり。作不知。
左に興正菩薩の自作の木像、右に忍性菩薩の是も自作の木像といふ。
文殊の坐像もあり。古への文殊堂の本尊なりといふ。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(山之内庄極楽寺村)極楽寺
霊鷲山感應院と号す。眞言律宗南都西大寺末。
北條陸奧守重時が草創なり、始正嘉(1257-1259年)中に一老衲ありて一宇を営み丈六の彌陀像を安じ、名づけて極楽寺と云ふ。然るに経営の功未だ完かずして老衲尋て寂しぬ
正元(1259-1260年)の初重時寺域の狭小なるを見て地を卜して新に創立せんと欲し僧忍性に議しけるに、性答て是より西南に当り地獄谷と云へる霊場あり、此地こそ招提の境なれと云て即性彼地に到り念誦す、須㬰にして感應あり、重時就て一宇を遷して斎場とす、地獄谷は今の境内なりと云ふ
重時の子武蔵守長時其弟業時等力を戮て修飾し、子院四十九院を構造す、堂宇壮麗に一刹となる
時に性(忍性)を請して開山始祖とす、文永四年(1267年)八月性(忍性)当寺に移住せり
弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺を御願場とす
性(忍性)嘉元元年(1303年)七月十二日寂す 嘉暦三年(1328年)後醍醐帝性(忍性)の行徳を追崇ありて菩薩の号を賜ふ
元弘二年(1332年)六月勅願寺幷寺領安堵の事
其後堂宇漸く衰廃し、今は仏殿一宇塔頭一院のみ残れり
本尊釋迦 大像長六尺余、興正作、十大弟子の像を置く 毘首羯磨作、脇に興正菩薩 坐像自作長三尺及び聖徳太子の像 立像長二尺三寸余、運慶作、又文殊の像あり、古昔域内別堂に安ぜし本尊なりと云ふ
寺寶
乾陀穀子袈裟 一領 東寺第三傳とあり、元は京都東寺にありしに、永仁元年(1293年)十二月八日、当寺に贈りしとなり、今按ずるに、この袈裟は、東寺の寶物にて【元亨釋書】空海の伝に、弘安十四年正月勅以東寺賜空海乃置惠果所付、健陀國袈裟及念珠為寺鎮と載す、文字違へり健陀●は西域の國名なり(中略)
二十五條袈裟 一領 八幡太神の御袈裟と云へど、是は八幡宮へ調進せし物ならんと
北條陸奧守重時墓
寺後の山にあり、重時は左京太夫義時の三男なり、弘長元年(1263年)十一月三日当所別業に在て卒す、法名を觀覺極楽寺と称す
塔頭
吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す、本尊不動を置く 座像二尺五寸智證作
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 真言律宗
山号寺号 霊鷲山感応院極楽律寺
建立 正元元年(1259年)
開山 忍性菩薩
開基 北条重時
開山は良観房忍性。奈良西大寺叡尊門下で戒律を学ぶ。弘長二年(一二六二)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、その後文永四年(一二六七)に極楽寺に開山として迎えられました。
極楽寺は正元元年(一二五九)に深沢に創建され、後に開基となる北条重時が現在地に移転したといわれています。元寇に際しては、幕府の命により異国降伏の祈祷を行い、また、鎌倉幕府滅亡後も勅命により国家安泰を祈る勅願所としての寺格を保ちました。かつての寺域は広大で、中心の七堂伽藍を囲むように多くの子院、そして療病院などの病院施設もあったことが当寺に伝わる絵図からわかります。
-------------------------


【写真 上(左)】 極楽寺駅
【写真 下(右)】 極楽寺駅ホームから
江ノ電「極楽寺」駅至近でホームから見えます。
駅の出口は反対側なので、桜橋で江ノ電の線路を渡って「導地蔵尊」の前を左に折れるとすぐです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標と墓標
少しく引きこんで山門。
手入れの行き届いた植栽、落ち着いたただずまいは鎌倉の名刹ならではのもの。
こちらは以前は境内撮影禁止でしたが、現在は解除されている模様です。
解除後参拝しておらず、山内の写真がまったくないので、↓の動画を参考にご案内します。
■ 極楽寺駅周辺と極楽寺 (鎌倉市極楽寺)
山門手前左に、開山忍性菩薩・開基北条重時の墓標と寺号標。
山門は趣ある茅葺屋根。左右に脇塀を備えた四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を置く堂々たる山門です。
主門は柵で閉ざされているので脇門の木戸から入内します。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
山門から真っ直ぐに桜並木の石畳参道が伸び、正面が本堂。
参道右手に大師堂と転法輪殿(収納庫)。
参道左手には客殿、納経所と本堂よこに資料館があります。


【写真 上(左)】 冬の山内
【写真 下(右)】 山門から本堂
度重なる天災や兵火のため当初の伽藍は失われ、現在は文久三年(1863年)再建の山門、本堂、大師堂、客殿がメインです。
西側山手には忍性塔があり、こちらは奥の院となっています。
忍性塔は高さ3.57メートルの大型の石造五輪塔で、納置品から嘉元三年(1303年)頃の建塔とみられ、国の重要文化財に指定されています。
通常は非公開で、毎年4月8日のみ公開の模様。
塔内納置品は良観房忍性和尚と同二世賢明房慈済和尚の舎利容器であることから、忍性の墓塔ともいわれます。こちらも国の重要文化財に指定されています。
五輪塔(伝・忍公塔、非公開)は忍性塔の右方にある石造五輪塔で、かつては北条重時の墓塔とされ、昭和2年国の史跡に指定されました。
しかし、昭和36年の豪雨で塔が倒れた際、塔内から発見された納置品より当山3世善願坊順忍と比丘尼禅忍の供養塔であることが判明しています。
忍性塔の周囲にある宝篋印塔が北条重時の墓塔とみる説もあります。
大師堂は宝形造銅板瓦棒葺で向拝柱はありません。
鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番の札所板が掲げられ、霊場拝所となっています。

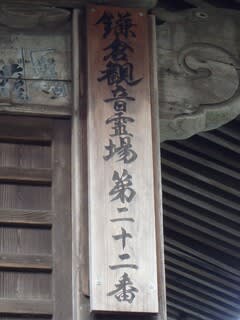
【写真 上(左)】 鎌倉観音霊場札所板
【写真 下(右)】 同 札所標

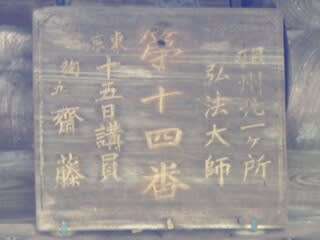
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-1
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-2
鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印には「常磐御前念持佛」の印判がありますが、これを裏付ける史料はみつかりませんでした。
転法輪殿(収納庫)はがっしりとした近代建築で、御本尊である秘仏「清凉寺式釈迦如来」、伝来の木造十大弟子像、木造釈迦如来坐像などが収納されています。
本堂はおそらく宝形造銅板葺流れ向拝で四周に高欄をまわし、屋根勾配が急な特徴ある意匠です。
頂部露盤には北条氏の家紋「三つ鱗紋」とおぼしき紋が刻まれています。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置いています。
Wikipediaによると、
本堂の須弥壇中央に不動明王坐像、向かって右に薬師如来坐像、左に文殊菩薩坐像を安置。右奥には忍性像、左奥には興正菩薩(叡尊)像を安置するとのこと。
文殊菩薩坐像はかつてあった文殊堂の御本尊ゆかりの像とみられ、忍性像、興正菩薩(叡尊)像も史料にあらわれています。
不動明王坐像は平安時代末期の作といい、島根県の勝達寺から大正5年に移されたとの由。
向拝に地蔵尊のご縁日が張り出されているので、地蔵尊も奉安とみられます。
通常本堂内は非公開で、4月7日-9日のみ入堂できるようです。
なお、史料に見える聖徳太子像(伝運慶作)、弘法大師が師の惠果阿闍梨から贈られた乾陀穀子袈裟(東寺蔵)の写し(?)などについては所在の調べがつきませんでした。
あるいは、転法輪殿(収納庫)か資料館に収蔵されているのかもしれません。
本堂前には「不許葷酒肉入山門」と刻した戒壇石。戒律の厳しい真言律宗らしい標石です。
本堂向かって右前には「千眼茶臼」「製茶鉢」。
開山の忍性菩薩が悲田院、施益院などを設置されたときに使用されたものと伝わります。
参道右手、授与所前には子育地蔵尊の露仏が御座、参道山門寄り左手には忍性菩薩が粥を施すために使用したという「極楽寺の井」もあります。
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。
複数の霊場札所を兼務されているので、霊場申告は必須です。
また、鎌倉二十四地蔵霊場第20番の導地蔵尊、同第21番の月影地蔵尊の御朱印もこちらで拝受できますが、当然先にお参りしてからの申告となります。
〔 極楽律寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 東国花の寺霊場の御朱印(御本尊)
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
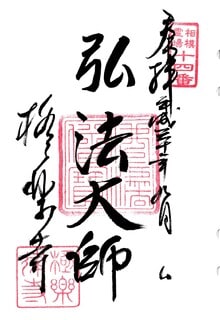

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

鎌倉十三仏霊場の御朱印
61.導地蔵堂(みちびきじぞうどう)
鎌倉市極楽寺2-2-2
真言律宗西大寺派?
御本尊:地蔵菩薩
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第20番
※御朱印は極楽律寺にて授与。
導地蔵堂は導地蔵尊を安する鎌倉二十四地蔵霊場第20番の札所で、極楽寺地蔵尊とも呼ばれます。
『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記の史料などを参考に縁起沿革を追ってみます。
導地蔵堂は文永四年(1267年)、極楽寺の忍性が運慶作の地蔵像を安置したのが創始といわれています。
『新編相模國風土記稿』には「(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二 一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持」とあり、おそらく前者の「運慶の作佛」が導地蔵尊とみられます。
子育てに霊験あらたかで、この地蔵尊の視野の中にいる子どもたちを災難から守るとされることから「導(き)地蔵」と呼ばれます。
幼い子の宮参りの帰りにはこの地蔵尊に赤飯を供え、子の安全成長を祈るのがこのあたりの風習といいます。
鎌倉時代~室町にかけて戦火に遭うも、室町時代に地蔵尊を新たに造立、堂宇に安置されたといいます。
なお、極楽寺の忍性については、60.極楽律寺の記事をご覧ください。
当尊については史料・資料がすこぶる少なく、この程度しかご紹介できません。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋
(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二
一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持。
-------------------------
江ノ電「極楽寺」駅至近です。
駅の出口は反対側、桜橋で江ノ電の線路を渡るとすぐに「導地蔵堂」があります。
山肌を背に、寄棟造で朱色の銅板本瓦棒葺の大ぶりな堂宇です。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
屋根は二重で、下の屋根は雨よけになっており、縁側には観光客が座って休んでいました。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
身舎に「導地蔵」の板がかかり、地蔵堂であることがわかります。
扉は開いている場合があり、そのときはお厨子のなかに御座す木立像の導地蔵尊を拝せます。
大きな瞳で前方を見つめられ、子供の安全を見守られているかのようです。


【写真 上(左)】 尊格板
【写真 下(右)】 導地蔵尊
御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。
〔 導地蔵堂(鎌倉二十四地蔵霊場)の御朱印 〕
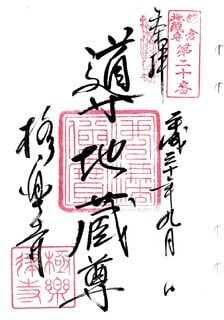
→ ■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)へつづく。
【 BGM 】
■ Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love
〔 From 『Bobby Caldwell』(1978)〕
■ Natalie Cole - Split Decision
〔 From 『Everlasting』(1987)〕
■ King Of Hearts - Don't Call My Name
〔 From 『King Of Hearts』(1994)〕
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-5
最新情報を追加しました。
Vol.-4からのつづきです。
■ 第15番 瑞光山 如意寺 密嚴院
(みつごんいん)
荒川区荒川4-16-3
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第83番
第15番札所は荒川区荒川の密嚴院・三河島大師です。
下記史料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。
密嚴院は天文二年(1533年)、覚錟ないし覺生和尚の開基と伝え、山内には同九年(1540年)銘の板碑(荒川区登録文化財)も残ります。
南側にある清瀧山観音寺の末寺で、新義真言宗豊山派に属します。
観音寺は、天文年中(1532-1553年)に長偏僧都が開基創建した名刹で、江戸時代には将軍鷹狩りの際の御膳所にあてられていました。
このエリアの獲物は鶴で、鶴の捕獲を目的とする将軍放鷹は「鶴お成り」と格別に称され、捕らえた鶴は天皇に献上する習わしとなっていました。
密嚴院の御本尊は、一尺八寸の如意輪観世音菩薩立像といいます。
『豊島八十八ヶ所巡礼』には「本尊の如意輪観音は弘法大師作と伝えられ、文化十四年(1817年)に高野山から勧請されたもの」とあります。
境内に弘法大師堂があり「三河島大師」と称され、毎月廿一日の護摩修行は信仰者で賑わったといいます。
御府内二十一霊場札所として、本寺の観音寺ではなく密嚴院が選ばれたのは「三河島大師」の名声が高かったためではないでしょうか。
なお、『荒川区史』には「当院は豊島『八十八ヶ所』の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。」とありますが、「新四國八十八ヶ所の内第四十二番」についてはよくわかりません。
境内には竜女塚があり、塚上にあった文政十三年(1830年)の石碑、本堂・庫裡等は昭和20年の東京大空襲の際に失われたといいます。
伽藍は終戦後に再建されていますが、現在は無住で、観音寺が護持されているようです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)
(三河島村)密嚴院
(三河島村)観音寺末 瑞光山如意寺ト号ス 本尊如意輪観音
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
密嚴院(三河島町五丁目九六七番地)
観音寺の北隣にある密嚴院は、瑞光山如意寺と号して、新義真言宗豊山派に属し観音寺の末寺である。本尊如意輪観音は其の丈け一尺八寸の立像である。
開山は覺生和尚と云はれるが詳細は不明である。
境内に弘法大師堂がある。敷地四百六十五坪余。毎月廿一日に護摩修行がある。
当院は豊島「八十八ヶ所」の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。
-------------------------
京成線「町屋」駅とJR常磐線「三河島」駅の中間くらい、近くに荒川区役所はありますが、区民以外はなかなか訪れないところ。
戸建て、マンション、ビルや町工場が混在する下町らしい街区です。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 院号標
観音寺の北東側の路地に面していますが、山内はなかなか広そうです。
参拝時は門扉が堅く閉ざされていたので、山内の詳細はわかりません。


【写真 上(左)】 三河島大師の標
【写真 下(右)】 弘法大師の石標
門柱には「院号」と「三河島大師」の刻字。
鉄扉には真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」。
門柱手前には「開運厄除弘法大師」の石標が建ち、弘法大師霊場であることを示しています。
鉄扉ごしに近代建築陸屋根の本堂が見えますが、詳細は不明です。
御朱印は観音寺にて拝受しました。(以前の情報)
「門扉が閉まっていたので、門前からの参拝となった旨」申告しましたが、現在、閉門中につきその参拝方法でよろしいということで、快く御朱印を授与いただけました。
※ 現在(2024年秋)、密嚴院の御朱印は円性寺(足立区東和1-29-22)で授与されています。
御府内二十一ヶ所霊場、豊島八十八ヶ所霊場ともに拝受できます。
〔 密嚴院の御朱印 〕
〔 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕
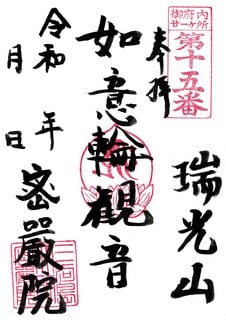
中央に如意輪観音の揮毫と如意輪観音のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内廿一ヶ所第十五番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第16番 五剣山 普門寺 大乗院
(だいじょういん)
台東区元浅草4-5-16
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番
第16番札所は元浅草の大乗院です。
下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
大乗院の創建年代は不詳ですが、『江戸志』には増誉法印の開山とあります。
『寺社書上』『御府内寺社備考』には、江戸大塚護国寺末、境内古跡拝領地五百坪とあります。
本堂は四間四方で、御本尊は丈壱尺三寸の不動明王立像と記されています。
本堂内奉安の弘法大師御像は「江戸八十八ヵ所之内八十一番」とあり、これは荒川辺八十八ヶ所霊場第81番をさしているとみられます。
『江戸砂子』には「波断不動」ともあるようです。
山内に護摩堂、天王社も擁していたとみられます。
当山は度々類焼に見舞われたためか史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。
しかし、荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺の3つの弘法大師霊場札所を兼務されているわけですから、弘法大師とのゆかりのふかい寺院であると考えられます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.45』
江戸大塚護國寺末 浅草新寺町
五釼山普門寺大乗院 境内古跡拝領地五百坪
当寺書留●度々類焼之為焼失仕 年数其外共●相知不申候
本堂 四間四方
本尊 不動明王、丈ヶ壱尺三寸立像
弘法大師 江戸八十八ヵ所之内八十一番
護摩堂
天王社 九尺四方 神体幣束
二王門 二天門 山門 楼門
波断不動(江戸砂子)
開山増誉法印 (江戸志)
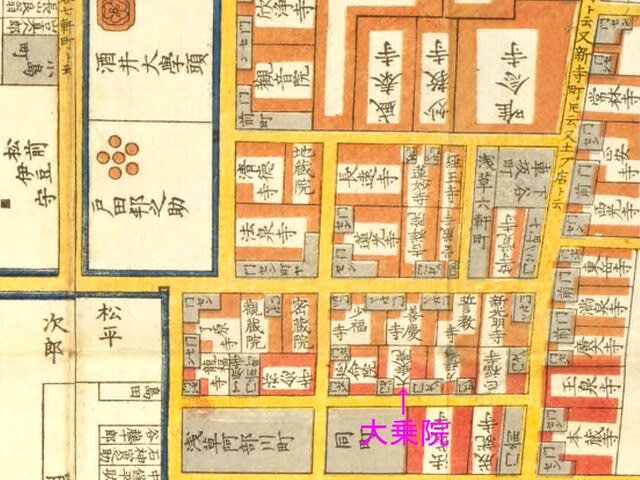
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。
住宅とオフィスビルが混在する立地。
元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から南下する左右衛門橋通りの1本東側の路地を南に入って正福院を過ぎたすぐ先です。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 院号標
路地から少し引きこんだ民家風の建物なので、参道入口の院号札を見落とすとそれとわかりません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
参道をたどり、本堂に近づくにつれて寺院らしい雰囲気が高まります。
建物手前が向拝。
正面はシックな格子扉、壁面には真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」、見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 札所標
向拝手前の「弘法大師 第十六番」と刻まれた立派な石標は、御府内二十一ヶ所霊場の札所標です。
こちらは何度かの参拝でご不在気味だったので、特別にお願いして御朱印を授与いただきました。
通常は不授与の可能性があります。
〔 大乗院の御朱印 〕

中央に不動明王の揮毫と、不動明王のお種子「カン/カ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左に山号・院号の揮毫があります。
■ 第17番 和光山 興源院 大龍寺
(だいりゅうじ)
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:(上田端)八幡神社
他札所:御府内八十八ヶ所霊場第13番-2、豊島八十八ヶ所霊場第21番、滝野川寺院めぐり第6番
※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4 をベースに再編しています。
第17番札所は田端の大龍寺です。
真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所でもあります。
こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。
御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。
そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。(ただし、こちらは別霊場とみられる「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。
ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。
ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺、当山を入れると8)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。
いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。
下記史料等によると創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。
『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

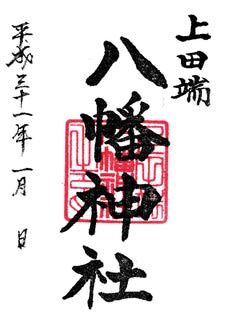
【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社
【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)
(西ヶ原村)大龍寺
眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ 天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置
八幡社 村ノ鎮守トス
稲荷社
-------------------------
JR「駒込」駅と「田端」駅のほぼ中間、上野から日暮里、田端、西ヶ原、飛鳥山とつづく台地のうえにあります。
落ち着いた住宅地のなかに名刹らしい広大な寺地を構えています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。
拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
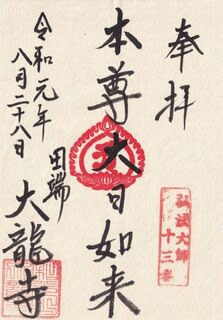
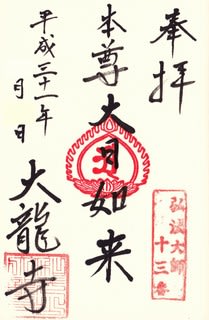
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第18番 象頭山 観音寺 本智院
(ほんちいん)
北区滝野川1-58-2
真言宗智山派
御本尊:
札所本尊:
司元別当:鳥越大明神(鳥越神社)?
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第80番、弘法大師二十一ヶ寺第18番、北豊島三十三観音霊場第28番
第18番札所は北区滝野川の本智院(滝野川不動尊)です。
下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
『御府内寺社備考』によると本智院は当初八丁堀辺に起立されたといいます。
明暦年間(1655-1658年)に記録焼失とあるので、すくなくともそれ以前の起立とみられます。(元和年中(1615-1624年)開基という資料あり。)
同書には「京都智積院末」とあり、智積院直末というすこぶる格の高い寺院であった可能性があります。
中興開山は権大僧都法印明実(元禄二年(1689年)寂)。
『寺社書上』(文政年間(1818-1830年)編纂)には「仮本堂」とあるので、この時期なんらかの理由で仮の本堂となっていたとみられます。
とはいえ間口六間奥行三間の堂々たる堂宇です。
御本尊は金剛界大日如来木像。
本堂には弘法大師木座像、興教大師木座像、阿弥陀木立像、正観音木立像を安すと記されています。
聖天堂は宗対馬守建立とあり、対馬藩主宗家の建立かもしれません。
安する長七寸五分の聖天銅立像は弘法大師の御作で赤松円心(赤松則村、1277-1350年、村上源氏赤松氏4代当主で播磨国守護)の所持と記されています。
甲宵聖天像も弘法大師の御作で赤松円心の所持とあります。
本地は十一面観世音菩薩木立像、長一尺七寸五分で恵心僧都作とあります。
弁財天並びに十五童子も弘法大師の御作で、「江の嶋にて十万座護摩修行、其灰を以て作り裏に手判有之」とあります。
正観音立像も弘法大師の御作とあります。
山内に鎮守十二所権現、長珠院・不動院の二ケ院を擁したとあります。
弘法大師御作と伝わる尊像を幾軆も安し、対馬の宗氏、赤松円心という名族とのゆかりをもつことからみても、相応の寺格を有していたとみられます。
荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺という3つの弘法大師霊場の札所を務められることについては、寺格の高さもさることながら、複数の弘法大師御作の尊像を安するという所以によるのではないでしょうか。
明暦年間(1655-1658年)に焼失後、浅草(不唱小名)に移転といいます。
『江戸切絵図』には、浅草新寺町の仙蔵寺と玉宗寺の間に「本智院」とみえるので、現在の台東区寿二丁目あたりとみられます。
大正になされたという滝野川への移転の経緯は、当然下記史料には記載がありません。
「猫のあしあと」様記載の『北区史』には「もと浅草区(現台東区)栄久町一三二にあつた。幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた程の由緒ある寺で、元和年中(1615-1624年)開基、大正六年五月区内の滝野川町四八都電飛鳥山終点の所に移転の許可を得て新築し、大正十年五月に移転をおえた。滝野川の不動として知られ本尊は不動明王である。」とあります。
『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた」という記載が気になるので、いささか長くなりますが鳥越神社(鳥越大明神)について辿ってみます。。
鳥越神社の別当は御府内八十八ヶ所霊場第51番であった鳥越の長樂寺だった筈です。
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17
鳥越大明神(鳥越神社)は白雉二年(651年)村人が日本武尊の遺徳を偲び、白鳥明神として鳥越山(白鳥山)に祀ったのが創祀と伝わる古社です。
往年のこの地は「鳥越(白鳥)の山」と呼ばれた小高い丘で、日本武尊が東夷御征伐の折に暫く御駐在された地といいます。
相殿の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、中臣(藤原)氏の祖神として祀られ、奈良時代に藤原氏が国司として武蔵に赴任した際、この地にお祀りされたといいます。
永承(1046-1053年)の頃、八幡太郎義家公の奥州征伐の折、この地で渡河に難儀しましたが、白い鳥に浅瀬を教えられて無事軍勢を進めることができました。
義家公はこれを白鳥大明神の御加護と称え、鳥越山(白鳥山)のお社を参拝され「鳥越大明神」の号を奉じられて、これより「鳥越」の地名が起こったとされます。
社地はすこぶる広く、三味線堀(姫が池)に熱田明神、森田町に第六天神(榊神社)が末社として御鎮座され「鳥越三所明神」と称していました。
徳川幕府による旗元・大名屋敷・御蔵地整備のため、鳥越山はとり崩されて埋め立てに使われました。
この際、熱田神社は三谷(現・今戸)へ、榊神社は堀田原(現・蔵前)へと御遷座され、鳥越大明神も御遷座を迫られましたが、第二代神主鏑木胤正の請願が容れられて元地に残られました。
別当・長樂寺は『寺社書上』によると、開山の法印の遷化が寛永二十年(1643年)なので、3代将軍家光公の治世(1623-1651年)までには創建とみられます。
鳥越山轉輪院長樂寺と号し、山号は本社から、院号は兼帯していた京都嵯峨轉輪院永院室から号したものとみられます。
本社・鳥越大明神の御本地馬頭観音、御本尊として不動明王を奉安していました。
弘法大師御像も奉安していたため、御府内霊場札所の要件はきっちり満たしていたとみられます。
鳥越大明神の神職鏑木氏は桓武平氏常将流と伝わり、鳥越神社の社紋として月星紋・九曜紋(千葉氏の紋)が使われているようです。
また、長樂寺に星供養曼荼羅が奉安されていたことからも、妙見信仰の千葉氏との関係がうかがわれます。
鳥越大明神と別当・長樂寺は源氏の棟梁・八幡太郎義家公、桓武平氏の代表姓・千葉氏いずれともゆかりをもつ、複雑な来歴をもたれているのかもしれません。
明治初期の神仏分離で別当の長樂寺は廃寺となり、以降は鳥越神社と号して郷社に列せられました。
例大祭・鳥越祭は都内随一の重さを誇る「千貫神輿」の渡御と、夜に行われる荘厳な宮入で「鳥越の夜祭り」として広く知られています。
以上、鳥越神社の沿革を辿ると、別当として長樂寺の名は出てきますが、本智院との関係は明示されていません。
結局のところ、『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあった」という記載の根拠についてはよくわかりませんでした。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [77] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.33』
京都智積院末 浅草不唱小名
象頭山観音密寺本地院 境内古跡拝領地六百七拾二坪
当寺往古八丁堀辺に起立之由申伝候得● 明暦年中(1655-1658年)類焼之節記録焼失仕相知不申候
中興開山 権大僧都法印明實(元禄二年(1689年)寂)
仮本堂 間口六間奥行三間
本尊 大日金剛界木像
弘法大師木座像 興教大師木座像 阿弥陀木立像 正観音木立像
聖天堂 土蔵造方三間 拝殿 二間四方宗対馬守建立
聖天銅立像 長七寸五分弘法大師作 赤松円心所持
甲宵聖天像 同作同人所持
本地十一面観音木立像 長一尺七寸五分恵心僧都作
辨財天并十五童子 各長七寸八分弘法大師作
右ハ江の嶋にて十万座護摩修行 其灰を以て作り裏に手判●●
天長七年(830年)七月七日と●●
正観音立像 長九分弘法大師作
大黒天立像 俵千十三俵其上ニ安置長一寸三分
鎮守十二所権現
末社稲荷木立像
右十二所権現稲荷合社ニ有之候所 先年類焼之節焼失仕 当時聖天堂二安置
寺中長珠院不動院と号し候 二ケ院有之候処退廃仕候 年代は相知不申候得共 延享年中(1744-1748年)御改之節 二ケ院共書上候由申伝候得ハ 其比ハ相続仕有之候義ニ御座

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅至近。「王子」駅からも歩けます。
滝野川は寺社が集まる御朱印エリアですが、その多くは明治通り北側の滝野川沿いに立地しています。
明治通りの南側に位置する本智院周辺は、一種のエアポケット的なエリアとなっており、筆者もこの界隈は初訪でした。
都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅のお隣りですが、フェンスがあったりして、やや複雑なアプローチです。


【写真 上(左)】 すぐ横が飛鳥山駅
【写真 下(右)】 外観
山内入口には門柱。院号と「滝野川不動尊」が刻字されています。
入口向かって右脇には身代地蔵堂。堂前の石碑には「江戸三大身代地蔵尊」とあるので、有名な地蔵尊なのかもしれません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 身代地蔵尊


【写真 上(左)】 狛犬と大日堂
【写真 下(右)】 大日堂
山内右手に狛犬と大日堂。
堂内には法界定印を結ばれる胎蔵大日如来が御座します。
Wikipediaに「境内には、1667年(寛文7年)製の石像の大日如来坐像があるが、これは移転時に一緒に移したものである。(出所:『北区史跡散歩』 (東京史跡ガイド17))」とあるので、こちらの大日如来はおそらく浅草時代に造立され、こちらに遷られたとみられます。
参道右手が庫裏で、その先が本堂です。
3階建の建物の右手1階が向拝となっているかたちです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
タイル壁に木造の千鳥破風の向拝が填め込まれたような、個性的な意匠です。
左右の向拝柱に木札が掛けられていますが、読みとれませんでした。
向拝上部に「阿遮羅尊」の扁額。
「阿遮羅」とは不動明王の梵名「acalanātha(アチャラナータ)」の漢字表記で、不動堂を
阿遮羅殿と記す場合があります。

 【写真 上(左)】 扁額
【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 本堂側からの大師堂
本堂から駅寄りに進むと大師堂です。
こちらは通常閉門されていますが、毎月二十一日(お大師さまのご縁日)には解放され、中のお砂踏み場にて巡拝することができます。

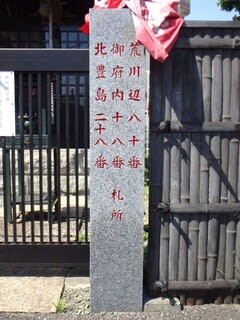
【写真 上(左)】 大師堂門前
【写真 下(右)】 札所標

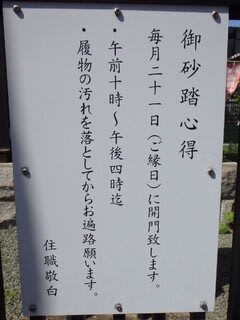
【写真 上(左)】 大師堂よこのお砂踏み場
【写真 下(右)】 御砂踏心得
堂前の門柱は「荒川辺八十番、御府内十八番、北豊島二十八番」の3つの霊場の札所標となっています。

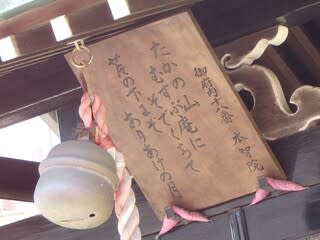
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御府内十八番の御詠歌
大師堂は切妻屋根銅板葺でシックな黒色系の格子扉。
見上には御府内二十一ヶ所第18番の御詠歌が掲げられています。
弘法大師霊場を巡拝していて、このようなしっかりとした大師堂に出会うのはやはり嬉しいものです。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
お不動様のご縁日(28日)に、事前にTELの上お伺いしました。
常時授与かはわからず、ご不在のこともありそうなので事前確認をおすすめします。
〔 本智院の御朱印 〕
〔 荒川辺霊場・御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「本尊 不動明王」の印判と三寶印。
右上に「御府内十八番 荒川辺八十番」の札所印。
左に「瀧野川不動尊」の印判と寺院印が捺されています。
■ 第19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院
(あしゃいん)
荒川区東尾久3-6-25
真言宗豊山派
御本尊:阿遮羅明王(不動明王)
札所本尊:阿遮羅明王(不動明王)
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第63番、荒川辺八十八ヶ所霊場第10番
第19番札所は荒川区東尾久の阿遮院です。
下記資料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。
阿遮院の開基創立等は不明ですが、延元三年(1338年)銘の板碑が所蔵されています。
尾久に於ける最古の寺院と伝えられ、「尾久町字大門」の地名は当院の大門があった事によるとの説があります。
『新編武蔵風土記稿』には、新義真言宗で田端村與楽寺の末とあります。
『江戸切絵図』には、東尾久とおぼしきところに「阿比院」とあります。
荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)
旧本堂は中興の巌永上人により天保二年(1831年)建立といいますが、震災により失いました。
御本尊の阿遮羅明王(不動明王)は、良辨僧都(689-774年)の作と伝えます。
『荒川区史』には「境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。」と記されています。
本尊は阿遮羅明王(不動尊、梵名アシャラナータ)で、こちらが山号・院号の由来といいます。
山内には延元三年(1338)の板碑が所蔵され、元禄十四年(1701年)の光明真言供養塔があります。
『新編武蔵風土記稿』には、東尾久の華蔵院、町屋の慈眼寺は阿遮院の末寺・門徒とあります。
当山についての史料類は多くはありませんが、末寺をもっていたこと、豊島八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、荒川辺八十八ヶ所霊場の3つの弘法大師霊場の札所を兼務されていること、また、現在の寺容からみても相当の名刹と思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)
(下尾久村)阿遮院
新義真言宗、田端村與楽寺ノ末 阿遮山蓮葉寺ト号ス 本尊不動
稲荷社
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
阿遮院(尾久町一丁目八九七番地)
新義真言宗豊山派に属し、田端與楽寺末である。
開基創立等は不明であるが、尾久に於ける最古の寺院と伝へられている。
尾久町字大門は、昔そこに当院の大門があった事により出たものとの説がある。
境内地は八百五十六坪である。
震災前の本堂は、中興巌永上人によって天保二年(1831年)に建立されたものであった。
本尊阿遮羅明王即ち不動尊は良辨僧都の作と伝える。
境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
※図中「阿比院」とあります。
荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)
-------------------------
最寄りは都営荒川線(東京さくらトラム)京成線「東尾久三丁目」駅。
まわりに寺社は少なく御朱印エリアではないですが、阿遮院は豊島八十八ヶ所霊場の札所なので一定の参拝客はいるのかもしれません。

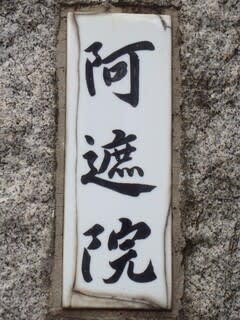
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の院号標
山内入口の門柱に院号標とその手前に御府内二十一ヶ所の札所標。
反対側には院号サイン。「出世石尊 子育(授)地蔵様 弘法大師霊場」とあります。
「弘法大師霊場」として「武蔵國 豊島八十八箇所第六十三番 荒川邊八十八箇所第十番 御府内二十一箇所第十九番」の掲示も出ています。

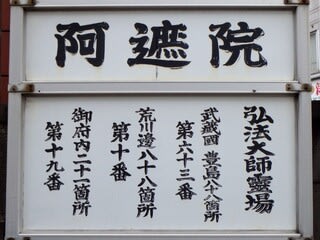
【写真 上(左)】 御府内二十一ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 弘法大師霊場案内
荒川区教育委員会の説明板には「山号・寺号は本尊不動明王の梵名阿遮羅囊他(アシャラナータ)にちなむもの」とあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
ブロック塀に沿って参道を進むと、正面に山門。
切妻屋根桟瓦葺でおそらく薬医門と思われます。
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 石仏群


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
山内は予想以上に広く、緑もゆたかです。
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。均整のとれた堂々たる堂宇です。
向拝柱はなく、開けた印象の向拝で、硝子扉の上に院号扁額を掲げています。

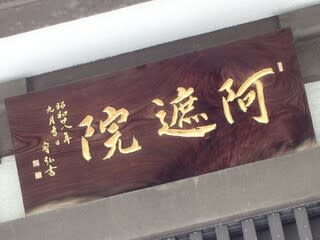
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
現地案内板には、文化財として江戸時代、百万遍念仏講で使用した鐘と数珠、建武三年(1338年)銘の板碑、元禄十四年(1701年)建立の光明真言三百六十万遍供養塔などが記されています、
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 阿遮院の御朱印 〕
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「不動明王」のお種子「カンマン」と尊格の揮毫と「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
右上に「武蔵國豊島六十三番」の札所印。
左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-6)
→ 記事リスト
【 BGM 】
■ Ring Your Bell - LiSA x Kalafina LisAni! LIVE 2017 Complete Ver CROSS STAGE 2017/01/27
■ 名もない花 - 遥海
■ 千年の恋 - ANRI/杏里
Vol.-4からのつづきです。
■ 第15番 瑞光山 如意寺 密嚴院
(みつごんいん)
荒川区荒川4-16-3
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第83番
第15番札所は荒川区荒川の密嚴院・三河島大師です。
下記史料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。
密嚴院は天文二年(1533年)、覚錟ないし覺生和尚の開基と伝え、山内には同九年(1540年)銘の板碑(荒川区登録文化財)も残ります。
南側にある清瀧山観音寺の末寺で、新義真言宗豊山派に属します。
観音寺は、天文年中(1532-1553年)に長偏僧都が開基創建した名刹で、江戸時代には将軍鷹狩りの際の御膳所にあてられていました。
このエリアの獲物は鶴で、鶴の捕獲を目的とする将軍放鷹は「鶴お成り」と格別に称され、捕らえた鶴は天皇に献上する習わしとなっていました。
密嚴院の御本尊は、一尺八寸の如意輪観世音菩薩立像といいます。
『豊島八十八ヶ所巡礼』には「本尊の如意輪観音は弘法大師作と伝えられ、文化十四年(1817年)に高野山から勧請されたもの」とあります。
境内に弘法大師堂があり「三河島大師」と称され、毎月廿一日の護摩修行は信仰者で賑わったといいます。
御府内二十一霊場札所として、本寺の観音寺ではなく密嚴院が選ばれたのは「三河島大師」の名声が高かったためではないでしょうか。
なお、『荒川区史』には「当院は豊島『八十八ヶ所』の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。」とありますが、「新四國八十八ヶ所の内第四十二番」についてはよくわかりません。
境内には竜女塚があり、塚上にあった文政十三年(1830年)の石碑、本堂・庫裡等は昭和20年の東京大空襲の際に失われたといいます。
伽藍は終戦後に再建されていますが、現在は無住で、観音寺が護持されているようです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)
(三河島村)密嚴院
(三河島村)観音寺末 瑞光山如意寺ト号ス 本尊如意輪観音
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
密嚴院(三河島町五丁目九六七番地)
観音寺の北隣にある密嚴院は、瑞光山如意寺と号して、新義真言宗豊山派に属し観音寺の末寺である。本尊如意輪観音は其の丈け一尺八寸の立像である。
開山は覺生和尚と云はれるが詳細は不明である。
境内に弘法大師堂がある。敷地四百六十五坪余。毎月廿一日に護摩修行がある。
当院は豊島「八十八ヶ所」の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。
-------------------------
京成線「町屋」駅とJR常磐線「三河島」駅の中間くらい、近くに荒川区役所はありますが、区民以外はなかなか訪れないところ。
戸建て、マンション、ビルや町工場が混在する下町らしい街区です。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 院号標
観音寺の北東側の路地に面していますが、山内はなかなか広そうです。
参拝時は門扉が堅く閉ざされていたので、山内の詳細はわかりません。


【写真 上(左)】 三河島大師の標
【写真 下(右)】 弘法大師の石標
門柱には「院号」と「三河島大師」の刻字。
鉄扉には真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」。
門柱手前には「開運厄除弘法大師」の石標が建ち、弘法大師霊場であることを示しています。
鉄扉ごしに近代建築陸屋根の本堂が見えますが、詳細は不明です。
御朱印は観音寺にて拝受しました。(以前の情報)
「門扉が閉まっていたので、門前からの参拝となった旨」申告しましたが、現在、閉門中につきその参拝方法でよろしいということで、快く御朱印を授与いただけました。
※ 現在(2024年秋)、密嚴院の御朱印は円性寺(足立区東和1-29-22)で授与されています。
御府内二十一ヶ所霊場、豊島八十八ヶ所霊場ともに拝受できます。
〔 密嚴院の御朱印 〕
〔 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕
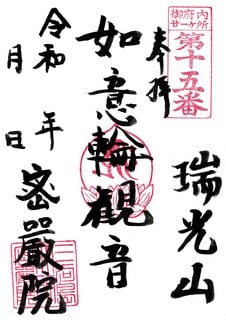
中央に如意輪観音の揮毫と如意輪観音のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内廿一ヶ所第十五番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第16番 五剣山 普門寺 大乗院
(だいじょういん)
台東区元浅草4-5-16
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番
第16番札所は元浅草の大乗院です。
下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
大乗院の創建年代は不詳ですが、『江戸志』には増誉法印の開山とあります。
『寺社書上』『御府内寺社備考』には、江戸大塚護国寺末、境内古跡拝領地五百坪とあります。
本堂は四間四方で、御本尊は丈壱尺三寸の不動明王立像と記されています。
本堂内奉安の弘法大師御像は「江戸八十八ヵ所之内八十一番」とあり、これは荒川辺八十八ヶ所霊場第81番をさしているとみられます。
『江戸砂子』には「波断不動」ともあるようです。
山内に護摩堂、天王社も擁していたとみられます。
当山は度々類焼に見舞われたためか史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。
しかし、荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺の3つの弘法大師霊場札所を兼務されているわけですから、弘法大師とのゆかりのふかい寺院であると考えられます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.45』
江戸大塚護國寺末 浅草新寺町
五釼山普門寺大乗院 境内古跡拝領地五百坪
当寺書留●度々類焼之為焼失仕 年数其外共●相知不申候
本堂 四間四方
本尊 不動明王、丈ヶ壱尺三寸立像
弘法大師 江戸八十八ヵ所之内八十一番
護摩堂
天王社 九尺四方 神体幣束
二王門 二天門 山門 楼門
波断不動(江戸砂子)
開山増誉法印 (江戸志)
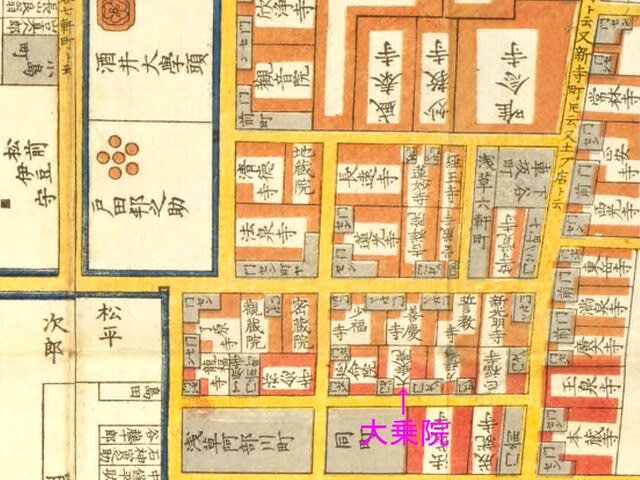
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。
住宅とオフィスビルが混在する立地。
元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から南下する左右衛門橋通りの1本東側の路地を南に入って正福院を過ぎたすぐ先です。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 院号標
路地から少し引きこんだ民家風の建物なので、参道入口の院号札を見落とすとそれとわかりません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
参道をたどり、本堂に近づくにつれて寺院らしい雰囲気が高まります。
建物手前が向拝。
正面はシックな格子扉、壁面には真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」、見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 札所標
向拝手前の「弘法大師 第十六番」と刻まれた立派な石標は、御府内二十一ヶ所霊場の札所標です。
こちらは何度かの参拝でご不在気味だったので、特別にお願いして御朱印を授与いただきました。
通常は不授与の可能性があります。
〔 大乗院の御朱印 〕

中央に不動明王の揮毫と、不動明王のお種子「カン/カ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左に山号・院号の揮毫があります。
■ 第17番 和光山 興源院 大龍寺
(だいりゅうじ)
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:(上田端)八幡神社
他札所:御府内八十八ヶ所霊場第13番-2、豊島八十八ヶ所霊場第21番、滝野川寺院めぐり第6番
※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4 をベースに再編しています。
第17番札所は田端の大龍寺です。
真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所でもあります。
こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。
御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。
そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。(ただし、こちらは別霊場とみられる「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。
ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。
ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺、当山を入れると8)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。
いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。
下記史料等によると創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。
『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

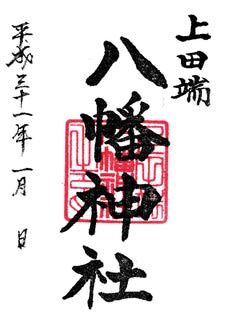
【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社
【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)
(西ヶ原村)大龍寺
眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ 天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置
八幡社 村ノ鎮守トス
稲荷社
-------------------------
JR「駒込」駅と「田端」駅のほぼ中間、上野から日暮里、田端、西ヶ原、飛鳥山とつづく台地のうえにあります。
落ち着いた住宅地のなかに名刹らしい広大な寺地を構えています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。
拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
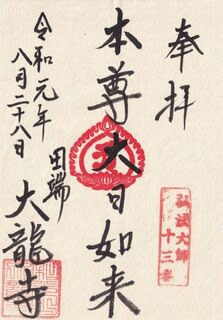
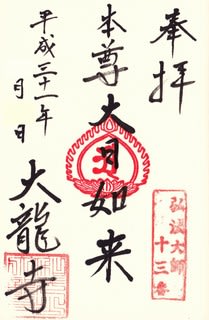
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第18番 象頭山 観音寺 本智院
(ほんちいん)
北区滝野川1-58-2
真言宗智山派
御本尊:
札所本尊:
司元別当:鳥越大明神(鳥越神社)?
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第80番、弘法大師二十一ヶ寺第18番、北豊島三十三観音霊場第28番
第18番札所は北区滝野川の本智院(滝野川不動尊)です。
下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
『御府内寺社備考』によると本智院は当初八丁堀辺に起立されたといいます。
明暦年間(1655-1658年)に記録焼失とあるので、すくなくともそれ以前の起立とみられます。(元和年中(1615-1624年)開基という資料あり。)
同書には「京都智積院末」とあり、智積院直末というすこぶる格の高い寺院であった可能性があります。
中興開山は権大僧都法印明実(元禄二年(1689年)寂)。
『寺社書上』(文政年間(1818-1830年)編纂)には「仮本堂」とあるので、この時期なんらかの理由で仮の本堂となっていたとみられます。
とはいえ間口六間奥行三間の堂々たる堂宇です。
御本尊は金剛界大日如来木像。
本堂には弘法大師木座像、興教大師木座像、阿弥陀木立像、正観音木立像を安すと記されています。
聖天堂は宗対馬守建立とあり、対馬藩主宗家の建立かもしれません。
安する長七寸五分の聖天銅立像は弘法大師の御作で赤松円心(赤松則村、1277-1350年、村上源氏赤松氏4代当主で播磨国守護)の所持と記されています。
甲宵聖天像も弘法大師の御作で赤松円心の所持とあります。
本地は十一面観世音菩薩木立像、長一尺七寸五分で恵心僧都作とあります。
弁財天並びに十五童子も弘法大師の御作で、「江の嶋にて十万座護摩修行、其灰を以て作り裏に手判有之」とあります。
正観音立像も弘法大師の御作とあります。
山内に鎮守十二所権現、長珠院・不動院の二ケ院を擁したとあります。
弘法大師御作と伝わる尊像を幾軆も安し、対馬の宗氏、赤松円心という名族とのゆかりをもつことからみても、相応の寺格を有していたとみられます。
荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺という3つの弘法大師霊場の札所を務められることについては、寺格の高さもさることながら、複数の弘法大師御作の尊像を安するという所以によるのではないでしょうか。
明暦年間(1655-1658年)に焼失後、浅草(不唱小名)に移転といいます。
『江戸切絵図』には、浅草新寺町の仙蔵寺と玉宗寺の間に「本智院」とみえるので、現在の台東区寿二丁目あたりとみられます。
大正になされたという滝野川への移転の経緯は、当然下記史料には記載がありません。
「猫のあしあと」様記載の『北区史』には「もと浅草区(現台東区)栄久町一三二にあつた。幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた程の由緒ある寺で、元和年中(1615-1624年)開基、大正六年五月区内の滝野川町四八都電飛鳥山終点の所に移転の許可を得て新築し、大正十年五月に移転をおえた。滝野川の不動として知られ本尊は不動明王である。」とあります。
『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた」という記載が気になるので、いささか長くなりますが鳥越神社(鳥越大明神)について辿ってみます。。
鳥越神社の別当は御府内八十八ヶ所霊場第51番であった鳥越の長樂寺だった筈です。
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17
鳥越大明神(鳥越神社)は白雉二年(651年)村人が日本武尊の遺徳を偲び、白鳥明神として鳥越山(白鳥山)に祀ったのが創祀と伝わる古社です。
往年のこの地は「鳥越(白鳥)の山」と呼ばれた小高い丘で、日本武尊が東夷御征伐の折に暫く御駐在された地といいます。
相殿の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、中臣(藤原)氏の祖神として祀られ、奈良時代に藤原氏が国司として武蔵に赴任した際、この地にお祀りされたといいます。
永承(1046-1053年)の頃、八幡太郎義家公の奥州征伐の折、この地で渡河に難儀しましたが、白い鳥に浅瀬を教えられて無事軍勢を進めることができました。
義家公はこれを白鳥大明神の御加護と称え、鳥越山(白鳥山)のお社を参拝され「鳥越大明神」の号を奉じられて、これより「鳥越」の地名が起こったとされます。
社地はすこぶる広く、三味線堀(姫が池)に熱田明神、森田町に第六天神(榊神社)が末社として御鎮座され「鳥越三所明神」と称していました。
徳川幕府による旗元・大名屋敷・御蔵地整備のため、鳥越山はとり崩されて埋め立てに使われました。
この際、熱田神社は三谷(現・今戸)へ、榊神社は堀田原(現・蔵前)へと御遷座され、鳥越大明神も御遷座を迫られましたが、第二代神主鏑木胤正の請願が容れられて元地に残られました。
別当・長樂寺は『寺社書上』によると、開山の法印の遷化が寛永二十年(1643年)なので、3代将軍家光公の治世(1623-1651年)までには創建とみられます。
鳥越山轉輪院長樂寺と号し、山号は本社から、院号は兼帯していた京都嵯峨轉輪院永院室から号したものとみられます。
本社・鳥越大明神の御本地馬頭観音、御本尊として不動明王を奉安していました。
弘法大師御像も奉安していたため、御府内霊場札所の要件はきっちり満たしていたとみられます。
鳥越大明神の神職鏑木氏は桓武平氏常将流と伝わり、鳥越神社の社紋として月星紋・九曜紋(千葉氏の紋)が使われているようです。
また、長樂寺に星供養曼荼羅が奉安されていたことからも、妙見信仰の千葉氏との関係がうかがわれます。
鳥越大明神と別当・長樂寺は源氏の棟梁・八幡太郎義家公、桓武平氏の代表姓・千葉氏いずれともゆかりをもつ、複雑な来歴をもたれているのかもしれません。
明治初期の神仏分離で別当の長樂寺は廃寺となり、以降は鳥越神社と号して郷社に列せられました。
例大祭・鳥越祭は都内随一の重さを誇る「千貫神輿」の渡御と、夜に行われる荘厳な宮入で「鳥越の夜祭り」として広く知られています。
以上、鳥越神社の沿革を辿ると、別当として長樂寺の名は出てきますが、本智院との関係は明示されていません。
結局のところ、『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあった」という記載の根拠についてはよくわかりませんでした。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [77] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.33』
京都智積院末 浅草不唱小名
象頭山観音密寺本地院 境内古跡拝領地六百七拾二坪
当寺往古八丁堀辺に起立之由申伝候得● 明暦年中(1655-1658年)類焼之節記録焼失仕相知不申候
中興開山 権大僧都法印明實(元禄二年(1689年)寂)
仮本堂 間口六間奥行三間
本尊 大日金剛界木像
弘法大師木座像 興教大師木座像 阿弥陀木立像 正観音木立像
聖天堂 土蔵造方三間 拝殿 二間四方宗対馬守建立
聖天銅立像 長七寸五分弘法大師作 赤松円心所持
甲宵聖天像 同作同人所持
本地十一面観音木立像 長一尺七寸五分恵心僧都作
辨財天并十五童子 各長七寸八分弘法大師作
右ハ江の嶋にて十万座護摩修行 其灰を以て作り裏に手判●●
天長七年(830年)七月七日と●●
正観音立像 長九分弘法大師作
大黒天立像 俵千十三俵其上ニ安置長一寸三分
鎮守十二所権現
末社稲荷木立像
右十二所権現稲荷合社ニ有之候所 先年類焼之節焼失仕 当時聖天堂二安置
寺中長珠院不動院と号し候 二ケ院有之候処退廃仕候 年代は相知不申候得共 延享年中(1744-1748年)御改之節 二ケ院共書上候由申伝候得ハ 其比ハ相続仕有之候義ニ御座

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅至近。「王子」駅からも歩けます。
滝野川は寺社が集まる御朱印エリアですが、その多くは明治通り北側の滝野川沿いに立地しています。
明治通りの南側に位置する本智院周辺は、一種のエアポケット的なエリアとなっており、筆者もこの界隈は初訪でした。
都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅のお隣りですが、フェンスがあったりして、やや複雑なアプローチです。


【写真 上(左)】 すぐ横が飛鳥山駅
【写真 下(右)】 外観
山内入口には門柱。院号と「滝野川不動尊」が刻字されています。
入口向かって右脇には身代地蔵堂。堂前の石碑には「江戸三大身代地蔵尊」とあるので、有名な地蔵尊なのかもしれません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 身代地蔵尊


【写真 上(左)】 狛犬と大日堂
【写真 下(右)】 大日堂
山内右手に狛犬と大日堂。
堂内には法界定印を結ばれる胎蔵大日如来が御座します。
Wikipediaに「境内には、1667年(寛文7年)製の石像の大日如来坐像があるが、これは移転時に一緒に移したものである。(出所:『北区史跡散歩』 (東京史跡ガイド17))」とあるので、こちらの大日如来はおそらく浅草時代に造立され、こちらに遷られたとみられます。
参道右手が庫裏で、その先が本堂です。
3階建の建物の右手1階が向拝となっているかたちです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
タイル壁に木造の千鳥破風の向拝が填め込まれたような、個性的な意匠です。
左右の向拝柱に木札が掛けられていますが、読みとれませんでした。
向拝上部に「阿遮羅尊」の扁額。
「阿遮羅」とは不動明王の梵名「acalanātha(アチャラナータ)」の漢字表記で、不動堂を
阿遮羅殿と記す場合があります。

 【写真 上(左)】 扁額
【写真 上(左)】 扁額【写真 下(右)】 本堂側からの大師堂
本堂から駅寄りに進むと大師堂です。
こちらは通常閉門されていますが、毎月二十一日(お大師さまのご縁日)には解放され、中のお砂踏み場にて巡拝することができます。

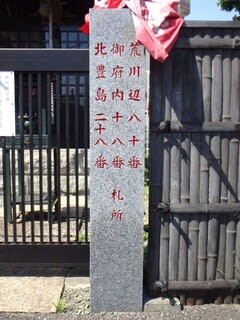
【写真 上(左)】 大師堂門前
【写真 下(右)】 札所標

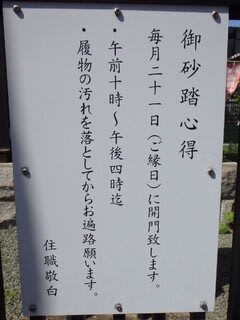
【写真 上(左)】 大師堂よこのお砂踏み場
【写真 下(右)】 御砂踏心得
堂前の門柱は「荒川辺八十番、御府内十八番、北豊島二十八番」の3つの霊場の札所標となっています。

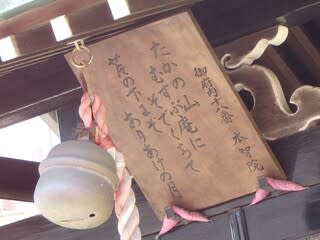
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御府内十八番の御詠歌
大師堂は切妻屋根銅板葺でシックな黒色系の格子扉。
見上には御府内二十一ヶ所第18番の御詠歌が掲げられています。
弘法大師霊場を巡拝していて、このようなしっかりとした大師堂に出会うのはやはり嬉しいものです。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
お不動様のご縁日(28日)に、事前にTELの上お伺いしました。
常時授与かはわからず、ご不在のこともありそうなので事前確認をおすすめします。
〔 本智院の御朱印 〕
〔 荒川辺霊場・御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「本尊 不動明王」の印判と三寶印。
右上に「御府内十八番 荒川辺八十番」の札所印。
左に「瀧野川不動尊」の印判と寺院印が捺されています。
■ 第19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院
(あしゃいん)
荒川区東尾久3-6-25
真言宗豊山派
御本尊:阿遮羅明王(不動明王)
札所本尊:阿遮羅明王(不動明王)
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第63番、荒川辺八十八ヶ所霊場第10番
第19番札所は荒川区東尾久の阿遮院です。
下記資料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。
阿遮院の開基創立等は不明ですが、延元三年(1338年)銘の板碑が所蔵されています。
尾久に於ける最古の寺院と伝えられ、「尾久町字大門」の地名は当院の大門があった事によるとの説があります。
『新編武蔵風土記稿』には、新義真言宗で田端村與楽寺の末とあります。
『江戸切絵図』には、東尾久とおぼしきところに「阿比院」とあります。
荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)
旧本堂は中興の巌永上人により天保二年(1831年)建立といいますが、震災により失いました。
御本尊の阿遮羅明王(不動明王)は、良辨僧都(689-774年)の作と伝えます。
『荒川区史』には「境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。」と記されています。
本尊は阿遮羅明王(不動尊、梵名アシャラナータ)で、こちらが山号・院号の由来といいます。
山内には延元三年(1338)の板碑が所蔵され、元禄十四年(1701年)の光明真言供養塔があります。
『新編武蔵風土記稿』には、東尾久の華蔵院、町屋の慈眼寺は阿遮院の末寺・門徒とあります。
当山についての史料類は多くはありませんが、末寺をもっていたこと、豊島八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、荒川辺八十八ヶ所霊場の3つの弘法大師霊場の札所を兼務されていること、また、現在の寺容からみても相当の名刹と思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)
(下尾久村)阿遮院
新義真言宗、田端村與楽寺ノ末 阿遮山蓮葉寺ト号ス 本尊不動
稲荷社
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
阿遮院(尾久町一丁目八九七番地)
新義真言宗豊山派に属し、田端與楽寺末である。
開基創立等は不明であるが、尾久に於ける最古の寺院と伝へられている。
尾久町字大門は、昔そこに当院の大門があった事により出たものとの説がある。
境内地は八百五十六坪である。
震災前の本堂は、中興巌永上人によって天保二年(1831年)に建立されたものであった。
本尊阿遮羅明王即ち不動尊は良辨僧都の作と伝える。
境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
※図中「阿比院」とあります。
荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)
-------------------------
最寄りは都営荒川線(東京さくらトラム)京成線「東尾久三丁目」駅。
まわりに寺社は少なく御朱印エリアではないですが、阿遮院は豊島八十八ヶ所霊場の札所なので一定の参拝客はいるのかもしれません。

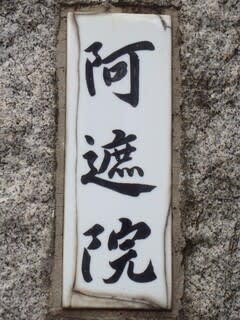
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の院号標
山内入口の門柱に院号標とその手前に御府内二十一ヶ所の札所標。
反対側には院号サイン。「出世石尊 子育(授)地蔵様 弘法大師霊場」とあります。
「弘法大師霊場」として「武蔵國 豊島八十八箇所第六十三番 荒川邊八十八箇所第十番 御府内二十一箇所第十九番」の掲示も出ています。

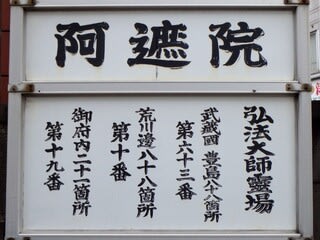
【写真 上(左)】 御府内二十一ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 弘法大師霊場案内
荒川区教育委員会の説明板には「山号・寺号は本尊不動明王の梵名阿遮羅囊他(アシャラナータ)にちなむもの」とあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
ブロック塀に沿って参道を進むと、正面に山門。
切妻屋根桟瓦葺でおそらく薬医門と思われます。
見上げには山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 石仏群


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
山内は予想以上に広く、緑もゆたかです。
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。均整のとれた堂々たる堂宇です。
向拝柱はなく、開けた印象の向拝で、硝子扉の上に院号扁額を掲げています。

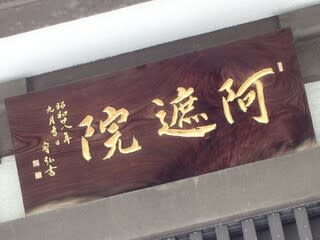
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
現地案内板には、文化財として江戸時代、百万遍念仏講で使用した鐘と数珠、建武三年(1338年)銘の板碑、元禄十四年(1701年)建立の光明真言三百六十万遍供養塔などが記されています、
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 阿遮院の御朱印 〕
〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「不動明王」のお種子「カンマン」と尊格の揮毫と「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
右上に「武蔵國豊島六十三番」の札所印。
左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-6)
→ 記事リスト
【 BGM 】
■ Ring Your Bell - LiSA x Kalafina LisAni! LIVE 2017 Complete Ver CROSS STAGE 2017/01/27
■ 名もない花 - 遥海
■ 千年の恋 - ANRI/杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
【 音楽コラム 】 「ヒーリング・ミュージック」リニューアルUP
ふたたびアクセスランキングに入ってきたので、最新テイクなど追加してリニューアルUPです。
なにかと疲れる時代に、清涼感あふれるヒーリング・ミュージックをどうぞ。
-------------------------
2023/08/26 UP
なんと2007年10月にUPした音楽記事(自分でも忘れてた)がアクセスランキングに入ってたので、埋め込みリンクを加えてリニューアルUPしてみます。
-------------------------
2007/10/30 UP
Vol.1からのつづきです。
(注:試聴のリンククリックは、読者個人の自己責任でお願いします。)
↓のよ~に、ザックリみてみると、H/Mの世界でいかに女性Voの存在が大きいかがわかる。
誰だったか忘れたが「男性ボーカルが10人束になってかかっても、優れた女性ボーカル1人に到底かなわない」とのたまった音楽評論家がいたが、すくなくともこのジャンルではこれがあてはまるのでは・・・。
で、最後に、女性Vo系洋楽H/M(ヒーリング・ミュージック)を10曲ほどリストしておきます。
01.Melanie Ross/”Hodie Christus natus est~Angels Of Ordinary Times”
「ミネラルヴォイス」というコピーがぴったりのたぐい稀な美声。曲のできも抜群。
02.Méav/「SAME」(LP) (→インタビュー)
■ Celtic Prayer - Méav
透明でやわらかな声質。この1stアルバム「Meav」はハズレ曲ほとんどなしの名盤。
03.Sara Brightman/”Scarborough Fair”
S&Gの名曲。Saraの曲はこてこてごーじゃす系が多いが、これはサラりと歌いこなしている。
04.Michelle Tumes/”Healing Waters”
オーストラリアのハイトーン系シンガー・ソングライター。
これは聴きどころの多い1stアルバム『Listen』のなかでも1.2を争う佳曲。
05.Amy Grant/”Lead Me On”
ちとROCK寄りの曲ですが、かなりと雰囲気いいライブなので・・・。
CCM(Contemporary Christian Music)を代表する歌姫。
06.Maire Brennan/”Sign From The Hills”
アイルランドのトラディショナル・バンド”CLANNAD”のリード・ヴォーカリストでENYAの姉でもあるヒーリング・ミュージックの大御所。
07.Lisa Kelly/”The Voice”
Celtic Womanの発足メンバーの一人。
現在は脱退しているが、そのハイトーンの透明度はCeltic Womanでも屈指だった。
08.Hayley Westenra/”The Last Rose of Summer (庭の千草)”(→試聴)
■ Hayley Westenra & Méav - The Last Rose of Summer
ニュージーランドの歌姫が唄うアイルランドの名曲。
09.Sissel Kyrkjebø /”The Gift Of Love”
1994年リレハンメルオリンピックのテーマソングで名を馳せたノルウェーのハイトーン・シンガー。
10.Enya/”Only Time”
1980~1990年代のヒーリング・ミュージックを語るに外せない第一人者。
(おまけ)Kate Bush/”Wuthering Heights(嵐が丘)”(→試聴)
ハイトーンボイスの元祖(?)のクリップがみつかったので・・・ (^^)。
ただしヒーリング系じゃなくてほとんど狂気系ですが・・・。やっぱり名曲。
-------------------------
2023/08/26・2024/11/16追記 UP
こうして聴いてみると、ヒーリング・ミュージックのキモは「ハイトーン&透明感」で、1990年代はアイルランド(ケルト)の歌姫たちがこのシーンのメインだったと思う。
ただ、その後日本の歌姫たちのレベルがさらに上がったので、筆者の嗜好はますます邦楽寄りとなっていまに至る。
*********
1980年代以前からもヒーリング度の高い邦楽曲はいくつもあった。
■ ノーサイド - 松任谷由実
■ 元気を出して - 竹内まりや - [Live Version / 2000@日本武道館]
■ Pray - 今井美樹
■ You Are Not Alone - ANRI 杏里
*********
小室哲哉の存在は邦楽の女性ヴォーカルの質をさらに高め、2000年初頭あたりでも、日本の歌姫たちのレベルは世界的にみてもすでにかなりのものだと思っていた。
■ LOVE BRACE - 華原朋美
小室哲哉がどうして珠玉の名曲の多くを彼女に注いだか、わかる気がする名テイク。
■ かのかCM(風と花と光と) - 上野洋子
たしか2005年頃のCMでZABADAKのヴォーカルをとった上野洋子のテイク。
透明感あふれるヒーリングヴォイスは、アイルランドの歌姫たちを凌駕するレベル。
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka (Live 2007 Concert)
LIVEでこのヒーリング感は、たしかな実力の証明。
■ いつも何度でも - 茂森あゆみ
歴代歌のお姉さんのなかでも癒し力は屈指の名シンガー。
■ Magic✨ - Rina Aiuchi(愛内里菜)
知る人ぞ知る? 名シンガー、愛内里菜。
フェミニンで包み込むようなヒーリングヴォイス。
ケルトの歌姫たちの競演 ↓
■ You Raise Me Up - Celtic Woman
ハイトーンの競演で、世界的な評価を得る。
だけど、まさかこんな逸材があらわれるとは・・・。
↓
■ You Raise Me Up - 熊田このは
2017/01/08 Beautiful Girls Vol.7/Flamingo the Arusha(大阪市浪速区)
このはちゃんの数ある名テイクのなかでも、屈指の名唱かと。
高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。
ここまで共鳴を効かせて艶やかなハイトーンを創り出せる歌い手は、ほんとうに希だと思う。
Celtic Womanと聴き比べてみても、このはちゃんの声質の素晴らしさがわかる。
→ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
---------------------------------
ここ数年、●芸会化する日本の音楽業界を揶揄することが多いけど、じつは優れた才能はたくさんいるから・・・
■ Erato - 志方あきこ
なかなかヒーリング系歌ってくれないのだが、まれに繰り出すヒーリング曲はどれも絶品。
■ Destiny - HoneyWorks feat.花たん
ハニワ(HoneyWorks)もさりげにヒーリング曲多い。
花たんの華麗なハイトーンも癒し曲向き。
■ 1/6 - みにゅ(歌ってみた)
硝子細工のような繊細なハイトーンをもつ歌い手。
ボカロとハイトーン系歌い手は相性抜群。
■ Drive_Qualia - 櫻川めぐ
声優&アニソン系もレベルが高い。
■ One Reason - milet
近年では屈指のヒーリング・チューンだと思う。
■ 星月夜 - 由薫
層が厚くないとこういう曲は出てこないし、ブレークしない。
これだけ話題になっているということは、潜在的なニーズは高いのでは。
■ ひらひら ひらら - ClariS
桜の国、日本の癒し曲。
佐久間 誠氏作の流麗なメロに、フェミニンで透明感あるハイトーンが冴えわたる名曲。
■ ヒカリノイト - 池田綾子 「酪農家たちのまっすぐな夢」篇 Webムービー
こういうストーリー感のあるCM、ようやく増えてきた感じも・・・。
■ 夏空の下 - やなわらばー
これも癒しのCM曲。
解散はあまりに惜しい名ユニット。
そして、このところ話題になることの多いベテランさんたち。
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
「いや~、音楽ってほんとうにいいものですね~」と思わずつぶやきたくなる名演。
-------------------------
でも、やっぱり日本のヒーリング・ミュージックを担っているのは梶浦由記さんだと思う。
■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
5:20~ の貝田さんのハイトーン!
■ Mirai 未来 - Kalafina
バックの演奏も抜群。
いま、こういうテイクを創り出せる国は、日本以外に思いつかない。
■ 【ひぐらしのなく頃に】 ~you / Vocal ~ 【癒月 Ver.】
Vocal Vers.の初出は2005年。
この頃から2015年頃まで、こういう美しい旋律&ヴォーカルのアニメ(ゲーム)曲がかなりつくられていた。
まわりまわっていま、再びこういう曲調が増えてきている気がする。
この手の精細な楽曲は世界でもあまり例がない(と思う)ので、これは貴重では?
→ ■ 風向きが変わった? ~ 女神系歌姫の逆襲 22曲 ~
■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.-/傘村トータ様 -cover-【Cereus】
傘村トータ氏の楽曲は、ヒーリング度高いと思う。
Cereusさんのハイトーンも絶品。
■ 私にはできない - Eiーvy
これもSuno AI使用ですばらしい仕上がり。
楽曲はともかく、ヒーリング系ヴォーカルはAIじゃムリだと思っていたが、これ聴くかぎりヤバイ。
やはりアニソンとボカロの存在が大きい。
これだけの美しい旋律や歌声を生み出せる国は、もう日本だけかもしれない・・・。
「シティ・ポップ」と「女神系歌姫」、日本はふたつのキラーコンテンツをもっていると思う。
このふたつは米国にも韓国にもないものだから、じっさいのところ日本はアドバンテージとりすぎでは?
→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲
→ ■ 鈴を転がすような声 ~ 究極のハイトーンボイス ~
なにかと疲れる時代に、清涼感あふれるヒーリング・ミュージックをどうぞ。
-------------------------
2023/08/26 UP
なんと2007年10月にUPした音楽記事(自分でも忘れてた)がアクセスランキングに入ってたので、埋め込みリンクを加えてリニューアルUPしてみます。
-------------------------
2007/10/30 UP
Vol.1からのつづきです。
(注:試聴のリンククリックは、読者個人の自己責任でお願いします。)
↓のよ~に、ザックリみてみると、H/Mの世界でいかに女性Voの存在が大きいかがわかる。
誰だったか忘れたが「男性ボーカルが10人束になってかかっても、優れた女性ボーカル1人に到底かなわない」とのたまった音楽評論家がいたが、すくなくともこのジャンルではこれがあてはまるのでは・・・。
で、最後に、女性Vo系洋楽H/M(ヒーリング・ミュージック)を10曲ほどリストしておきます。
01.Melanie Ross/”Hodie Christus natus est~Angels Of Ordinary Times”
「ミネラルヴォイス」というコピーがぴったりのたぐい稀な美声。曲のできも抜群。
02.Méav/「SAME」(LP) (→インタビュー)
■ Celtic Prayer - Méav
透明でやわらかな声質。この1stアルバム「Meav」はハズレ曲ほとんどなしの名盤。
03.Sara Brightman/”Scarborough Fair”
S&Gの名曲。Saraの曲はこてこてごーじゃす系が多いが、これはサラりと歌いこなしている。
04.Michelle Tumes/”Healing Waters”
オーストラリアのハイトーン系シンガー・ソングライター。
これは聴きどころの多い1stアルバム『Listen』のなかでも1.2を争う佳曲。
05.Amy Grant/”Lead Me On”
ちとROCK寄りの曲ですが、かなりと雰囲気いいライブなので・・・。
CCM(Contemporary Christian Music)を代表する歌姫。
06.Maire Brennan/”Sign From The Hills”
アイルランドのトラディショナル・バンド”CLANNAD”のリード・ヴォーカリストでENYAの姉でもあるヒーリング・ミュージックの大御所。
07.Lisa Kelly/”The Voice”
Celtic Womanの発足メンバーの一人。
現在は脱退しているが、そのハイトーンの透明度はCeltic Womanでも屈指だった。
08.Hayley Westenra/”The Last Rose of Summer (庭の千草)”(→試聴)
■ Hayley Westenra & Méav - The Last Rose of Summer
ニュージーランドの歌姫が唄うアイルランドの名曲。
09.Sissel Kyrkjebø /”The Gift Of Love”
1994年リレハンメルオリンピックのテーマソングで名を馳せたノルウェーのハイトーン・シンガー。
10.Enya/”Only Time”
1980~1990年代のヒーリング・ミュージックを語るに外せない第一人者。
(おまけ)Kate Bush/”Wuthering Heights(嵐が丘)”(→試聴)
ハイトーンボイスの元祖(?)のクリップがみつかったので・・・ (^^)。
ただしヒーリング系じゃなくてほとんど狂気系ですが・・・。やっぱり名曲。
-------------------------
2023/08/26・2024/11/16追記 UP
こうして聴いてみると、ヒーリング・ミュージックのキモは「ハイトーン&透明感」で、1990年代はアイルランド(ケルト)の歌姫たちがこのシーンのメインだったと思う。
ただ、その後日本の歌姫たちのレベルがさらに上がったので、筆者の嗜好はますます邦楽寄りとなっていまに至る。
*********
1980年代以前からもヒーリング度の高い邦楽曲はいくつもあった。
■ ノーサイド - 松任谷由実
■ 元気を出して - 竹内まりや - [Live Version / 2000@日本武道館]
■ Pray - 今井美樹
■ You Are Not Alone - ANRI 杏里
*********
小室哲哉の存在は邦楽の女性ヴォーカルの質をさらに高め、2000年初頭あたりでも、日本の歌姫たちのレベルは世界的にみてもすでにかなりのものだと思っていた。
■ LOVE BRACE - 華原朋美
小室哲哉がどうして珠玉の名曲の多くを彼女に注いだか、わかる気がする名テイク。
■ かのかCM(風と花と光と) - 上野洋子
たしか2005年頃のCMでZABADAKのヴォーカルをとった上野洋子のテイク。
透明感あふれるヒーリングヴォイスは、アイルランドの歌姫たちを凌駕するレベル。
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka (Live 2007 Concert)
LIVEでこのヒーリング感は、たしかな実力の証明。
■ いつも何度でも - 茂森あゆみ
歴代歌のお姉さんのなかでも癒し力は屈指の名シンガー。
■ Magic✨ - Rina Aiuchi(愛内里菜)
知る人ぞ知る? 名シンガー、愛内里菜。
フェミニンで包み込むようなヒーリングヴォイス。
ケルトの歌姫たちの競演 ↓
■ You Raise Me Up - Celtic Woman
ハイトーンの競演で、世界的な評価を得る。
だけど、まさかこんな逸材があらわれるとは・・・。
↓
■ You Raise Me Up - 熊田このは
2017/01/08 Beautiful Girls Vol.7/Flamingo the Arusha(大阪市浪速区)
このはちゃんの数ある名テイクのなかでも、屈指の名唱かと。
高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。
ここまで共鳴を効かせて艶やかなハイトーンを創り出せる歌い手は、ほんとうに希だと思う。
Celtic Womanと聴き比べてみても、このはちゃんの声質の素晴らしさがわかる。
→ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
---------------------------------
ここ数年、●芸会化する日本の音楽業界を揶揄することが多いけど、じつは優れた才能はたくさんいるから・・・
■ Erato - 志方あきこ
なかなかヒーリング系歌ってくれないのだが、まれに繰り出すヒーリング曲はどれも絶品。
■ Destiny - HoneyWorks feat.花たん
ハニワ(HoneyWorks)もさりげにヒーリング曲多い。
花たんの華麗なハイトーンも癒し曲向き。
■ 1/6 - みにゅ(歌ってみた)
硝子細工のような繊細なハイトーンをもつ歌い手。
ボカロとハイトーン系歌い手は相性抜群。
■ Drive_Qualia - 櫻川めぐ
声優&アニソン系もレベルが高い。
■ One Reason - milet
近年では屈指のヒーリング・チューンだと思う。
■ 星月夜 - 由薫
層が厚くないとこういう曲は出てこないし、ブレークしない。
これだけ話題になっているということは、潜在的なニーズは高いのでは。
■ ひらひら ひらら - ClariS
桜の国、日本の癒し曲。
佐久間 誠氏作の流麗なメロに、フェミニンで透明感あるハイトーンが冴えわたる名曲。
■ ヒカリノイト - 池田綾子 「酪農家たちのまっすぐな夢」篇 Webムービー
こういうストーリー感のあるCM、ようやく増えてきた感じも・・・。
■ 夏空の下 - やなわらばー
これも癒しのCM曲。
解散はあまりに惜しい名ユニット。
そして、このところ話題になることの多いベテランさんたち。
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
「いや~、音楽ってほんとうにいいものですね~」と思わずつぶやきたくなる名演。
-------------------------
でも、やっぱり日本のヒーリング・ミュージックを担っているのは梶浦由記さんだと思う。
■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
5:20~ の貝田さんのハイトーン!
■ Mirai 未来 - Kalafina
バックの演奏も抜群。
いま、こういうテイクを創り出せる国は、日本以外に思いつかない。
■ 【ひぐらしのなく頃に】 ~you / Vocal ~ 【癒月 Ver.】
Vocal Vers.の初出は2005年。
この頃から2015年頃まで、こういう美しい旋律&ヴォーカルのアニメ(ゲーム)曲がかなりつくられていた。
まわりまわっていま、再びこういう曲調が増えてきている気がする。
この手の精細な楽曲は世界でもあまり例がない(と思う)ので、これは貴重では?
→ ■ 風向きが変わった? ~ 女神系歌姫の逆襲 22曲 ~
■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.-/傘村トータ様 -cover-【Cereus】
傘村トータ氏の楽曲は、ヒーリング度高いと思う。
Cereusさんのハイトーンも絶品。
■ 私にはできない - Eiーvy
これもSuno AI使用ですばらしい仕上がり。
楽曲はともかく、ヒーリング系ヴォーカルはAIじゃムリだと思っていたが、これ聴くかぎりヤバイ。
やはりアニソンとボカロの存在が大きい。
これだけの美しい旋律や歌声を生み出せる国は、もう日本だけかもしれない・・・。
「シティ・ポップ」と「女神系歌姫」、日本はふたつのキラーコンテンツをもっていると思う。
このふたつは米国にも韓国にもないものだから、じっさいのところ日本はアドバンテージとりすぎでは?
→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲
→ ■ 鈴を転がすような声 ~ 究極のハイトーンボイス ~
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 寺尾 聰のライブ
さきほど放送してた、NHK MUSIC SPECIAL「寺尾 聰 人生の集大成ライブ!」、サウンドのレベルが凄すぎた。
バックはおなじみの井上 鑑(key)、今 剛(g)高水″大仏″健司(b)、山木 秀夫(ds)。
4つ打ち全盛のいまの時代に、こんなグルーヴ&キメが聴けるとはある意味驚愕。
■ 寺尾聰 Terao Akira - ルビーの指環 (1981)
やっぱりこの曲は、腕利きのミュージシャンたちが揃わなければ成立しないと思う。
まぁ、彼らはPARACHUTE&KAZUMI BANDの混生軍団のようなものだから、たとえヴォーカルがいなくてもふつうに良質な音楽として楽しめるし・・・。
寺尾 聰さん、このサウンドに身を委ねて本当に気持ちよさそうに歌っていた。
■ 今剛、松原正樹 ギタープレイ 「HERCULES」from 『PARACHUTE 35th Anniversary LIVE 栄養有ツアー2014』
■ Shadow City~寺尾聰【GTA5+mod】
洋楽のエッセンスと日本的な陰りが絶妙に交錯する1980年代前半ならではの空気感。
つくろうとしてつくれる曲じゃないと思う。
■ 寺尾聰 「ルビーの指環」20171009 公開リハーサル [日光]
この状況のリハで、この余裕かましたサウンド。おそるべし。
こういう大人の音楽が、もっともっと聴かれるといいな。
バックはおなじみの井上 鑑(key)、今 剛(g)高水″大仏″健司(b)、山木 秀夫(ds)。
4つ打ち全盛のいまの時代に、こんなグルーヴ&キメが聴けるとはある意味驚愕。
■ 寺尾聰 Terao Akira - ルビーの指環 (1981)
やっぱりこの曲は、腕利きのミュージシャンたちが揃わなければ成立しないと思う。
まぁ、彼らはPARACHUTE&KAZUMI BANDの混生軍団のようなものだから、たとえヴォーカルがいなくてもふつうに良質な音楽として楽しめるし・・・。
寺尾 聰さん、このサウンドに身を委ねて本当に気持ちよさそうに歌っていた。
■ 今剛、松原正樹 ギタープレイ 「HERCULES」from 『PARACHUTE 35th Anniversary LIVE 栄養有ツアー2014』
■ Shadow City~寺尾聰【GTA5+mod】
洋楽のエッセンスと日本的な陰りが絶妙に交錯する1980年代前半ならではの空気感。
つくろうとしてつくれる曲じゃないと思う。
■ 寺尾聰 「ルビーの指環」20171009 公開リハーサル [日光]
この状況のリハで、この余裕かましたサウンド。おそるべし。
こういう大人の音楽が、もっともっと聴かれるといいな。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-21 (C.極楽寺口-4)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)から。
57.明鏡山 円満院 星井寺(虚空蔵堂)(ほしいでら)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市坂ノ下18-28
真言宗大覚寺派
御本尊:虚空蔵菩薩
司元別当:
札所:鎌倉十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)
※現在は普明山成就院の境外仏堂
星井寺(虚空蔵堂)は虚空蔵菩薩を御本尊とする密寺で、現在は普明山成就院の境外仏堂となっています。
鎌倉十三仏霊場第13番の札所として知られています。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
星井寺(虚空蔵堂)は、天平年間(729-749年)、古井戸「星月井」のなかに虚空蔵菩薩の御影を見い出した行基菩薩が、自ら虚空蔵菩薩像を彫刻し建立した堂宇と伝わります。
「星月井」は鎌倉十井(かまくらじっせい)の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれます。
極楽寺坂ののぼり口にあたるこのあたりは、木々が生い茂り昼なお暗かったため「星月夜」(ほしづきよ)と呼ばれ、ここにある井戸なので「星月夜の井」と呼ばれたといいます。
あるいは、暗い井戸のなかに昼でも星の影が見えたことから、この名がついたとも。
源頼朝公はこちらの虚空蔵尊を内陣仏として崇敬し、仏師運慶に外陣仏を刻させて御前立としたといいます。
虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は、無限の智恵と大慈大悲を持たれる菩薩とされます。
梵語はアーカーシャガルバ。明星天子、大明星天王などの別名があります。
御真言はノウボウ・アキャシャキャラバヤ・オンアリキャ・マリボリソワカ。
種子はタラーク。三昧耶形は宝剣、如意宝珠、ご縁日は毎月13日です。
高野山霊宝館Web、Wikipediaによると、虚空蔵菩薩は大日如来の福智の二徳を司る仏で、とくに「智恵を授ける仏さま」「頭脳明晰となり記憶力が高まる功徳」として信仰を集めています。
虚空蔵尊信仰はすでに奈良時代からあったといい、若かりし弘法大師も虚空蔵尊を御本尊とする「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を阿波太龍岳や土佐室戸崎などで修行されたと伝わります。
また、虚空蔵尊に礼するものは、三世十方一切の諸仏を礼することと同じともされる強力な尊格です。
虚空蔵菩薩の誓願に「人には三期の厄あり。その厄災のうち、とりわけて変体の厄を除き、智徳を与え、二世の願いを成就せしめん。」という項目があり、「変体」とは子供から大人に変わる年頃をいいます。
虚空蔵尊は「十三詣り」の御本尊として知られます。
「十三詣り」とは旧暦の3月13日前後に、数え年13歳でおこなう寺院詣でで、とくに虚空蔵尊にお参りします。
京都嵯峨の虚空蔵法輪寺が有名ですが、各地でみられる風習で星井寺でも「十三詣り」がおこなわれます。
この「十三詣り」はおそらく「変体(子供から大人に変わる年頃)の厄払い」から来ているものと思われます。
虚空蔵信仰は星宿、日月などの星神信仰と深い関係をもち、「星月井」とのゆかりも、この信仰からきているのでは。
一見なじみのない尊格にも思えますが、弘法大師とのゆかりもあって、真言密教ではことに重要な尊格とされ、禅刹でもしばしば御本尊となられます。
虚空蔵尊は「十三仏詣で」の一尊です。
「十三仏詣で」とは室町時代に日本で成立した信仰で、十三回の追善供養(初七日〜三十三回忌)をそれぞれ司る仏尊を供養ないし詣でるものです。
虚空蔵尊は三十三回忌の尊格で、札番13番の結願尊となります。
星井寺の虚空蔵尊も鎌倉十三仏霊場第13番の札所本尊となっています。
(詳細は→こちら。)
また、十二支守り本尊参りでは、虚空蔵尊は丑歳、寅歳の守り本尊となっています。
虚空蔵尊の像容は、右手に宝剣、左手に如意宝珠を持つタイプ、法界定印の掌中に五輪塔を持つタイプ、与願印を結ぶタイプなどがみられ多彩です。
かつて、「星月井」(星月夜の井)は鎌倉を代表する名所でした。
慶長五年(1600年)6月、徳川家康公は京・伏見城から上杉氏征伐のため江戸に向かう途中、「星月井」に立ち寄っています。(6月29日とみられる)
「慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ」(「星月井」碑文)
神奈川県Webによると、「星月夜の井」は「鎌倉」を導く枕詞とされています。
我ひとり鎌倉山を越へ行けば 星月夜こそうれしかりけれ (後堀川百首)
鎌倉市の旧徽章は「星月夜」がモチーフにされていたともいいます。
鎌倉宮近くの通りに、この旧徽章を描いたマンホールが一枚だけ残っています。
鉄道唱歌にも「星月井」(星月夜の井)は下記のとおり歌われ、鎌倉を代表する名所であったことを裏付けています。
「北は円覚建長寺 南は大仏星月夜 片瀬腰越江の島も ただ半日の道ぞかし」
こぢんまりとした山内ですが、上記のようにさまざまな由緒沿革をもち、鎌倉を代表する虚空蔵尊霊場として重要な堂宇です。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
星月夜井
極楽寺の切通へ上る坂の下、右の方にあり。里老云、昔は此井の中に、昼も星の影見ゆる故に名く。此邊の奴碑、此井を汲に来り、誤て菜刀を井中へ落したり。爾しより来星影不見と。
又此井の西に、虚空蔵堂あり。星月山星井寺と号す。極楽寺村の、成就院の持ち分なり。成就院は、真言宗。虚空蔵は、行基作、長二尺五寸。縁起一巻あり。其略に云、聖武帝の天平中(729-749年)に、此井に光りあり。里民不思議の思をなし、これを見れば、井の邊に、虚空蔵の像現じ給。此由を奏しければ、行基に勅し、此像を作らしめ、爰に安置し給ふとあり。
【後堀河百首】に常陸が歌に
「我ひとり 鎌倉山を越行ば、星月夜こそ うれしかりけれ」
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
虚空蔵堂
極楽寺村のうち、星月夜の井の西にあり。この堂を星月山星井寺と号す。
村内成就院の持なり。これは真言宗。
虚空蔵は行基作、長二尺五寸。縁起の略に、聖武天皇の天平年中(729-749年)、此寺井に光有。里民不思議のおもひをなし、是を見れば井の邊に虚空蔵の像現じ給ふと。此よしを奏しければ、行基に勅し此像を造らしめ、爰に安置し給ふと云云。【堯恵法印紀行】に、星の御堂と書しは、この堂のことなり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(坂之下村)虚空蔵堂
明鏡山(【鎌倉志】には星月山に作る)星井寺と号す、極楽寺村成就院持なり
本尊は行基の作像なり 木佛立像長三尺
縁起に拠るに聖武帝の天平年中(729-749年)此寺の井に光あり、村民奇として是を見るに井の邊に虚空蔵の形出現す、此由天聴に達しければ行基に勅ありて此像を造らせられ、即爰に安置ありしと云へり、堯惠が紀行に星の御堂とあるは此堂なり
【什寶】
明星石一顆 星ノ井より出し物と云ふ
独鈷 行基所持の物と云ふ、下同じ
唐錢六文 是も照天姫、所持せし物と云ふ、祟寧通寶二文、祟寧重寶四文とあり
駒爪 小栗判官の乗馬、鬼鹿毛の爪なりと伝ふ
■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)
明鏡山円満院星の井寺(御本尊虚空蔵菩薩安置)
天平年間(729-749年)、聖武天皇の御代に諸国行脚中の行基僧正が当地の古井戸「星月の井」に明るく輝く明星の光りが移るとのうわさを地元民から聴き、井戸をのぞくと中に虚空蔵菩薩のお姿が写し現われていた
行基はそのお姿を仏像に彫り当地にお堂を建立し安置した。
かの像は明星の照曜の如き光を放ち、鏡に影の移る如くでありました。
以後数百年経って幕下の征夷大将軍源頼朝公はこの菩薩を崇敬し、この菩薩像を内陣仏の秘仏とし、仏師運慶に外陣仏を作らせた これが前立尊であるという。
秘仏虚空蔵菩薩はわが国では唯三体の木彫の仏像で大変貴重な仏像であります。
これに加えてこの御仏は明星と一体で、その分身であり限りない知恵をそなえた御仏で、経典では虚空蔵菩薩は、西方香集世界の教主で娑婆世界の苦難する人々の利益のために無不畏陀羅尼を説くことを、釈迦・敷蔵の二仏に許された御仏であります。
即ちその本尊に礼するものは三世十方一切の諸仏を礼することと同じであるといわれます。
又、虚空蔵菩薩を本尊として修業する虚空蔵求聞持法では心を静かにしこの真言を唱えれば天より明星が口に入り、菩薩の威はあらわれて頭脳は明晰となり記憶力は増進するといわれております。
秘仏であるが衆生に縁を結ばせるべきでるとして三十五年一度に開帳し衆生にそのお姿を拝する事が許されました。
近代に至り熱心な信仰者の意に添うようにと毎年正月十三日に開帳し善男善女もそのお姿を毎年拝することが出来るようになりました。
正月十三日の初護摩供養には、丑年寅年の人々の守本尊として、また、知恵、記憶力をお授け下さる虚空蔵様として地元民をはじめ各地より善男善女が参詣に集まります。
■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)
舟守地蔵(虚空蔵堂境内安置)
いつの時代に開眼されたお地蔵であるか不明であるが往年より海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係した一切の事業に従事しておられる人々に大きな功徳をお授け下さるお地蔵として近郷、近在の人々に深く崇敬されております。
また、その昔より願主の心清く精進すれば願い事を数日で成就させていだ(ママ)ける有難いお地蔵様であるとも言い伝えられております。
■ 現地掲示((社)鎌倉青年会議所)
星の井(ほしのい)
この井戸は、鎌倉十井の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれています。
昔、この井戸の中に昼間も星の影が見えたことから、この名がついたといわれています。
奈良時代の名僧・行基は、井戸から出てきた光り輝く石を虚空蔵菩薩の化身と思い、お堂を建てて虚空蔵菩薩をまつったという伝説もあります。
井戸の水は清らかで美味だったので、昭和初期まで旅人に飲料水として売られていたそうです。
■ 現地掲示(「星月井」碑文、昭和二年三月建 鎌倉青年団)
星月夜ノ井ハ一ニ星ノ井トモ言フ鎌倉十井ノ一ナリ
坂ノ下ニ属ス往時此附近ノ地老樹蓊鬱トシテ昼尚暗シ故ニ称シテ星月谷ト曰フ後転ジテ
星月夜トナル井名蓋シ此ニ基ク里老言フ古昔此井中昼モ星ノ影見ユ故ニ此名アリ近傍ノ婢女誤ツテ菜刀ヲ落セシヨリ以来星影復タ見エサルニ至ルト此説最モ里人ノ為メニ信ゼラルルガ如シ慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ以テ
其名世ニ著ハルルヲ知ルベシ水質清冽最モ口ニ可ナリ
-------------------------
長谷と極楽寺のあいだにある極楽寺切通の長谷側ののぼり口にあります。
ちょうど鎌倉・長谷の市街から極楽寺切通の山手にさしかかるところで、周囲は木々に覆われています。
極楽寺切通は、新田義貞勢がついに攻め落とすことができなかった要衝です。
極楽寺坂切通は極楽寺開山の忍性(1217-1303年)により拓かれたという説があるので、新田義貞の時代はもっと厳しい道のりだったのかもしれません。

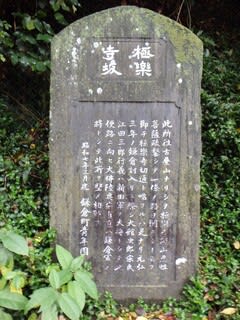
【写真 上(左)】 極楽寺坂
【写真 下(右)】 極楽寺坂の碑
長谷から行くと、極楽寺坂の右手手前に宝形の屋根が掛かった「星月井」とその石碑。
そのおくが虚空蔵堂の参道です。


【写真 上(左)】 星月井と虚空蔵堂の参道
【写真 下(右)】 星月井


【写真 上(左)】 星月井の碑
【写真 下(右)】 参道-1
筆者の参拝時に建てられていた「初護摩供」の看板には「日本三虚空蔵」とありましたが詳細は不明です。
こちらの御本尊(虚空蔵尊)はもともと秘仏でしたが、35年に一度御開帳されるようになり、いまは毎年1月13日の初縁日にご開帳されています。(毎年1月、5月、9月の13日とも)


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 狛犬と虚空蔵堂
「南無虚空蔵菩薩」の奉納幟がはためく急な石段を登ると左右に立派な狛犬。
正面が本堂で、向かって左手前に舟守地蔵尊の堂宇があります。


【写真 上(左)】 本堂(虚空蔵堂)
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
本堂(虚空蔵堂)はおそらく入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

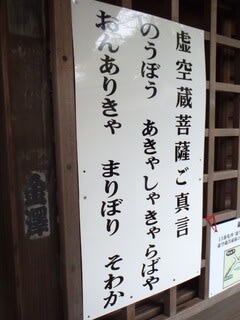
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩の御真言
右手身舎には虚空蔵菩薩の御真言。
向拝見上には山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 舟守地蔵尊
舟型地蔵尊の堂宇は切妻造銅板葺の妻入りで、舟形台座のうえに御座する地蔵尊を間近で拝せます。
開眼の時期は不明ですが、海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係する業に従事する人々に功徳をお授けくださるお地蔵様とのこと。
願主の心が清く、精進すれば願い事を数日で成就いただけるともいいます。
もともと虚空蔵尊と地蔵尊とは対になっていたという説があります。
星井寺で虚空蔵尊と地蔵尊(舟守地蔵尊)が奉安されているのは、この流れによるものかもしれません。
御朱印は、極楽寺坂を3分ほど登った成就院で拝受できます。
なお、星井寺から成就院へ向かう極楽寺坂の途中に、日限六地蔵尊のお堂があります。
説明板によると、道行く人々をお守り下さり、願いを期日を極めておすがりすれば、その期日までに功徳がいただける有難いお地蔵様とのことです。


【写真 上(左)】 日限六地蔵尊
【写真 下(右)】 日限六地蔵尊の説明板
〔 星井寺の御朱印 〕

58.普明山 法立寺 成就院(じょうじゅいん)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市極楽寺1-1-5
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
司元別当:御霊神社(坂の下)、星井寺虚空蔵堂(坂の下)
札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番
成就院は弘法大師空海とのゆかりを伝え、鎌倉幕府第3代執権北条泰時公が創建という古刹です。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
弘法大師が相州江島に留錫されたとき、この地で数日間護摩供を修されたといいます。
Wikipediaによると、伝承によれば弘法大師が江ノ島の金窟(現・岩屋)に参拝し国土守護・万民救済を祈願、社殿(岩屋本宮)を創建されたのは、弘仁五年(814年)とあるので、成就院の護摩供伝説もおそらくその頃とみられます。
弘法大師は成就院の裏山で虚空蔵求聞持法を修されたと伝わります。
であれば、成就院よりも虚空蔵菩薩を御本尊とする星井寺の由緒にこの伝承がでてきそうですが、調べた限りでは星井寺の由緒には弘法大師の虚空蔵求聞持法は記されていないようです。
弘法大師は相模湾や富士山を望む高台で護摩を焚かれ、その煙は海風にのってたなびき、厳修の鈴の音は里々に響き渡り、その煙や鈴の音が届いた里は作物がよく実り、人々は安心して暮らすことができたといいます。
この伝承を聞いた鎌倉幕府第3代執権北条泰時公は、高僧を請して承久元年(1219年)不動明王を御本尊として堂宇を建立、普明山願成就院と号したといいます。
元弘三年(1333年)、新田義貞鎌倉攻めの際に伽藍を焼失し、西谷に遁れたものの願成就院はひきつづき鎌倉幕府で重んじられ、第5代鎌倉公方足利成氏公(1449-1455年)は、毎年正月に願成就院の住持を招いて饗待したと伝わります。
元禄年中(1688-1704年)、祐尊和尚のときに旧地に還って再興したため、祐尊和尚を中興とします。
元寇の役の供養のために植えられたという、262株(般若心経の文字数と同じ)の紫陽花が有名で、花の寺としても知られています。
こちらの御本尊・不動明王は古来から「縁結び不動明王」と崇められ、良縁成就の寺としても知られています。
成就院の寺宝として、真言僧・文覚(1139-1203年)が自ら彫ったとされる「文覚上人荒行像」が伝わります。
日本の近代彫刻の大家・荻原碌山(おぎわらろくざん/守衛)の代表作「文覚」は、この像に触発されて作られたといいます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(極楽寺村)成就院
普明山法立寺と号す、古義真言宗 手廣村青蓮寺末 北條泰時開基すと云ふ
縁起に拠に空海江島に錫を駐めし時此地に於て数日護摩供を修す、此時泰時高僧を請して承久元年(1219年)一宇を建立し願成就院と称し大師護摩の靈場なるを以て普明山と号すとなり、管領成氏が時は毎年正月住持を営中に饗待あり(中略)
永禄五年(1562年)十月大道寺駿河守政繁寺内制札の副状を出せり(中略)
当寺元弘の乱(1331-1333年)に寺地を蹂踐せられ、西谷に遁れて星霜を送りけるが元禄年中(1688-1704年)現住祐尊が時舊地に還住し再興せり、故に祐尊を中興とす(元禄十四年(1701年)十月十一日寂す)本尊不動を置く
稲荷社 境内の鎮守とす
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
普明山法立寺成就院と号する。
古義真言宗。もと青蓮寺末、いま京都大覚寺末。
縁起によれば、承久元年(1219年)十一月廿一日、北条泰時の創建で、空海が護摩供を修した跡に建立したという。
本尊、不動明王。
境内地596坪。本堂・山門・庫裏等あり。
『風土記稿』には元文六年二月二十一日岩沢重●の作った縁起により、元弘の乱に寺地を蹂踐され、西谷に移っていたのを元禄年中(1688-1704年)に祐尊が旧地に還って再興した。とあるが、現在寺にはこのことを証すべき史料がない。
ただし、極楽寺の奥に西方寺屋敷とよんでいるところがあり、ここが成就院の持地であるから、もとここに移っていたのかもしれない。(中略)
明鏡山円満院星井寺と号する虚空蔵堂を管理している。
-------------------------
長谷から星井寺(虚空蔵堂)を過ぎて極楽寺坂を登ると極楽寺切通。
成就院は、極楽寺切通の上方にあります。


【写真 上(左)】 極楽寺切通
【写真 下(右)】 東参道


【写真 上(左)】 東参道からの由比ヶ浜
【写真 下(右)】 山内からの由比ヶ浜
参道・山内からは由比ヶ浜の海岸が、思いがけないアングルで見下ろせます。
こういう景色は山が海に迫る鎌倉ならでは。


【写真 上(左)】 東参道の山門
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 西参道
【写真 下(右)】 西参道の山門
長谷方向からの参道の山門には「東結界」の扁額と傍らには院号標。
極楽寺方向からの参道登り口には山号標、その先の山門には「西結界」の扁額が掲げられています。
東参道の石段は108段あるそうで、なかなか登りごたえがあります。


【写真 上(左)】 山号標
【写真 下(右)】 山門
東西の参道が合わさって正面階段うえに切妻屋根銅板葺の山門。四脚門とも思いますが、山内側から撮影し忘れたので薬医門かもしれません。
桁行一間、梁間二間の禅宗様で、江戸時代後期のものとのこと。
二軒の繁垂木、四連の中備と脇塀を備えた立派な山門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 秋の山内
【写真 下(右)】 なで蛙
高台にある山内はさほど広くないものの見どころ多数。
いつも観光客で賑わい、明るい雰囲気のお寺さまです。
向かって左手には庫裏と授与所。


【写真 上(左)】 手水鉢
【写真 下(右)】 修行大師像


【写真 上(左)】 御分身不動明王
【写真 下(右)】 御朱印案内
右手には手前から立派な龍をおいた手水鉢と修行大師像。
その先の矜羯羅・制多伽の二童子を従えた「御分身不動明王」は、パワースポット「縁結び不動明王」として有名なようです。
そのおくに子授け・安産・子育ての功徳のある子安地蔵菩薩と子生み石がある筈ですが、なぜか写真が残っていません。


【写真 上(左)】 聖徳太子堂
【写真 下(右)】 チベット招来仏(レプリカ)
さらにそのおくに聖徳太子1300年御忌を記念して造立された多角堂がおかれ、覆堂には「和貴」の扁額が掲げられています。
河口慧海釈迦菩行像は、河口慧海師(1866-1945年)がチベットから持ち帰られた像のレプリカです。
さらに文覚上人荒行像のブロンズ像がある筈ですが、なぜかこちらも写真がありません。
こちらは3回お参りしているのですが、すみません、なぜか撮影忘れが目立ちます。
文覚上人荒行像は「日本のロダン」と称された明治時代の彫刻家、荻原碌山の作品に大きな影響を与えたとされるものです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺でボリューム感のある堂宇。
向拝柱はなく、堂前はすっきりとしています。
向拝見上げに院号扁額。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂内には、御本尊の不動明王、大日如来、地蔵菩薩が御座します。
不動明王は、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所本尊です。
鎌倉三十三観音霊場第21番の札所本尊・聖観世音菩薩と相州二十一ヶ所霊場第13番の札所本尊・弘法大師座像も本堂内に奉安で、こちらが拝所となります。
〔 成就院の御朱印 〕
こちらは鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所です。
新四国東国八十八ヶ所霊場は、川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)で、鎌倉市内では、補陀洛寺(材木座)、浄光明寺(扇ヶ谷)、成就院(極楽寺)、満福寺、浄泉寺、宝善院(以上腰越)、青蓮寺(手広)の7寺院が札所で、結願は手広の青蓮寺です。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
新四国東国八十八ヶ所霊場については、こちらの記事をご覧ください。
なお、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印については申告して拝受した記憶がありますが、札所印は捺されていません。あるいは札所印つき御朱印を拝受できるかもしれません。

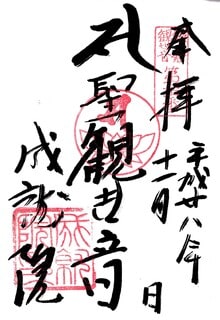
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳)
※相州二十一ヶ所霊場の御朱印は、専用納経帳では「弘法大師」、御朱印帳では「遍照金剛」の揮毫をいただいています。
59.月影地蔵堂(つきかげじぞうどう)
鎌倉市極楽寺3-1
真言律宗西大寺派?
御本尊:地蔵菩薩(月影地蔵尊)
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第21番
月影地蔵堂は、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所です。
下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
月影地蔵尊には、以下のような哀しい逸話が伝わっています。
昔、このあたりに鎌倉幕府第8代執権時宗公の連署・北条業時邸に仕える母娘が住んでいました。
母親は悪女でしたが、娘の「露」は気立てのよい孝行娘でした。
ある時、母親が業時愛用の白磁の皿を割ってしまい、これを咎められるとその罪を娘の露になすりつけ、露も自分が割ったと申し述べました。
業時は露の罪ではないと見抜いたものの、行きがかり上やむなく母娘に暇を出しましたが、その折に露には「梅小紋の小袖」を与えました。
その後、母親は露の「梅小紋の小袖」を奪って姿を消しました。
業時は露を屋敷で保護しましたが、露は追放された母の身をいとうあまり病に倒れついにこの世を去りました。
人々は露を哀れにおもい、露の生まれた「月影ヶ谷」に墓を立てました。
いつしかその墓には「梅の木苔」がびっしりと生え、人々は「梅小紋の小袖」に袖を通すこともなく亡くなった不憫な露のために、月影地蔵尊が「梅の木苔」を着せたのだと噂したといいいます。
露の墓所はいまは不明ですが、月影地蔵堂境内にある石像は露を祀ったともいわれます。
月影地蔵尊は極楽寺建立(正元元年(1259年))以前から「月影ヶ谷」に御座し、江戸時代に稲村ケ崎小学校の奥の西ヶ谷(現在地)に遷されたといいます。
「月影ヶ谷」は鎌倉時代中期に成立し、中世三大紀行文のひとつに数えられる『十六夜日記』(いざよいにっき)ゆかりの地です。
『十六夜日記』は藤原為家の側室・阿仏尼によって書かれた名作です。
藤原為家(1198-1275年)は、歌道の本流ともいわれる御子左家(みこひだりけ)・藤原定家の嫡男として生まれ、鞠道や歌道の大家として名を馳せ、政治的手腕も備えていたため、後嵯峨院のもとで正二位・権大納言までのぼりました。
阿仏尼(あぶつに、1222?-1283年)は、平維茂の子孫である奥山度繁の娘ないし養女で、後堀河帝の准母・安嘉門院(邦子内親王)に仕え、失恋の失意から一旦尼となりましたが、30歳の頃藤原為家の側室となり、冷泉為相を産みました。
為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。
鎌倉下向時のことどもを紀行として著したのが『十六夜日記』です。
阿仏尼は当時の女流文人にはめずらしく紀行文をものしたこと、領地返還の訴訟をおこしたことなどから、かなり現実的な行動をする女性とみられています。
『十六夜日記』は当初無題で『阿仏日記』などと呼ばれていましたが、書き出しが10月16日であることから後世に『十六夜日記』と題されたといいます。
阿仏尼の訴訟は最終的に勝訴したといい、子の為相は冷泉家をおこして正二位・権中納言までのぼり、晩年は母親ゆかりの鎌倉にあって鎌倉歌壇を指導したといいます。
「鎌倉と(旧)鎌倉郡の歴史をたずねて」様によると、江ノ電「極楽寺」駅と「七里ヶ浜」駅の中間にある江ノ島車庫の南側の線路沿いに「阿陀邸旧蹟」があり、そこから西北に伸びる谷筋が「月影ヶ谷」(つきかげがやつ)です。
弘安二年(1279年)(建治三年(1277年)とも)、訴訟のため京を発ち鎌倉へ下った阿仏尼は、翌年秋まで(数年間とも)「月影ヶ谷」に滞在したと伝わります。
「月影ヶ谷」という風流な地名は、『十六夜日記』に「すむところは月影の谷」と記されているゆえんともいいます。
東にてすむ所は月影の谷とぞいふなる、浦近き山もとにて風いと荒し
山寺の傍らなればのどかに凄くて 波の音松風絶えず
阿仏尼の没地は鎌倉ではないといいますが、英勝寺墓地の崖下には阿仏尼の墓と伝わる供養塔があります。
「鎌倉市中央図書館資料」(PDF)によると、近所の人は月影地蔵尊に「こどもがじょうぶに育ちますように。」とお祈りするそうですが、これは若くしてなくなった娘(露)を供養された月影地蔵尊の逸話によるものと思われます。
観光客もまばらな山際の目立たない地蔵堂ですが、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所なので参拝者はそれなりにいると思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
月影谷附阿佛屋敷
月影谷は、極楽寺の境内、西の方なり。昔は暦を作る者居住せしとなり。此所に阿佛屋敷あり。【十六夜日記】に、東にて住む所は月影谷とぞ云なる。浦近き山本にて、風いとあらし、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風たへずとあり。
英勝寺の境内に阿佛屋敷と云有。彼こは葬たる所故に、阿佛卵塔屋敷と云有。
住し所は此谷なり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
月影の谷
此谷は極楽寺より西寄、阿佛尼の故居なり。
【十六夜日記】に、あつまにてすむ所は月影のやつとそいふなる。浦近き山もとにて風いとあらし、山寺のかたはらなれはのとかにすこくて、浪の音松の風たへずと云々。
此日記は下向の時の紀行なり。此阿佛尼と申は定家卿の室にて、公達五人ましましける。
播磨の國細川の庄を為家卿よりゆすりおかれるを、為氏卿は他腹たるによりて横領し給ひしを、そしゆうのために鎌倉え下られける。
為相卿もちんぢやうのため、両人ともにかまくらにて死去せられし。
そしやうは為氏卿のかたへはつけらすとかや。
此阿佛は安嘉門院四條と申人なり。為相卿の母堂なり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
阿佛尼第蹟
月影谷にあり今阿佛屋鋪と唱へ陸田の寺に残れり
阿佛は為家の室にて為相の母なり
【十六夜日記】にも当所に在しと記せり
曰、東にて住む所は月影谷とぞ云なる浦近き山にて、風いとあらし、山寺の傍なればのどかに凄くて浪の音松風絶えず云々
母子ともに鎌倉に在て死せしと云ふ、今も扇ヶ谷村に為相の墓あり
又同村英勝寺域内に阿佛卵塔屋鋪と云あり是尼が葬地なり
■ 山内掲示(文学案内板)
鎌倉時代中期の女流歌人、阿仏尼は夫である藤原為家の没後、先妻の子為氏と実子為相とのあいだにおこった遺産相続の訴訟のため、京都から鎌倉へ下った。
その間のことを記したのが「十六夜日記」で、前半は東海道の紀行文、後半は鎌倉での日記となっている。鎌倉では月影ヶ谷に滞在した。
為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。
「十六夜日記」には次のように記されている。
東にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風絶えず。
-------------------------
江ノ電「極楽寺」駅から徒歩約5分。
導地蔵を通り過ぎ、北の山側に道なりにいくと稲村ヶ崎小学校があり、その先の小路を左に入り右に折れてすぐです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 尊格碑
道が二股になるところ、数段高く置かれた参道の向こうに地蔵堂がみえます。
参道右手には「月影地蔵」の石標とそのおくに数基の墓石。
右手には数体の石仏が並び、そのうちのいずれかが露を祀った像とされています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 地蔵堂
地蔵堂はおそらく寄棟造銅板葺で、前面に小屋根を置き軒下が向拝となっています。
向拝柱はなく、柱と見上げに「月影地蔵」の板と扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 尊格標
御内陣に御座す月影地蔵尊は木造の立像で、赤い衣を着て頭巾をかぶられています。
ふっしらとした面立ちでやさしい印象のお地蔵さまです。
「子供が丈夫に育ちますように」と祈願される地蔵尊で、堂内には千羽鶴が奉納されています。
御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。
〔 月影地蔵堂の御朱印 〕
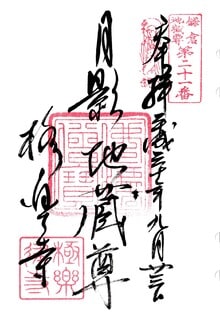
→ ■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)へつづく。
【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-1)
■ シャ・ラ・ラ (1982年)
■ 海 (『人気者で行こう』1984年)
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)
■ 同-19 (C.極楽寺口-2)
■ 同-20 (C.極楽寺口-3)から。
57.明鏡山 円満院 星井寺(虚空蔵堂)(ほしいでら)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市坂ノ下18-28
真言宗大覚寺派
御本尊:虚空蔵菩薩
司元別当:
札所:鎌倉十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)
※現在は普明山成就院の境外仏堂
星井寺(虚空蔵堂)は虚空蔵菩薩を御本尊とする密寺で、現在は普明山成就院の境外仏堂となっています。
鎌倉十三仏霊場第13番の札所として知られています。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
星井寺(虚空蔵堂)は、天平年間(729-749年)、古井戸「星月井」のなかに虚空蔵菩薩の御影を見い出した行基菩薩が、自ら虚空蔵菩薩像を彫刻し建立した堂宇と伝わります。
「星月井」は鎌倉十井(かまくらじっせい)の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれます。
極楽寺坂ののぼり口にあたるこのあたりは、木々が生い茂り昼なお暗かったため「星月夜」(ほしづきよ)と呼ばれ、ここにある井戸なので「星月夜の井」と呼ばれたといいます。
あるいは、暗い井戸のなかに昼でも星の影が見えたことから、この名がついたとも。
源頼朝公はこちらの虚空蔵尊を内陣仏として崇敬し、仏師運慶に外陣仏を刻させて御前立としたといいます。
虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は、無限の智恵と大慈大悲を持たれる菩薩とされます。
梵語はアーカーシャガルバ。明星天子、大明星天王などの別名があります。
御真言はノウボウ・アキャシャキャラバヤ・オンアリキャ・マリボリソワカ。
種子はタラーク。三昧耶形は宝剣、如意宝珠、ご縁日は毎月13日です。
高野山霊宝館Web、Wikipediaによると、虚空蔵菩薩は大日如来の福智の二徳を司る仏で、とくに「智恵を授ける仏さま」「頭脳明晰となり記憶力が高まる功徳」として信仰を集めています。
虚空蔵尊信仰はすでに奈良時代からあったといい、若かりし弘法大師も虚空蔵尊を御本尊とする「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を阿波太龍岳や土佐室戸崎などで修行されたと伝わります。
また、虚空蔵尊に礼するものは、三世十方一切の諸仏を礼することと同じともされる強力な尊格です。
虚空蔵菩薩の誓願に「人には三期の厄あり。その厄災のうち、とりわけて変体の厄を除き、智徳を与え、二世の願いを成就せしめん。」という項目があり、「変体」とは子供から大人に変わる年頃をいいます。
虚空蔵尊は「十三詣り」の御本尊として知られます。
「十三詣り」とは旧暦の3月13日前後に、数え年13歳でおこなう寺院詣でで、とくに虚空蔵尊にお参りします。
京都嵯峨の虚空蔵法輪寺が有名ですが、各地でみられる風習で星井寺でも「十三詣り」がおこなわれます。
この「十三詣り」はおそらく「変体(子供から大人に変わる年頃)の厄払い」から来ているものと思われます。
虚空蔵信仰は星宿、日月などの星神信仰と深い関係をもち、「星月井」とのゆかりも、この信仰からきているのでは。
一見なじみのない尊格にも思えますが、弘法大師とのゆかりもあって、真言密教ではことに重要な尊格とされ、禅刹でもしばしば御本尊となられます。
虚空蔵尊は「十三仏詣で」の一尊です。
「十三仏詣で」とは室町時代に日本で成立した信仰で、十三回の追善供養(初七日〜三十三回忌)をそれぞれ司る仏尊を供養ないし詣でるものです。
虚空蔵尊は三十三回忌の尊格で、札番13番の結願尊となります。
星井寺の虚空蔵尊も鎌倉十三仏霊場第13番の札所本尊となっています。
(詳細は→こちら。)
また、十二支守り本尊参りでは、虚空蔵尊は丑歳、寅歳の守り本尊となっています。
虚空蔵尊の像容は、右手に宝剣、左手に如意宝珠を持つタイプ、法界定印の掌中に五輪塔を持つタイプ、与願印を結ぶタイプなどがみられ多彩です。
かつて、「星月井」(星月夜の井)は鎌倉を代表する名所でした。
慶長五年(1600年)6月、徳川家康公は京・伏見城から上杉氏征伐のため江戸に向かう途中、「星月井」に立ち寄っています。(6月29日とみられる)
「慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ」(「星月井」碑文)
神奈川県Webによると、「星月夜の井」は「鎌倉」を導く枕詞とされています。
我ひとり鎌倉山を越へ行けば 星月夜こそうれしかりけれ (後堀川百首)
鎌倉市の旧徽章は「星月夜」がモチーフにされていたともいいます。
鎌倉宮近くの通りに、この旧徽章を描いたマンホールが一枚だけ残っています。
鉄道唱歌にも「星月井」(星月夜の井)は下記のとおり歌われ、鎌倉を代表する名所であったことを裏付けています。
「北は円覚建長寺 南は大仏星月夜 片瀬腰越江の島も ただ半日の道ぞかし」
こぢんまりとした山内ですが、上記のようにさまざまな由緒沿革をもち、鎌倉を代表する虚空蔵尊霊場として重要な堂宇です。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
星月夜井
極楽寺の切通へ上る坂の下、右の方にあり。里老云、昔は此井の中に、昼も星の影見ゆる故に名く。此邊の奴碑、此井を汲に来り、誤て菜刀を井中へ落したり。爾しより来星影不見と。
又此井の西に、虚空蔵堂あり。星月山星井寺と号す。極楽寺村の、成就院の持ち分なり。成就院は、真言宗。虚空蔵は、行基作、長二尺五寸。縁起一巻あり。其略に云、聖武帝の天平中(729-749年)に、此井に光りあり。里民不思議の思をなし、これを見れば、井の邊に、虚空蔵の像現じ給。此由を奏しければ、行基に勅し、此像を作らしめ、爰に安置し給ふとあり。
【後堀河百首】に常陸が歌に
「我ひとり 鎌倉山を越行ば、星月夜こそ うれしかりけれ」
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
虚空蔵堂
極楽寺村のうち、星月夜の井の西にあり。この堂を星月山星井寺と号す。
村内成就院の持なり。これは真言宗。
虚空蔵は行基作、長二尺五寸。縁起の略に、聖武天皇の天平年中(729-749年)、此寺井に光有。里民不思議のおもひをなし、是を見れば井の邊に虚空蔵の像現じ給ふと。此よしを奏しければ、行基に勅し此像を造らしめ、爰に安置し給ふと云云。【堯恵法印紀行】に、星の御堂と書しは、この堂のことなり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(坂之下村)虚空蔵堂
明鏡山(【鎌倉志】には星月山に作る)星井寺と号す、極楽寺村成就院持なり
本尊は行基の作像なり 木佛立像長三尺
縁起に拠るに聖武帝の天平年中(729-749年)此寺の井に光あり、村民奇として是を見るに井の邊に虚空蔵の形出現す、此由天聴に達しければ行基に勅ありて此像を造らせられ、即爰に安置ありしと云へり、堯惠が紀行に星の御堂とあるは此堂なり
【什寶】
明星石一顆 星ノ井より出し物と云ふ
独鈷 行基所持の物と云ふ、下同じ
唐錢六文 是も照天姫、所持せし物と云ふ、祟寧通寶二文、祟寧重寶四文とあり
駒爪 小栗判官の乗馬、鬼鹿毛の爪なりと伝ふ
■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)
明鏡山円満院星の井寺(御本尊虚空蔵菩薩安置)
天平年間(729-749年)、聖武天皇の御代に諸国行脚中の行基僧正が当地の古井戸「星月の井」に明るく輝く明星の光りが移るとのうわさを地元民から聴き、井戸をのぞくと中に虚空蔵菩薩のお姿が写し現われていた
行基はそのお姿を仏像に彫り当地にお堂を建立し安置した。
かの像は明星の照曜の如き光を放ち、鏡に影の移る如くでありました。
以後数百年経って幕下の征夷大将軍源頼朝公はこの菩薩を崇敬し、この菩薩像を内陣仏の秘仏とし、仏師運慶に外陣仏を作らせた これが前立尊であるという。
秘仏虚空蔵菩薩はわが国では唯三体の木彫の仏像で大変貴重な仏像であります。
これに加えてこの御仏は明星と一体で、その分身であり限りない知恵をそなえた御仏で、経典では虚空蔵菩薩は、西方香集世界の教主で娑婆世界の苦難する人々の利益のために無不畏陀羅尼を説くことを、釈迦・敷蔵の二仏に許された御仏であります。
即ちその本尊に礼するものは三世十方一切の諸仏を礼することと同じであるといわれます。
又、虚空蔵菩薩を本尊として修業する虚空蔵求聞持法では心を静かにしこの真言を唱えれば天より明星が口に入り、菩薩の威はあらわれて頭脳は明晰となり記憶力は増進するといわれております。
秘仏であるが衆生に縁を結ばせるべきでるとして三十五年一度に開帳し衆生にそのお姿を拝する事が許されました。
近代に至り熱心な信仰者の意に添うようにと毎年正月十三日に開帳し善男善女もそのお姿を毎年拝することが出来るようになりました。
正月十三日の初護摩供養には、丑年寅年の人々の守本尊として、また、知恵、記憶力をお授け下さる虚空蔵様として地元民をはじめ各地より善男善女が参詣に集まります。
■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)
舟守地蔵(虚空蔵堂境内安置)
いつの時代に開眼されたお地蔵であるか不明であるが往年より海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係した一切の事業に従事しておられる人々に大きな功徳をお授け下さるお地蔵として近郷、近在の人々に深く崇敬されております。
また、その昔より願主の心清く精進すれば願い事を数日で成就させていだ(ママ)ける有難いお地蔵様であるとも言い伝えられております。
■ 現地掲示((社)鎌倉青年会議所)
星の井(ほしのい)
この井戸は、鎌倉十井の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれています。
昔、この井戸の中に昼間も星の影が見えたことから、この名がついたといわれています。
奈良時代の名僧・行基は、井戸から出てきた光り輝く石を虚空蔵菩薩の化身と思い、お堂を建てて虚空蔵菩薩をまつったという伝説もあります。
井戸の水は清らかで美味だったので、昭和初期まで旅人に飲料水として売られていたそうです。
■ 現地掲示(「星月井」碑文、昭和二年三月建 鎌倉青年団)
星月夜ノ井ハ一ニ星ノ井トモ言フ鎌倉十井ノ一ナリ
坂ノ下ニ属ス往時此附近ノ地老樹蓊鬱トシテ昼尚暗シ故ニ称シテ星月谷ト曰フ後転ジテ
星月夜トナル井名蓋シ此ニ基ク里老言フ古昔此井中昼モ星ノ影見ユ故ニ此名アリ近傍ノ婢女誤ツテ菜刀ヲ落セシヨリ以来星影復タ見エサルニ至ルト此説最モ里人ノ為メニ信ゼラルルガ如シ慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ以テ
其名世ニ著ハルルヲ知ルベシ水質清冽最モ口ニ可ナリ
-------------------------
長谷と極楽寺のあいだにある極楽寺切通の長谷側ののぼり口にあります。
ちょうど鎌倉・長谷の市街から極楽寺切通の山手にさしかかるところで、周囲は木々に覆われています。
極楽寺切通は、新田義貞勢がついに攻め落とすことができなかった要衝です。
極楽寺坂切通は極楽寺開山の忍性(1217-1303年)により拓かれたという説があるので、新田義貞の時代はもっと厳しい道のりだったのかもしれません。

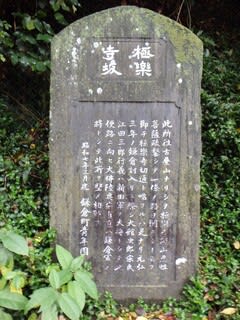
【写真 上(左)】 極楽寺坂
【写真 下(右)】 極楽寺坂の碑
長谷から行くと、極楽寺坂の右手手前に宝形の屋根が掛かった「星月井」とその石碑。
そのおくが虚空蔵堂の参道です。


【写真 上(左)】 星月井と虚空蔵堂の参道
【写真 下(右)】 星月井


【写真 上(左)】 星月井の碑
【写真 下(右)】 参道-1
筆者の参拝時に建てられていた「初護摩供」の看板には「日本三虚空蔵」とありましたが詳細は不明です。
こちらの御本尊(虚空蔵尊)はもともと秘仏でしたが、35年に一度御開帳されるようになり、いまは毎年1月13日の初縁日にご開帳されています。(毎年1月、5月、9月の13日とも)


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 狛犬と虚空蔵堂
「南無虚空蔵菩薩」の奉納幟がはためく急な石段を登ると左右に立派な狛犬。
正面が本堂で、向かって左手前に舟守地蔵尊の堂宇があります。


【写真 上(左)】 本堂(虚空蔵堂)
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
本堂(虚空蔵堂)はおそらく入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

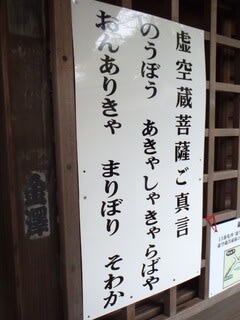
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩の御真言
右手身舎には虚空蔵菩薩の御真言。
向拝見上には山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 舟守地蔵尊
舟型地蔵尊の堂宇は切妻造銅板葺の妻入りで、舟形台座のうえに御座する地蔵尊を間近で拝せます。
開眼の時期は不明ですが、海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係する業に従事する人々に功徳をお授けくださるお地蔵様とのこと。
願主の心が清く、精進すれば願い事を数日で成就いただけるともいいます。
もともと虚空蔵尊と地蔵尊とは対になっていたという説があります。
星井寺で虚空蔵尊と地蔵尊(舟守地蔵尊)が奉安されているのは、この流れによるものかもしれません。
御朱印は、極楽寺坂を3分ほど登った成就院で拝受できます。
なお、星井寺から成就院へ向かう極楽寺坂の途中に、日限六地蔵尊のお堂があります。
説明板によると、道行く人々をお守り下さり、願いを期日を極めておすがりすれば、その期日までに功徳がいただける有難いお地蔵様とのことです。


【写真 上(左)】 日限六地蔵尊
【写真 下(右)】 日限六地蔵尊の説明板
〔 星井寺の御朱印 〕

58.普明山 法立寺 成就院(じょうじゅいん)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市極楽寺1-1-5
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
司元別当:御霊神社(坂の下)、星井寺虚空蔵堂(坂の下)
札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番
成就院は弘法大師空海とのゆかりを伝え、鎌倉幕府第3代執権北条泰時公が創建という古刹です。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
弘法大師が相州江島に留錫されたとき、この地で数日間護摩供を修されたといいます。
Wikipediaによると、伝承によれば弘法大師が江ノ島の金窟(現・岩屋)に参拝し国土守護・万民救済を祈願、社殿(岩屋本宮)を創建されたのは、弘仁五年(814年)とあるので、成就院の護摩供伝説もおそらくその頃とみられます。
弘法大師は成就院の裏山で虚空蔵求聞持法を修されたと伝わります。
であれば、成就院よりも虚空蔵菩薩を御本尊とする星井寺の由緒にこの伝承がでてきそうですが、調べた限りでは星井寺の由緒には弘法大師の虚空蔵求聞持法は記されていないようです。
弘法大師は相模湾や富士山を望む高台で護摩を焚かれ、その煙は海風にのってたなびき、厳修の鈴の音は里々に響き渡り、その煙や鈴の音が届いた里は作物がよく実り、人々は安心して暮らすことができたといいます。
この伝承を聞いた鎌倉幕府第3代執権北条泰時公は、高僧を請して承久元年(1219年)不動明王を御本尊として堂宇を建立、普明山願成就院と号したといいます。
元弘三年(1333年)、新田義貞鎌倉攻めの際に伽藍を焼失し、西谷に遁れたものの願成就院はひきつづき鎌倉幕府で重んじられ、第5代鎌倉公方足利成氏公(1449-1455年)は、毎年正月に願成就院の住持を招いて饗待したと伝わります。
元禄年中(1688-1704年)、祐尊和尚のときに旧地に還って再興したため、祐尊和尚を中興とします。
元寇の役の供養のために植えられたという、262株(般若心経の文字数と同じ)の紫陽花が有名で、花の寺としても知られています。
こちらの御本尊・不動明王は古来から「縁結び不動明王」と崇められ、良縁成就の寺としても知られています。
成就院の寺宝として、真言僧・文覚(1139-1203年)が自ら彫ったとされる「文覚上人荒行像」が伝わります。
日本の近代彫刻の大家・荻原碌山(おぎわらろくざん/守衛)の代表作「文覚」は、この像に触発されて作られたといいます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(極楽寺村)成就院
普明山法立寺と号す、古義真言宗 手廣村青蓮寺末 北條泰時開基すと云ふ
縁起に拠に空海江島に錫を駐めし時此地に於て数日護摩供を修す、此時泰時高僧を請して承久元年(1219年)一宇を建立し願成就院と称し大師護摩の靈場なるを以て普明山と号すとなり、管領成氏が時は毎年正月住持を営中に饗待あり(中略)
永禄五年(1562年)十月大道寺駿河守政繁寺内制札の副状を出せり(中略)
当寺元弘の乱(1331-1333年)に寺地を蹂踐せられ、西谷に遁れて星霜を送りけるが元禄年中(1688-1704年)現住祐尊が時舊地に還住し再興せり、故に祐尊を中興とす(元禄十四年(1701年)十月十一日寂す)本尊不動を置く
稲荷社 境内の鎮守とす
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
普明山法立寺成就院と号する。
古義真言宗。もと青蓮寺末、いま京都大覚寺末。
縁起によれば、承久元年(1219年)十一月廿一日、北条泰時の創建で、空海が護摩供を修した跡に建立したという。
本尊、不動明王。
境内地596坪。本堂・山門・庫裏等あり。
『風土記稿』には元文六年二月二十一日岩沢重●の作った縁起により、元弘の乱に寺地を蹂踐され、西谷に移っていたのを元禄年中(1688-1704年)に祐尊が旧地に還って再興した。とあるが、現在寺にはこのことを証すべき史料がない。
ただし、極楽寺の奥に西方寺屋敷とよんでいるところがあり、ここが成就院の持地であるから、もとここに移っていたのかもしれない。(中略)
明鏡山円満院星井寺と号する虚空蔵堂を管理している。
-------------------------
長谷から星井寺(虚空蔵堂)を過ぎて極楽寺坂を登ると極楽寺切通。
成就院は、極楽寺切通の上方にあります。


【写真 上(左)】 極楽寺切通
【写真 下(右)】 東参道


【写真 上(左)】 東参道からの由比ヶ浜
【写真 下(右)】 山内からの由比ヶ浜
参道・山内からは由比ヶ浜の海岸が、思いがけないアングルで見下ろせます。
こういう景色は山が海に迫る鎌倉ならでは。


【写真 上(左)】 東参道の山門
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 西参道
【写真 下(右)】 西参道の山門
長谷方向からの参道の山門には「東結界」の扁額と傍らには院号標。
極楽寺方向からの参道登り口には山号標、その先の山門には「西結界」の扁額が掲げられています。
東参道の石段は108段あるそうで、なかなか登りごたえがあります。


【写真 上(左)】 山号標
【写真 下(右)】 山門
東西の参道が合わさって正面階段うえに切妻屋根銅板葺の山門。四脚門とも思いますが、山内側から撮影し忘れたので薬医門かもしれません。
桁行一間、梁間二間の禅宗様で、江戸時代後期のものとのこと。
二軒の繁垂木、四連の中備と脇塀を備えた立派な山門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 秋の山内
【写真 下(右)】 なで蛙
高台にある山内はさほど広くないものの見どころ多数。
いつも観光客で賑わい、明るい雰囲気のお寺さまです。
向かって左手には庫裏と授与所。


【写真 上(左)】 手水鉢
【写真 下(右)】 修行大師像


【写真 上(左)】 御分身不動明王
【写真 下(右)】 御朱印案内
右手には手前から立派な龍をおいた手水鉢と修行大師像。
その先の矜羯羅・制多伽の二童子を従えた「御分身不動明王」は、パワースポット「縁結び不動明王」として有名なようです。
そのおくに子授け・安産・子育ての功徳のある子安地蔵菩薩と子生み石がある筈ですが、なぜか写真が残っていません。


【写真 上(左)】 聖徳太子堂
【写真 下(右)】 チベット招来仏(レプリカ)
さらにそのおくに聖徳太子1300年御忌を記念して造立された多角堂がおかれ、覆堂には「和貴」の扁額が掲げられています。
河口慧海釈迦菩行像は、河口慧海師(1866-1945年)がチベットから持ち帰られた像のレプリカです。
さらに文覚上人荒行像のブロンズ像がある筈ですが、なぜかこちらも写真がありません。
こちらは3回お参りしているのですが、すみません、なぜか撮影忘れが目立ちます。
文覚上人荒行像は「日本のロダン」と称された明治時代の彫刻家、荻原碌山の作品に大きな影響を与えたとされるものです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺でボリューム感のある堂宇。
向拝柱はなく、堂前はすっきりとしています。
向拝見上げに院号扁額。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂内には、御本尊の不動明王、大日如来、地蔵菩薩が御座します。
不動明王は、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所本尊です。
鎌倉三十三観音霊場第21番の札所本尊・聖観世音菩薩と相州二十一ヶ所霊場第13番の札所本尊・弘法大師座像も本堂内に奉安で、こちらが拝所となります。
〔 成就院の御朱印 〕
こちらは鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所です。
新四国東国八十八ヶ所霊場は、川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)で、鎌倉市内では、補陀洛寺(材木座)、浄光明寺(扇ヶ谷)、成就院(極楽寺)、満福寺、浄泉寺、宝善院(以上腰越)、青蓮寺(手広)の7寺院が札所で、結願は手広の青蓮寺です。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
新四国東国八十八ヶ所霊場については、こちらの記事をご覧ください。
なお、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印については申告して拝受した記憶がありますが、札所印は捺されていません。あるいは札所印つき御朱印を拝受できるかもしれません。

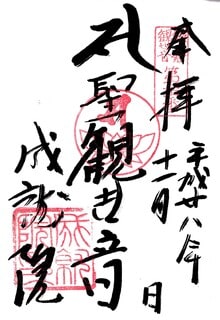
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 同(御朱印帳)
※相州二十一ヶ所霊場の御朱印は、専用納経帳では「弘法大師」、御朱印帳では「遍照金剛」の揮毫をいただいています。
59.月影地蔵堂(つきかげじぞうどう)
鎌倉市極楽寺3-1
真言律宗西大寺派?
御本尊:地蔵菩薩(月影地蔵尊)
司元別当:
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第21番
月影地蔵堂は、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所です。
下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。
月影地蔵尊には、以下のような哀しい逸話が伝わっています。
昔、このあたりに鎌倉幕府第8代執権時宗公の連署・北条業時邸に仕える母娘が住んでいました。
母親は悪女でしたが、娘の「露」は気立てのよい孝行娘でした。
ある時、母親が業時愛用の白磁の皿を割ってしまい、これを咎められるとその罪を娘の露になすりつけ、露も自分が割ったと申し述べました。
業時は露の罪ではないと見抜いたものの、行きがかり上やむなく母娘に暇を出しましたが、その折に露には「梅小紋の小袖」を与えました。
その後、母親は露の「梅小紋の小袖」を奪って姿を消しました。
業時は露を屋敷で保護しましたが、露は追放された母の身をいとうあまり病に倒れついにこの世を去りました。
人々は露を哀れにおもい、露の生まれた「月影ヶ谷」に墓を立てました。
いつしかその墓には「梅の木苔」がびっしりと生え、人々は「梅小紋の小袖」に袖を通すこともなく亡くなった不憫な露のために、月影地蔵尊が「梅の木苔」を着せたのだと噂したといいいます。
露の墓所はいまは不明ですが、月影地蔵堂境内にある石像は露を祀ったともいわれます。
月影地蔵尊は極楽寺建立(正元元年(1259年))以前から「月影ヶ谷」に御座し、江戸時代に稲村ケ崎小学校の奥の西ヶ谷(現在地)に遷されたといいます。
「月影ヶ谷」は鎌倉時代中期に成立し、中世三大紀行文のひとつに数えられる『十六夜日記』(いざよいにっき)ゆかりの地です。
『十六夜日記』は藤原為家の側室・阿仏尼によって書かれた名作です。
藤原為家(1198-1275年)は、歌道の本流ともいわれる御子左家(みこひだりけ)・藤原定家の嫡男として生まれ、鞠道や歌道の大家として名を馳せ、政治的手腕も備えていたため、後嵯峨院のもとで正二位・権大納言までのぼりました。
阿仏尼(あぶつに、1222?-1283年)は、平維茂の子孫である奥山度繁の娘ないし養女で、後堀河帝の准母・安嘉門院(邦子内親王)に仕え、失恋の失意から一旦尼となりましたが、30歳の頃藤原為家の側室となり、冷泉為相を産みました。
為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。
鎌倉下向時のことどもを紀行として著したのが『十六夜日記』です。
阿仏尼は当時の女流文人にはめずらしく紀行文をものしたこと、領地返還の訴訟をおこしたことなどから、かなり現実的な行動をする女性とみられています。
『十六夜日記』は当初無題で『阿仏日記』などと呼ばれていましたが、書き出しが10月16日であることから後世に『十六夜日記』と題されたといいます。
阿仏尼の訴訟は最終的に勝訴したといい、子の為相は冷泉家をおこして正二位・権中納言までのぼり、晩年は母親ゆかりの鎌倉にあって鎌倉歌壇を指導したといいます。
「鎌倉と(旧)鎌倉郡の歴史をたずねて」様によると、江ノ電「極楽寺」駅と「七里ヶ浜」駅の中間にある江ノ島車庫の南側の線路沿いに「阿陀邸旧蹟」があり、そこから西北に伸びる谷筋が「月影ヶ谷」(つきかげがやつ)です。
弘安二年(1279年)(建治三年(1277年)とも)、訴訟のため京を発ち鎌倉へ下った阿仏尼は、翌年秋まで(数年間とも)「月影ヶ谷」に滞在したと伝わります。
「月影ヶ谷」という風流な地名は、『十六夜日記』に「すむところは月影の谷」と記されているゆえんともいいます。
東にてすむ所は月影の谷とぞいふなる、浦近き山もとにて風いと荒し
山寺の傍らなればのどかに凄くて 波の音松風絶えず
阿仏尼の没地は鎌倉ではないといいますが、英勝寺墓地の崖下には阿仏尼の墓と伝わる供養塔があります。
「鎌倉市中央図書館資料」(PDF)によると、近所の人は月影地蔵尊に「こどもがじょうぶに育ちますように。」とお祈りするそうですが、これは若くしてなくなった娘(露)を供養された月影地蔵尊の逸話によるものと思われます。
観光客もまばらな山際の目立たない地蔵堂ですが、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所なので参拝者はそれなりにいると思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
月影谷附阿佛屋敷
月影谷は、極楽寺の境内、西の方なり。昔は暦を作る者居住せしとなり。此所に阿佛屋敷あり。【十六夜日記】に、東にて住む所は月影谷とぞ云なる。浦近き山本にて、風いとあらし、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風たへずとあり。
英勝寺の境内に阿佛屋敷と云有。彼こは葬たる所故に、阿佛卵塔屋敷と云有。
住し所は此谷なり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
月影の谷
此谷は極楽寺より西寄、阿佛尼の故居なり。
【十六夜日記】に、あつまにてすむ所は月影のやつとそいふなる。浦近き山もとにて風いとあらし、山寺のかたはらなれはのとかにすこくて、浪の音松の風たへずと云々。
此日記は下向の時の紀行なり。此阿佛尼と申は定家卿の室にて、公達五人ましましける。
播磨の國細川の庄を為家卿よりゆすりおかれるを、為氏卿は他腹たるによりて横領し給ひしを、そしゆうのために鎌倉え下られける。
為相卿もちんぢやうのため、両人ともにかまくらにて死去せられし。
そしやうは為氏卿のかたへはつけらすとかや。
此阿佛は安嘉門院四條と申人なり。為相卿の母堂なり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
阿佛尼第蹟
月影谷にあり今阿佛屋鋪と唱へ陸田の寺に残れり
阿佛は為家の室にて為相の母なり
【十六夜日記】にも当所に在しと記せり
曰、東にて住む所は月影谷とぞ云なる浦近き山にて、風いとあらし、山寺の傍なればのどかに凄くて浪の音松風絶えず云々
母子ともに鎌倉に在て死せしと云ふ、今も扇ヶ谷村に為相の墓あり
又同村英勝寺域内に阿佛卵塔屋鋪と云あり是尼が葬地なり
■ 山内掲示(文学案内板)
鎌倉時代中期の女流歌人、阿仏尼は夫である藤原為家の没後、先妻の子為氏と実子為相とのあいだにおこった遺産相続の訴訟のため、京都から鎌倉へ下った。
その間のことを記したのが「十六夜日記」で、前半は東海道の紀行文、後半は鎌倉での日記となっている。鎌倉では月影ヶ谷に滞在した。
為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。
「十六夜日記」には次のように記されている。
東にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風絶えず。
-------------------------
江ノ電「極楽寺」駅から徒歩約5分。
導地蔵を通り過ぎ、北の山側に道なりにいくと稲村ヶ崎小学校があり、その先の小路を左に入り右に折れてすぐです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 尊格碑
道が二股になるところ、数段高く置かれた参道の向こうに地蔵堂がみえます。
参道右手には「月影地蔵」の石標とそのおくに数基の墓石。
右手には数体の石仏が並び、そのうちのいずれかが露を祀った像とされています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 地蔵堂
地蔵堂はおそらく寄棟造銅板葺で、前面に小屋根を置き軒下が向拝となっています。
向拝柱はなく、柱と見上げに「月影地蔵」の板と扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 尊格標
御内陣に御座す月影地蔵尊は木造の立像で、赤い衣を着て頭巾をかぶられています。
ふっしらとした面立ちでやさしい印象のお地蔵さまです。
「子供が丈夫に育ちますように」と祈願される地蔵尊で、堂内には千羽鶴が奉納されています。
御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。
〔 月影地蔵堂の御朱印 〕
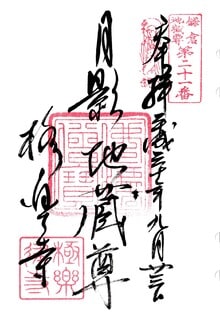
→ ■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)へつづく。
【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-1)
■ シャ・ラ・ラ (1982年)
■ 海 (『人気者で行こう』1984年)
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 青蛙堂鬼談 / 岡本綺堂

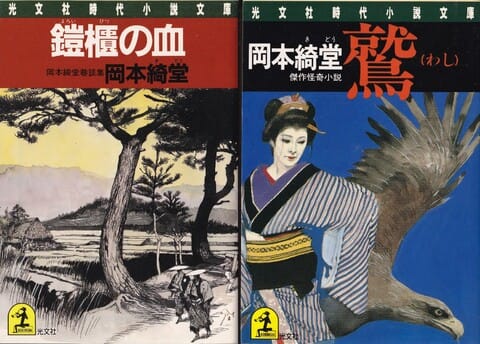
ひさびさに気に入りの小説を読み返してみたので一稿。
筆者はどちらかというと小説よりもノンフィクション派ですが、文体に惚れこんだひとりの作家がいます。
岡本綺堂(おかもと きどう)。
小説家とも、劇作家とも括られるこの人は大正から昭和初期にかけて代表作を遺し、『半七捕物帳』の作者としても知られています。
筆者が好きなのは綺堂の小編で、とくに怪奇譚。
-----------------------
綺堂は元旗本の子弟として育ち、英語が堪能で、中国にも渡り、長く新聞記者をつとめて新歌舞伎の作者としても第一人者だった。
このような経歴が、平明でムダのないリズミカルな文体を生み出したのだと思う。
たとえば名作として知られる『青蛙堂鬼談』(せいあどうきだん)の序段から引用してみると
「午後四時頃からそろそろと出る支度をはじめると、あいにく雪はまたはげしく降り出して来た。その景色を見てわたしはまた躊躇したが、ええ構わずにゆけと度胸を据えて、とうとう真っ白な道を踏んで出た。小石川の竹早町で電車にわかれて、藤坂を降りる、切支丹坂をのぼる。この雪の日にはかなりに難儀な道中をつづけて、ともかくも青蛙堂まで無事たどり着くと、もう七、八人の先客があつまっていた。」
この短い節のなかで、語り手のこころの動き、東京の雪景色と道行きをまじえ、出支度から、もう行き先の青蛙堂には七、八人の先客がいることまで語り尽くしている。
並みの技倆ではない。
『青蛙堂鬼談』はいわゆる「百物語」的な展開だが、その振り出しはこんな感じ。
「それが済んで、酒が出る、料理の膳が出る。雪はすこし衰えたが、それでも休みなしに白い影を飛ばしているのが、二階の硝子戸越しにうかがわれた。あまりに酒を好む人がないとみえて酒宴は案外に早く片付いて、さらに下座敷の広間へ案内されて、煙草をすって、あついレモン茶をすすって、しばらく休息していると、主人は勿体らしく咳(しわぶき)して一同に声をかけた。」
『中国怪奇小説集』の「開会の辞」でも似たような展開がみられる。
昭和のはじめ、午後一時から夜中の十二時過ぎまで、茶菓晩餐をはさみつつ延々と怪談を楽しむ風流人たちがいたことをこの書きぶりは示しており、案外、時間に余裕のあったこの時代の方が文化的に贅沢であったような感じがしないでもない。
「青蛙堂は小石川の切支丹坂、昼でも木立の薄暗いところにある。広東製の大きい竹細工の蝦蟆を床の間に飾ってあるので、主人みずから青蛙堂と称している。(略)この青蛙堂の広間で、俳句や書画の会が催されることもある。怪談や探偵談などの猟奇趣味の会合が催されることもある。」
「ことしの七月と八月は暑中休会であったが、秋の彼岸も過ぎ去った九月の末、きょうは午後一時から例会を開くという通知を受け取ったので、あいにくに朝から降りしきる雨のなかを小石川へ出てゆくと、参会者はなかなかの多数で」(略)
「例のごとくに茶菓が出る。来客もこれで揃ったという時に、青蛙堂主人は一礼して今日の挨拶に取りかかった。『例会は大抵午後五時か六時からお集まりを願うことになって居りますが、こんにちはお話し下さる方々が多いので、いつもより繰り上げて午後一時からお出でを願った次第でございます。』」
「それが終わってきょうの講演者が代わるがわるに講話を始めた。火ともし頃に晩餐が出て、一時間ほど休憩。それから再び講話に移って、最後の『閲微草堂筆記』を終わったのは、夜の十一時を過ぐる頃であった。さらに茶菓の御馳走になって、十二時を合図に散会。秋雨蕭々、更けても降り止まなかった。」
綺堂の状況描写は動的でたくみだが、どこかにしんとした静謐感が流れている。
この世界に曳き込まれるとなかなか抜け出すことができず、気がつくと完読している。
とくにこれから事がはじまるまえの、一片の情景の切りとり方が凄い。
「叔父は承知して泊まることになった。寝るときに僧は雨戸をあけて表をうかがった。今夜は真っ暗で星ひとつ見えないと言った。こうした山奥にはありがちの風の音さえもきこえない夜で、ただ折おりにきこえるのは、谷底に遠くむせぶ水の音と、名も知れない夜の鳥の怪しく啼き叫ぶ声が木霊してひびくのみであった。更けるにつれて、霜をおびたような夜の寒さが身にしみて来た。」(「くろん坊」(光文社文庫『鷲』収録)より)
水の音と夜の鳥を配することで、かえって飛騨の山奥の夜更けの静寂と、闇のふかさを浮き彫りにしている。
綺堂の怪談の多くはすっきり解決しないでおわる。
描写は的確で語り漏らすことがないのだが、なぜそのような怪異がおこるかについての説明がない。
もやっとしたなぞかけが、読後、じわじわとした怖さにかわっていく。
これが綺堂の怪談の身上だと思う。
綺堂の登場人物の語り口は大概に上品だ。
たしか「山の手の武士階級のことば」と表現した評論家がいたと思うが、これはおそらく綺堂が旗本の家に育ったというところが大きい。
「いえ、どうも年をとりますとお話がくどくなってなりません。前置きはまずこのくらいに致しまして、本文(ほんもん)に取りかかりましょう。まことに下らない話で、みなさまがたの前で仔細らしく申上げるようなことではないのでございますが、席順が丁度わたくしの番に廻ってまいりましたので、ほんの申訳ばかりにお話をいたしますのですから、どうぞお笑いなくお聴きください。」
これは「青蛙堂鬼談」でも傑作と評される「猿の眼」の導入で、年配の女性の上品で落ち着いた語り口から怪談に曳き込む手法をもちいている。
英語や中国語を知り尽くしたうえで、日本語のうつくしさを表現できる作家。
もっと読まれてもいいと思う。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 渾身の一撃的洋楽バラード15曲
かつての洋楽には、メロディのかたまりのようなこういう曲たちがありました。
思いつくままに15曲アゲてみます。
■ Klymaxx - Finishing Touch
■ Bob Carlisle - Butterfly Kisses
■ Warren Hill - Shelter From The Storm
■ George Benson - Starting All Over
■ Barry Manilow - Mandy
■ Whitney Houston - Didn't We Almost Have It All
■ Ray Kennedy - My Everlasting Love
■ Linda Ronstadt feat. Aaron Neville - Don't Know Much
■ L.T.D. - For You
■ Bill Champlin - No Wasted Moments
■ Eric Carmen - Every Time I Make Love To You
■ Bill LaBounty - Crazy
■ Elton John - Candle in the Wind (Live at Madison Square Garden, NYC 2000)HD *Remastered
■ The Four Tops - Back Where I Belong
■ Journey - When You Love a Woman (Official HD Video - 1996)
思いつくままに15曲アゲてみます。
■ Klymaxx - Finishing Touch
■ Bob Carlisle - Butterfly Kisses
■ Warren Hill - Shelter From The Storm
■ George Benson - Starting All Over
■ Barry Manilow - Mandy
■ Whitney Houston - Didn't We Almost Have It All
■ Ray Kennedy - My Everlasting Love
■ Linda Ronstadt feat. Aaron Neville - Don't Know Much
■ L.T.D. - For You
■ Bill Champlin - No Wasted Moments
■ Eric Carmen - Every Time I Make Love To You
■ Bill LaBounty - Crazy
■ Elton John - Candle in the Wind (Live at Madison Square Garden, NYC 2000)HD *Remastered
■ The Four Tops - Back Where I Belong
■ Journey - When You Love a Woman (Official HD Video - 1996)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ カラバトU-18黄金の世代の7人+1人
昨日の佐久間彩加ちゃんのLIVE聴いて、あらためて彼女たちの実力を実感した。
でも、いまの時代、ソロシンガーとしてブレークするのはすこぶるむずかしい。
「坂道シリーズ」の隆盛以降、この傾向はますます強まっていて、少なくとも数人のユニットでなければインパクトがよわくなっている。
あの実力者揃いのkalafinaだって、ソロで成功するのは容易でなかったワケだから・・・。
---------------------------------
往年の名シンガーの名曲のもとには、かならずといっていいほど名クリエイターがいた。
プロのクリエイターの紡ぐ優れたメロディやアレンジメントが、シンガーの個性とあいまってヒット曲や人気曲をつくりあげた。
□ 織田哲郎
■ ZARD(坂井泉水) - 揺れる想い
□ D・A・I(長尾大)
■ 浜崎あゆみ - Voyage
□ 柿原朱美
■ 今井美樹 - 空に近い週末
□ 五十嵐充
■ Every Little Thing(持田香織) - Over and Over
□ 上田知華
■ 今井美樹 - Boogie-Woogie Lonesome High-Heel
□ 小室哲哉
■ 華原朋美 - LOVE BRACE
□ GIORGIO
■ 西野カナ - 私たち
□ 川江美奈子
■ 中島美嘉 - 桜色舞うころ
いまでいうと、天野月さんとか傘村トータさんとか・・・。
■ 天野月「栞」 feat.YURiCa/花たん
■ 傘村トータ「おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.」Covered by Cereus
でも、やっぱり梶浦由記さんかな・・・。
オリジナリティを備えた名シンガーたちが名クリエイターのもとに集結すると、こういうことになる ↓
■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)
〔 Solo Parts 〕
0:27~ / 3:46~ 貝田由里子
0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)
2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)
3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)
↑ こういう名クリエイターのもとで、1曲でもいいからコラボかまして世間の耳目を集めてほしい。
個人的には、彼女たちが集えば、少なくともリトグリよりは上、FictionJunctionと肩を並べると思っている。
---------------------------------
2023/ 05/31 UP
いろいろな歌番組を視るにつけ、どうしても彼女たちの歌のレベルの高さを再認識してしまう。
歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。
-------------------------
2023/05/31 UP
カラバトの川嵜心蘭ちゃんのテイク(予選曲)、森アナイチオシ動画でUPされてました。
(森アナイチオシ動画、どれもナイスチョイスです。)
■ 【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)
やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。
歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?
現在高3。
佐久間 彩加ちゃんの一学年下だから、「カラバトU-18黄金の世代」に入る年代かも。
-------------------------
2023/01/23 UP
昨日放送のU-18歌うま甲子園 2023開幕戦、録画したやつ視てみました。
優勝は川嵜心蘭ちゃんだと思ったけどね、個人的には・・・。
(もちろん、優勝者さんも好テイクだったが)
川嵜心蘭ちゃんのテイク(別番組、一部)↓
→ プロフィール
この子は2021/12/23放送の「歌唱王」にも出ていて、そのときも →この記事で「声に深みがあって聴いてて心地よい。」とコメントつけてた。
やっぱり今回も印象は同様で、聴いてて心地よかった。
歌にスケール感があって、感情が入り込んでいた。
しかし、この上質なビブラートで決勝曲のG(拡張形)は気の毒。
どう聴いてもボックスB-1かB-2だと思う。
それと、中川寛大さんの歌いまわしはかなりエモかった。
これで94点台は気の毒すぎる。
でも、やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。
(順不同です)
■ 佐久間彩加ちゃん
■ 三阪咲ちゃん
■ 原藤由衣ちゃん
■ 富金原佑菜ちゃん
■ 熊田このはちゃん
■ 鈴木杏奈ちゃん
■ 堀優衣ちゃん
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「冬のうた」Kiroro/2017.2.8 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
・初優勝
【カラオケバトル公式】熊田このは:BENI「見えないスタート」/2017.8.23 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
・優勝(2回目)
↑ どちらのテイクも音程・リズムの正確さはもちろん、ほとんどブレスどりを感じず、歌に入り込んでいる。
-------------------------
2023/01/14 UP
以前のカラバトのU-18特集、何本か視返してみました。
やっぱり凄い面子だったことを実感。
カラオケで点数争っているのに、あふれ出るオリジナリティ。
原曲のよさを引き出す歌いまわし。
そして歌にこもるエモーション。
どれをとってもそれぞれに一級品だったと思う。
これは、個人的に勝手に選んだベスト7人です。
一度でいいから、この面子でコラボってほしかった。
できれば梶浦由記さんの楽曲・ブロデュースで・・・。
→ ■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
■ 佐久間彩加 - 君がいたから/Crystal Kay 2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。
荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。
それにこの情感の入り方って、いったい何事?
→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦
■ 三阪咲 - Rollercoaster (Acoustic Live Performance)
声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。
ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。
■ 原藤由衣 - 私はピアノ - 高田みづえ 2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ 溝ノ口劇場
美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。
いそうだけど、なかなかいない存在。
■ 富金原佑菜 - 流星群 2018/09/17 あべのAステージ
声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)
細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。
そして、わき上がってくるエモーション。
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
■ 熊田このは - アイノカタチ/feat.HIDE(GReeeeN) MISIA 2020/02/23 LIVE
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。
切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。
この子の声って絶対セラピー効果あると思う。
→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
■ 鈴木杏奈 - 炎/LiSA 【カラオケバトル公式】(森アナイチオシ動画)
このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。
そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?
■ 堀優衣 - LOVE SONG/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。
-------------------
■ 砂塵の彼方へ....
FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。
↑ ↑の7人ならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?
でも、いまの時代、ソロシンガーとしてブレークするのはすこぶるむずかしい。
「坂道シリーズ」の隆盛以降、この傾向はますます強まっていて、少なくとも数人のユニットでなければインパクトがよわくなっている。
あの実力者揃いのkalafinaだって、ソロで成功するのは容易でなかったワケだから・・・。
---------------------------------
往年の名シンガーの名曲のもとには、かならずといっていいほど名クリエイターがいた。
プロのクリエイターの紡ぐ優れたメロディやアレンジメントが、シンガーの個性とあいまってヒット曲や人気曲をつくりあげた。
□ 織田哲郎
■ ZARD(坂井泉水) - 揺れる想い
□ D・A・I(長尾大)
■ 浜崎あゆみ - Voyage
□ 柿原朱美
■ 今井美樹 - 空に近い週末
□ 五十嵐充
■ Every Little Thing(持田香織) - Over and Over
□ 上田知華
■ 今井美樹 - Boogie-Woogie Lonesome High-Heel
□ 小室哲哉
■ 華原朋美 - LOVE BRACE
□ GIORGIO
■ 西野カナ - 私たち
□ 川江美奈子
■ 中島美嘉 - 桜色舞うころ
いまでいうと、天野月さんとか傘村トータさんとか・・・。
■ 天野月「栞」 feat.YURiCa/花たん
■ 傘村トータ「おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.」Covered by Cereus
でも、やっぱり梶浦由記さんかな・・・。
オリジナリティを備えた名シンガーたちが名クリエイターのもとに集結すると、こういうことになる ↓
■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)
〔 Solo Parts 〕
0:27~ / 3:46~ 貝田由里子
0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)
2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)
3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)
↑ こういう名クリエイターのもとで、1曲でもいいからコラボかまして世間の耳目を集めてほしい。
個人的には、彼女たちが集えば、少なくともリトグリよりは上、FictionJunctionと肩を並べると思っている。
---------------------------------
2023/ 05/31 UP
いろいろな歌番組を視るにつけ、どうしても彼女たちの歌のレベルの高さを再認識してしまう。
歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。
-------------------------
2023/05/31 UP
カラバトの川嵜心蘭ちゃんのテイク(予選曲)、森アナイチオシ動画でUPされてました。
(森アナイチオシ動画、どれもナイスチョイスです。)
■ 【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)
やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。
歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?
現在高3。
佐久間 彩加ちゃんの一学年下だから、「カラバトU-18黄金の世代」に入る年代かも。
-------------------------
2023/01/23 UP
昨日放送のU-18歌うま甲子園 2023開幕戦、録画したやつ視てみました。
優勝は川嵜心蘭ちゃんだと思ったけどね、個人的には・・・。
(もちろん、優勝者さんも好テイクだったが)
川嵜心蘭ちゃんのテイク(別番組、一部)↓
2021年第9回の #歌唱王 をみて、この3名の方は今後注目したいと思います。#下尾礼子 さん#島津心美 さん#川嵜心蘭 さんいずれも未来の歌姫になりうる才能だと思いました。 pic.twitter.com/yHwuEDFs1h
— 天使の歌声を聞いた (@tenshinoutagoe_) December 23, 2021
→ プロフィール
この子は2021/12/23放送の「歌唱王」にも出ていて、そのときも →この記事で「声に深みがあって聴いてて心地よい。」とコメントつけてた。
やっぱり今回も印象は同様で、聴いてて心地よかった。
歌にスケール感があって、感情が入り込んでいた。
しかし、この上質なビブラートで決勝曲のG(拡張形)は気の毒。
どう聴いてもボックスB-1かB-2だと思う。
それと、中川寛大さんの歌いまわしはかなりエモかった。
これで94点台は気の毒すぎる。
でも、やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。
(順不同です)
■ 佐久間彩加ちゃん
■ 三阪咲ちゃん
■ 原藤由衣ちゃん
■ 富金原佑菜ちゃん
■ 熊田このはちゃん
■ 鈴木杏奈ちゃん
■ 堀優衣ちゃん
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「冬のうた」Kiroro/2017.2.8 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
・初優勝
【カラオケバトル公式】熊田このは:BENI「見えないスタート」/2017.8.23 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
・優勝(2回目)
↑ どちらのテイクも音程・リズムの正確さはもちろん、ほとんどブレスどりを感じず、歌に入り込んでいる。
-------------------------
2023/01/14 UP
以前のカラバトのU-18特集、何本か視返してみました。
やっぱり凄い面子だったことを実感。
カラオケで点数争っているのに、あふれ出るオリジナリティ。
原曲のよさを引き出す歌いまわし。
そして歌にこもるエモーション。
どれをとってもそれぞれに一級品だったと思う。
これは、個人的に勝手に選んだベスト7人です。
一度でいいから、この面子でコラボってほしかった。
できれば梶浦由記さんの楽曲・ブロデュースで・・・。
→ ■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
■ 佐久間彩加 - 君がいたから/Crystal Kay 2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。
荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。
それにこの情感の入り方って、いったい何事?
→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦
■ 三阪咲 - Rollercoaster (Acoustic Live Performance)
声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。
ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。
■ 原藤由衣 - 私はピアノ - 高田みづえ 2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ 溝ノ口劇場
美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。
いそうだけど、なかなかいない存在。
■ 富金原佑菜 - 流星群 2018/09/17 あべのAステージ
声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)
細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。
そして、わき上がってくるエモーション。
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
■ 熊田このは - アイノカタチ/feat.HIDE(GReeeeN) MISIA 2020/02/23 LIVE
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。
切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。
この子の声って絶対セラピー効果あると思う。
→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2
■ 鈴木杏奈 - 炎/LiSA 【カラオケバトル公式】(森アナイチオシ動画)
このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。
そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?
■ 堀優衣 - LOVE SONG/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。
-------------------
■ 砂塵の彼方へ....
FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。
↑ ↑の7人ならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 天賦の才! 歌姫・佐久間彩加ちゃん
間抜けにもISO設定ミスってたので、ほとんどいい写真が撮れておりません(泣)
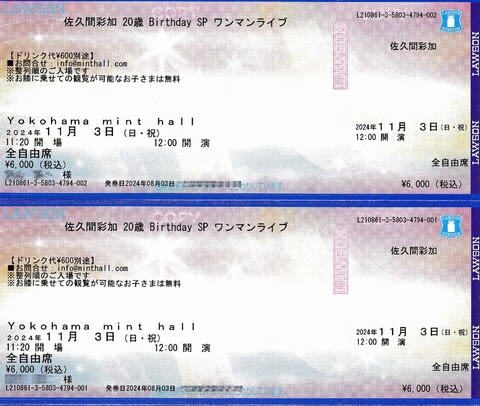




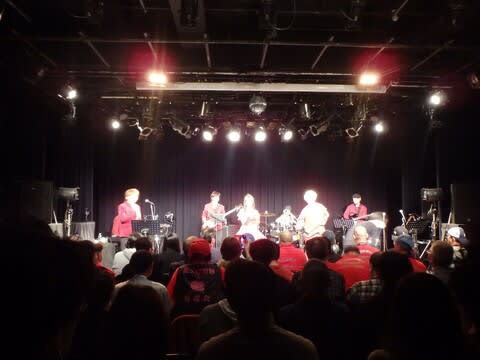





オープニングはなんと「Feel Like Makin' Love」(愛のため息)。
初出はRoberta Flack(1974年)、ヒットはMarlena Shaw(1975年)だけど、1983年のGeorge Bensonのアレンジに近かった ↓
■ Feel Like Making Love - George Benson
この曲、ヴォーカル、インストともに巧者が揃わないと成立しないけど、見事に構成されていた。
これは期待できそう・・・。
じっさい、インスト陣、PAともまったく文句なしの出来でした。
ゲストの辻本美博氏のsaxが見事だった。
正直知らなかったけど、いるところにはいるもんですね、逸材。
■ Isn't She Lovely (辻本美博 with Neighbors Complain)
鎌倉の名刹、浄土宗光明寺の僧侶さまがハーモニカで参画されていてびっくり。
彩加ちゃん、→ 光明寺でLIVEやってるんですね。
MCで、阿弥陀如来(仏様)を「神様」と呼んで、僧侶さまから突っ込まれてた(笑)
ほんとにこの子のMC、ほのぼのとしていいです。
ファンを本当に大事にしている感じがあって、彩ラーさんたちが狂うのもわかる気がする。
歌い始めると一転、DIVAモードばりばり。
以前よりもハイトーンが繊細で、表現の幅が広がっている感じがする。
音節の途中から、ターボかけたように声の圧強めていく振る舞いなど、並みの才能じゃない。
それと、圧倒的なリズム感。
やっぱりR&B志向なのか・・・。
いまの若手で、R&B系の歌いこなしの巧さは、彩加ちゃんと三阪 咲ちゃんがおそらく双璧だと思う。
今日は聴いててChaka Khanを思い起こした。
■ Chaka Khan - Do You Love What You Feel
■ Chaka Khan - Through The Fire, Live In Pori Jazz 2002 (10.)
20歳の日本の女子のパフォ聴いて、Chaka Khan思い起こすとはちょっと自分でも信じられない。
やはりそれだけ優れた才能をもっているのだと思う。
テクニックもさることながら、歌に魂がのっている。
歌にこれだけの感情の量を織り込める歌い手はそうそういない。↓
■ 佐久間 彩加「Jupiter」| The Voice Japan ブラインドオーディション
もっともっと、高みにのぼりつめて欲しい。
---------------------------------
2024/11/02 UP
明日です。
生バンドの彩加ちゃん、絶品なので楽しみ。
■ 駅(竹内まりや)
名テイク。
彩加ちゃんが歌う竹内まりやの曲は名テイク揃い。さすがに難曲キラー。
---------------------------------
2024-08-03 UP
🩷佐久間彩加 20歳 記念SPワンマンライブ🩷
2024/11/3 (日)
Yokohama mint hall(神奈川県横浜市)
[開 場] 11:20
[開 演] 12:00
全自由席 6,000円+ワンドリンク
※席数はおそらく150~200。
レア・チケットかも・・・。
2024/8/3販売開始
予約は→ こちらから
予約しました。
生バンドの彩加ちゃん、絶品なので楽しみ。
■ 配信ドラマ「見上げた空に、あなたを想う(#2 春)」主題歌 / 佐久間彩加
---------------------------------
2024/06/06 UP
■ 【カラオケバトル公式】唯一無二の中低音ボイス 佐久間彩加 歌唱まとめ
↑ これって、カラバトスタッフが編集してUPしたのか?
それだけ素晴らしい歌い手だということ。
---------------------------------
2023/05/31 UP
なぜかアクセスをいただいているので、動画を追加リンクしてみます。
■ カラオケ四天王の佐久間彩加ちゃん登場!! 極上の歌声をご堪能下さい!!
コミュニケーション能力が抜群だと思う。
-------------------------
2023/03/27 UP
ついにU-18卒業ですね。
やっぱり最後の最後まで戦っていた。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:いきものがかり「SAKURA」(森アナイチオシ動画)
天賦の才のうえに努力家だから、まだまだ伸びていくのだと思う。
応援しています。
ps.
森香澄アナもカラバト卒業とのこと。
「森アナイチオシ動画」もなくなってしまうのかな?
Ai判定機、しばしば好テイクに低得点かますから、これをフォローしてくれる「森アナイチオシ動画」はとても貴重だった。
-------------------------
2023-03-04 UP
↓「皆さまと一緒に戦ってきました」
本当に「戦う」という言葉がぴったりのパフォーマンスを繰り広げてくれた彩加ちゃん。
彼女のU-18卒業でひとつの時代が終わったような気がする。
いつかこのメンバーで、ふたたびバトルを繰り広げてほしい。
3月~4月にかけてワンマンライブが予定されています。
→ こちら
-------------------------
2022/12/26 UP
2022/12/25放送のカラバト、優勝おめでとう。
予選、伊沢さんの高得点で、Ai機種で自身の最高得点出さなければ決勝行けない背水の陣。
でも、ここできっちり結果出すとはやっぱり勝負師だと思う。
サビパートの頭と二小節でどうしても赤バーが出て、これはむずかしいか? とも思ったけど、その他のポイントで伸ばして100点近い点数。
※もう一度聴き直してみたら、音程の外しは「ハンマリング」(わざと音符の半音下から発音を始めて表現力を高めるテク、バーは頭の0.5秒ほど赤になる)かもしれぬ。
だからあれだけ赤バー出しても点数に響かなかったのかも。
(赤バー多発のサビ部で、むしろ音程正確率が上がっている。)
ex.
3:19~ の降メロ(瞬きするほど~)、完璧にバーを黄色トレースしているのに、
3:36~ の昇メロ(聴こえる?)でビブラート&しゃくり絡みの赤バー規則的に出してる。
少なくともこのパートは「ハンマリング」だと思う。
ただしAi機種の裏加点要素がよくわからないので、「ハンマリング」がどこまで効いたかは不明だし、この子のフックあふれる声色からするとそもそも「ハンマリング」なんぞ(Ai採点じゃなかったら)不要な気もするが・・・。
(こういう些末なテクに、彩加ちゃんのような貴重な才能を費やさせるのもAi機種の罪のひとつだと思う。)
この子ほどAi機種ととことん戦った歌い手はいないと思うほど、テクニカル面でツボ押さえてる。
とくにビブラートのかましは、ほとんど芸術的。(54秒42回のボックス形B-2)
今回は「勝つべくして勝った」と思う。
■ 今回(Ai機種)↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:スピッツ「楓」/2022.12.25 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
■ 以前の機種 ↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「未来予想図Ⅱ」DREAMS COME TRUE/2018.2.21 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
■ Ai機種に打ち勝った?例
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
歌い出しから前半は、”置きに行く” 唱いまわししていたと思う。
ところが、1:32~ 「強く 手を握りしめた」からモードを一気に変えて? Ai機種に打ち勝った?
(とくに「しめた」の全開ビブラート)
ただしこれでも99.870で、じっさいのところ今回これでは足りなかった。
以前のフックかましまくりのキレッキレな歌いまわしでは、Ai機種で100点近い高得点とれないこと重々わかった上で、あえて表現を抑えて丁寧に置きに行ってる?
だから、予選曲が「楓」になったんだと思う。
予選は本当に凄い表情をしてた。
そして織り込まれた感情の量がハンパじゃなかった。
それだけこの1曲に期するものが大きかったのでは。
荒牧さん、選曲ミスかも・・・
荒牧さんの実力、こんなもんじゃないでしょ。
この唱法だったら、倖田來未あたりの曲の方がはまっていたような感じがする。
■ 倖田來未 「あなただけが」を荒牧陽子のガイドボーカルで
荒牧さん、彩加ちゃん、オペラ魔女さんの決勝。ほんとうに見たかった。
ただし、自身の得意曲で・・・。
今回の決勝のシステムってなんなん?
歌い手と曲の相性って絶対にある。
それを決勝で有無を云わさず曲指定かけるとは・・・。
ほんとうにどうかしている。
彩加ちゃん、「恋人がサンタクロース」唱ったことないってコメントしてたけど、本当にそうなんだろうと思う。
(「恋人がサンタクロース」のコード、ユーミンがターゲット層拡大を狙って意図的に平易なコード進行を仕組んだ曲だと思う。)
こういう音域の狭いUP曲って、彩加ちゃんならではの歌いまわしに合っていないから。
UP曲やるなら、もっとオクターブの広い、あるいはコード進行の複雑な曲の方がたぶんこの子の魅力が出る。
なんといっても希代の難曲キラーだから・・・。
それでも優勝はさすがの実力。
これをバネにして、志望校いけるといいね。
**************
今回思ったのは、海蔵さん、宮本さん、オペラ魔女さんなどの往年のウィナーは、みな曲の魅力を引き出して唱っていること。
だから単調にならず聴いてて飽きない。(点数はともあれ)
それとAi機種のナゾがますます深まった。
松浦さんにせよ吉田さんにせよ、これまででベストでは?というエモーショナルな好テイクをみせていた。
でも、点数はさほど伸びていない。
本人たちも納得いかない部分があったかもしれぬ。
-----------------------------
2022/03/25 UP
3/21のセトリです。
〔前半〕


01.Crystal Kay - 恋におちたら
02.夢の途中 - 来生たかお
03.あなたに - 安全地帯
04.J.BOY - 浜田省吾
05.三日月 - 絢香
06.Wonderland - iri
07.ふたりごと - RADWIMPS


(休憩)
〔後半〕


01.炎 - LiSA
02.Sweet Impact - BoA
03.悲しみにさよなら - 安全地帯
04.接吻 -kiss- - ORIGINAL LOVE
05.Best Friend - 西野カナ
06.Hello, Again 〜昔からある場所〜 - My Little Lover
〔アンコール〕
01.木蘭の涙 - スターダストレビュー


曲のバラエティ感が凄かった。
そして高音にさらに華と艶が出ている。
それになにを歌っても「佐久間彩加オリジナル」感。
「あなたに」「J.BOY 」「ふたりごと」「接吻 -kiss-」「Best Friend」がよかった。
・「あなたに」は、ファンのリクエスト曲。彩加ちゃんに曲調が合っていると思う。
・「J.BOY 」は、お父上のリクエストとのこと。1986年ならではの16ビートバックビートのグルーヴ曲。
彩加ちゃんの世代がこんな曲歌ってくれるとは・・・。しかもしっかり彩加オリジナルになってる。
・「ふたりごと」は、難符割、難音階のむずかしい曲。でも、こういう難曲の方が彩加ちゃんの真価が発揮されると思う。
・「接吻 -kiss-」は、スイングビート、Just The Two Of Us進行のオトナ曲だけど、見事に歌いこなしていた。拍手。
・「Best Friend」は、この前のカラバトで鈴木杏奈ちゃんに贈ったトリビュート曲。こういうエモーショナルな曲歌ったら敵なしじゃわ。
あと、↑には挙げてないけど「Sweet Impact」の発声が凄かった。
ファルセットやヒーカップを散りばめて、さらにいろいろなテクにトライしている。
ほとんど天才の域と思うのに、こういう努力を重ねているところがいいですね。
やっぱり「佐久間LIVE」面白かった。そろそろやっぱり生LIVEで生の声聴きたい。
-----------------------------
2022/03/21 UP
本日でしたね。
後日アーカイブじっくり視てからセトリなど入れます。
-----------------------------
2022/03/17 UP
■ 季節の訪れ(オリジナル) - 佐久間彩加
情報遅くてすみません。↓
● 佐久間彩加 第五回配信ワンマンライブ
2022.3.21(祝) 14:30~16:30 ツイキャス
アーカイブ、4/4まであり
「今回も…泣ける曲、盛り上がる曲とご用意致します✨」とのことです。
詳細は → こちら
チケ買いましたわ。
当日外出予定なので、アーカイブで視てセトリ入れます。
-----------------------------
2022/03/15 UP
■ サーカスナイト / 佐久間 彩加cover.
一気に大人びて・・・。でもまだ高校生なんだよね。
■ Lovin' You · Minnie Riperton
↑ なんかこの曲浮かんできた。
彩加ちゃんだったら、どうこなすんかな?
----------------------
2022/01/17 UP
この記事、急にアクセス数が増えたので、もしや、と思ったらやっぱりこれ ↓ か・・・。
すみませぬ。いそがしくてカラパトの録画まだ視てないので・・・。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:浜田省吾「もうひとつの土曜日」/2022.01.16 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
「もうひとつの土曜日」。そう来たか・・・。
1980年代にしてはベタなバラードで、一般人が歌うと冗長になりがちな難曲。
音色と歌いまわしに変化をもたせて、ラストまで一気に聴かせてしまう”歌ぢから”はさすがに佐久間彩加ちゃん。
でもって、優勝か。
今度はボカロ的なアップテンポ曲聴いてみたい。
きっともの凄いこなし、みせてくれると思う。
たとえば、こんなやつ ↓
■ 空奏列車 歌ってみた /めありー
■ [2015GP 優勝 佐久間彩加 様] やさしさで溢れるように/juju~カラオケ大会 グランプリ大会 首都圏カラオケバトル2015 GP~
これっていくつのとき?? 11歳? 小5?
聴き手を惹き込んでしまう音色の魅力は、すでにこの頃から。
やっぱり黄金の世代だ!
■ 空と君のあいだに 佐久間彩加
歌う前の不敵な微笑み。歌ってるときの勝負師的な表情。
そして完璧な”佐久間オリジナル”。なみの歌い手じゃないわ・・・。
----------------------
2021/05/10 UP
さっき放映してたカラバト。
彩加ちゃんの選曲は「STARS」(中島美嘉)。
曲調があっていると思うし、実際申し分のないできだったと思う。
このパフォーマンスで予選落ちは、正直いってどうなのかな???
このカラバト判定機の能力じゃ、変化自在で深みのある彩加ちゃんの歌唱はたぶん正当に評価できない。
(宇都宮聖くんの歌唱の評価も、この判定機じゃムリだと思う。この子もの凄い逸材では?)
ハイトーンのこなしがますます巧くなってるし、ニュアンスの込め方が抜群。そして洗練感がでてきている。
個人的にはいつか本格的なR&B聴いてみたい。
たとえば、こんなやつ ↓
■ Anita Baker - "Giving You The Best That I Got" [Official Music Video]
■ Toni Braxton - Un-Break My Heart (Official HD Video)
日本では「R&B=シャウト」あるいは「R&B=ホイッスルボイス」(笑) みたく思われてるけど、
本当のR&B系の名手って、こういうミディアム曲で真価を発揮すると思うし、
これまでこういう曲を歌いこなせそうかな? と思った歌手は(個人的には)日本には一人もいない。
彩加ちゃん(と加藤礼愛ちゃん)がはじめてかも・・・。
----------------------
2020/04/12 UP
4/3(土)の第4回配信ワンマンライブのセトリです。


〔前半〕
01.う、ふ、ふ、ふ、 - EPO
02.BLONDE - 中森明菜
03.優里 - ドライフラワー
04.カムフラージュ - 竹内まりや
05.駅 - 竹内まりや
06.六本木心中 - アン・ルイス
07.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬


(休憩20分)


〔後半〕
01.MOON - レベッカ(REBECCA)
02.ボヘミアン - 葛城ユキ 〔リクエスト〕
03.Story - AI
04.瞳がほほえむから - 今井美樹
05.春風 - Rihwa
06.Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 - YEN TOWN BAND
07.たしかなこと - 小田和正
〔アンコール〕
01.星のかけらを探しに行こう - 福耳
02.FINAL DISTANCE - 宇多田ヒカル


声の圧が増して、しかも安定感が凄い。
なにを歌っても「佐久間彩加オリジナル」感。
「ドライフラワー」「駅」「Story」「Swallowtail Butterfly」「FINAL DISTANCE」がよかった。
とくに「ドライフラワー」と「駅」。
エモーショナルな難曲で、彩加ちゃんの天才ぶりが際立つ感じがする。
それにしてもスタジオライブ状況で、これだけの感情移入できる力量って、やっぱりただものじゃないと思う。
駅【佐久間彩加】
----------------------
2020/04/06 UP
4/3(土)の第4回配信ワンマンライブ、なんとまたしても見逃しました(笑)
さきほどチケット買ったので、アーカイブ(4/17まで)視て後日セトリをUPします。
チケ購入は→こちら。
----------------------
2021/03/09 UP




このところやたらに忙しかったので、さきほどようやくセトリとりました。
↑ スクショも時間がなかったのでいまいちかも。すみませぬ。
〔前半〕
01.SAKURA - いきものがかり
02.本当の恋 - May J.
03.元気を出して - 竹内まりや
04.Hero - さなり
05.ORION - 中島美嘉
06.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
07.あゝ無情 - アン・ルイス
08.unlasting - LISA
〔後半〕
01.誰より好きなのに - 古内東子
02.イエスタデイ - Official髭男dism
03.366日 - HY
04.あなた - 宇多田ヒカル
05.あなたに会えてよかった - 小泉 今日子
06.トイレの神様 - 植村花菜
〔アンコール〕
僕が死のうと思ったのは - 中島美嘉
「unlasting」「誰より好きなのに」「イエスタデイ」「あなた」「僕が死のうと思ったのは」がよかった。
とくに「あなた」と「僕が死のうと思ったのは」。
どれも難曲だけど、こういう曲で彩加ちゃんの真価が発揮される気がする。
「僕が死のうと思ったのは」は、歌詞はシリアスだけど曲調はアップビートのグルーヴ曲でバックのキーボードがよく効いている。
こういうシンプルでお洒落な曲調、歌い崩せるしすごく向いていると思う。
「僕が死のうと思ったのは」聴いてて、やにわに佐野元春のバラッドを想い起こした。
自分でもどうしてかわからないけど・・・。
Heart Beat/小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド - 佐野元春(LIVE 1983)
----------------------
2021/02/28 UP
2/23(火) 14:30~の「第3回 佐久間彩加 配信ワンマンライブ」、うかつにも見逃しました。
先ほどチケ購入したので、後ほど視聴してセトリ上げます。
3/9(火)まで視聴できます。
見逃した方は→こちらから。
**************
2/21放映のカラオケバトルの「超絶ハーモニー連発・最強デュエット王決定戦!」、彩加ちゃんが名演してたので、Blog内マルチポストですが載っけてみます ↓
〔 予選 〕
■ life AAA - 佐久間彩加 / 鈴木杏奈
このふたり、初コラボ?? 超面白かった。
アニソン歌手?らしく、杏奈ちゃんがかなりヒーカップかましてる。
ビブラート、19秒、61回のD型(上昇型)。
このふたりはまずほとんどボックスB-2型で、D型はみたことがない。
ビブラートが干渉したのかも・・・。でも不安定感はまったくなし。
〔 決勝 〕
■ ハッピーエンド - 佐久間彩加 / 鈴木杏奈
0:47~ 最後は嘘になって (杏奈ちゃんの中低音)
2:08~ もう離さないで (彩加ちゃんのハイトーン)
杏奈ちゃんがハイトーン、彩加ちゃんが中低音ってパート振られてたけど、↑ 聴くとそんなこと全然ないと思う。
ハモリ部、ふたりの声がはっきり聴き分けできるのに、絶妙にハモってる。
実力に裏付けられたオリジナルな個性が際立っているので、共演してもブレることがない。
それぞれの個性がぶつかって、新しいなにかを生み出しそうな予感ばりばり。
またまたいまごろ言っても詮ないことだけど、一度でいいから「U-18プロジェクト」もやってほしかった。
堀優衣ちゃん、鈴木杏奈ちゃん、佐久間彩加ちゃん、熊田このはちゃん、原藤由衣ちゃんあたりで・・・。
----------------------
2020/12/31 UP
佐久間彩加ちゃん配信ライブ
『大晦日~ツイキャスプレミア配信ワンマン』のセトリです。
〔前半〕
01.雪の華 - 中島美嘉
02.ゲレンデがとけるほど恋したい - 広瀬香美
03.雪のクリスマス - DREAMS COME TRUE
04.あの頃へ - 安全地帯
05.なごり雪 - イルカ
06.炎(ほむら) - LISA
07.あなた - 宇多田ヒカル
08.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
「炎(ほむら)」 と「あなた」がよかった。
「あなた」みたいな難曲をこなしていくのが、彩加ちゃんLIVEの醍醐味だと思う。
「炎(ほむら)」はやっぱり名曲。これから多くの歌姫を育てていく歌では。
〔後半〕
01.夜空のムコウ - SMAP
02.NAO - HY
03.Aitai - 加藤ミリヤ
04.ドライフラワー - 優里
05.プラスティック・ラブ - 竹内まりや
06.Everything - MISIA
07.流星群 - 鬼束ちひろ
08.遠く遠く - 槇原敬之
〔アンコール〕
木蘭の涙 - スターダスト レビュー
後半、エモーショナルな曲が多くて聴き応えがあった。
一見、あっけらかんとして見えるけど、繊細な感受性と強いきもちを持っているのだと思う。
だから、こんなにこころに響く歌が歌えるのでは。
それと「プラスティック・ラブ」にはびっくり。
もともと広い曲幅が、さらに広がっているような。
来年は、カラバトU-18の面々のますますのご活躍をお祈りします。
----------------------
2020/12/29・2019/12/16 UP
チケットゲット!
まだ販売中なので、ぜひ。
佐久間彩加ちゃん配信ライブ
『大晦日~ツイキャスプレミア配信ワンマン』
2020.12.31(木) 14:30~16:30(アーカイブ2021.1.14まで)
チケット販売中です。(2,500円+手数料)
詳細は→こちら。
難曲ほど燃える感ばりばり。セトリが楽しみ。
ちなみに、10/25の配信ライブのセトリは ↓ (数曲抜けあるかも・・・)
・手をつなごう - 絢香
・奏(かなで) - スキマスイッチ
・流星群 - 鬼束ちひろ
・夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
・あゝ無情 - アン・ルイス
・初恋 - 村下孝蔵
・香水 - 瑛人
・U&I(ユーアンドアイ) - Ailee(エイリー)
・白い恋人達 - 桑田佳祐
・If 〜I know〜 - EXILE
・ピエロ - 上木彩矢
・God knows - 涼宮ハルヒ
・季節の訪れ - 佐久間彩加(オリジナル)
・かくれんぼしてる君に - 佐久間彩加(オリジナル)
・トイレの神様 - 植村花菜
*************
(blog内マルチポストですが、入れときます。)
先ほど放送してた12/13放送のカラバト、やっぱりまたしてもU-18の強さを物語る内容だった。
→ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
優勝した佐久間彩加ちゃん、凄かった。
予選の「奇跡を望むなら...」は、2020.11.1 OAの「風が吹いている」と似たような歌いまわしだったと思う。
精密機械のように冷静に、淡々と置きに行く歌い方。
これで99.664で決勝に・・・。
決勝の「君がいたから」。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
歌い出しから前半は、「風が吹いている」や「奇跡を望むなら...」と同じ歌いまわししていたと思う。
ところが、1:32~ 「強く 手を握りしめた」からモードが一気に変わったような感じがする。
(とくに「しめた」の全開ビブラート)
いつもの「佐久間モード」に入ったら、もう「置きに行く」歌い方には戻れないと思うし、実際戻っていない。
さすがに我慢できなくなったのかな(笑)。
後半~ラストはほとんど「佐久間モード」全開でDIVA状態に・・・。
結果は99.870で優勝。
しかし、決勝でこんな超難しい曲選んで、しかも途中で歌い方変えて(?)優勝とは、やっぱりこの子ただものじゃない。
----------------------
2019/11/02 UP
昨日放送のカラバト、やっぱりU-18世代レベル高いと思った。
下尾礼子ちゃん、いいパフォーマンスだったけど残念。
佐久間彩加ちゃん、優勝おめでとう!
予選:ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~
決勝:風が吹いている
決勝は、Ai判定機最高得点の99.8点台ゲット。
これです ↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:いきものがかり「風が吹いている」 /2020.11.1 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
こんなに慎重に歌ってる彩加ちゃん、はじめてみた。
バーの上に歌声を置きに行ってる感じか。
おそらく、意識的に声色の幅と声の広がりを絞ってると思う。
それと、予選曲のビブラート回数18回にもびっくり。ここまでビブラートを抑えたテイクも聴いたことがない。
でも、Ai判定機で勝つためには、これしかなかったのだと思う。
↓ も声色が暴れにくい曲だけど、これだけ多彩な声色とビブラートを繰り出してるのが、↑と聴き比べてみるとよくわかる。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「未来予想図Ⅱ」DREAMS COME TRUE/2018.2.21 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
勝ちに行くために、あえてこういうテクニカルな戦略とれる才能って、やっぱりただごとじゃないと思う。
(でも、個人的にはLIVEの歌い方のほうが好きだけど・・・(笑))
----------------------
2019/10/26 UP
15:00~ LIVEで聴く予定だったけど、急な用事が入って聴けず、さきほどアーカイブでざっくり聴いてみました。
配信LIVEはこれができるからいいですね。
配信LIVEは観客のリアクションがないので、けっこうやりにくいと思う。
でも面白い内容だった。
個人的にとくに面白かった曲は、
■ 手をつなごう/絢香 20:55~
この曲で表情と左手のうごきが変わった感じがある。
彩加ちゃん、調整気味のときは、ちょっと迷ったふうの表情になるし、乗ってきたときはキレのある勝負師的な眼になる感じがする。
それと、左手の動きがしなやかになってきたときは、声も乗ってる感じがする。
この曲では、勝負師的な眼としなやかな左手の動きがあった(と思う)。
声のつくり方が絢香より多彩なので、オリジナルよりも変化に富んだ仕上がりになっていたと思う。
■ 流星群/鬼束ちひろ 32:30~
富金原佑菜ちゃんの「流星群」凄いけど、彩加ちゃんの流星群も凄い。
こういうメロディーの輪郭がはっきりした曲、ほんとに巧い!
鬼束ちひろって、カラバトU-18世代(黄金の世代?)育てた一人だと思う。
■ 香水/瑛人 1:15:16~
テクがないとふつうにお経になる曲調。
これだけ変化のある曲に仕上げられるとは、やっぱり「声色の魔術師」だと思う。
それにしてもこの曲って、YouTubeの再生回数1億回超えなんだ。ふ~ん・・・。
■ 白い恋人達/桑田佳祐 1:23:36~
音幅の広い曲。もの凄く複雑な発声でこなしていて面白かった。
それと、サビ部分の高音の伸び。
ヒーカップでもファルセットでもなく、ひっくり返すようにたおやかなハイトーンが出てくるこの発声ってなに?
■ かくれんぼしてる君に/佐久間彩加(オリジナル) 1:43:25~
この曲むずかしいわ・・・。
でも、このくらいの曲の方が、彩加ちゃんの才能が活きるような気もする。
いくつもの声色を紡ぎあわせていくような歌いまわし。
並みの才能でできるワザじゃないと思う。
それと、アップテンポ系では、ピエロ/上木彩矢、アンコールのトイレの神様もしみじみとよかった。
ときおり聴けた、スキャットやフェイクが凄く気になったので、もっとばりばりかましてくれるとさらに面白くなるかも(笑)
まだざっくりとしか聴いていないので、気になるところがあったら追記します。
----------------------
2019/10/16 UP
佐久間彩加ちゃんの配信ライブ(初めてのツイキャスプレミア配信)情報です。
『佐久間 彩加 16th 〜Anniversary Live〜』
2020.10.25(日) 15:00~17:00
11/8までアーカイブ視聴可能 fee:2,500円
詳細は →こちら
もちろん購入しましたよ。この子のLIVEすごく面白いもん。
驚愕のテイク ↓
■ やさしさで溢れるように【佐久間彩加】
完璧なオリジナル化。すでにDIVAの貫禄!
■ 空と君のあいだに 佐久間彩加
ほんとにこの曲めちゃくちゃ合ってるわ。
もはや点数気にしてない感あり。音楽の面白さを実感させてくれるパフォーマンス。
はじめて作詞したオリジナル曲。↓
■ 『かくれんぼしてる君に / 佐久間彩加』music video
----------------------
2020/06/22 UP
「CDTVライブ!ライブ! 4時間生放送で完全復活! 」、さっきまで視てたけどちょっと抜け出してきました(笑)
こういうLIVEってどんどんやってほしいんだけど、スタジオライブは誤魔化しがきかず、いろいろ見えて(聴けて)しまうからな~。
ある意味こわい。
佐久間彩加ちゃんが名唱を残している曲が何曲か歌われていたので、聴き比べしてみました。
たとえば ↓こんな曲。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:YEN TOWN BAND「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」/2018.9.12 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
やっぱり凄い、このオリジナル感。
歌にぐいぐい引き込まれてく。
音楽の楽しさすばらしさをストレートに伝えてくれる希有の才能。
こういうすばらしい才能が、もっともっと広く聴かれていくような ”場” がほしい。
この子のLIVE、まじで凄かったから・・・ ↓
----------------------
2019/12/21 UP
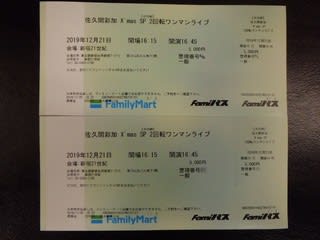



カラバトの上位陣はだいたい生(LIVE)で聴いているのですが、佐久間彩加ちゃんは未聴。
ようやく本日聴いてきました。
■2019.12.21 新宿21世紀 生バンド 佐久間彩加 2回転ワンマンライブ
昼と夜の2回転で、夜の部に行きました。
昼夜で計30曲以上も歌うという耐久LIVE。
しかし、夜の部のラストでも全然声の勢いが落ちていない。
でもってアンコールは2曲!
どんだけ強い声帯持ってるんだ(笑)
すでにプロアーティスト的なオーラをまとっていて、ほんとに彼女中学生??
ふつう中学生クラスだとどうしてもバックに飲まれがちになるけど、この子はバックを従えている感ばりばり(笑)
多彩な声色持っているので曲幅が広く、エンタメ的にも面白いステージでした。
カラバトでも中低音の声の深みやフックのあるビブラートは堪能できたけど、LIVEとなるとやっぱり違う。
とくに高音。
LIVEの出だしは「やっぱりハイトーンのメインはファルセットか?」と思ったけど、中盤から飛ばしてきて、フラジオレットやヒーカップ含むいろいろなパターンのハイトーンを縦横無尽に繰り出してた。
とくにあでやかに開いていく感じのハイトーンがあって、これは絶品。
(裏声系ではない。ミックスボイスかとも思うが、それらしくない質感もあってよくわからず・・・。)
来年1月にリリース予定のCD収録のオリジナル曲2曲をアンコールで演ったけど、ハイトーン寄りの曲調。
やっぱり高音にも相当自信があるのだと思う。
それと、彩加ちゃんのビブラートって、たぶん1/fゆらぎ入っていると思う。
個人的なベストは、Jupiter(平原綾香)。
リズムの立ったJupiterで、これは生バンドならでは。
色気と深みのある低音から、↑で書いた「あでやかに開いていく感じのハイトーン」までの引き上げは信じられない展開。
まさに声色の魔術師!
前にも書いたけど、こんなの意識して出せるとは思えないから、たぶん天性のものだと思う。だから天才。
--------------------
熊田このはちゃんフリークとしては、どうしてもこのはちゃんと比較してしまう(笑)
両者の個性はかなり対照的で、このはちゃんが持っていないものを彩加ちゃんが持ち、彩加ちゃんが持っていないものをこのはちゃんが持っていると思う。
具体的にいろいろ思い当たったけど、これは安易には書き散らせないので、確信をもてたら後日書いてみます。
それにしても、カラバトU-18世代の実力おそるべし!
やっぱり彼女たち黄金の世代では? → 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
次回のワンマンLIVEは↓ チケット発売中とのことです。(オリジナルCDもその時発売)
⚪2020.1.19 新宿ARISE舞の館 2回転和装ワンマンライブ → 情報
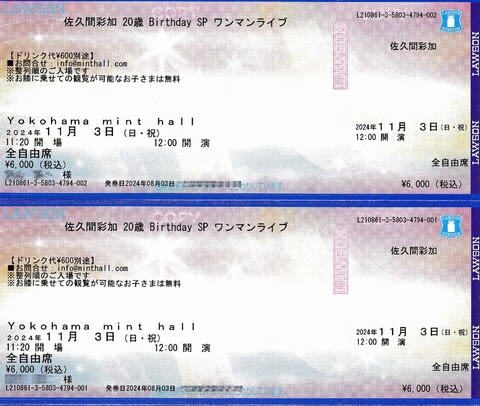




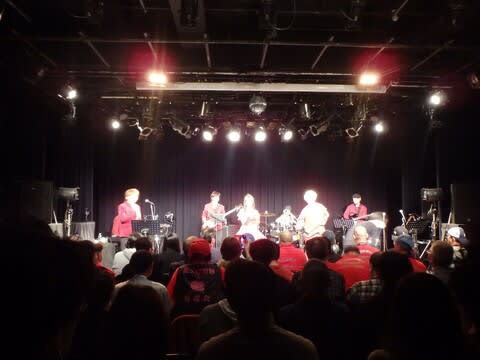





オープニングはなんと「Feel Like Makin' Love」(愛のため息)。
初出はRoberta Flack(1974年)、ヒットはMarlena Shaw(1975年)だけど、1983年のGeorge Bensonのアレンジに近かった ↓
■ Feel Like Making Love - George Benson
この曲、ヴォーカル、インストともに巧者が揃わないと成立しないけど、見事に構成されていた。
これは期待できそう・・・。
じっさい、インスト陣、PAともまったく文句なしの出来でした。
ゲストの辻本美博氏のsaxが見事だった。
正直知らなかったけど、いるところにはいるもんですね、逸材。
■ Isn't She Lovely (辻本美博 with Neighbors Complain)
鎌倉の名刹、浄土宗光明寺の僧侶さまがハーモニカで参画されていてびっくり。
彩加ちゃん、→ 光明寺でLIVEやってるんですね。
MCで、阿弥陀如来(仏様)を「神様」と呼んで、僧侶さまから突っ込まれてた(笑)
ほんとにこの子のMC、ほのぼのとしていいです。
ファンを本当に大事にしている感じがあって、彩ラーさんたちが狂うのもわかる気がする。
歌い始めると一転、DIVAモードばりばり。
以前よりもハイトーンが繊細で、表現の幅が広がっている感じがする。
音節の途中から、ターボかけたように声の圧強めていく振る舞いなど、並みの才能じゃない。
それと、圧倒的なリズム感。
やっぱりR&B志向なのか・・・。
いまの若手で、R&B系の歌いこなしの巧さは、彩加ちゃんと三阪 咲ちゃんがおそらく双璧だと思う。
今日は聴いててChaka Khanを思い起こした。
■ Chaka Khan - Do You Love What You Feel
■ Chaka Khan - Through The Fire, Live In Pori Jazz 2002 (10.)
20歳の日本の女子のパフォ聴いて、Chaka Khan思い起こすとはちょっと自分でも信じられない。
やはりそれだけ優れた才能をもっているのだと思う。
テクニックもさることながら、歌に魂がのっている。
歌にこれだけの感情の量を織り込める歌い手はそうそういない。↓
■ 佐久間 彩加「Jupiter」| The Voice Japan ブラインドオーディション
もっともっと、高みにのぼりつめて欲しい。
---------------------------------
2024/11/02 UP
明日です。
生バンドの彩加ちゃん、絶品なので楽しみ。
〖明日は横浜でお待ちしてます🩷〗皆さま、天候により交通機関が大変とのニュースですが明日は晴れます🌞☂️マークから変わりました。。皆さまの熱い想いに感謝の気持ちで今回のみ特別に⏬◎前半3曲目の新オリジナル曲 『JET BLACK』 動画撮影🆗とします💡※TikTokのみ20秒ならアップ🆗🩷… pic.twitter.com/aEnsiLsIyD
— 佐久間彩加 (@sumieeeeeeeeeee) November 2, 2024
■ 駅(竹内まりや)
名テイク。
彩加ちゃんが歌う竹内まりやの曲は名テイク揃い。さすがに難曲キラー。
---------------------------------
2024-08-03 UP
🩷佐久間彩加 20歳 記念SPワンマンライブ🩷
🩷20歳 記念SPワンマンライブ🩷◇…2024.11.3(日) 横浜ミントホール…◇8/3(土) 12:00~チケット販売開始皆さまのお越しをお待ちしてますスペシャルゲストにサックス演奏者の辻本美博さんをお迎えして最高の時間をプレゼントします😆生演奏で盛り上がりましょう✨#佐久間彩加ワンマンライブ pic.twitter.com/16kCb8dxPw
— 佐久間彩加 (@sumieeeeeeeeeee) August 1, 2024
2024/11/3 (日)
Yokohama mint hall(神奈川県横浜市)
[開 場] 11:20
[開 演] 12:00
全自由席 6,000円+ワンドリンク
※席数はおそらく150~200。
レア・チケットかも・・・。
2024/8/3販売開始
予約は→ こちらから
予約しました。
生バンドの彩加ちゃん、絶品なので楽しみ。
■ 配信ドラマ「見上げた空に、あなたを想う(#2 春)」主題歌 / 佐久間彩加
---------------------------------
2024/06/06 UP
■ 【カラオケバトル公式】唯一無二の中低音ボイス 佐久間彩加 歌唱まとめ
↑ これって、カラバトスタッフが編集してUPしたのか?
それだけ素晴らしい歌い手だということ。
---------------------------------
2023/05/31 UP
なぜかアクセスをいただいているので、動画を追加リンクしてみます。
■ カラオケ四天王の佐久間彩加ちゃん登場!! 極上の歌声をご堪能下さい!!
コミュニケーション能力が抜群だと思う。
-------------------------
2023/03/27 UP
ついにU-18卒業ですね。
やっぱり最後の最後まで戦っていた。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:いきものがかり「SAKURA」(森アナイチオシ動画)
天賦の才のうえに努力家だから、まだまだ伸びていくのだと思う。
応援しています。
ps.
森香澄アナもカラバト卒業とのこと。
「森アナイチオシ動画」もなくなってしまうのかな?
Ai判定機、しばしば好テイクに低得点かますから、これをフォローしてくれる「森アナイチオシ動画」はとても貴重だった。
-------------------------
2023-03-04 UP
↓「皆さまと一緒に戦ってきました」
本当に「戦う」という言葉がぴったりのパフォーマンスを繰り広げてくれた彩加ちゃん。
彼女のU-18卒業でひとつの時代が終わったような気がする。
いつかこのメンバーで、ふたたびバトルを繰り広げてほしい。
〖U-18四天王ラスト出演✨〗皆さまと一緒に戦ってきました7年の時間…パワーMAXでラスト飾らせて頂きます🧡○2023.3.26(日)18:30~ テレビ東京系列『THEカラオケ★バトル』…四天王VS最強挑戦者…皆さま最強の👊で応援してね涙出そう…頑張る❣️ https://t.co/qWKh8i391y#カラオケバトル pic.twitter.com/Jg5Yw2W37q
— 佐久間彩加 (@sumieeeeeeeeeee) March 1, 2023
3月~4月にかけてワンマンライブが予定されています。
→ こちら
-------------------------
2022/12/26 UP
2022/12/25放送のカラバト、優勝おめでとう。
予選、伊沢さんの高得点で、Ai機種で自身の最高得点出さなければ決勝行けない背水の陣。
でも、ここできっちり結果出すとはやっぱり勝負師だと思う。
サビパートの頭と二小節でどうしても赤バーが出て、これはむずかしいか? とも思ったけど、その他のポイントで伸ばして100点近い点数。
※もう一度聴き直してみたら、音程の外しは「ハンマリング」(わざと音符の半音下から発音を始めて表現力を高めるテク、バーは頭の0.5秒ほど赤になる)かもしれぬ。
だからあれだけ赤バー出しても点数に響かなかったのかも。
(赤バー多発のサビ部で、むしろ音程正確率が上がっている。)
ex.
3:19~ の降メロ(瞬きするほど~)、完璧にバーを黄色トレースしているのに、
3:36~ の昇メロ(聴こえる?)でビブラート&しゃくり絡みの赤バー規則的に出してる。
少なくともこのパートは「ハンマリング」だと思う。
ただしAi機種の裏加点要素がよくわからないので、「ハンマリング」がどこまで効いたかは不明だし、この子のフックあふれる声色からするとそもそも「ハンマリング」なんぞ(Ai採点じゃなかったら)不要な気もするが・・・。
(こういう些末なテクに、彩加ちゃんのような貴重な才能を費やさせるのもAi機種の罪のひとつだと思う。)
この子ほどAi機種ととことん戦った歌い手はいないと思うほど、テクニカル面でツボ押さえてる。
とくにビブラートのかましは、ほとんど芸術的。(54秒42回のボックス形B-2)
今回は「勝つべくして勝った」と思う。
■ 今回(Ai機種)↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:スピッツ「楓」/2022.12.25 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
■ 以前の機種 ↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「未来予想図Ⅱ」DREAMS COME TRUE/2018.2.21 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
■ Ai機種に打ち勝った?例
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
歌い出しから前半は、”置きに行く” 唱いまわししていたと思う。
ところが、1:32~ 「強く 手を握りしめた」からモードを一気に変えて? Ai機種に打ち勝った?
(とくに「しめた」の全開ビブラート)
ただしこれでも99.870で、じっさいのところ今回これでは足りなかった。
以前のフックかましまくりのキレッキレな歌いまわしでは、Ai機種で100点近い高得点とれないこと重々わかった上で、あえて表現を抑えて丁寧に置きに行ってる?
だから、予選曲が「楓」になったんだと思う。
予選は本当に凄い表情をしてた。
そして織り込まれた感情の量がハンパじゃなかった。
それだけこの1曲に期するものが大きかったのでは。
荒牧さん、選曲ミスかも・・・
荒牧さんの実力、こんなもんじゃないでしょ。
この唱法だったら、倖田來未あたりの曲の方がはまっていたような感じがする。
■ 倖田來未 「あなただけが」を荒牧陽子のガイドボーカルで
荒牧さん、彩加ちゃん、オペラ魔女さんの決勝。ほんとうに見たかった。
ただし、自身の得意曲で・・・。
今回の決勝のシステムってなんなん?
歌い手と曲の相性って絶対にある。
それを決勝で有無を云わさず曲指定かけるとは・・・。
ほんとうにどうかしている。
彩加ちゃん、「恋人がサンタクロース」唱ったことないってコメントしてたけど、本当にそうなんだろうと思う。
(「恋人がサンタクロース」のコード、ユーミンがターゲット層拡大を狙って意図的に平易なコード進行を仕組んだ曲だと思う。)
こういう音域の狭いUP曲って、彩加ちゃんならではの歌いまわしに合っていないから。
UP曲やるなら、もっとオクターブの広い、あるいはコード進行の複雑な曲の方がたぶんこの子の魅力が出る。
なんといっても希代の難曲キラーだから・・・。
それでも優勝はさすがの実力。
これをバネにして、志望校いけるといいね。
**************
今回思ったのは、海蔵さん、宮本さん、オペラ魔女さんなどの往年のウィナーは、みな曲の魅力を引き出して唱っていること。
だから単調にならず聴いてて飽きない。(点数はともあれ)
それとAi機種のナゾがますます深まった。
松浦さんにせよ吉田さんにせよ、これまででベストでは?というエモーショナルな好テイクをみせていた。
でも、点数はさほど伸びていない。
本人たちも納得いかない部分があったかもしれぬ。
-----------------------------
2022/03/25 UP
3/21のセトリです。
〔前半〕


01.Crystal Kay - 恋におちたら
02.夢の途中 - 来生たかお
03.あなたに - 安全地帯
04.J.BOY - 浜田省吾
05.三日月 - 絢香
06.Wonderland - iri
07.ふたりごと - RADWIMPS


(休憩)
〔後半〕


01.炎 - LiSA
02.Sweet Impact - BoA
03.悲しみにさよなら - 安全地帯
04.接吻 -kiss- - ORIGINAL LOVE
05.Best Friend - 西野カナ
06.Hello, Again 〜昔からある場所〜 - My Little Lover
〔アンコール〕
01.木蘭の涙 - スターダストレビュー


曲のバラエティ感が凄かった。
そして高音にさらに華と艶が出ている。
それになにを歌っても「佐久間彩加オリジナル」感。
「あなたに」「J.BOY 」「ふたりごと」「接吻 -kiss-」「Best Friend」がよかった。
・「あなたに」は、ファンのリクエスト曲。彩加ちゃんに曲調が合っていると思う。
・「J.BOY 」は、お父上のリクエストとのこと。1986年ならではの16ビートバックビートのグルーヴ曲。
彩加ちゃんの世代がこんな曲歌ってくれるとは・・・。しかもしっかり彩加オリジナルになってる。
・「ふたりごと」は、難符割、難音階のむずかしい曲。でも、こういう難曲の方が彩加ちゃんの真価が発揮されると思う。
・「接吻 -kiss-」は、スイングビート、Just The Two Of Us進行のオトナ曲だけど、見事に歌いこなしていた。拍手。
・「Best Friend」は、この前のカラバトで鈴木杏奈ちゃんに贈ったトリビュート曲。こういうエモーショナルな曲歌ったら敵なしじゃわ。
あと、↑には挙げてないけど「Sweet Impact」の発声が凄かった。
ファルセットやヒーカップを散りばめて、さらにいろいろなテクにトライしている。
ほとんど天才の域と思うのに、こういう努力を重ねているところがいいですね。
やっぱり「佐久間LIVE」面白かった。そろそろやっぱり生LIVEで生の声聴きたい。
-----------------------------
2022/03/21 UP
本日でしたね。
後日アーカイブじっくり視てからセトリなど入れます。
-----------------------------
2022/03/17 UP
■ 季節の訪れ(オリジナル) - 佐久間彩加
情報遅くてすみません。↓
● 佐久間彩加 第五回配信ワンマンライブ
2022.3.21(祝) 14:30~16:30 ツイキャス
アーカイブ、4/4まであり
「今回も…泣ける曲、盛り上がる曲とご用意致します✨」とのことです。
詳細は → こちら
チケ買いましたわ。
当日外出予定なので、アーカイブで視てセトリ入れます。
-----------------------------
2022/03/15 UP
■ サーカスナイト / 佐久間 彩加cover.
一気に大人びて・・・。でもまだ高校生なんだよね。
■ Lovin' You · Minnie Riperton
↑ なんかこの曲浮かんできた。
彩加ちゃんだったら、どうこなすんかな?
----------------------
2022/01/17 UP
この記事、急にアクセス数が増えたので、もしや、と思ったらやっぱりこれ ↓ か・・・。
すみませぬ。いそがしくてカラパトの録画まだ視てないので・・・。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:浜田省吾「もうひとつの土曜日」/2022.01.16 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
「もうひとつの土曜日」。そう来たか・・・。
1980年代にしてはベタなバラードで、一般人が歌うと冗長になりがちな難曲。
音色と歌いまわしに変化をもたせて、ラストまで一気に聴かせてしまう”歌ぢから”はさすがに佐久間彩加ちゃん。
でもって、優勝か。
今度はボカロ的なアップテンポ曲聴いてみたい。
きっともの凄いこなし、みせてくれると思う。
たとえば、こんなやつ ↓
■ 空奏列車 歌ってみた /めありー
■ [2015GP 優勝 佐久間彩加 様] やさしさで溢れるように/juju~カラオケ大会 グランプリ大会 首都圏カラオケバトル2015 GP~
これっていくつのとき?? 11歳? 小5?
聴き手を惹き込んでしまう音色の魅力は、すでにこの頃から。
やっぱり黄金の世代だ!
■ 空と君のあいだに 佐久間彩加
歌う前の不敵な微笑み。歌ってるときの勝負師的な表情。
そして完璧な”佐久間オリジナル”。なみの歌い手じゃないわ・・・。
----------------------
2021/05/10 UP
さっき放映してたカラバト。
彩加ちゃんの選曲は「STARS」(中島美嘉)。
曲調があっていると思うし、実際申し分のないできだったと思う。
このパフォーマンスで予選落ちは、正直いってどうなのかな???
このカラバト判定機の能力じゃ、変化自在で深みのある彩加ちゃんの歌唱はたぶん正当に評価できない。
(宇都宮聖くんの歌唱の評価も、この判定機じゃムリだと思う。この子もの凄い逸材では?)
ハイトーンのこなしがますます巧くなってるし、ニュアンスの込め方が抜群。そして洗練感がでてきている。
個人的にはいつか本格的なR&B聴いてみたい。
たとえば、こんなやつ ↓
■ Anita Baker - "Giving You The Best That I Got" [Official Music Video]
■ Toni Braxton - Un-Break My Heart (Official HD Video)
日本では「R&B=シャウト」あるいは「R&B=ホイッスルボイス」(笑) みたく思われてるけど、
本当のR&B系の名手って、こういうミディアム曲で真価を発揮すると思うし、
これまでこういう曲を歌いこなせそうかな? と思った歌手は(個人的には)日本には一人もいない。
彩加ちゃん(と加藤礼愛ちゃん)がはじめてかも・・・。
----------------------
2020/04/12 UP
4/3(土)の第4回配信ワンマンライブのセトリです。


〔前半〕
01.う、ふ、ふ、ふ、 - EPO
02.BLONDE - 中森明菜
03.優里 - ドライフラワー
04.カムフラージュ - 竹内まりや
05.駅 - 竹内まりや
06.六本木心中 - アン・ルイス
07.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬


(休憩20分)


〔後半〕
01.MOON - レベッカ(REBECCA)
02.ボヘミアン - 葛城ユキ 〔リクエスト〕
03.Story - AI
04.瞳がほほえむから - 今井美樹
05.春風 - Rihwa
06.Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 - YEN TOWN BAND
07.たしかなこと - 小田和正
〔アンコール〕
01.星のかけらを探しに行こう - 福耳
02.FINAL DISTANCE - 宇多田ヒカル


声の圧が増して、しかも安定感が凄い。
なにを歌っても「佐久間彩加オリジナル」感。
「ドライフラワー」「駅」「Story」「Swallowtail Butterfly」「FINAL DISTANCE」がよかった。
とくに「ドライフラワー」と「駅」。
エモーショナルな難曲で、彩加ちゃんの天才ぶりが際立つ感じがする。
それにしてもスタジオライブ状況で、これだけの感情移入できる力量って、やっぱりただものじゃないと思う。
駅【佐久間彩加】
----------------------
2020/04/06 UP
4/3(土)の第4回配信ワンマンライブ、なんとまたしても見逃しました(笑)
さきほどチケット買ったので、アーカイブ(4/17まで)視て後日セトリをUPします。
チケ購入は→こちら。
----------------------
2021/03/09 UP




このところやたらに忙しかったので、さきほどようやくセトリとりました。
↑ スクショも時間がなかったのでいまいちかも。すみませぬ。
〔前半〕
01.SAKURA - いきものがかり
02.本当の恋 - May J.
03.元気を出して - 竹内まりや
04.Hero - さなり
05.ORION - 中島美嘉
06.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
07.あゝ無情 - アン・ルイス
08.unlasting - LISA
〔後半〕
01.誰より好きなのに - 古内東子
02.イエスタデイ - Official髭男dism
03.366日 - HY
04.あなた - 宇多田ヒカル
05.あなたに会えてよかった - 小泉 今日子
06.トイレの神様 - 植村花菜
〔アンコール〕
僕が死のうと思ったのは - 中島美嘉
「unlasting」「誰より好きなのに」「イエスタデイ」「あなた」「僕が死のうと思ったのは」がよかった。
とくに「あなた」と「僕が死のうと思ったのは」。
どれも難曲だけど、こういう曲で彩加ちゃんの真価が発揮される気がする。
「僕が死のうと思ったのは」は、歌詞はシリアスだけど曲調はアップビートのグルーヴ曲でバックのキーボードがよく効いている。
こういうシンプルでお洒落な曲調、歌い崩せるしすごく向いていると思う。
「僕が死のうと思ったのは」聴いてて、やにわに佐野元春のバラッドを想い起こした。
自分でもどうしてかわからないけど・・・。
Heart Beat/小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド - 佐野元春(LIVE 1983)
----------------------
2021/02/28 UP
2/23(火) 14:30~の「第3回 佐久間彩加 配信ワンマンライブ」、うかつにも見逃しました。
先ほどチケ購入したので、後ほど視聴してセトリ上げます。
3/9(火)まで視聴できます。
見逃した方は→こちらから。
**************
2/21放映のカラオケバトルの「超絶ハーモニー連発・最強デュエット王決定戦!」、彩加ちゃんが名演してたので、Blog内マルチポストですが載っけてみます ↓
〔 予選 〕
■ life AAA - 佐久間彩加 / 鈴木杏奈
このふたり、初コラボ?? 超面白かった。
アニソン歌手?らしく、杏奈ちゃんがかなりヒーカップかましてる。
ビブラート、19秒、61回のD型(上昇型)。
このふたりはまずほとんどボックスB-2型で、D型はみたことがない。
ビブラートが干渉したのかも・・・。でも不安定感はまったくなし。
〔 決勝 〕
■ ハッピーエンド - 佐久間彩加 / 鈴木杏奈
0:47~ 最後は嘘になって (杏奈ちゃんの中低音)
2:08~ もう離さないで (彩加ちゃんのハイトーン)
杏奈ちゃんがハイトーン、彩加ちゃんが中低音ってパート振られてたけど、↑ 聴くとそんなこと全然ないと思う。
ハモリ部、ふたりの声がはっきり聴き分けできるのに、絶妙にハモってる。
実力に裏付けられたオリジナルな個性が際立っているので、共演してもブレることがない。
それぞれの個性がぶつかって、新しいなにかを生み出しそうな予感ばりばり。
またまたいまごろ言っても詮ないことだけど、一度でいいから「U-18プロジェクト」もやってほしかった。
堀優衣ちゃん、鈴木杏奈ちゃん、佐久間彩加ちゃん、熊田このはちゃん、原藤由衣ちゃんあたりで・・・。
----------------------
2020/12/31 UP
佐久間彩加ちゃん配信ライブ
『大晦日~ツイキャスプレミア配信ワンマン』のセトリです。
〔前半〕
01.雪の華 - 中島美嘉
02.ゲレンデがとけるほど恋したい - 広瀬香美
03.雪のクリスマス - DREAMS COME TRUE
04.あの頃へ - 安全地帯
05.なごり雪 - イルカ
06.炎(ほむら) - LISA
07.あなた - 宇多田ヒカル
08.夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
「炎(ほむら)」 と「あなた」がよかった。
「あなた」みたいな難曲をこなしていくのが、彩加ちゃんLIVEの醍醐味だと思う。
「炎(ほむら)」はやっぱり名曲。これから多くの歌姫を育てていく歌では。
〔後半〕
01.夜空のムコウ - SMAP
02.NAO - HY
03.Aitai - 加藤ミリヤ
04.ドライフラワー - 優里
05.プラスティック・ラブ - 竹内まりや
06.Everything - MISIA
07.流星群 - 鬼束ちひろ
08.遠く遠く - 槇原敬之
〔アンコール〕
木蘭の涙 - スターダスト レビュー
後半、エモーショナルな曲が多くて聴き応えがあった。
一見、あっけらかんとして見えるけど、繊細な感受性と強いきもちを持っているのだと思う。
だから、こんなにこころに響く歌が歌えるのでは。
それと「プラスティック・ラブ」にはびっくり。
もともと広い曲幅が、さらに広がっているような。
来年は、カラバトU-18の面々のますますのご活躍をお祈りします。
----------------------
2020/12/29・2019/12/16 UP
チケットゲット!
まだ販売中なので、ぜひ。
佐久間彩加ちゃん配信ライブ
『大晦日~ツイキャスプレミア配信ワンマン』
2020.12.31(木) 14:30~16:30(アーカイブ2021.1.14まで)
チケット販売中です。(2,500円+手数料)
詳細は→こちら。
難曲ほど燃える感ばりばり。セトリが楽しみ。
ちなみに、10/25の配信ライブのセトリは ↓ (数曲抜けあるかも・・・)
・手をつなごう - 絢香
・奏(かなで) - スキマスイッチ
・流星群 - 鬼束ちひろ
・夢見る少女じゃいられない - 相川七瀬
・あゝ無情 - アン・ルイス
・初恋 - 村下孝蔵
・香水 - 瑛人
・U&I(ユーアンドアイ) - Ailee(エイリー)
・白い恋人達 - 桑田佳祐
・If 〜I know〜 - EXILE
・ピエロ - 上木彩矢
・God knows - 涼宮ハルヒ
・季節の訪れ - 佐久間彩加(オリジナル)
・かくれんぼしてる君に - 佐久間彩加(オリジナル)
・トイレの神様 - 植村花菜
*************
(blog内マルチポストですが、入れときます。)
先ほど放送してた12/13放送のカラバト、やっぱりまたしてもU-18の強さを物語る内容だった。
→ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
優勝した佐久間彩加ちゃん、凄かった。
予選の「奇跡を望むなら...」は、2020.11.1 OAの「風が吹いている」と似たような歌いまわしだったと思う。
精密機械のように冷静に、淡々と置きに行く歌い方。
これで99.664で決勝に・・・。
決勝の「君がいたから」。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
歌い出しから前半は、「風が吹いている」や「奇跡を望むなら...」と同じ歌いまわししていたと思う。
ところが、1:32~ 「強く 手を握りしめた」からモードが一気に変わったような感じがする。
(とくに「しめた」の全開ビブラート)
いつもの「佐久間モード」に入ったら、もう「置きに行く」歌い方には戻れないと思うし、実際戻っていない。
さすがに我慢できなくなったのかな(笑)。
後半~ラストはほとんど「佐久間モード」全開でDIVA状態に・・・。
結果は99.870で優勝。
しかし、決勝でこんな超難しい曲選んで、しかも途中で歌い方変えて(?)優勝とは、やっぱりこの子ただものじゃない。
----------------------
2019/11/02 UP
昨日放送のカラバト、やっぱりU-18世代レベル高いと思った。
下尾礼子ちゃん、いいパフォーマンスだったけど残念。
佐久間彩加ちゃん、優勝おめでとう!
予選:ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~
決勝:風が吹いている
決勝は、Ai判定機最高得点の99.8点台ゲット。
これです ↓
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:いきものがかり「風が吹いている」 /2020.11.1 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
こんなに慎重に歌ってる彩加ちゃん、はじめてみた。
バーの上に歌声を置きに行ってる感じか。
おそらく、意識的に声色の幅と声の広がりを絞ってると思う。
それと、予選曲のビブラート回数18回にもびっくり。ここまでビブラートを抑えたテイクも聴いたことがない。
でも、Ai判定機で勝つためには、これしかなかったのだと思う。
↓ も声色が暴れにくい曲だけど、これだけ多彩な声色とビブラートを繰り出してるのが、↑と聴き比べてみるとよくわかる。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加 「未来予想図Ⅱ」DREAMS COME TRUE/2018.2.21 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
勝ちに行くために、あえてこういうテクニカルな戦略とれる才能って、やっぱりただごとじゃないと思う。
(でも、個人的にはLIVEの歌い方のほうが好きだけど・・・(笑))
----------------------
2019/10/26 UP
15:00~ LIVEで聴く予定だったけど、急な用事が入って聴けず、さきほどアーカイブでざっくり聴いてみました。
配信LIVEはこれができるからいいですね。
配信LIVEは観客のリアクションがないので、けっこうやりにくいと思う。
でも面白い内容だった。
個人的にとくに面白かった曲は、
■ 手をつなごう/絢香 20:55~
この曲で表情と左手のうごきが変わった感じがある。
彩加ちゃん、調整気味のときは、ちょっと迷ったふうの表情になるし、乗ってきたときはキレのある勝負師的な眼になる感じがする。
それと、左手の動きがしなやかになってきたときは、声も乗ってる感じがする。
この曲では、勝負師的な眼としなやかな左手の動きがあった(と思う)。
声のつくり方が絢香より多彩なので、オリジナルよりも変化に富んだ仕上がりになっていたと思う。
■ 流星群/鬼束ちひろ 32:30~
富金原佑菜ちゃんの「流星群」凄いけど、彩加ちゃんの流星群も凄い。
こういうメロディーの輪郭がはっきりした曲、ほんとに巧い!
鬼束ちひろって、カラバトU-18世代(黄金の世代?)育てた一人だと思う。
■ 香水/瑛人 1:15:16~
テクがないとふつうにお経になる曲調。
これだけ変化のある曲に仕上げられるとは、やっぱり「声色の魔術師」だと思う。
それにしてもこの曲って、YouTubeの再生回数1億回超えなんだ。ふ~ん・・・。
■ 白い恋人達/桑田佳祐 1:23:36~
音幅の広い曲。もの凄く複雑な発声でこなしていて面白かった。
それと、サビ部分の高音の伸び。
ヒーカップでもファルセットでもなく、ひっくり返すようにたおやかなハイトーンが出てくるこの発声ってなに?
■ かくれんぼしてる君に/佐久間彩加(オリジナル) 1:43:25~
この曲むずかしいわ・・・。
でも、このくらいの曲の方が、彩加ちゃんの才能が活きるような気もする。
いくつもの声色を紡ぎあわせていくような歌いまわし。
並みの才能でできるワザじゃないと思う。
それと、アップテンポ系では、ピエロ/上木彩矢、アンコールのトイレの神様もしみじみとよかった。
ときおり聴けた、スキャットやフェイクが凄く気になったので、もっとばりばりかましてくれるとさらに面白くなるかも(笑)
まだざっくりとしか聴いていないので、気になるところがあったら追記します。
----------------------
2019/10/16 UP
佐久間彩加ちゃんの配信ライブ(初めてのツイキャスプレミア配信)情報です。
『佐久間 彩加 16th 〜Anniversary Live〜』
2020.10.25(日) 15:00~17:00
11/8までアーカイブ視聴可能 fee:2,500円
詳細は →こちら
もちろん購入しましたよ。この子のLIVEすごく面白いもん。
驚愕のテイク ↓
■ やさしさで溢れるように【佐久間彩加】
完璧なオリジナル化。すでにDIVAの貫禄!
■ 空と君のあいだに 佐久間彩加
ほんとにこの曲めちゃくちゃ合ってるわ。
もはや点数気にしてない感あり。音楽の面白さを実感させてくれるパフォーマンス。
はじめて作詞したオリジナル曲。↓
■ 『かくれんぼしてる君に / 佐久間彩加』music video
----------------------
2020/06/22 UP
「CDTVライブ!ライブ! 4時間生放送で完全復活! 」、さっきまで視てたけどちょっと抜け出してきました(笑)
こういうLIVEってどんどんやってほしいんだけど、スタジオライブは誤魔化しがきかず、いろいろ見えて(聴けて)しまうからな~。
ある意味こわい。
佐久間彩加ちゃんが名唱を残している曲が何曲か歌われていたので、聴き比べしてみました。
たとえば ↓こんな曲。
【カラオケバトル公式】佐久間彩加:YEN TOWN BAND「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」/2018.9.12 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)
やっぱり凄い、このオリジナル感。
歌にぐいぐい引き込まれてく。
音楽の楽しさすばらしさをストレートに伝えてくれる希有の才能。
こういうすばらしい才能が、もっともっと広く聴かれていくような ”場” がほしい。
この子のLIVE、まじで凄かったから・・・ ↓
----------------------
2019/12/21 UP
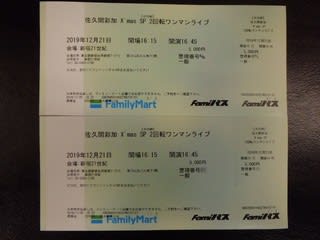



カラバトの上位陣はだいたい生(LIVE)で聴いているのですが、佐久間彩加ちゃんは未聴。
ようやく本日聴いてきました。
■2019.12.21 新宿21世紀 生バンド 佐久間彩加 2回転ワンマンライブ
昼と夜の2回転で、夜の部に行きました。
昼夜で計30曲以上も歌うという耐久LIVE。
しかし、夜の部のラストでも全然声の勢いが落ちていない。
でもってアンコールは2曲!
どんだけ強い声帯持ってるんだ(笑)
すでにプロアーティスト的なオーラをまとっていて、ほんとに彼女中学生??
ふつう中学生クラスだとどうしてもバックに飲まれがちになるけど、この子はバックを従えている感ばりばり(笑)
多彩な声色持っているので曲幅が広く、エンタメ的にも面白いステージでした。
カラバトでも中低音の声の深みやフックのあるビブラートは堪能できたけど、LIVEとなるとやっぱり違う。
とくに高音。
LIVEの出だしは「やっぱりハイトーンのメインはファルセットか?」と思ったけど、中盤から飛ばしてきて、フラジオレットやヒーカップ含むいろいろなパターンのハイトーンを縦横無尽に繰り出してた。
とくにあでやかに開いていく感じのハイトーンがあって、これは絶品。
(裏声系ではない。ミックスボイスかとも思うが、それらしくない質感もあってよくわからず・・・。)
来年1月にリリース予定のCD収録のオリジナル曲2曲をアンコールで演ったけど、ハイトーン寄りの曲調。
やっぱり高音にも相当自信があるのだと思う。
それと、彩加ちゃんのビブラートって、たぶん1/fゆらぎ入っていると思う。
個人的なベストは、Jupiter(平原綾香)。
リズムの立ったJupiterで、これは生バンドならでは。
色気と深みのある低音から、↑で書いた「あでやかに開いていく感じのハイトーン」までの引き上げは信じられない展開。
まさに声色の魔術師!
前にも書いたけど、こんなの意識して出せるとは思えないから、たぶん天性のものだと思う。だから天才。
--------------------
熊田このはちゃんフリークとしては、どうしてもこのはちゃんと比較してしまう(笑)
両者の個性はかなり対照的で、このはちゃんが持っていないものを彩加ちゃんが持ち、彩加ちゃんが持っていないものをこのはちゃんが持っていると思う。
具体的にいろいろ思い当たったけど、これは安易には書き散らせないので、確信をもてたら後日書いてみます。
それにしても、カラバトU-18世代の実力おそるべし!
やっぱり彼女たち黄金の世代では? → 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
次回のワンマンLIVEは↓ チケット発売中とのことです。(オリジナルCDもその時発売)
⚪2020.1.19 新宿ARISE舞の館 2回転和装ワンマンライブ → 情報
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )





