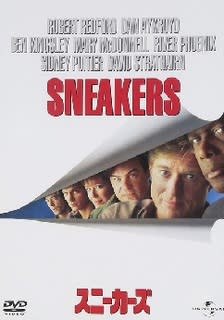2000年作品。石井克人監督の演出タッチはその前に撮った快作「鮫肌男と桃尻女」(99年)と同じで、新鮮味がない。しかしながら、まだこの頃は前作からの“勢い”は持続しており、ハチャメチャな展開で笑わせてくれる。その意味では、観て損はない映画かもしれない。
ヤクザから2億円を横領したシュンイチロウ(永瀬正敏)は、隠れ場所としては最適な“ホテルニューメキシコ”に潜伏する。ところが、そこに借金返済を迫る元彼女のカナと彼女の婚約者のトドヒラが押しかけてくる。さらには、組長から金を取り戻すように命令されたソノダまでやってくる。

シュンイチロウは仕方なく金を山分けにして皆で逃げようと提案するが、そこにソノダの裏切りを予見した組の若頭であるイソムラが乱入。一方、隣の部屋でこの一件を立ち聞きしていたのが、覗き癖のあるオキタとキャプテンバナナだ。この2人も事態に介入し、騒ぎはさらに大きくなる。
映画の舞台が“ホテルの一室に集まる珍奇な奴ら”と“その部屋を覗いているホテルオーナーと、その親友の息子”に分かれ、それぞれテンポが違うため展開がスムーズにいってない。その覗き部屋にいるコンビを演じるのが、原田芳雄と浅野忠信というのも釈然としない(この2人の演技パターンは全然合わない)。基本的に密室劇であることも、前作に比べれば爽快感に欠けると言える。
しかしそれでも、映画が何とか終盤に差し掛かると、怒濤の(?)クライマックスにやっぱり爆笑してしまう。そして、ラストのオチにも思わずニヤリだ。脇を固めているのが岡田義徳に堀部圭亮、我修院達也、松金よね子、津田寛治、大杉漣、田中要次、加瀬亮という濃すぎる面々。ジェイムス下地による調子のいい音楽と、町田博の効果的な撮影もドラマを盛り上げる。石井監督は最近はアニメーションのクリエイティヴ・アドバイサー等の仕事が多いようだが、そろそろ劇場用映画を撮ってもらいたいものだ。
ヤクザから2億円を横領したシュンイチロウ(永瀬正敏)は、隠れ場所としては最適な“ホテルニューメキシコ”に潜伏する。ところが、そこに借金返済を迫る元彼女のカナと彼女の婚約者のトドヒラが押しかけてくる。さらには、組長から金を取り戻すように命令されたソノダまでやってくる。

シュンイチロウは仕方なく金を山分けにして皆で逃げようと提案するが、そこにソノダの裏切りを予見した組の若頭であるイソムラが乱入。一方、隣の部屋でこの一件を立ち聞きしていたのが、覗き癖のあるオキタとキャプテンバナナだ。この2人も事態に介入し、騒ぎはさらに大きくなる。
映画の舞台が“ホテルの一室に集まる珍奇な奴ら”と“その部屋を覗いているホテルオーナーと、その親友の息子”に分かれ、それぞれテンポが違うため展開がスムーズにいってない。その覗き部屋にいるコンビを演じるのが、原田芳雄と浅野忠信というのも釈然としない(この2人の演技パターンは全然合わない)。基本的に密室劇であることも、前作に比べれば爽快感に欠けると言える。
しかしそれでも、映画が何とか終盤に差し掛かると、怒濤の(?)クライマックスにやっぱり爆笑してしまう。そして、ラストのオチにも思わずニヤリだ。脇を固めているのが岡田義徳に堀部圭亮、我修院達也、松金よね子、津田寛治、大杉漣、田中要次、加瀬亮という濃すぎる面々。ジェイムス下地による調子のいい音楽と、町田博の効果的な撮影もドラマを盛り上げる。石井監督は最近はアニメーションのクリエイティヴ・アドバイサー等の仕事が多いようだが、そろそろ劇場用映画を撮ってもらいたいものだ。