ヒトラー、とタイトルにあるけど
明るくやさしく、決してつらくないんです。

「ヒトラーに盗られたうさぎ」74点★★★★




**********************************
1933年2月。
ベルリンに住む9歳のアンナ(リーヴァ・クリマロウスキ)は
批評家でユダヤ人である父(オリヴァー・マスッチ)と
音楽家の母(カーラ・ジュリ)、
賢いお兄ちゃん(マノルス・ホーマン)に囲まれ
生き生きと毎日を送っていた。

が、新聞で辛口のヒトラー批判をしていた父は
次の選挙でヒトラーが勝つと
弾圧の対象になる――と忠告される。
そして、ある朝アンナは母から突然
「一家でスイスに逃げる」と告げられる。
持って行けるものは2つだけ。
アンナは迷った末に
大好きなももいろうさぎのぬいぐるみを置いて
スイスに旅立つことになるが――?


**********************************
世界的な絵本作家ジュディス・カー(1923-)の
『ヒトラーにぬすまれたももいろうさぎ』をもとに
「点子ちゃんとアントン」(00年)「名もなきアフリカの大地で」(01年)などで知られる
カロリーヌ・リンク監督が手がけた映画です。
ヒトラー、とタイトルにあり、さらに「うさぎ」とあるけれど
動物がかわいそうなことはなく
不穏な空気は、たしかにあるものの
意外なほどに、明るく、やさしく、決してつらくない物語なので
拒否反応を示さずに、観て欲しいなあと思います。
実際、監督も35年以上前に、学校でこの本を読んだとき
「内容が明るくて驚いた」そうなんですね。
映画の主人公は
1933年、ベルリンに住むユダヤ人である9歳のアンナ。
お父さんは舞台批評などをしていた文人でお母さんは音楽家。
頭がよくて優しいお兄ちゃんがいる。
お父さんは新聞などで、きっぱりとヒトラー批判をしていた人なのですが
この年の選挙で、投票率43.9パーセントの中
ヒトラーが勝ってしまう。
「ドイツ人は理性を失った」――と、新聞を読みながら言うお父さんのつぶやきが
どうにもめちゃくちゃ、“いま”に刺さる。
そんなビミョーな投票率で、こんなことになってしまったんだ・・・
誰も「そんなこと、起こらないでしょ」と、思っていたことが
するすると、ゆらゆらと、起こってしまったんだ・・・
ヒトラー台頭を市井の視線から描く作品で、実によく語られるこのシチュエーションが
ホントに、いま、怖い気がしませんか。
で、お父さんは政府の弾圧の対象になり、
その前に、一家でスイスに逃げることになる。
実際、不穏な雰囲気は映画全体に淡く漂っているけれど
でも、映画は不思議なほど、つらくない。
アンナの快活さと、生き生きとした日々、
賢いお兄ちゃんのやさしさ。
スイスの美しい自然、


さらに移り住んだパリでの貧しくも温かい暮らしや、幻想的な夜の街――

すべてがやさしい色調で描かれ
重く暗い状況でも、誇り高く、たくましく生き抜く一家の姿に
気持ちが明るくなるんです。
映像もやさしくて
グラスに入ったアイスティーや、アンナのカーディガンなど
あちこちにピンクが挿し色であるのもかわいくて、効果的。
(欲を言えば、タイトルは原作どおり
「ももいろうさぎ」としたほうがよかったんじゃないかなぁと思うけど)
そして
子どもにとって、両親の心の持ちようが、
どれだけ大切で多大な影響になるかを、深く考えさせられました。
知識人であるアンナの一家は
ベルリンでまずまずリッチな階層に属するのだと思うのですが
誤解を恐れずに言えば、
それは金銭的な「貧困」には関わらない。
自分で考える意思を持ち、
それを手放すまいとする「矜持」の持ちようなのかな、と。
でも
歴史として振り返れば、アンナたち一家の旅路が、
あと一歩のところで死の危険を回避していたことがわかる。
スイスも安全ではなく、
ましてや彼らがいたフランスでは1942年、
「サラの鍵」(10年)や「黄色い星の子供たち」(10年)に描かれた
ユダヤ人一斉検挙があったんだもんね・・・。
映画はこうして、いろんなことをつなげて
教えてくれるんですねえ。
★11/27(金)からシネスイッチ銀座ほか全国順次公開。













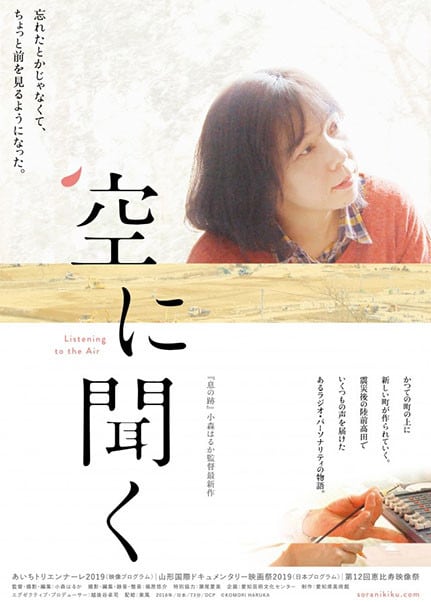
 みたいに
みたいに


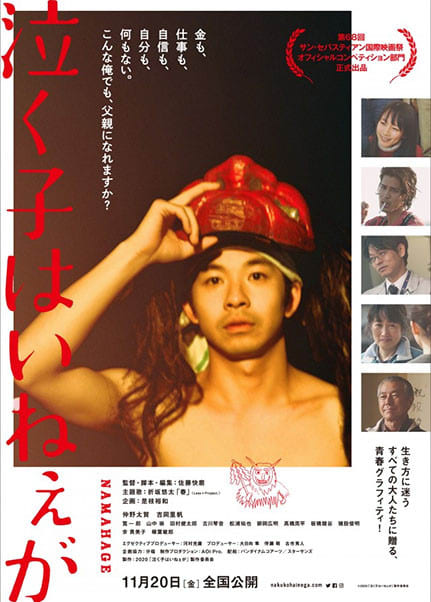











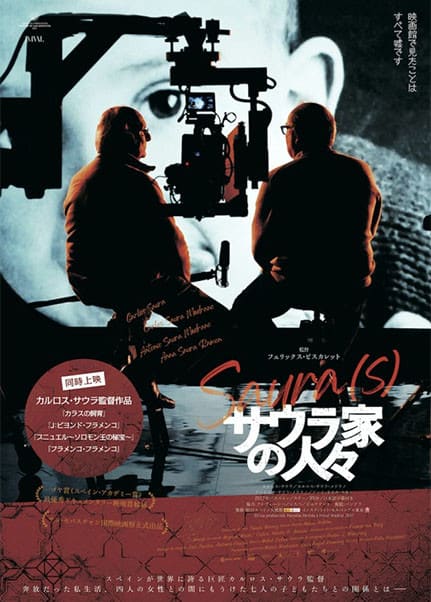

 )
) 」みたいな感じ(笑)
」みたいな感じ(笑)






 と思ってしまうのですが
と思ってしまうのですが









