
「ノルウェイの森」村上春樹 講談社 1987年
私の親友、以前の人生にも以後の人生にも彼女以上の親友は現れなかった。その彼女が、「この中の登場人物であなたに似てる人がいるのよ。そっくりなのよ」と言ってこの本を薦めてくれた。しかしどうにも物語に入ることが出来ず、早々と投げ出してしまった。それから多くの月日が流れ、縁があって貸してくれる人がいて、読んでみた。
不思議な事が多い。1969年が舞台なのに今と何も変わらない。人々、台詞。1987年に大ベストセラーになった。しかし時はバブル。なぜこのような暗い(?)物語が売れたのだろうか。
ムラカミハルキ作品全般に言えることかも知れないのだが、<面白い>という言葉でくくれない。纏められない。<いい>とだけしか言えない。ノルウェイの森がいいと思えるほど私は大人になったのか、あるいは世間から背を向けるようになったのか。
読んでいて、まるで白いご飯のようだと思った。よく噛まないと味がしない。殺人事件があったり、謎があったり、ロマンスがあったり、悪党がいたり、そんな小説はご飯に醤油やタルタルソースやナンプラーがかけてあるようなものである。ちょっと舐めてみればすぐに味が分かる、味わえる。子供でも、これは甘いとか酸っぱいとかすぐに言える。
よく噛まないと味わえないご飯をずっと噛んでいると、顎がしっかりしてゆくのだろうか。
ハルキムラカミやガルシア・マルケスを読むのはシェークスピアを原書で読むようなモノであって、何が楽しいのか分かるのには時間がかかる。私にはよく分からないのだが、技術すらいるのかも知れない。ムラカミハルキ世界ぐらいしか読まないという友人がいれば、彼は苦手だという友人もいるし、ムラカミ世界と同時にそうでない世界も堪能している友人もいる。いやいや。世界をムラカミとNotムラカミの二つに分けようとしている私もどこかおかしくなってきた。
大きな一つのテーマが自殺であると思う。そんな物語を読んでも何も感じずにいられるほど私は不感症ではなかったといふ事か。
冒頭で私に似た人が登場するという事であった。主人公ワタナベの事だと思って読んでいたが、たぶん永沢の事であろうとふと思った。今の私はワタナベ的な人間であるが、昔はたぶん永沢的な人間であったと思う。今も友達は皆無と言ってよい人生を生きているが、当時付き合いのあった人間たちは私が何かを失ったとたん全員が私の元を去っていった。人望がないどころではない。今はそこまでではないと思う(当社比)
などと昔を思ったり自らを省みたりする毒にも薬にもなるのが「ノルウェイの森」である。
 | ノルウェイの森 上 (講談社文庫)村上 春樹講談社このアイテムの詳細を見る |
 | ノルウェイの森 下 (講談社文庫)村上 春樹講談社このアイテムの詳細を見る |
宮崎あおいちゃんがテレビで歌っている。
ザ・ブルーハーツの曲だとは知らなかった。
しかも私にはこう聴こえる。

ひ~らやまほどの~消しゴムひと~つ~♪
平山って消しゴムみたいな顔してないっすかね。
「現代霊性論」内田樹・釈徹宗 講談社 2010年
神戸女学院大学で行われた二人の対談形式の講義が本になった。内田さんの本はずいぶん読んだが釈さんの本は初めて。釈さんと言っても釈由美子じゃないけど。そう言えば釈お酌というおもちゃはどこに行ったのだろうか?東急ハンズでまだ売ってる?
なんてことは置いておいて、宗教について知らなかったこと、なんとなくしか分かっていなかったこと、知りたかったことがこれでもかと出て来る出て来る。宣伝としては、怪しい宗教に騙されないようにこれを読もう的なアプローチをとっているように感じられる。でもそれはごく一部にすぎないというか、特に何の期待もせずに読むと色々と収穫がある、広い範囲を扱った本だと思う。釈さんの関西弁は私にはとても心地が良かった。以下【】内は私の独白。
・ 人間に特に発達している白目。ない方が敵に目の動きを読まれない。猿とか他の動物は黒目しかない。にも関わらずどうして人間に発達しているかというと、相手に自分を読んでもらうというコミュニケーションツールとして、【って話が面白い】
・ 我々が全て自己決定できないし、自己責任なんてとれないのに、自己自己しすぎ。自己と他者を区別しすぎ【自己他者の区別は非常に宗教的な話題。今度どっかで友人と語ってみよう。いやお前に友人なんていないではないか】
・ 世の中は本質的にワケワカランことばかり。自分が全て説明できるわけがない。自分が説明できないでもリアルなモノがあるとしてそれを尊重して欲しいのなら、他人が説明できない、でもリアルなモノを尊重せねばならない【確かに!】
・ インドの北の方にはドロボウのカーストがある。生まれながらにしてドロボウになる運命にある【ふむ。すると私はダメ人間のカースト生まれなのか?】
・ 現代人は毎日がハレである。そりゃおかしくなるだろう?【プラスの異常日がハレでマイナスの異常日がケガレ、それ以外の日常がケであると私は解釈している。葬式がケガレなのかはむつかしいが。現代の毎日=フェスティバル&カーニバルのような生活をしていてケへ戻ることが極端にまで少ないとすれば、それが様々な問題の原因なのかも知れない。これについてはもうちょっと考えてみよう】
と特に感じ入った事を書いてみた。日本の新宗教の歴史について結構詳しく説明してくれている。出口王仁三郎なんて知らないよって人は読んでみればとても面白いんじゃないかな。
 | 現代霊性論内田 樹,釈 徹宗講談社このアイテムの詳細を見る |
都内某所の居酒屋のトイレ。
した後に流そうと思って、スイッチを押そうが蹴りを入れようが全く流れない。泥酔していたのでたぶんそのまま出てきたような気がする。後で考えてみて、
1.実はこれはスイッチではなかった。
2.自分が出た後に自動的に流してくれるシステムだった。
3.実はここはトイレではなかった。
「ボクは坊さん。」白川密成 ミシマ社 2010年
祖父が死んだ後、寺を継いだボク。ボクの坊さんの日々。ネタが興味深いし面白いし文章もいい。ほぼ日刊イトイ新聞に書かれていたそうだ。
バリバリのキリスト教者の人が人生とか何とかそういう事について語った本を読んだことがない(から感銘を受けた事もない)某知り合いがバリバリのカトリック信者なのだが、彼が延々とキリスト教の矛盾について語ってくれたことならあった。
必ずしも比較の対象がキリスト教であることは正しくないかも知れないが、仏教者が書いた文章って結構ふむと頷いたり、うーむと唸ってしまうことが多いような気がする。「自分から自由になる沈黙入門」とか、「もう、怒らない」の小池龍之介さんと同じ事が言える。
<途中提出>のススメにうなった。そうだよな。完璧なモノなんて永遠に出来ないのだから、今現在のモノを、今現在提出出来るモノを提出すればよいではないか、と自分の生き方とか生活とかを省みてしまった。
<生きるということはお祭りのようなこと>も、ああその通りだと思ったよ。うんうん。生まれる前と死んだ後が言わば、普通の状態であって、生きている時期というのは祭りのように普通じゃない状態だ。ずっとお祭りじゃ疲れちゃうもんね。だから死ぬということは不幸なことではなく、普通に戻るだけのこと、かも知れない。
しかし、戸籍上の名前を変更するのは難しいが、宗教家だとそうでもないというのも面白い。そうそう。上のような堅い話ばかりじゃなく、高野山大学時代の話とか坊主用のバリカンを買う話とか堅くなくて面白く読みやすいエピソードがたくさんありまする。なむなむ。
 | ボクは坊さん。白川密成ミシマ社このアイテムの詳細を見る |
新宿南口の天狗(だったよな?)土曜日だというのにエラク混んでいる。6人での飲み。
タバコをやめないのに酒をやめたという自称女性自称アラフォーのKさん。「お前アラフォーじゃねえだろ?アラフィフいやアラシクスだろ?体重が」と言ったらぶたれた。
最初彼女はウーロン茶を普通に頼んでいたのだが、面倒になって、ジョッキで頼んだ。すると

デカンタの半分入れた状態で来た。笑ってしまった。それは=ジョッキ、ではないだろう。後にワインを頼んだら、
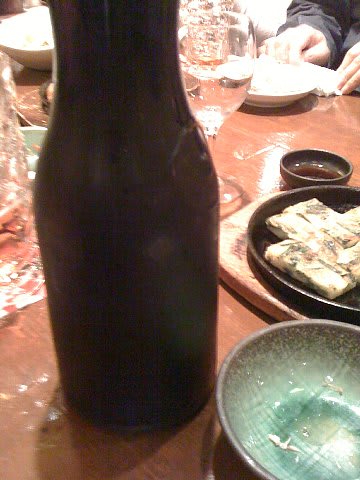
こうやって来たのだから(結構量は多い)
久しぶりに呂律が回らなくなるほど飲んでしまった。でも翌朝後悔するような暴言は今回は吐かなかった。多分。○○さんと××さんが付き合っていたとか、△△さんが仕事やめてしまったとかちょっと驚く話が出たり。私も悔しいので、妊娠したとか言ってみた。いや言ってない。
「北帰行」佐々木譲 角川書店 2010年(初出本の旅人2007年6月号~2009年7月号)
ロシア人娼婦を暴力団組長が殺してしまう。敵討ちにロシアから送られてきた凄腕の女殺し屋。彼女をアテンドすべく日本人ガイドが。日本人暴力団VSロシアマフィアという単純な図式には当てはまらない闘いそして逃避行。
いやいや。途中でなんだかつまらなくなって何日か放っておいた自分がよく分からない。単に自分の調子の問題であって本作とは無関係である。3分の2くらい読み進んでいくと、だいたいこの物語がどこに落ち着いていくか予想がつく。その予想が100%裏切られるわけでもないけれど、予想とは全く違うラスト直前の事態に胸が焦げた。
基本的にはターニャという殺し屋と卓也というガイドによるアテンドのエスカレートしていく様と彼らを追いかける藤倉というやくざが中心になるが、何気なく絡んでくる脇役たちと、逢坂剛の「兇弾」と共通する、<どうしてこのネタでこんなに面白いのか分からない>状態が似ている。
佐々木譲のここ数年の作品にはハズレがないと本当に思う。
なお、私が読んでいた「北帰行」を見て、友人が「ほっけこう?」と読み笑ってしまった。
 | 北帰行佐々木 譲角川書店(角川グループパブリッシング)このアイテムの詳細を見る |
ドラマ「不毛地帯」のラスト、雪模様の中しわがれ声のおっさんの唄が響く。トム・ウエイツ。は知っていたけど、特にジム・ジャームッシュ作品では役者として。しかしこの曲は知らなかった。サビの所では子供が欲しいと言っているのだけは分かった。ウオーンティングアチルドレンと。a childrenにはツッコンではいけないのだろうと思っていた。前後に兵士っぽい事を歌っているので、戦争に行って帰還してやっと待っていてくれた奥さんと子供を作ろうという歌だと。
サビでそう言っているように聴こえないだろうか?しかし調べてみたら、Waltzing Matildaと言っているのだ。なんてこと。しかしマチルダを踊る?マチルダをワルツるって何だ?オーストラリアでは国歌に次ぐぐらいの有名な歌だそうだ。
マチルダとはずた袋のことで、ワルチングとは放浪するという意味らしい。うーむ。知らないことがあまりにも多い。地球は狭くて広い。それからYouTubeの波にさらわれて、
ジミヘンがアコギを弾いている珍しい映像を見つけたり、ロッド・スチュワートの映像を見たり。
YouTubeは怖い。お金がかからない危険なドラッグだ。
日本は相変わらずというか期待したほどメダルは取れなかったようだが。開幕前にNHKで放送していたミラクル・ボディというNHKスペシャルっぽい番組が面白かった。ジャンプのシモン・アマン、アルペンスキーのダウンヒル、アクセル・スビンダルとフィギュアのブライアン・ジュベールのトレーニング、試合中の肉体を計測するというなかなかの意欲作。特にスピンダルは凄いと思ったので、本選に期待して見ようと思ったが夜の放送がほんのちょっとしかなかった。BSかどこかで放送していたのを録画すればよいんだがそれもなんだか面倒。
知り合いのフィギュアおたくに言わせると、浅田真央は銀メダルを取ることが予定されていた、とか。キムヨナの構成からすると彼女はこの得点で、浅田はこの得点。それは決してキムさんを上回ることがないと。よっぽど大きなミスでもすれば違うのだろうが。
これがよく分からない。タラソワコーチの考えがよく分からない。初めから勝てないと分かっているような演技になぜするのだろうか。見ている方からすれば充分逆転できるような得点だからこそドキドキして見るわけだし。勿論色々と事情があるのだろうが。そのおたくは、「ブライアン・オーサー(キムヨナのコーチ)はやっぱりうまい。ブライアンは好きだからキムヨナが勝ってもそれはそれでいい。タラソワはあまり好きじゃない」と言っていた。もはや私のような常人には理解できない。
セミは何年も地中にいるそうだ。
オリンピックになると突然熱く語り始める人がいる。ワールドカップのときだけ、実は自分はサッカーおたくだと言い始める人がいる。しかし基本的には4年間は沈黙しているので、私はこのような人たちのことを
4年ゼミと読んでいる。
アメリカ中西部、アジア系移民が多く住む町。クリント・イーストウッド演じるウォルト・コワルスキーの長く連れ添った妻の葬式から始まる。子供や孫たちは、口が悪くすぐ怒る彼をよく思っていない。最愛の妻を失い、家族からは疎んじられ、何のために生きているか分からない彼。隣に住むモン族(中国やミャンマー出身の部族で迫害された歴史がある)の家族。男の子タオは根性がなくやる気がなく姉ちゃんにも頭が上がらない。ギャングの従兄弟は彼を誘おうとする。あろうことか、イーストウッドが愛情を注ぐフォード72年製のグラン・トリノを彼らは盗もうとするのだ。従兄弟たちが外で見張る中、ガレージで車を盗もうとしていたところを、タオはウォルトに見つかり、もう少しで射殺されそうになる。
家族に馬鹿にされ、車も仕事も彼女も持たないタオ。ウォルトは関わろうとしなかったのに、どういう訳か関わりを持ってゆく。氷のように冷たかったウォルトがタオと触れ合う内に見つけた自分の人生の締めくくり方とは・・・
いやいやいや。こんなラストとは。泣けた。コピーに「俺は迷っていた、人生の締めくくり方を。少年は知らなかった。人生の始め方を」とある。特に意識していなかったこのコピーが観た後にじわじわと来る。DVDについている特典映像では、車を愛する男たちが描かれ、車がある種のフェティシズムの対象になっているとさんざ語られる。しかしそれがメインテーマだとは私は受け取らなかった。
ウォルトが溺愛する対象はシカゴ・カブスでもグリーンベイ・パッカーズでもハーレーでも68年のギブソン・レスポールでもよいような気がする。グラン・トリノ=ウォルトの分身であるように表現されていたことと、祖父は嫌いだけど死んだらあたしに遺産として残して欲しいと思う孫娘がいるので、それはこんな風なモノ=車だったら一番しっくりくるのかも知れないけど。
それよりも、タオとウォルト、そしてモン族のチンピラたち。あれがああなってこうなるなんて、現実の世界でも充分に起き得ることなのに。でももし自分がタオだったら気が狂うだろう。
クリント・イーストウッドがカッコいい。オフィシャルサイトからダウンロードしてPCの壁紙にしてしまった(それまではレディ・ジェーン・グレイの処刑の絵が壁紙だったので、これでもまともになったのだ。)声はかすれ手も顔も皺だらけなのに、古き良き男たちが持っていた、そして近頃の爺さんの多くが失ってしまった何かを持っている。私はそれをずっと探しているのに、それが何だかいまだに分からない。もちろん見つかってもいない。
人生の締めくくり方も分からず、まだ人生も始めていない。そんな私はあと何本映画を観る事が出来るのだろうか。
 | グラン・トリノ [DVD]ワーナー・ホーム・ビデオこのアイテムの詳細を見る |
「さよならドビュッシー」中山七里 宝島社 2010年
第8回このミステリーがすごい!大賞受賞作。遥は親を失った従姉妹のルシアと家族とともに暮らす。火事でさらに、遥は火事で自分の祖父と従姉妹を失う。ピアニストになるために入ったばかりの学校。しかし皮膚移植をしたばかりで体を動かすことすらままならない。新進気鋭のイケメンピアニストの助けを借りてピアノの腕を上げようとしていると、さらに身辺がきな臭くなってくる。起こった事件とそしてこれから起こる事件。どう解決していくのか。
ふむ。遥のピアニストとしての成長、葛藤と殺人事件の解決が二本立てで進む。悪くない。ラストの解決は特にミステリーとしての王道というか実にミステリーらしい落とし方で気に入った。ピアノとか音楽に関しては最近読むことが多いので読み飛ばしてしまったが。
35頁の爺さんの台詞が実に良かった。
「(途中略)ほれ、コスプレとかいったか珍妙な扮装して物語の登場人物になりきるのが流行っとるだろう。あれもそうや。みんな、今の自分がよっぽど嫌いなんや。きっと自分ではない誰か、ここではないどこかを望んでおるんやろうなあ。そう言やテレビで流れている歌はどれもこれもお前は特別だの、違う自分を探せだの呆けた台詞の大合唱だ。ただな、わしの考えでは、これが欲しいあんな風になりたいとかの希望やら願望は果実みたいなモンや。若いうちに食せば滋養にも美容にもなろう。しかし時を経れば果実は傷み、腐る。腐った果実は毒素を持つ。当然それを食し続けるものは腹の内から蝕まれていく。そして現実と喧嘩する力を失のうていく。それにな、どんなに美味しくとも腹いっぱい以上食べれば腹を壊すのは道理や。人にはそれぞれ果実を食していい限度が予め決められておって、それを分と言う。分を弁えん者の末路はたいていが自滅や」(35頁より引用)
うーん。これを読んで鋭い、そして痛いと思ったのは私だけだろうか。
 | さよならドビュッシー中山 七里宝島社このアイテムの詳細を見る |



















