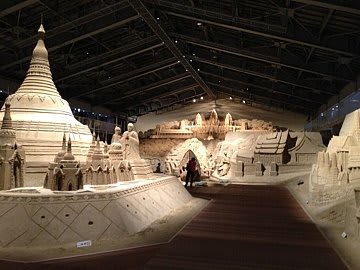力道山と木村政彦のプロレス対決をご存じだろうか。
1954年12月22日、史上最強の柔道家で後にプロレスに転じた木村政彦と相撲出身で人気プロレスラー力道山の世紀の対決。テレビ視聴率もラジオ聴取率もほぼ100パーセント。日本国民が固唾を飲んで注目した日。
プロレスという「ショー」を見せていたはずなのに、突如としてキレた力道山による右ストレート、掌底、そしてサッカーボールキック。木村は失神しKO負け。
この木村の人生の外に見えるもの全てを振り返り、そして力道山を殺そうと思うまでに至る彼の内面に迫る壮絶なドキュメント。
読中読後、何度ため息をついたことか。
木村が人類史上最も強い柔道家らしいとは聞いていた。現役時代なら山下よりも井上康生でも全く歯が立たないとか。そんな最強の男はどうやって出来上がったのか。師匠の牛島辰熊(牛+辰+熊 どんだけアニマルな名前なんだ)との出会い。1日10時間の練習。戦前からの不敗記録。立ち技だけじゃなく寝技に強い。寝技一直線「七帝柔道記」で描かれた高専柔道の世界。
そして思想のある牛島と思想のない木村の対比。利用できる人間なら誰でも利用し、利用できなくなれば乗り換える、ビジネスマンであった力道山と、ただ強い柔道がしたいだけだった少年だった木村との対比。
空手やボクシング、サンボなど他の格闘技を取り入れて練習する、現代の総合格闘技と同様のものを何十年も前に考えていた木村。その先見性。しかし力道山のように大物に取り入る「知恵」がなかったので金には縁がなかった。その先見性のなさ。一人の男の伝記として、これを上回るものに今後出会えるであろうかと思うほどの傑作だった。ロバート・ホワイティングの「東京アンダーグラウンド」で描かれたの似た昭和裏面史としても抜群に面白い。
グレイシー一族をご存じだろうか。総合格闘技PRIDEやDYNAMITE!で高田延彦や桜庭一志、吉田秀彦たちと死闘を繰り広げた。ヒクソン・グレイシーやホイス、ホイラーの父がエリオ・グレイシー。ブラジルワールドカップのために1950年に建設されたマラカナンスタジアムは20万人収容できる。そこで1951年に木村と闘った。
冒頭の大外刈りの切れ味。亡くなった現在でもグレイシー一族にリスペクトされる木村。それが力道山との闘いでは… いったい何があったのか。書かれているのが本書だ。
では、また。

1954年12月22日、史上最強の柔道家で後にプロレスに転じた木村政彦と相撲出身で人気プロレスラー力道山の世紀の対決。テレビ視聴率もラジオ聴取率もほぼ100パーセント。日本国民が固唾を飲んで注目した日。
プロレスという「ショー」を見せていたはずなのに、突如としてキレた力道山による右ストレート、掌底、そしてサッカーボールキック。木村は失神しKO負け。
この木村の人生の外に見えるもの全てを振り返り、そして力道山を殺そうと思うまでに至る彼の内面に迫る壮絶なドキュメント。
読中読後、何度ため息をついたことか。
木村が人類史上最も強い柔道家らしいとは聞いていた。現役時代なら山下よりも井上康生でも全く歯が立たないとか。そんな最強の男はどうやって出来上がったのか。師匠の牛島辰熊(牛+辰+熊 どんだけアニマルな名前なんだ)との出会い。1日10時間の練習。戦前からの不敗記録。立ち技だけじゃなく寝技に強い。寝技一直線「七帝柔道記」で描かれた高専柔道の世界。
そして思想のある牛島と思想のない木村の対比。利用できる人間なら誰でも利用し、利用できなくなれば乗り換える、ビジネスマンであった力道山と、ただ強い柔道がしたいだけだった少年だった木村との対比。
空手やボクシング、サンボなど他の格闘技を取り入れて練習する、現代の総合格闘技と同様のものを何十年も前に考えていた木村。その先見性。しかし力道山のように大物に取り入る「知恵」がなかったので金には縁がなかった。その先見性のなさ。一人の男の伝記として、これを上回るものに今後出会えるであろうかと思うほどの傑作だった。ロバート・ホワイティングの「東京アンダーグラウンド」で描かれたの似た昭和裏面史としても抜群に面白い。
グレイシー一族をご存じだろうか。総合格闘技PRIDEやDYNAMITE!で高田延彦や桜庭一志、吉田秀彦たちと死闘を繰り広げた。ヒクソン・グレイシーやホイス、ホイラーの父がエリオ・グレイシー。ブラジルワールドカップのために1950年に建設されたマラカナンスタジアムは20万人収容できる。そこで1951年に木村と闘った。
冒頭の大外刈りの切れ味。亡くなった現在でもグレイシー一族にリスペクトされる木村。それが力道山との闘いでは… いったい何があったのか。書かれているのが本書だ。
では、また。