
「三千枚の金貨」(上下)宮本輝 光文社 2010年(初出BRIO2006年4月号~2009年8月号+書き下ろし)
冒頭、三千枚の金貨を和歌山の山中に埋めたという話を病院できいた、という話から始まる。しかしそのエピソードがストーリーとどう関わるかはすぐには分からない。斉木光生はなぜかタクラマカン砂漠に2週間行ってきた(なぜそんな所に行ったのか分からない。)成田に着いて、会社には行かず自宅に戻らず、銀座のバーに直行する(なぜかは分からない。)斉木は痔瘻になったと判明する。治療する。32頁まで読むと彼がなぜタクラマカンに行ったのかは分かってくる。
そんな感じで、先に、ある現象(心象風景だったり)を描写して、読者に「なぜ?」と疑問を抱かせて、後になってその疑問を解いていく。そのすぐに答えが分からない、じれったい感じがたまらない。
さらに宮本輝が描く男の内面がまたたまらない。純文学とエンターテイメントとの間を行くギリギリの感じがまたたまらない。
タクラマカンに猛烈に行きたい気持ちにさせてくれるのもまたうまい。思わず未読山脈に埋もれているブルース・スターリングのSF「タクラマカン」を掘り出してきてパラパラとめくってしまった(だったら読めばいいのに。)そういう○○したい気分にさせるという意味でも宮本輝のうまさがビシビシと光る。
「そういうものがただの徳利にしか見えないまま、一生を終える人。あるとき、突然、ただの徳利に命のようなものを感じる人。男はこの二種類の分かれていいくそうですよ。それがはっきりと感性にあらわれるのが四十歳だそうです。どっちがいい悪いの問題じゃなくてね」(上巻44頁より銀座のバーテンダーの台詞を引用)
「斉木さんとおない歳で、独身で、二十年間ある人妻と恋愛関係を続けて、老子の研究家で、その世界では知られた存在で、中学の先生を辞めてからずっと一日も休まずにゴルフの練習を続けてるの。でもまだ一度もゴルフ場でプレーしたことはないの。誰にどんなに誘われてもゴルフ場ではプレーしない。ただ練習だけ。十八年間、ひたすらゴルフ練習場でボールを打つだけ。一日二百球」(上巻100頁より喫茶店のマスターについての描写を引用)
幻術師になろうとする者の修行は、まず催眠術から始まる。まず右目で三十センチ先の物を見つめる。それから左目で一キロ先の物を見つめる。どちらの目も対象物に焦点が合うようになったら、今度は逆のことをやる。そうやって右目と左目が自在に遠近の異なるものに焦点が合うように修行を続ける(中略)しかし、長い修行によってその技を会得した人間にそのような目で見つめられ、目と目が合った瞬間、こちらは異次元の世界へと引きずり込まれる。目の錯覚という次元を超えた、心、もしくは精神の錯覚の世界へ飛んでいくのだ(上巻135頁よりフンザの星空鑑賞と不思議な快感を覚えた斉木の独白より引用)
自分が浮遊した感じがするとき、あるいは自分に触れる人が浮遊したような感じがするときがたまにある。それはこのようなことで説明できるのかも、と自分に痴漢して、いや自分に置換して考えると、ちょっと背筋ゾクになった。
基本的には大人の男の自分探し+宝探し+過去への旅が物語の軸になる。本を読むのがたぶん速い(と思う)私が1時間かけても10頁も読めない。行と行の間に何かが詰まっている。宮本輝砂漠に足をとられてもがいている。そんな牛歩の読書がいい。ただ単に面白いなどという言葉では片付けたくない。
冒頭三千枚の金貨を埋めたと語った、芹沢由郎はもうこの世にいない。少しずつ明らかになる芹沢の過去。あなたは芹沢の人生を是とするだろうか非とするだろうか。
 | 三千枚の金貨 上宮本 輝光文社このアイテムの詳細を見る |
 | 三千枚の金貨 下宮本 輝光文社このアイテムの詳細を見る |
8月ももうすぐ終わる。まだまだ暑いけど、8月が過ぎればなんだか何かが終わったような気分。
たまにはと、YouTubeを観ていたら、森山直太朗の「夏の終わり」を見つけた。な~つ~のお~わ~り~♪という高音ばかりが印象的だったけれど、よく聴いてみたらいい歌詞だった。背景になっている画像もとても良い。
なぜか、特にファンではないんだけど、永ちゃんを探してみたら、1977年の武道館ライブの映像が。夏の終わりにヒリヒリした心を癒してくれる(ような気がした)
では、また。
朝日新聞8月22日付に、ブックファースト川越店の店長のブログが出版界で話題だと書いてあった。早速読んでみた。なかなか小気味いいというか、おっしゃる通りだと思った。8月12日の池上彰「伝える力」というタイトルの記事を全文引用させていただく。
いま書店界で一番話題なのが、
いつ「池上バブル」が弾けるかということです。
最近の書店バブルに「茂木バブル」「勝間バブル」があります。
書店の中の、新刊台やらランキング台やらフェア台やら
いたるところに露出を増やし、その露出がゆえに書店員にあきられ、
また出版点数が多いためにお客さんに選択ばかりを強い、
結果弾けて身の丈に戻っていくのが書店「バブル」です。
「茂木バブル」は出版点数が増えるにつれて1冊1冊のつくりが
スピード重視で雑になり、文字の大きさが大きくなり、
内容が薄くなってきて、でもそれに対して書店での露出は増え、
そして点数が多いことでお客さんが何を買っていいか分からなくなり、
バブルが弾けました。
「勝間バブル」ははじめの切れ味のいい論旨が、
出版点数を重ねるにつれて人生論や精神論のワールドに入り、
途中「結局、女はキレイが勝ち。」などどう売ったらいいか書店界が
困る迷走の末、対談のような企画ものが増え、
結果飽和状態になり、弾けました。
書店「バブル」になった著者は、自分の持っている知識なり、
考え方が他の人の役に立てばとの思いで本を出すのだと思うのですが、
そうであるならばなぜ出版点数を重ねる度に、
「なんで、こんなにまでして出版すんの?」
と悲しくなるような本を出すのでしょう。
すべて「バブル」という空気のせいだと思います。
このクラスの人にお金だけで動く人はいないと思います。
そうでなくてせっかく時代の流れがきて、要請があるのだから、
全力で応えようという気持ちなのだと思います。
けれどそれが結果、本の出来に影響を与え、
つまり質を落とし消費しつくされて、
著者本人にまで蝕んでいくことは、悲しくなります。
著者もそれが分からなくなってしまうほど、
「売れる」というのは怖い世界なのかも知れません。
いつ「池上バブル」が弾けるかということです。
最近の書店バブルに「茂木バブル」「勝間バブル」があります。
書店の中の、新刊台やらランキング台やらフェア台やら
いたるところに露出を増やし、その露出がゆえに書店員にあきられ、
また出版点数が多いためにお客さんに選択ばかりを強い、
結果弾けて身の丈に戻っていくのが書店「バブル」です。
「茂木バブル」は出版点数が増えるにつれて1冊1冊のつくりが
スピード重視で雑になり、文字の大きさが大きくなり、
内容が薄くなってきて、でもそれに対して書店での露出は増え、
そして点数が多いことでお客さんが何を買っていいか分からなくなり、
バブルが弾けました。
「勝間バブル」ははじめの切れ味のいい論旨が、
出版点数を重ねるにつれて人生論や精神論のワールドに入り、
途中「結局、女はキレイが勝ち。」などどう売ったらいいか書店界が
困る迷走の末、対談のような企画ものが増え、
結果飽和状態になり、弾けました。
書店「バブル」になった著者は、自分の持っている知識なり、
考え方が他の人の役に立てばとの思いで本を出すのだと思うのですが、
そうであるならばなぜ出版点数を重ねる度に、
「なんで、こんなにまでして出版すんの?」
と悲しくなるような本を出すのでしょう。
すべて「バブル」という空気のせいだと思います。
このクラスの人にお金だけで動く人はいないと思います。
そうでなくてせっかく時代の流れがきて、要請があるのだから、
全力で応えようという気持ちなのだと思います。
けれどそれが結果、本の出来に影響を与え、
つまり質を落とし消費しつくされて、
著者本人にまで蝕んでいくことは、悲しくなります。
著者もそれが分からなくなってしまうほど、
「売れる」というのは怖い世界なのかも知れません。
遠藤店長の「心に残った本」より引用
私は初めて訪れる町の書店を必ずのぞいてみるようにしている。しかし、書店の平台がつらい。同じような自己啓発本が並ぶ。その啓発台からは独特のオーラ(意味不明にデカイPOPなど)が出ているのでそこら辺には行かないし視線も送らないようにしている。
書店の側がどう売ったら分からないという本を出している、というのが現代出版をめぐる状況のようだ。
内田樹さんは「ウチダバブルの崩壊」という記事の中で、自分の名前があがっていないにも関わらず自分の著作を塩漬けにすると書いておられた。さすがだ。
茂木健一郎さんは、クオリア日記で、「客観的な立場から見ると、ある時期、特定の著者の本がたくさん出て、それが潮が引くように消えていくように見えるのかもしれないけれども、著者、編集者の側からすれば、一冊一冊を誠心誠意作っているだけのことである」と書いておられる。なるほど、そう答えるだろうという答えだ。しかし雑で字が大きくなっているという具体的な批判に対して具体的な反論をされていないのが残念。http://kenmogi.cocolog-nifty.com/
勝間和代さんがこれに対して反論しているのは私には見つけられなかった。その代わりに、昔の記事で、再現性のあるベストセラーづくりの条件を5つあげておられて、http://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/point_of_view/2007/11/5_b048.html
3. 出版社のPush以上に、市場からのPullが強いこと。
これは出版社の方、みんないいますが、売れない本は、どんなに広告しても売れないそうです。広告すると、これまでその本を知らない人に知らせることができるので大事なのですが、それでも、売れる本以外は広告をしても、ムダだそうです。
そして、市場からの引きが強いかどうかは、多くの場合、キャンペーンをしていない中小型書店でどのくらい、よく売れているかが鍵になるそうです。
確かに、勉強法も、お金は銀行に預けるなも、発売初期に、中小型店での品切れが相次ぎました。すなわち、宣伝をしていなくても、目利きが本屋で目にして手にとって、買っていく本かということが大事なのです。
この初速、特に中小型店での初速の売上は、とても大事です。市場での目利き力は侮れないものがあると、つくづく思います。
これは出版社の方、みんないいますが、売れない本は、どんなに広告しても売れないそうです。広告すると、これまでその本を知らない人に知らせることができるので大事なのですが、それでも、売れる本以外は広告をしても、ムダだそうです。
そして、市場からの引きが強いかどうかは、多くの場合、キャンペーンをしていない中小型書店でどのくらい、よく売れているかが鍵になるそうです。
確かに、勉強法も、お金は銀行に預けるなも、発売初期に、中小型店での品切れが相次ぎました。すなわち、宣伝をしていなくても、目利きが本屋で目にして手にとって、買っていく本かということが大事なのです。
この初速、特に中小型店での初速の売上は、とても大事です。市場での目利き力は侮れないものがあると、つくづく思います。
これは遠藤店長の意見に反するように思える。遠藤店長は、ムダ本がダラダラと書店に送られてきて、どう売っていいか分からないと言う。勝間氏は、わたしの本はとても良い本だから宣伝しなくても、書店に置いておけば、目利きが勝手に買って行ってくれると言っているように読める。なるほどね。
うむ。何が正しいとか正しくないとか、私のような下賤な者が言うことじゃない。しかし何が好きで何が好きじゃないということぐらいは言ってもいいだろう。だから嫌なモノは嫌なのだ。
ふぅ。似合わない真面目な話は疲れるな。では、また。
「あんじゅう 三島屋変調百物語事続」宮部みゆき 中央公論社 2010年 (初出読売新聞の連載)
江戸の不思議話を聞いてくれる。あのおちかが帰ってきた。相変わらずの三島屋の面々たち。「おそろし」に続いて、どんな話が飛び出してくるか。
さすが宮部みゆき。話の出しどころ、最後の収め方、途中の流れ、全てがうまい。いかにも宮部みゆきらしい、人情の絡め方もにくい。
これは読んで文句言う人が少ない作品だなーと思った。イラストがかわいいと思ったら南伸坊さんだった。なるほど。
うーむ。こんなんでレビューとしてOKなのかと言えば、後で自分が見返す用の備忘録としてすらOKではないだろう。ましてや人様に読んでいただくものとしては・・・
しかしながら現在、今年で一番疲れてるってぐらい疲れているのでこれ以上書くちからが残っていない。ので失礼いたす。すまぬすまぬ。めんごめんご。
 | あんじゅう―三島屋変調百物語事続宮部 みゆき中央公論新社このアイテムの詳細を見る |

このようなプレゼントを頂戴した。
スヌーピーじゃなくてチャーリー・ブラウンというところがいい。
Wikipediaを読んでいたら、スヌーピーはコンタクトレンズをはめているそうだ。へぇ。
「悪の教典」(上下)貴志祐介 文藝春秋社 2010年(初出別冊文藝春秋)
町田の高校の英語教師蓮実は生徒の人気者。授業をこなし、叱るべきは叱り、生徒の面倒見もよく、同じ高校の暴力教師ともやる気がないでもしか教師とも一線を画している。担任を受け持っている2年4組で起こるいじめや暴力、カンニングにも懸命に手を尽くし、出来る教師として仕事をこなす。しかし、何かがおかしい。蓮実は妙に心理テストに詳しい。蓮実は妙に格闘技に詳しい。蓮実は妙に策士である。その違和感が・・・
いやいやいや。うまい。上下巻と分厚いのにあっと言う間に読み終えてしまった。学校+サイコ=好きな人にはたまらないし、そうでない人には嫌悪感でいっぱいになるような作品となった。
全部で12章ある。第10章はちょっとどうなのかなと思った。それと散弾銃はちょっとなとも。しかしそれ以外、少しずつ明らかになる蓮実の過去とその描き方、用意周到な様など実に読ませる。11章と終章の終わらせ方は悪くない。
映像化されることを強く意識したような書き方も小説というより、脚本に近いように感じた。描写が細かい割りに、それってどうなのよ?というツッコミを入れたくなる。それが物語の瑕疵であるとは考えずに、全体として楽しめればよいのではないかと思いながら読んでいた。サイコとサイコパスは違うという台詞が出てくるが、まさにその違いを味わうことができる、と言ったら変な褒め方になるだろうか。
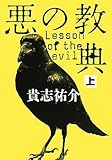 | 悪の教典 上貴志 祐介文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
 | 悪の教典 下貴志 祐介文藝春秋このアイテムの詳細を見る |























