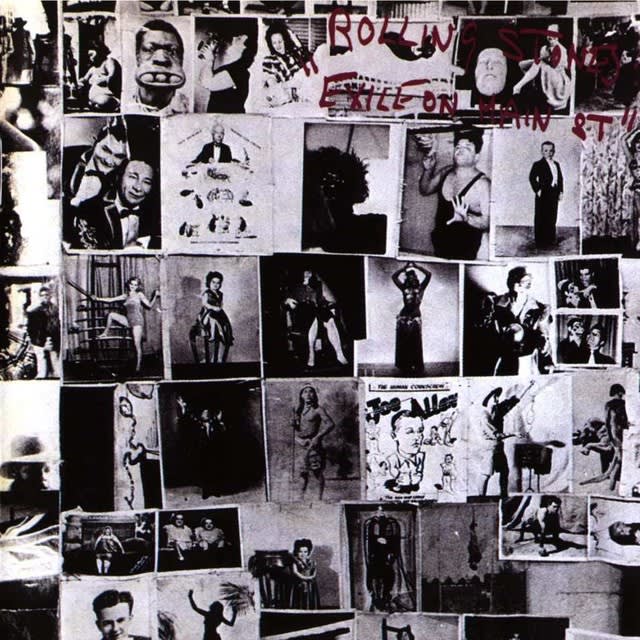イジドール・デュカスの『マルドロールの歌』は、最終第6歌に出てくる「解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会いのように(美しい)」という一節によって有名であり、それがシュルレアリスムの先駆的な表現とみなされたのだったが、この部分の全体を読めば、それが奇態な直喩の連続の中にあって、最後のとどめを刺す役割を果たしていることが理解される。こうである。
「彼は美しい、猛禽類の爪の伸縮性のように。あるいはまた、後頸部の柔らかい部分の傷口における、筋肉の動きの不確かさのように。あるいはむしろ、捕獲された鼠によって絶えず仕掛け直されるので、この齧歯目の動物を自動的に際限なく捕らえることができ、藁の下に隠されていても機能できる、あの永久鼠捕り器のように。そしてとりわけ、解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会いのように!」
ここに見られる直喩の連投は、マルドロールの犠牲となる14歳と4か月の少年メルヴィンヌの美しさを形容しているのだが、人間の美しさとは全くかけ離れた、それどころか美しさ一般とは何の共通項もない比喩が執拗に積み重ねられ、比喩するものは比喩されるものからどんどん離れていく。そして「解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会い」というイメージが、少年美の概念を揺さぶりながら、comme(のように)という統辞によって着地に至るのである。
直喩の連投は、この一節に極まっているが、奇態な直喩は『マルドロールの歌』の第1歌から第6歌までの至るところに仕掛けられている。たとえば、次のような第4歌の直喩を読んでみよう。
「しかしただちに夢のことに移るとしよう、こらえ性のない連中が、この種の話が読みたくてじりじりするあまり、妊娠した雌をめぐってたがいに喧嘩する巨頭マッコウクジラの群のように吠えはじめるといけないからな。」
この直喩は情景に対する比喩として使われているのではなく、マルドロールがこれから変身の夢を語ろうとしているのに、いつまでもじらされて待ちきれない読者の苛立ちに対する比喩として使われている。一般的に直喩は人間の五感に与えられる情報を形容するために、それに直接関係しなくても、似たような情報を持ったものを持ち出してくることによって成立するが、ここではそうした一般的な慎みの範疇は越えられている。あらゆるものが直喩の対象となり、ありとあらゆるイメージが直喩のために駆り出されてくる。『マルドロールの歌』の基調はそうした直喩の上に成り立っている。いや、直喩だけでなく隠喩もまた直喩と共同して『マルドロールの歌』の独特の世界を形成していくのだが、隠喩についてはもう少し後で分析することにしよう。
では、『パラディーソ』におけるレサマ=リマの直喩の使い方を見て行くことにしよう。