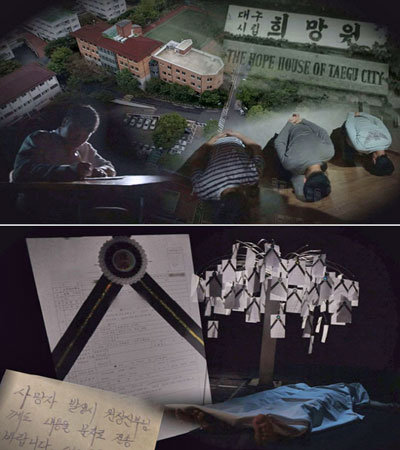“ネガティブすぎるイケメンモデル”のキャッチコピーでブレイクした、モデルの栗原類さん。今月発売の新著『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由』では、自身の発達障害に向き合ったことで注目されている。
インタビュー前編では、ADD(注意欠陥障害)の告知・受容、アメリカと日本での支援体制の違いについて語っていただいたが、今回の後編では、過去のイジメ体験や、周囲から受けてきた支援を振り返りつつ、発達障害者特有の生きづらさを解消するためにはどうしたらよいかを伺った。
* * *
―「自分に興味がない」と言われていましたが、それはどういう意味でしょうか?
栗原 自分に興味がないというか、自分を認識できてなかったんです。僕は自分の内面の変化に注意を払って、意識を向け続けるのが難しいので、自分自身について認識できるようになったのは中学生くらいでしたね。自分に興味が湧かないのと同時に、他人に興味を持つのも難しいんです。
発達障害者はよく「空気が読めない」と言われますが、僕の場合は、相手の表情を見て、何を表現しているのかを読み取ることも苦手です。母と一緒に映画やドラマを観ている際に「このシーンはこういう気持ちを表しているんだよ」といちいち解説してもらわないと理解できない。他のことでも、母が何度も繰り返し指摘してくれて、ここ最近やっと「ああ、自分自身はここが問題なのか」って自覚できるようになったことがたくさんあります。
―お母様の泉さんの手記からは、日常生活でもかなり細部にわたってフォローされていたのがうかがえます。
栗原 母はよく「人生はマラソン、長い目で見守るのが大事」と言います。子育てでは、よく「1歳でもう歩けた」「○歳で言葉がしゃべれた」と、他の子供より早めに成長できることがよしとされがちですが、こういったことは焦らなくてもいずれはできるようになることだと。母は、「今すぐできなくてもいい、いずれできるようになればいい」という考え方だったんです。だから「どうして○○くんみたいにできないの」と、他の子供と比べて叱られたことは一度もありません。
―ちなみに栗原さんがADDの診断を受けた際に、泉さんも「あなたも典型的なADHD(注意欠陥・多動性障害)ですね」と診断されたそうですが。
栗原 本書でも母自身が書いているのですが、母の場合は、大人になるまで自分が発達障害って知らなくて、何度も失敗を重ねながら、健常者に追い付く努力を必死にしてきたそうです。だからこそ、僕には情緒面での基本をきちんと教えてあげたいという一心で、丁寧に説明してくれたようです。
―その手記からも、アメリカでは発達障害への支援が充実しているのに比べて、日本は未だに発達障害への理解が進んでおらず、“母親への風当たりが強い”ことが伝わってきます。
栗原 日本の発達障害への支援体制はアメリカの40年遅れと言われます。アメリカでは「発達障害児には、継続して支援をする義務がある」という考え方なので、親子ともどもサポートするのが当たり前でした。一方、日本では、支援が必要な子供でも見過ごされてしまう場合が多い印象です。
―見過ごされやすい、とは?
栗原 例えばですが、多動性が顕著で授業中に立ち歩いてしまうような子供は、教室でも目立つので気付かれやすい。でも僕のように目立った問題行動がない受動的なタイプの子供は放置されやすいんです。確かに僕は授業中、おとなしく座っていることはできましたが、先生の話を聞いても全く頭に入っていませんでしたから。なんらかの支援は必要でした。
―日本では、目に見える問題行動がなければ見逃され、放置されてしまうのが現状だと?
栗原 実は、小学生の頃から僕をイジメていた子供が、まさに発達障害を放置されていたコだったんです。
―主治医の高橋猛医師の手記に出てくる、多動性が強くて、明らかにADHDの可能性が高かったと書かれているコですね。
栗原 だから、高橋先生に「僕自身は早期に発達障害の診断を受けて、支援を受けて改善する環境にいる。それなのに、彼は発達障害を見過ごされて、なんの支援も受けないまま放置されているのはおかしい」って訴えたんですが、彼は結局、最後まで診断を受けないままでしたね。おかげで、僕は理不尽なイジメに耐えるしかなかったんです。
―その結果、一時期は不登校になったとか。
栗原 ええ、学校に行けなくて2週間くらい休んだこともあります。特に小学校5年生から中学校3年間は本当に地獄のような日々でした。普通の人が青春を楽しんでいる時期に、僕は「青春なんてクソくらえ!」と思いながら、サンドバックのように、ひたすら言葉の暴力に耐えていました。
―学校の教師は何も対処してくれなかったんですか?
栗原 日本の先生は何もしてくれませんでしたね。アメリカでは「生徒に問題が起きたら、先生はそれを解決する義務がある」という考え方なので、生徒同士でトラブルがあると、初期段階ですぐに先生が介入します。だけど日本では、先生にイジメを報告しても介入してくれない、「チクってるんじゃねーよ」となって、余計ひどくなるパターンが多いです。
―前述のイジメっ子のように、発達障害を見過ごされたまま成人する人も少なくないと思いますが、成人後でも診断を受けるべきと?
栗原 よく“診断されるのが怖い”とか“レッテル貼りになる”という声も聞きますが、僕自身は早期診断・支援の重要性を、身をもって実感しましたし、診断を受けないことには支援のスタート地点に立てません。少しでも「自分も発達障害なのかな?」って思うのだったら、まずは一度、医師の診断を受けたほうがいいのではないでしょうか。
―もっとも、診断を受けたからといって、職場や学校で理解が得られずに苦労している人もいます。ご自身はどのような考えで今のお仕事を選ばれたのですか?
栗原 そもそも僕は「会社員とか絶対無理」と思っていたんです。毎日同じ職場・人間関係の中でルーティーンを続けるのは、僕にとって苦痛でしかないですから。でも、芸能界は毎回違う現場に行って、違う人と会えて、程良い刺激が得られる。ぶっちゃけ、僕はこの業界でしかやっていけないんです。でも、だからこそ、どんなことがあっても今の仕事は続けたいですね。
―仕事面では、配慮をしてもらっているんですか?
栗原 実は以前、映画や舞台など、同時進行でお芝居の仕事を受けたことがあったのですが、僕はとにかく刺激に疲れやすいので、完全に容量オーバーに陥った結果、パニックになってありえないミスをしたことがあって。そういう状態になってから初めて、マネージャーも理解してくれたんです。それからは、お芝居の仕事をする時には、その時期にはその1本しかお芝居の仕事を入れない等、僕の許容範囲を超えないようにスケジュールを調整してくれるようになり、ずいぶん働きやすくなりました。
―最初から完璧に理解してくれたわけではなく、お互いに失敗や経験を重ねて…。
栗原 正直、最初の頃は自分の障害について説明して、弱点をさらけ出すことに抵抗もありましたけど、でも最近では「恥ずかしいからと隠すほうが恥ずかしい」と思えるようになりました。もちろん、いくら説明しても全員が全員、理解してくれるわけではありません。今でも時々「発達障害を言い訳にしている」「甘えだ」と言ってくる人もいますが、そんな声は無視すればいいんです。僕のような、パっと見でわかりにくい、“見えない”障害の当事者は、自分から周囲に理解を求めていく努力が必要なのだと思います。
―しかし、“できないことは無理にやらなくていい”ということになると、本人の可能性を奪ってしまうのではないか?という考え方もあるようですが。
栗原 僕は、自分の発達障害については、どんなに努力しても100%克服できるものではないと捉えていますし、大人になった今でもできないことはたくさんあるので、周囲にサポートを求めることは決して悪いことではないと考えています。
とはいえ、発達障害だから大目に見てもらおうというわけではないですよ。生活面や仕事面では、苦手なことであっても最低限はできるようになったほうがいい。無理がない範囲で少しずつチャレンジして、できることを増やしていくのがいいと思います。
―少しずつ挑戦して、諦めずに続けていくのが大切だと。
栗原 例えばですが、僕は手先が不器用なので洗濯物を畳むのも苦手で、Tシャツを5枚畳むだだけで疲れてしまったり、リサイクル用に牛乳パックをハサミで切り開くのも本当にできなくて「うう~~」ってなったりしていました。でも何十回、何百回と繰り返していたら、だんだんできるようになってきたんです。
だから10年前に比べたら、少しずつですが、できることは確実に増えています。発達障害者がどこまでできて、どこまでができないのか、見極めが難しいところですが、相性のよい主治医などを見つけて、家族や友人以外の視点から客観的にアドバイスしてくれる専門家の力を借りて、訓練していくのがよいのではないでしょうか?
―今回、本書を執筆されたことで、改めて気付いたことも多かったんでしょうか?
栗原 実は、前述のように僕は自分に興味がなかったので、子供の頃の出来事をほとんど覚えていなくて、本の完成が危ぶまれたほどだったんですよ。周囲の人からいろいろ話を聞いて、なんとか思い出して書けたんです。
今回、誰かに伝えるために文章を書いたことで、自分でも新たな発見がたくさんありました。本を書き終えた今、やっと自分自身に向き合えた気がします。今振り返ってみても、早期に適切な対応をしてもらえたのは本当にありがたかったですし、イジメでつらかった時期も、心から信頼できる友達や主治医の高橋先生、母の存在があったからこそ乗り越えられたと思います。
今だって、普通の21歳が100できることを、僕は10しかできないですが、環境を調整し、周囲の力を借りて訓練すれば、対処法を見つけることができますし、発達障害の生きづらさは、必ず解消できるものだと思います。
―まさにタイトル通り、『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由』ですね。本書では、過去4回におよぶ失恋話なども赤裸々に書かれていますが、将来のこと、特に結婚や仕事については、どう考えていますか?
栗原 僕は先のことを見通して、ゴールを設定するのが苦手なので、40年後の未来とか聞かれたって全くわかりません。今の仕事をずっと続けて、ゆくゆくは市村正親さんやクリストファー・ウォーケンのように、60歳を越えても芝居に対して貪欲な生き方をしていたいですし、観た人の心に爪痕(あと)を残せるような印象的な役者になりたい。
僕だって、いずれは結婚とか考えなくもないですが、人生は長いですから、あまり「○歳までにこうする!」とか前のめりにならずに、とりあえず「30代頃には仕事を安定させられたらいいな~」くらいのスタンスでいます。
―お話を伺うと、全然、ネガティブじゃないですね(笑)!
栗原 だから、僕自身は自分のことを「ネガティブ」だなんて言ったことは一度もないですよ。もう慣れましたけど、今でもそう言われるのはあまり好きじゃないです(笑)。
2016年10月16日 週プレNEWS