黒井千次著『老いのかたち』中公新書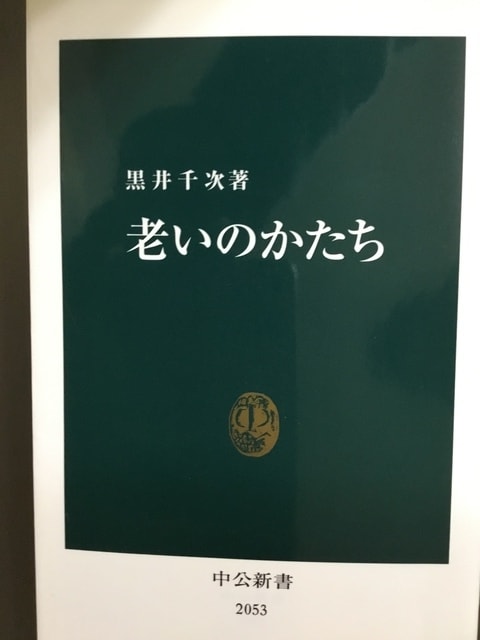
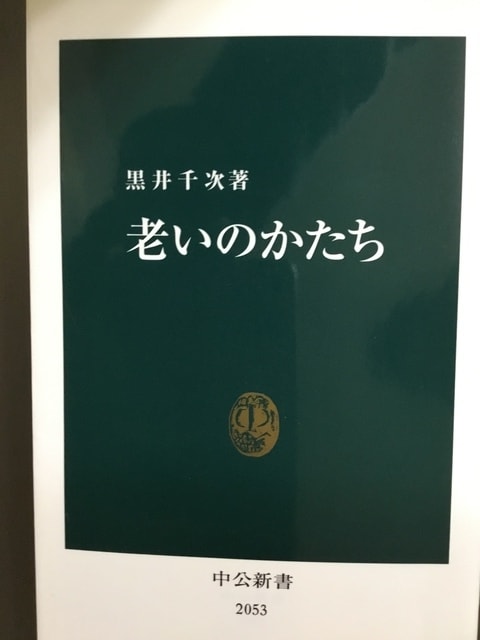
昭和一桁生まれの作家が、自らの日常を通して、〈現代の老いの姿〉を綴るエッセイ集(カバー書きより)
老いをどうかたちつくっていくかは、ひとそれぞれなのかもしれない。
自分の眼に映る「老いの光影」は、光の部分と影の部分がある。
老いて往くと、物忘れや記憶が抜け落ちて往く。
流石作家の表現だなと感じてしまった。
手から落ちた物は、幾度でも拾えばいいが、記憶の指先から消えたものは取り戻すのが難しい。(47頁)
老いてからの齢を重ねていく一年は、時間の中に命の影を覗き込もうとするような静けさが孕んでいる(113頁)
老いの齢を重ねていく一年は、樹木で言えば年輪であり、
顔に刻み込まれた深い皺は、年輪のようでもある。
90の齢を越え、また一つ齢を重ねるたびに、「お迎えはまだ来ないのか」、と死を言葉にしながらも
歩行器につかまり家の近くに在る内科クリニックを受診している98歳の婆さんがいる。
他者の老いの光影を通し、また感じながら、
自分自身の《老いのかたち》をどう創っていくのか
考えさせられた新書であった。





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます