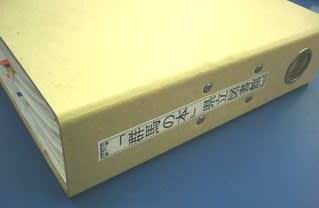そこで、タイミングは少し遅いかもしれませんが、うちも経営の4分の1を教科書に依存している店なので、教科書のデジタル化、電子ブックへの移行の見通しについての問題を私なりにこの機会に整理してみたいと思います。
1、現在、すでに起きている変化
すでに紹介されていますが、今年アメリカで高校の教科書にアマゾンが開発した読書端末キンドルが導入されました。
アメリカの場合、教科書版元の独占が進んでいるので、今回導入した大手三社で全体の教科書市場の6割を占めると言われます。
このニュースは、日本でも衝撃的に伝えられましたが、にもかかわらずまだキンドルは英語版しか出ていないことや、日本のメーカーが過去、電子ブックで失敗していることなどから、日本で同様な変化が起きるのはまだ先のことになるかの憶測もされています。
しかし、以下の項目で説明するような理由で、すぐではないといっても、それは決して遠い先のことでなく近いうちに必ず起きる変化であることも間違いがないのではないかと思います。
電子ブックというかたちではなくとも、すでに教材のなかには印刷製本せず、ダウンロード版のみというものも出だしています。
それと見過ごせないのは、教科書問題とはまったく別次元で実際の教科書取り扱い店が経営難に陥り、その業務を受け継ぐ場所がなくなる問題が多発している現実もあります。
今、扱っている書店の延命・保護も大事ですが、外部からみると衰退しつづける教科書取り扱い店の延命を考えることよりも、「既得権にしがみついている業者」は、これを機会に整理してしまおうとの意見も時代の流れからすると無視できないものがあります。
取り扱い書店と教科書取次ぎを除くすべての業界関係者が、教育現場、子供と父兄、版元などどの立場からもデジタル化することの方がメリットがあるとデジタルアレルギーの精神的な抵抗感以外は、世論の多くがまとまってしまう流れは否めないのではないでしょうか。
2、デジタル化の持つ意味への根深い誤解
それでも、紙の良さはデジタルに変えられるものではないという意見は、教育現場でも根強く存在し続けます。
事実、デジタル化が進めば進むほど紙ならではの良さの再評価も高まることも間違いありません。
しかし、受験勉強などの学習方法の効率を問う分野ほど、その差は歴然と開いていきます。
デジタル化とは、ただ紙の情報をデジタルに置き換えたコンパクトで便利なものということではありません。
学習の方法が革命的といっても良いほど大きく変わるのです。
既に電子辞書の普及は、英語学習において先生以上に正確なネイティブの発音で単語にとどまらず例文や問題まで生徒がいつでも聞ける環境になりました。
昔の「アイ、キャノット、スピーク、イングリッシュ」などという先生はもう生徒からも相手にされない時代なのです。
こうした音声機能とともに、画像表現や画面の拡大縮小機能、情報のリンク、ジャンプ機能、快適な操作性などの進歩にはこの数年を見ても目覚しいものがありますが、これらは今後日々さらなる進化を遂げていくものです。
紙の良さはあります。またそれゆえに残るものもあります。
しかしそれは、高価な特殊付加価値商品ということです。
圧倒的部分は、デジタル化することで、経済的でエコでもあるゆえに多くの人が恩恵を受けることができます。
3、出版社側の事情
日本では光村教育図書が、デジタル教科書の開発をすでにすすめて商品化していますが、そうした開発を急ぐ最大の理由は、出版社自身の延命策としてなによりも有効であるからです。
児童数の減少により市場そのものが縮小し続けるだけでなく、大判教科書の比率が増たり、カラー刷りページもどんどん増えていながら、 定価は簡単に上げることの出来ない今のままでは、出版社の自助努力の範囲ではとても対応しきれない現実があります。
そこに紙の印刷と製本、物流のコストを省けるデジタル教科書は、版権製作料部分の純利益比率を上げても、 最終商品価格を下げられる競争力をつけられる有望な商品になります。
これまで長い歴史のあるつきあいをしてきた書店に対して冷酷な発言をすることはできない立場ですが、こうした事情をみると出版社がたやすく書店を擁護できるわけではありません。
4、ハードメーカー側の事情
電子ブックは、かつていくつかの日本メーカーが参入しながら失敗に終わった苦い経験がありますが、amazonのキンドルがアメリカで急速に普及したことで、完全に仕切りなおしがされたといえます。
これまで普及の障害になってしたのは、
1、コンテンツの絶対量不足
2、液晶画面の見にくさ
3、バッテリー寿命
などがありましたが、すでにこれらの問題はどれも日本メーカーはその気になれば十分解決できる時代に入っています。
さらに決定的なのは、電子辞書の普及で経験したことですが、児童・生徒へのこうしたハードの普及は、一般市場のヒット商品を産むことよりもはるかに「大きな市場に化ける」ということです。
小中高の全校採用ともなれば、電子辞書とは比べものにならないほどの大きな需要が、一気に見込めるのです。
このことに気づいたメーカーが、文部科学省、教育委員会をはじめとした教育機関に相当な営業をかけることは間違いありません。
そして児童・生徒のそうしたデバイスの利便性を体験させたならば、さらに社会人への需要開拓の大きな布石になることも期待できます。
パソコンメーカーと、カシオやシャープなどが競って、これからamazonやMacの商品と開発を競いあう時代がはじまっています。
5、文部科学省、教育委員会など行政の対応
一般にこれらの問題に対して行政は、保守的である場合が多いものですが、上記のような環境から各メーカーが競って営業をかけることが予想され、一部の先進的行政マンやその長がそれに気づけば一気に様相が変わります。
本来であれば、教育現場でどのように活用されるべきか、しっかりとした現場との協議を経て決定されるべき問題ですが、過去のこうした問題の経緯から推測すると、トップダウン式にある日突然その決定がなされることもおおいにありえます。
これはどのような可能性があるか推論の精度を争うよりも、まず、最悪の事態にいち早くそなえることを優先することが求められます。
5、当面の予測
次回の教科書改訂は、すでに目前になってしまうので当然間に合わないと思いますが(ヘタをするとそれも・・・)、おそらくアメリカほど教科書会社の独占は進んでいないので急激でなないかもしれませんが、まず高校の進学校からデジタル教科書の普及がはじまることと予想されます。
既に電子辞書の普及率が有名進学校ほぼ100%に近い実態になっていることから、受験校であれば、デジタル化によるメリット、学習効率の違いに真っ先に注目すると思います。
その次に他の高等学校や中学校が続くと考えるのが自然ですが、この段階になると、もしかしたら徐々にということではなく、文部科学省などの行政判断によって、ある日突然、全国一斉にということも十分考えられます。
教科書のデジタル化が実施される前に、様々な教材類がデジタル化され、その利便性などが現場に実感されていくことと思います。
これが次の次の教科書改訂時期、つまり5年後までの間に大勢の流れは決まるのではないかと思います。
運良くか悪くか、最も長引くことを予想しても10年(2回の改定機会の範囲)はかからない話なのではないでしょうか。
教科書デジタル化のゆくえと展望 その2
教科書デジタル化のゆくえと展望 その3
補足 デジタル技術への抵抗感について
モノの記憶