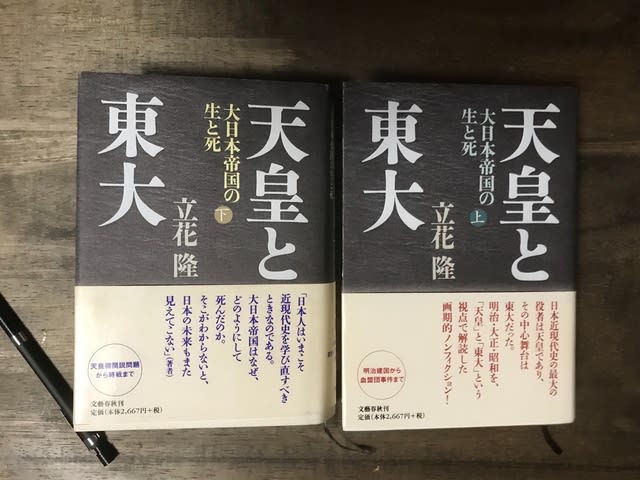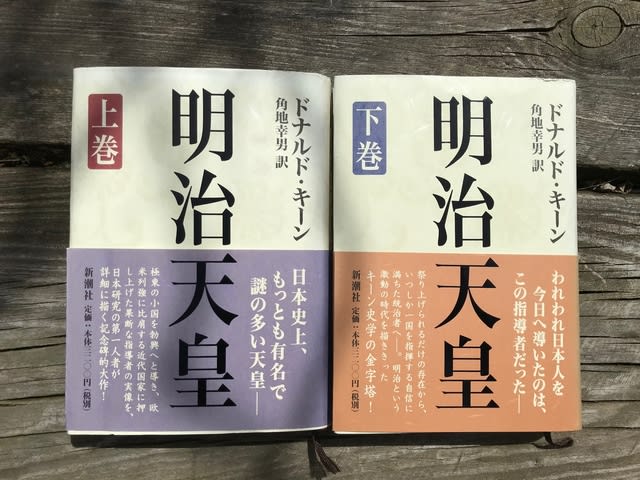WEB上で取り上げるのは、とても勇気のいるテーマです。
「国体」の定義ってなに?
最近、とてもお世話になっているKさんが、SNSのあるリレー企画のなかで、『国体の本義・精解』三浦藤作(昭和12年初版15年110版!)という本を紹介していました。
そこで、チャットで
「国体って、文脈としてはなんの疑問もないほど普通に使われるけど、明確な定義ってどこかに書いてあるの?」
と聞いてみました。
すると、Kさん
「この本に、定義、歴史、意義、特色などなど全て記述されています。
古事記から神皇正統記などに至る経緯、まあ、基本は水戸学なんですが、このその思想としては、体系的になってますね。北一輝もそうだけど、昭和の国家主義的右翼は、基本、マルクス主義の影響が強く、目指す理想は、ソ連型、北朝鮮型社会主義国家ですな。」
(私)古事記から神皇正統記などに至る経緯、まあ、基本は水戸学とかの説明はわかるのですが、たとえば、極東軍事裁判がまともな裁判になったと仮定して、日本側弁護団が真面目に裁判に勝つことを目標にして判事側に理解できるように戦争の大義を「国体」から説明するとしたら・・・
(Kさん)東京裁判の日本側主張は基本、資源確保の防衛戦、植民地解放、有色人種への差別解消、みたいなところじゃないかな。その場合、日本は普通の国民国家で、普通に国際法にあるような戦争しました、別に特殊な国じゃないよ、という立場だったと思う。
といったやり取りがその後も続き、結局、この対話は結論には至らずに終わりました。
私のなかでは、「国体」について皇統のことや思想背景だとかいろいろ説明はできるだろうけれども、外国人にも理解できる「国体」の定義とはどのようなものなのだろうかということがその時はどうしてもわからなかったのです。
その後ひとりで長い間、悶々と頭のなかを整理していたら、次第に次のようなイメージが浮かんできました。
通常、国家は「国民の生命と財産を守る」ために存在するものと思いますが、それに対して「国体」は、「国民の生命と財産を犠牲にしてでも守るものがあるとするなんらかの価値の体系」と言えるのではないかと思えました。
そのためには、国家や軍隊どころか町内会までもが動員されていったわけです。
「国体」という表現を外国語ではなんと翻訳するのか知りませんが、誰もがこれは日本独特の国家観に由来するものと考えていると思います。しかし、だからといって皇統の継続性や水戸学由来の説明だけでは、戦時中の特別な「国体」像と、それ以外の古代以来の長く様々な変節を経てきた天皇制や国体概念の明確な説明にはなっていない気がしてなりません。
それだけに、外人に対して明確な説明表現が求められると思うのですが、不幸なことに同じ敗戦国でも、戦前と戦後の歴史観のドイツやイタリアと日本では以下のような相違があります。
日本だけが戦時の政体が継続
ドイツで終戦協定を結んだのは、敗戦したナチ政権ではありません。
イタリアもムッソリーニではありません。
新しいところでは、アフガニスタンもタリバンではありません。
イラクもフセイン政権ではありません。
日本だけが、戦中から敗戦後へ政権、国家体制の継続性があったわけです。しかも、明確な政権交代があったわけでもありません。
もちろん、大日本帝国憲法は廃され、国民主権と象徴天皇の戦後憲法に変わり、戦犯の処刑も行われましたが、その他の政治指導者たちの多くはそのままで、「政体」そのものは継続しました。
これは、必ずしも日本側の意向が強く働いたことによるわけではありません。
圧倒的理由は、占領軍、マッカーサー側の意向です。
占領軍側からすれば、カミカゼ、玉砕突撃などを繰り返した日本軍が、占領後もゲリラなどの反乱なく統治することは、マッカーサーが厚木に到着するまで容易でないと想像されていたからです。
加えてGHQ側も日本の占領統治が、ドイツのような直接統治ではなく間接統治であったことも忘れてはなりません。
陸軍省、海軍省、軍需省のような軍需面の中央行政機関はすぐに解体されましたが、大蔵省、文部省、内務省などの中枢行政省は継続しています。これが、「戦後日本」を語るときの日本独特のわかりにくさを生んでいるのではないかと思います。
それだけに、この問題は時の政権政府以上に、戦時の重い責任を負っていた天皇ただ一人が一貫して最も明確に深く自覚して戦前のそれとを区別しようとしているのを感じます。
当事者であった昭和天皇を筆頭に、平成天皇しかり。
(令和天皇はまだよくわかりませんが、おそらく平成天皇の姿勢を受け継がれていることと思います)
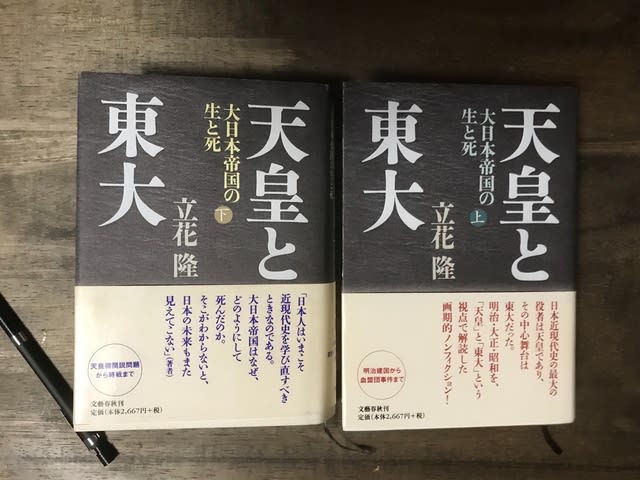
継続したからこその天皇のこだわり
戦後の象徴天皇という立場は、ただ国民統合の象徴という意味だけでなく、
自らの身体が、いかなることがあっても戦前のように「国民の生命・財産を守る」ことより優位の立場に置かれてはならない、という点にこそ力点がおかれていると思われます。
このことが、戦後天皇の言葉のひとつひとつ、行為のひとつひとつに強くあらわれているのを感じます。
「象徴天皇」として憲法に特別な立場として位置づけられ、国民から広く尊敬され敬われている存在であるけれども、いかなることがあってもそれは「国民の生命・財産を犠牲にして」まで守られるようなものではないということです。
戦後天皇のゆるぎないこの姿勢こそが、世界に例をみない「皇統」や権威などのことよりも、国民の心からの敬意を生んでいるものと思います。
私は、戦後天皇が沖縄、広島、長崎をはじめとして、硫黄島、サイパンなど激戦地への慰霊、訪問を続けていること、自らの体調がすぐれない時でも各種災害時の被災者へのお見舞いを優先していること、1975年を最後に靖国神社を訪れなくなったことや、それぞれの場で簡潔に話される言葉すべてにそれを感じます。
他方、宮中祭祀は、戦前戦後とも何も変わること無く継続性を持って行われています。
「天皇が統治権の総覧者から象徴へと憲法の上では変わったわけですが、言葉が変わっただけで、本質はそんなに変わったわけではない。陛下は同じですよ。」(『侍従長の遺言』朝日新聞社 1997)との見方も歴然とあります。
このお堀の内側の継続性とお堀の外側の変容については後ほど触れます。
個人的に私は、制度としての天皇制には必ずしもすべて同意できるものではありません。
むしろ戦後、何らかの責任を昭和天皇が負ってけじめをつける方法もあったのではないかとさえ思います。
それは、東京裁判の場に立つかどうかより、たとえば中世の天皇がしたように自ら出家するとか、退位するとかの選択肢はあったのではないかといったイメージです。
事実、昭和天皇自身、退位することを考えて口にもしていました。
最後の1年に犠牲者が集中した責任
戦争責任ということでは、開戦責任、継続責任、敗戦責任、人道的責任などいろいろありますが、国体という問題を議論するうえでは、以下の1944年から終戦に至る最後の1年間の問題を強調しなければなりません。
1944年6月のマリアナ沖海戦以後に日本人は、なんと200万人が死んでいます。
第二次世界大戦の死者の3分の2近くが最後の一年で亡くなっているのです。
しかも戦死者の6割は、餓死・戦病死です。
もともと、短期戦でなければ勝てる見込みはほとんどないことを軍部も認めていた戦争が、グアム、サイパン、テニアンを落とした時点で制空権、制海権ともに失い、軍事的に勝てる見込みはほぼゼロになっていました。にもかかわらず、止めることを考えずに200万人が死んでしまっているのです。
1944年 6月15日:米軍サイパン島上陸、日本軍7月7日玉砕
6月19日:マリアナ沖海戦に日本敗れ西太平洋に制空権・制海権を喪失
7月4日:日本、インパール作戦中止
8月2日:テニアン島の日本軍玉砕
8月11日:グアム島の日本軍玉砕
戦略的に勝てる見込みが立たないのに戦争を継続して、異常な死者を出し続けてしまった原因は、指導部から現場に至まで「国体」の概念が大きく意思決定に影響していたことは否めないと思います。
確かに日本政府内部でも、終戦への努力はされていました。
原爆投下後、8月15日に至る数日間の攻防ですら、関係者は誰もが命がけであったことからも、1年前の時点で終戦の決断を遂行することがどれだけ困難なことであったかは、容易に想像できます。
でも、だから仕方がなかった、と言えるでしょうか。
もちろん、仮に日本が早く白旗をあげたとしても、アメリカの中枢部は原爆を使用することこそが最優先目的であったため、広島、長崎に原爆を落とすまで日本の降伏は認めなかった可能性が高かったとは思います。
だからこそ、手が打てなくなってしまう前に、一人ひとりが、責任を負う者としての決断と行動の積み重ねのあり方が大事だと思うのです。ここに昭和天皇の戦争責任につながる重い問題もあります。
しかしアメリカ側からしても、日本に武装解除を徹底できるのは「天皇」しかいないことはわかっていました。また占領政策をスムーズにすすめるためにも、天皇の存在は必要であると認識していました。
GHQの意向もありましたが、「象徴天皇」というかたちでの継続性が前提にされたからこそ、天皇自身の中では、何を持って戦中の立場との区切りをつけるかということには、戦後の自らのあり方として厳格に一線を引くことを強く意識していたことと思われます。
それこそが、天皇制が継続されたとしても、そこに国民の生命・財産を犠牲にしてまで守るような優位な価値観があってはならないという立場へ、戦後の昭和天皇、平成天皇へ徐々に変化しながら明確化していった面であると言えます。
私もこの一点で、制度としての現行天皇制に同意できない部分があっても、戦後天皇の平和を願う姿勢や厳しい制約下の行動やお言葉には、100%の信頼と尊敬の念を持っていられるのです。
「国体」と「天皇制」は同じか?
このような意味で私は、戦前・戦後の天皇を通して見たときに、「国体」とは必ずしも「天皇制」とイコールではないといったようなイメージで考えていました。このブログ記事もここで終わる予定でした。
ところが、最近になって保阪正康さんの2018年の日本記者クラブでの講演をみて、「国体」「政体」といった分け方で戦前・戦後の日本史を見事に保阪さんが整理されているのを知り、我が意を得たりと思いつも、自分の考えが未整理であったことにも気づかされました。
「平成とは何だったのか」(1) ノンフィクション作家・保阪正康氏 2018.5.16
Masayasu Hosaka, Nonfiction Writer 「平成時代は、天皇、政治、災害の3つの組み合わせで語ることができる」...
youtube#video
この講演は、まったくメモも原稿も見ることなく理路整然と的確な事例をひきながら、保阪さんの歴史に対する強い思いを戦後に生きる私たち日本人に訴えるとても重要なものです。
保阪さんの講演では、以下のように語られています。
敗戦までは「政体」の上に「国体」がありました。
政治的になにかを決めたり行ったりすることは「国体」の下でのみ、自由であったわけです。
それが戦後になってからは、「国体」の上に「政体」は位置づけられ、「政体」は「国体」に左右されずに決めたり行うことができるようになりました。
しかしこの20年ほどの間に国は「国民の生命・財産を守る」という原則に、様々な理由で制限が付けることが多くなってきました。
「テロとの戦い、自由主義社会を守るための「世界」が行っている戦いに、日本だけが参加しない、またはお金を出すだけではすまされない」
「中国や北朝鮮の軍事的脅威が増すなか、日本の軍事予算やアメリカ軍駐留への思いやり予算の増額は避けられない」
「膨らむ国の財政赤字の現状を考えれば、高齢者の医療・福祉や教育予算の削減はやむを得ない」
もちろん現実は、様々なパワーバランス要因のなかで起きているので、どんなことがあっても無条件にすべて保証されるべきものではないかもしれません。
しかしGDP世界3位、対外純資産ではダントツの世界1位の日本が、なぜこうした理由で先進国最低レベルの教育・福祉・国民生活水準の国になってしまったのでしょうか。
「公共」のための「犠牲」?
こうした政治の動きに対して、保阪さんが指摘しているように天皇は極めて慎重に言葉を選びながら、かなり踏み込んだ言葉を発せられるようになってきています。
つまり、「国体」は「政体」の下にあることを自らに厳しく科す身でありながら、「政体」が間違った方向に進んでしまったときでも「国体」は「政体」の下のままでいられるのか、といった問題です。
国民の生命・財産を犠牲にしてでも守る何かが現れたとき、
それが「公共」という言葉でくるめられたとき、
私たちは十分に注意しなければなりません。
明治天皇、大正天皇が「創られた伝統」として一定の距離をおいた宮中祭祀が、昭和天皇以降はお堀の内側で厳格に守られ継続しています。そこで「政体」に関わることはありません。
他方、お堀の外側での天皇の戦没者慰霊や災害被災地訪問などの活動が増えるにしたがい、「政体」と無関係とは言えない領域が否応にも増えてきているのも紛れもありません。
このあたりを天皇は極めて慎重に、言葉も選びながら行動されています。
たしかに、子どもが危機に瀕したときに自らのいのちもかえりみずにわが子を守る母親のように、生命・財産を犠牲にしてでも守ることは、現実にはあることと思います。
でもそれは、あくまでも生命主体である個人が個人の価値判断で選択するものです、
他人によって、あるいは国家によって安易に強制されるものではありません。
でもそれが、やむをえずの選択であるとか、背に腹は替えられないなどといった言葉とともに出てくる場合は、特に要注意です。
いざ自分がその立場になったら、どれだけのことができるのかは確かにそれは私にもわかりません。
でもだからこそ、どうにもならない状況に追い込まれる前に10分の1でも、100分の1でも、日々の努力の積み重ねと自分の覚悟をもつように心がけたいと思うのです。
「生とはこれすべて、自己自身たるための戦いであり、努力である」 オルティガ
とかく誰もが目の前の問題に追われ、より大切なことを見失いがちなものですが、10年、100年、1000年というスパンでものごとをとらえ考えてくれる「天皇」という存在が、ひとりその道理を貫いていてくれるだけで、私たちが多少道を踏み外してもすぐに気づき戻ってこれる社会にいる幸せも感じています。
それは、国民が天皇にこうあってほしいと望むような筋合いのことではありません。
日本のなかで最も地位が上にある天皇自身が、自らが国民の生命財産を犠牲にしてまで守られるような地位ではないことを、その行為と姿によって示し続けてくれることが、私たちの尊敬と信頼をもたらすのだと思います。それは、公益を優先し、豊かな国民こそが国家の財産であると、安定成長と国際協調を願うの立場を示し続けてくれることです。
もちろん、なかには自分の命をかけてでも天皇を守りたいと純粋に思う人はいることと思います。でも、天皇自身は、そうあってはいけないのだよ、との姿勢を示してくれることが尊敬される由縁でもあると思います。
このような意味からもあらためて、世界標準の言葉で「国体」とは何かを説明するならば、中国や北朝鮮のように、国民の生命・財産・信条の自由を犠牲にしてでも守ろうとするなんらかの優位の価値を掲げた国家観であると言ってよいのではと私は確信します。 したがって「国体」と「天皇制」を同じとして語ることは、とてもできません。(もちろん保阪さんも、区別はされているでしょうが)
定義を語る場合、私は万世一系や皇統の継続などの説明も必要でしょうが、この一点こそが「国体」定義の核心であると思います。とりわけ、世界の中でも日本だけが戦時と戦後の間で、軍部の解体、戦犯の処刑、戦後憲法の制定以外、国家中枢にいた人間の大半に継続性がはかられた国であるだけに、とても大事なポイントであると思います。
天皇が天皇たる由縁はどこに
では、天皇が天皇たる由縁はどこにあるのでしょうか。
当然、皇統や三種の神器の問題になってきます。詳しいことは私の手に負えるようなことではありませんが、歴史的経緯では以下の点だけは押さえておきたいと思います。
1910年の国定教科書『尋常小学校日本歴史』の教師用教科書発行をきっかけに、いわゆる南北朝正閏(せいじゅん)論争が起こった。南北朝時代については南北朝を対等に扱い、両朝のうちどちらが正統かは論ずるべきでないとする執筆者の喜田貞吉に対して、11年、南朝正統論社から非難の声が上がり、桂太郎内閣が喜田を休職処分にして南朝正統の採用を閣議決定するとともに、南朝を正統とする勅裁まで下された。これにより南北朝時代は「吉野朝時代」と改められ、北朝の天皇の存在はいっさい認められなくなった。(略)
けれども、天皇家は南朝ではなく、北朝の血統を継いでいた。にもかかわらず南朝が正統とされたことで、天皇家は血統に代わる正統性の根拠を見出さなければならなくなった。そこで浮上してきたのが、1392年の南北朝合一のさい、南朝から北朝に譲り渡されたとされる「三種の神器」であった。
後に昭和天皇の侍従武官長となる本庄繁の35年3月29日の日記には、「自分の如きも北朝の血を引けるものにて」という天皇自身の言葉がある。それとともに、当時の宮内大臣であった湯浅倉平の次のような言葉が書き留められている。
御血統は南北何れにしても同一にして、只皇統は三種の神器を受け継がれたる処を正しとす、即ち北朝の天子が南朝の天子より神器が引嗣かれたる後は、其方を正統にせざるべからず。(『本庄日記』原書房 1989)
以上、原武史『昭和天皇』岩波新書 2008より
以降、「三種の神器」は「万世一系の皇統」を担保する神聖なものとなりました。

明治天皇の場合にしても、国体の根幹とみる伝統的祭祀に対して、後期水戸学の影響のもとに「創られた伝統」と見なしてどこか冷めた対応をしているのは、まだ東京を正式な首都と認めたくなかった背景があるばかりではなかったようにも見えます。
このように、それぞれの時代の天皇は、個々の置かれた環境やそれぞれの考えに応じて、単純に伝統や法規範だけに基づいて規程しきれるものではないと思います。
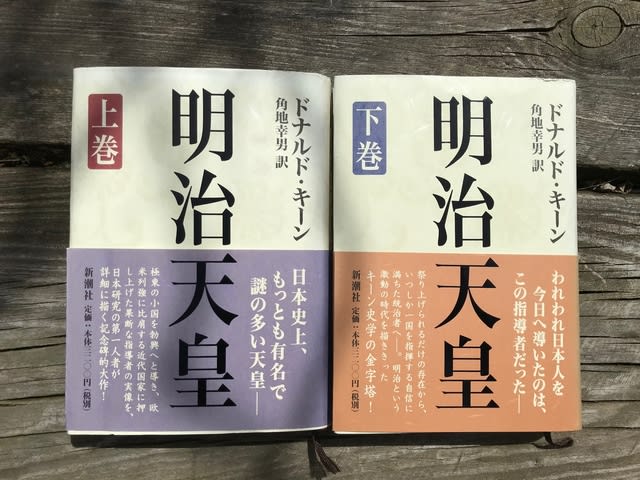
昭和天皇は、その当事者として時代とともに迷いながらも自らのとるべき立場を定めていきました。
平成天皇は、その昭和天皇の姿から多くを学び、美智子様とともに立派な姿勢を貫かれました。
令和の天皇は、まだ具体的な発言や行動から十分読み取ることはできませんが、平成天皇の姿勢をきちんと受け継がれ自らが現代のあるべき姿を模索し決断されていくことと思います。
天皇の立場は、憲法や皇室典範で明確に規定されているようでありながら、それぞれの時代によって、それぞれの立場によって変わらざるを得ない面、違う面が自ずとあるものです。
思いつくままに書き出してしまいましたが、予想外にどの側面をとっても深い問題につながるので、文を整理できないままです。
随時、書き足し校正をこれから重ねていく予定ですのでご了承ください。
よってわたしは「国体」とは明確に決別した「戦後天皇」のそれぞれの自ら問い続ける姿勢をこそ、制度としての天皇制よりも世界から尊敬されるに値する天皇の姿として限りなく尊敬するものです。