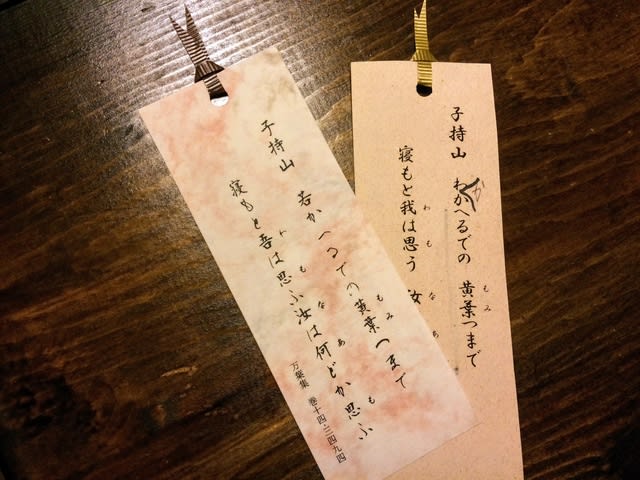ほとんどの地域で稲刈りは、遅くても10月末には終えているのが普通ですが、いまいろいろお世話になっている田村さんの田んぼは、毎年11月に入ってから刈り入れをします。
といっても、暦を見て、稲の生育を見て、天気を見て決めることなので、明確にいつと決められることでもないようですが、今年の夏の猛暑は農家にとって様々な影響を与えたようです。
数日前から、この田村さんの遅い刈り入れの稲を撮影しに寄っていたのですが、昨夜、田村さんの方から是非写真を撮ってもらいたい稲があるとの連絡をいただきました。
それは、この夏の猛暑が原因なのかどうかはわかりませんが、突然変異の稲が出たので、それを撮影してほしいというのです。
それは喜んで、と今朝すっ飛んで行ってきました。
聞くとそれは稲の茎が異常に太いものが出たのだと言います。
前にも、こうした茎の太い稲が出たことはあるそうですが、今回で2回目であるとのこと。
これも手作業の稲刈りでなければ気づかないことでしょう。

リンゴやミカンなどの果実類は、突然変異が出やすいそうですが、稲の場合は滅多にないそうです。
いろいろ話を伺っていると、異常気象の時こそ、自然界の生き物にとって多くは災難であるかもしれないけれど、同時に新しい生命が生まれるチャンスでもあるようです。
田村さんいわく、環境が激変する時こそ、それまでの環境では生まれてこなかった新しい異端児が出てくるものだと。厳密には、突然変異種は異端児よりももっと稀なもので、革命児とか異星人に近いレベルのものです。
この異端児というのは、環境が安定している時にはあくまでも異端児として排除されていく立場なのだけれども、これまでになかった環境が現れると、この異端児こそが次の時代を作る主役の側になる可能性があるというのです。
その意味で、異常気象というのはこうした異端児が生まれてくるチャンスでもあるので、農業の未来にとっては必ずしも悪いことばかりではないのかもしれないと話してくれました。
苗や種を買ってきて植える農業と違って、親から生まれた子どもをきちんと育てる農業を行っている田村さんにとっては、こうした一つ一つの突然変異の事例は、とても大切なもののようです。
DNA解析や遺伝子組かえ技術で組み立てる生命ではなく、生まれ育った一つひとつ固有の環境の中でこそ生命は輝きを増すのですから。
田村さんと農業の話をしていると、いつも子育てや教育の話をしているのか、現代医療の話をしているのか、はたまた哲学の話なのかわからなくなります。

田村さんに何か太さを比較する目印になるものはないかと言ったら、綿棒を出してくれました。
帰ってから気づいたのですが、普通の稲と並べるのが一番わかりやすかったですね。
また次に撮影してくることにします。
農業を経済効率だけで考えてしまうと、細胞の数は変わらないまま、ただ太らせることや、より甘くなることのみを追いもとめがちですが、本来は、生命そのものの力を強くすることこそが基本であるはずです。
それには、畑に実ったものの姿だけを見ていたのでは何もわかりません。
育つ前の土の中の環境にこそ、まず目を向けなければなりませんが、それは目に見えるミミズや昆虫だけではなく、人間の目には見えないたくさんの微生物によってこそ支えられているものです。
現代農業は、そのデータを全くとっていません。
たとえが古いかもしれませんが、窒素、リン、カリの配分比率の問題ではありません。
確かに昔に比べたら、化学肥料や農薬が人間に取ってどれだけ害があるかどうかは、しっかりとしたデータを取り「安全」なものを「より多く」生産する農業は飛躍的に進歩してきました。
でもどんなにデータで立証されようが、生命が痩せ衰えていく農業に未来はありません。
農業をめぐっては、後継者問題をはじめ太刀打ちできない大きな問題が山ほどのしかかっていますが、だからと言って目先の利益を追求したところでその場しのぎにしかならないことも確かです。
農業に限らず、世の中全体が「生命」とどう付き合うかを、一つひとつ考えること、見つめること抜きには突破口は出ないものと思っています。
そんな意味でも、田村さんの畑にお邪魔することは私にとって最高の時間です。

同じく、下の写真は、昔はなかった姿だと言います。
稲を刈ったそばから新しい芽が見事に出ています。
こんな光景が最近はあちこちで見られるようになったそうです。

原因は、気温が暖かくなったからなのか、栄養の与えすぎによるのか一概に断定はできないようですが、これならそのまま二毛作ができそうです(笑)
もしかしたら、これから本当にそんな時代になっていくのでしょうか。