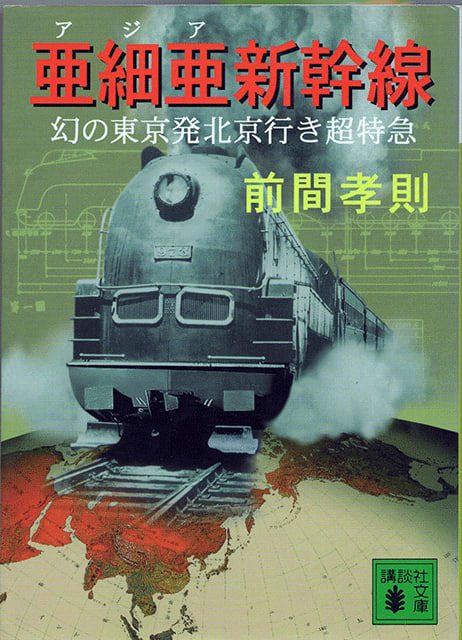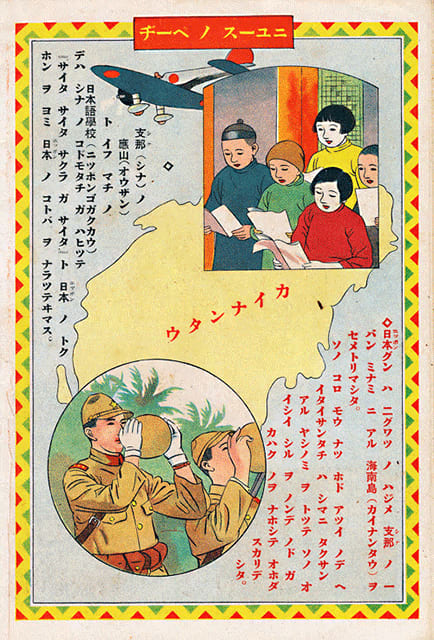話は明治の頃にさかのぼる。明治20年〜30年代、関西鉄道(かんせいてつどう)と官営鉄道(国鉄)は、乗客獲得をめぐって激しい攻防戦を繰り広げた。
 明治40年 関西鉄道路線図
明治40年 関西鉄道路線図
関西鉄道のそもそもの起こりは、桑名・関・土山・草津と、江戸時代の旧東海道沿いに施設された鉄道であり、近江・伊勢の筋金入りの商人たちが後押しした鉄道であった。果敢に路線を延ばしていった経営陣や株主たちのなかには、江戸期のメインストリートで商いした根性が息づいていたともいえるのである。
 「日本鉄道物語」橋本克彦著 講談社文庫より
「日本鉄道物語」橋本克彦著 講談社文庫より
官営鉄道が関ヶ原廻りとなって、幕府と同様に凋落してしまった旧東海道沿いの素封家たちは、あるいは暗に、官営鉄道をへこませてやりたいという切ない感情を、へそのあたりに抱いていたのかも知れないのである。

明治33年秋、イギリスのナスミス・ウイルソン社製A8系の機関車は、四日市で島安次郎を乗せて、暮れかかる大和路を西へ疾走していた。
※ 下総人さんからお借りした本を参考にさせていただきます。感謝!