「日経新聞」に「リーダーの本棚」という記事が日曜版に掲載されている。
各界における会長さんや社長さんなどの、いわゆる「登りつめた」トップリーダーたちが自己の愛読書について逐一解説している。
日経新聞といえばなんといっても最新の経済記事が売り物だが、こういう肩の凝らない記事は大好きなのでいつも興味深く読ませてもらっている。
紹介される本の種類は各人によってさまざまだが、お仕事には関係のない本が紹介されたりすると、おそらく「想像を絶する修羅場」や「目が回るような多忙」を限りなく「くぐり抜けた」経験をお持ちのはずなのに「余裕がある人なんだなあ!」といつも感心する。
たとえば、過去には「日本取引所自主規制法人理事長」(当時)の「佐藤隆文」氏が「バッハにみる悠久の秩序」と題し座右の書として「バッハ全集」を掲げられていた。
佐藤氏は財務省の主計官出身だが、「リーダーの本棚」でクラシック音楽関係の書を見かけたのは後にも先にもこれが初めてなので強く印象に残っている。
また、人事院総裁の「一宮なほみ」氏(当時)が大のミステリーファンとして「ジェフリー・アーチャー」(イギリス)のスパイ小説を挙げられており同じミステリーファンとしてとても親しみが持てた。
さらには、ロイヤルホールディングス会長さんの愛読書が8冊ほど紹介してあって、その中に「空気の研究」(山本七平著)というのがあった。
「人が意思決定をする際に、それを支配するのは議論の結果ではなく、その場の雰囲気であることが往々にしてある」という趣旨のもとに、「雰囲気=空気」とはいったいどこに由来しているのか、むやみにその場の空気に流されないための解決法は何かということが書かれている(そうだ)。
「空気の重要性」については、組織で働いた経験のある方ならおそらくピンとくるに違いない。
自分も曲がりなりにも37年間の宮仕えを務め終えたが、空気を読むことの大切さ、ひいては人を納得させ動かすことの難しさを痛感する毎日だった。
組織の運営には「理屈だけではどうしても足りないものがある」ということだけは分かったつもりだが、とうとうその辺を満足に習得することなく未完のまま卒業してしまった憾みが今でも残っていないといえばウソになる(笑)。
そういうわけで「後悔先に立たず」だが、遅ればせながら「空気の研究」をぜひ読んでみたいと思い立った。
さっそく図書館から借りてきたのはいいものの、とても寝転がって読めるような本ではなく想像以上に堅苦しくて学術書並みの難解さだった(笑)。
以下、曲がりなりにも自説を交えて箇条書き風に要約してみた。興味のない方はどうか読み飛ばしてください。
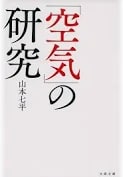
★ 「空気」とは言い換えればその場の「雰囲気」である。
山本氏はこれを「臨在的把握」と称されている。対象物の背後にある何か「恐れ」のようなものを感じることをいう。
その背景には「万物に霊魂が宿る」的な意識が色濃く残る日本と、一神教である西洋文明との対比が際立っており、結局「日本人論」が主題となっている。
★ なぜ「空気」を取り上げるのか
戦前、戦中、戦後と時代は変わっても「空気」なるものが我々日本人の意思決定の目を曇らせていることに尽きる。
★ あの時はそういうことを言える「空気」ではなかった
あの無謀な戦争に突入しようとしていた時点で、軍部を中心にマスコミひいては国民全体が戦争一本やりになったことを私たちは忘れてはならない。
ちなみに、マレーシアのリーダーだった「マハティール」氏はかっての日本の軍国主義を顧みて「日本人は直線的に行動したがる」と評している。
★ 戦後においてもその「空気」による意思決定は脈々と続いている
たとえばかっての公害問題において学術的論議を無視した企業叩き、自民党からお粗末な民主党政権への移行時の熱狂ぶり、スポーツ界のパワハラ問題など、もうウンザリするぐらい報道が続いている。寄ってたかって誰かを悪者扱いにする風潮がみられる。
★ どうしてそういう空気が蔓延するのか
幕末、明治あたりと違ってこの100年ほどは一部のエリートが無知な民衆を導くという政治の形から、(一応の)民主主義体制への転換によって一般庶民にまで情報が行き渡りメディアの充実とあいまって「全体のムード」(=空気)が生まれやすくなった。
★ どうも我々日本人は集団ヒステリーに罹りやすいようだ
そこで山本七平氏は「水を差す」というアイデアを挙げる。みんなで盛り上がっているときに否定的な意見を言って現実に引き戻す役割を担う。
★ ただしそれも結局は「まあまあ、ここはそれとして」とウヤムヤになってしまいがちだ
どうもその辺が「和をもって尊し」とする日本人と一神教の欧米人との違いがありそうだ。
★ 本書で「空気」への対抗手段は示されない
あくまでも分析に終始していて、その答えを導き出すのは我々の宿題である。
結局、「その場の空気に流されるのを潔しとしない」冷静さを我々一人ひとりが持つことが新しい日本流の「個人主義」につながっていくのではなかろうか。
という結びだが、どうしても「隔靴掻痒」の感を覚える方はどうか原書をお読みくださいね(笑)。
さいごに、「雰囲気=空気」の影響力で特に記憶に遺っているのが戦時中の「カミカゼ特攻隊」の志願状況である。
隊員を一堂に整列させて志願者を募るときに、指揮官が厳かにそして悲壮感を持って訓示をした後「志願者は手を上げろ!」と怒鳴った場合と、一方では「一人っ子などで親を悲しませたくないと思う奴は遠慮なく行かなくていいんだぞ」と、くだけた調子で言った場合とでは、確実に後者に不参加者が出たそうである。
人間にとっていちばん大切な命がかかった「究極」の場面でも「雰囲気に左右される」なんて、悲しいですよね・・。
積極的にクリック → 
















