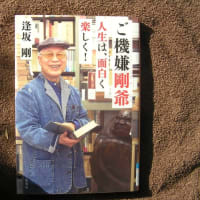由紀さおり(敬称略)の「1969」というアルバムが欧米で大ヒットしているという。つい先日のNHKの朝のテレビ番組でも紹介されていたし、ネット情報でもすでにご承知のとおり。
12月8日付の朝日の朝刊「ひと」欄にも次のような紹介が。

「由紀さおり」の「夜明けのスキャット」は大好きな曲だった。大学を出て就職したての頃なのでもう40年以上も昔の話。
まさに「光陰矢のごとし!」。
当時はまだレコード全盛の時代で、45回転のドーナツ盤を購入して粗末な一体型のレコードプレイヤーでよく聴いたものだった。
今でもレコード盤には未練があってプレイヤーのほうはとっくの昔に処分したものの、倉庫の片隅に大切に保管しているので、この機会にと覗いてみたところ、LP盤ばかりでドーナツ盤はすべて整理したとみえて残念なことをしてしまった。
この「1969」には、文字通り1969年当時に流行った曲が収録されており、懐かしさのあまりすぐに購入しようといつものとおり「HMV」のネットで検索。
すぐに見つかったのはいいものの、同じジャケットの「1969」なのに値段に差があって、2、500円と1,200円とに分かれている。
一体どうしてだろうと、首を傾げながらもとにかく貧乏人なので安い方の1200円をクリックして「カート」に放り込んだ。3枚買うと送料がタダになるので、かねて狙っていたモーツァルトのクラリネット・クィンテットを2枚抱き合わせ。
うち1枚は、近年、売れ行きが良くて評判がいい「デイヴィッド・シフリン」とエマーソン弦楽四重奏団のコラボによるもので、もう一枚は歴史的な名盤とされるウラッハ盤。
このウラッハ盤はずっと以前に「20bit」のデジタル・リマスター盤を購入したのだが、明らかに失敗作で滅茶苦茶に悪い音質だったので、買い直すことにしたものだが今回は「変ないじり方」をしていない盤のようである。
現在の手持ちは、ほかにもプリンツ盤、シュミードル盤の計3枚持っているが今回は追加したこの2枚の聴き比べが楽しみである。
古いモノラル録音と最新のデジタル録音、演奏力のいずれが音楽鑑賞に影響を及ぼすのか、そういう興味も尽きない。
さて、この3枚をHMVで注文したのはいいけれど、待てど暮らせど到着しない。ようやくメールが届いたと思ったら、クラリネット・クィンテットは2枚とも入荷済だが、由紀さおりの「1969」は未入荷とある。
えっ、国内ではあれほど溢れているのにどうしてと思ったが、たちどころに疑問が氷解した。
な~んだ、輸入盤なんだ!道理で~。これで値段が安かったのが分かった。
結局、犬がエサを前にしてお預けをくわされたようなもので「待ち賃」が値段の差(2,500円-1,200円)の1,300円というわけである。ただし、輸入盤と国内盤ではこれまでの経験で音質にどうも差があるような気がしてならない。
総じて国内盤より輸入盤の方が音質が良かった記憶があって、とりわけ、CBSソニー盤などでは顕著な違いを感じているが、これはあくまでも個人的な経験なので断言は差し控えたい。
さて、まあ、そのうち到着するだろうと腹を括って待っていたらようやく4日(日)の午後に到着した。結局、注文してから2週間ぐらいかな。なにせお金はないが時間だけはたっぷりとあるのだから、1,300円の節約効果の方が素直にうれしい。やっぱりケチなのかな~?
5日(月)の朝からさっそく試聴開始。
先ず「1969」から。

全体12曲をずっと通して試聴したが、外国のバンド(ピンク・マルティーニ)とのコラボによる和風+洋風のエキゾチック性が欧米で受けているのだろうと推測できた。
総体的な印象としては「由紀さおりはやっぱりうまい、軽快なロック調の曲からスローバラードまで難なく歌いこなしている。ものすごくレパートリーが広いが、いったい今、何歳(いくつ)なんだろう、相当、歳をくってるはずだが軽い発声法だから長持ちするのかなあ」と独り言を言いながら大いに感心した。
とにかく買って損はしない、十分に楽しめるアルバムだった。一番好みだった曲目は9トラックの「イズ・ザット・オール・ゼア・イズ?」で、こればかりは由紀さおりの魅力と歌唱力全開。この1曲だけで購入の価値あり!この絶妙のリズムとスイング感はアメリカのジャズバンドでないと出せない。
逆にちょっぴり残念だったのは「夜明けのスキャット」で昔のオリジナルのイメージどおりを期待していたものだから相当アレンジされていたためちょっと物足りなかった。まあ、期待するほうが無理というものだろう。
さて、残るのはいよいよクラリネット・クィンテット(五重奏曲)の試聴である。
こんな穏やかな冬日和の絶好の日を自分独りだけで聴くのはもったいないような気がしたので、湯布院のAさんに「一緒に試聴してみませんか」とお誘いしたところ、「Axiom80で聴くクラリネットの音色が楽しみですねえ」と一つ返事で引き受けていただき、午後3時から一緒に試聴ということになった。
当日は好天気のため、暖房を入れなくて済んだのでエアコンの音が気にならなくて大助かり。


初めにシフリン盤、次にウラッハ盤の順に試聴した。
さすがにこれほどの名曲になると曲目自体が録音の差や演奏の差を超越しているような印象がして、両方とも無難に鑑賞できるように思ったが、あえて指摘するとシフリン盤はたしかに録音はいいものの全体的に現代人がせかせかと仕事をこなしていくような印象を受けて、もっと余裕と潤いが欲しいような気がした。まだ芸格が備わっていないとみたが断言は控えておこう。
ウラッハ盤はモノラル録音ながら、明らかに手持ちの「20bit」盤よりも音質が良好だったのでほっと一息。演奏のほうは、ゆったりとしてほのぼのとした慈父のような味わい深さがあって落ち着いて鑑賞できるのが実にいい。1950年代初頭に録音された歴史的名盤とされているだけのことはあると再確認した。
いずれもアバウトな感想だが、Aさんのご意見となると、もっとはっきりしたものだった。
「シフリン盤はそれぞれ5人の演奏者の自己主張が強すぎて平板な音楽になってます。この五重奏は、クラリネット、チェロ、和音を受け持つバイオリン(3人)の3つのパートがそれぞれ出たり引っ込んだりして役割分担をしながらあざなえる縄のように音楽を構成すべきものです。その点、ウラッハ盤の方が明らかに多彩な演奏になっていて一枚上です」とのことだった。
穏やかな冬の午後、ゆったりと時間が流れる中で音楽仲間とモーツァルトの名曲の聴き比べができるなんて実に”至福のひととき”だったが、クラリネットの豊かにして何か物悲しいような訴えかけるような音彩はこういう冬日和にこそふさわしいのではなかろうかと思ったことだった。
最後にこのクラリネット・クィンテットについて音楽評論家「小林利之」氏により「永遠に色あせぬ名曲」として、次の名解説(「ステレオ名曲に聴く」1976年)があるので第一楽章と第二楽章のサワリの部分を紹介しておこう。
興味のある方は目を通してください。
「ステンドグラスの窓の色彩とその美しさにも似たと言われる多彩な音感で繰り広げられる第一楽章アレグロ、それは豊潤で透明な弦の四重奏(第一主題)で始まるのですが、続いて現れるクラリネットの閃くような動き、またピチカートの低音と長くひきのばした中音部の和音の上に、第一ヴァイオリンが歌う流れるような第二主題。コンチェルトふうにきらびやかな装いを示すクラリネットの活躍、すべてが円熟した手法です。
第二楽章はラルゲットでいちだんと深い味わいと静穏な抒情性を発揮し、弱音器つきの弦がクラリネットのやわらかい音をやさしく包むように引くとクラリネットは飾り気のない美しい旋律を歌います。ロマンティシズムの音楽の芽生えです。」(以下、略~)