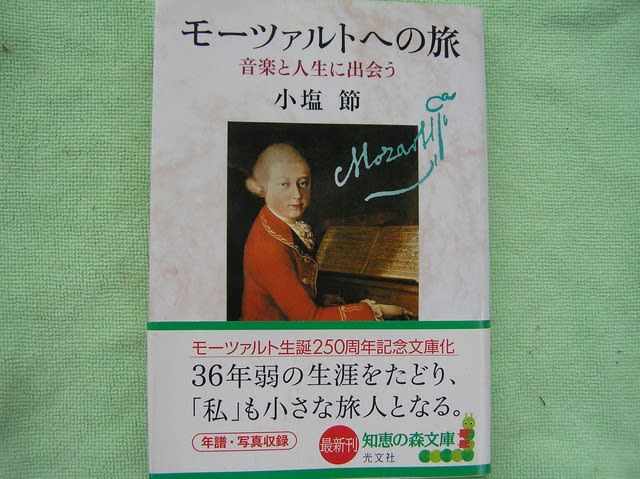前回からの続きです。
ドナルド・キーンさんの著作「オペラへようこそ!」を読み終えたところ、オペラに対する熱情にすっかり感化されてしまい、何だかずっと昔からのオペラファンだったような錯覚を覚えてしまった(笑)。
それほど本書にはオペラに対する熱情がほとばしっている。何事につけ人の胸を打つのは最後は「情熱」ということを改めて思い知らされた。

それでは前回のお約束どおり、キーンさんの大好きなオペラ「ベスト10」を挙げてみよう。
1位 ドン・カルロス(ヴェルディ) 2位 トラヴィアータ(椿姫:ヴェルディ) 3位 神々の黄昏(ワーグナー) 4位 カルメン(ビゼー) 5位 フィガロの結婚(モーツァルト) 6位 セビーリャの理髪師(ロッシーニ) 7位 マリーア・ストゥアルダ(ドニゼッティ) 8位 湖上の美人(ロッシーニ) 9位 エヴゲーニイ・オネーギン(チャイコフスキー) 10位 連隊の娘(ドニゼッティ)
偏ることなく、とても幅の広いオペラファンであることが伺えるが、惜しいことに自他ともに認めるオペラの最高峰「魔笛」(モーツァルト)が入っていない!
5位の「フィガロの結婚」(モーツァルト)も凄くいいけど、それよりは上だと思うけどなあ(笑)。
このことで、キーンさんのオペラへの嗜好性が垣間見えた気がした。
おそらく魔笛を外された理由は「ドラマ性」が物足りないといったことだろう。
周知のとおり「魔笛」は荒唐無稽の「おとぎ話」の世界だからストーリー性は皆無といっていいくらいだが、その反面、音楽の美しさといったらもうこの世のものとは思えないほどだ。
その辺りに自分のようにクラシックから分け入ったオペラ・ファンと、キーンさんのようにオペラ・オンリーの生粋のファンとの違いが鮮明にあぶり出されてくるような気がした。
ところで上記のベスト10には指揮者が特定されていないのが残念。あえて無視されたのかもしれない。
そのかわり、「思い出の歌手たち」の一項がわざわざ設けてあった。
✰ キルステン・フラグスタート(キーンさん一押しのソプラノ歌手)
✰ エリザベート・シュワルツコップ(類い稀な美人かつ際立った声の個性)
✰ ビルギット・ニルソン(ついにフラグスタートの後継者が登場)
✰ マリア・カラス(スーパースターが持つ独特の雰囲気を発散)
✰ プラシド・ドミンゴ(パバロッティを上回る魅力的な声を持つテノール)
ほかにもいろんな歌手が登場するがこのくらいに留めておこう。
さて、キーンさん一押しのソプラノ「フラグスタート」だが、幸いなことに手元にフルトヴェングラー指揮の「トリスタンとイゾルデ」(ワーグナー)がある。

これまで「フラグスタート」をそこまで意識して聴いたことがないが、稀代のオペラファンが絶賛するのだからいやが上でも興趣が募る。
まず、ネットでのコメントを紹介しておこう。
「1895年7月12日、ノルウェーのハーマル生まれのソプラノ歌手。1962年12月7日、オスロにて没。父は指揮者、母はピアニストという恵まれた音楽環境の中で育ち、オスロのヤコブセン夫人の下で声楽を学ぶ。
1913年、同地の歌劇場でデビューしたが、30年代に入ってバイロイトに招かれ、ジークリンデ役で大成功を収める。その後も、ブリュンヒルデやイゾルデなどの歌唱で高く評価され、ワーグナー歌手としての名声を不動のものにした。
その声量は極めて豊かで、膨大なオーケストラの強音をも圧して響き渡ったにもかかわらず、清澄な美しさを失わず、劇的表現と気品に満ちたもので、ワーグナー・オペラのヒロインとして理想的であった。
また、R.シュトラウスの歌曲の歌唱においても、歴史的名歌手として名を残している。」
以上のとおりで、これを前にして素人の分際であれこれコメントするのは気が引けようというものだが、気の遠くなるような長い前奏の後でようやくフラグスタートが登場してくれた(笑)。
後継者とされる「ブリギット・ニルソン」と比べると、やや声質が柔らかくて軽やかで高音域への伸びが一段と際立っているような印象を覚えた。さすがキーンさん一押しのソプラノですね。
あとは彼女の声で「4つの最後の歌」(R・シュトラウス)をぜひ聴いてみたいですねえ。
この内容に共感された方は積極的にクリック →