 不正を防げない科学界の体質
不正を防げない科学界の体質
2014年12月20日
理化学研究所がSTAP細胞の検証実験の打ち切りを発表しました。「まったく新しい万能細胞の作製。ノーベル賞級の世界的な大発見」は、研究上の不正どころか、研究の名に値する研究でさえなかったという批判がでるほどです。ノーベル物理学賞の日本人3人の受賞で科学の素晴らしさを知った一方で、科学界のどうにもならない閉ざされた体質を知らされた1年です。
検証チームのリーダーが、モニターや立会人の監視下で実施したことについて「犯罪人を扱うような形で行うのは科学のやり方ではない。科学のことは科学のやり方で処理しなければならない」と、感情をたかぶらせて述べましたね。一瞬、誰のことを批判しているのだろうと思いました。自分たちでそういうやり方を採用しながら、そのことを自ら批判するとは、不可解です。
独特の言語表現と思考回路
STAP細胞は存在するのかどうかの質問に、この人は、「科学者としてお答えできない。言えることは、再現できなかったということだ」とも述べました。厳密にいえば、そういうことなのでしょう。「理研の女性研究員がやったというSTAP細胞は存在しない。捏造の不正研究だった」と、分りやすくいわないのは、この人たち独特の言語表現、頭の思考回路があるからなのでしょうか。
女性研究員のコメントで引っ掛かったのは、「与えられた環境のなかでは、魂の限界まで取り組み、今はただ疲れきり・・」と言うと箇所です。突然、「魂の限界」という表現が飛び出し、戸惑いました。不正や捏造の疑いにはいっさいふれませんでした。事件の中心人物はこの女性です。と同時に、この女性は犠牲者でもあるのではないかという思いです。それが本人の口から「魂の限界」という言葉が飛び出した理由かもしれませんね。科学界の特異な体質が生み出した事件であり、この女性をいくらやり玉にあげたところで、再発を防げないでしょう。
ノーベル賞受賞者の野依理事長は、退職する女性研究員について「前向きに新しい人生を歩まれることを期待する」というコメントを出しました。そんなことより、不正を生みやすい科学界の体質に警鐘をならしてほしかったのです。
シェーン事件の再現そのもの
科学研究に関心を持つ人から、あるメールを受け取りました。たまたま、「論文捏造」(村松秀著、 2006年、中公新書ラクレ)という本を読んだといいます。「2000年ころ、アメリカの名門、ベル研究所で起きた、高温超電導の分野での論文捏造事件を題材にした本です。有名なシェーン事件です。細部にわたってSTAP細胞事件があまりにも酷似しており、驚いた」というのです。
「登場人物や組織の名前を変えれば、そのままストーリーが通用する。ノーベル賞間違いなしと言えるほどの大発見。追試には誰も成功しない。周囲では疑いが持ち上がる。斯界の権威が共同研究者であるため、自分たちの追試技術が未熟であるためかとの考えも捨てきれない。そのうちグラフの使いまわしが発覚し、それをきっかけに、杜撰な研究態度(研究ノートの不備、データやサンプルが残っていないなど)が分った」
「次に、間違ったグラフを掲載してしまったという本人の言い訳に疑いの目が向けられた。調査委員会の決定により、結局、数々の論文は取り消され、本人は解雇された」。「一方、研究のリーダー(斯界の権威で論文の共著者)でも、一流とされる配下の研究者には、生データやノートを見せろとかは言えない」、「共著者は論文の内容には自分が全責任を負う立場にはないとの態度をとる」、「ベルの研究所は当時、地盤が沈下し、挽回のため、この世紀の大発見を売り出すべく躍起となっていた」、「今はひっそりと暮らすこの研究者は、論文の不備は認めているものの、不思議にも、その研究結果の正しさについては、今もって信じている様子だ」。
わたしもさっそく本屋で、数々の受賞歴があるこの本を買いました。確かに、ベル研を理科学研、シェーン(30歳前後、ドイツ人)を小保方、超伝導をSTAP細胞と置き換えると、全くといっていいほどストーリーは同じになります。パトログ博士(超伝導研究の大家)に相当する人物も今回、おりました。論文発表の舞台になった科学誌「サイエンス」、「ネーチャー」はまったく同じです。
不正摘発機関が必要だ
捏造が発覚したのは、「二つの論文をよく見比べてください」という密告電話が、著名な物理学者のもとにかかり、グラフの使いまわしを見つけたのがきっかけです。今回の事件でも、二つの証拠写真を重ねると、映像がまったく同じでした。「うっかりして」という言い訳まで、2人は共通しています。この本は、欧米では研究の不正、捏造事件が多発しており、米国が政府に研究公正局を設置した経緯にもふれています。
さらに「他人の不正を追及しようとすると、膨大なエネルギーをとられ、自分の研究がストップしてしまう」、「最先端の分野であればあるほど、同じ分野に秀でた研究者は少ない」、「内部告発しても、不正がないことが分ったら告発者は生きて生きていけなくなる」、「そこで米国では告発者の名前を伏せて、研究公正局が摘発に取り組んでいる」などと、指摘しています。
最先端科学はカネになる、研究所や研究者間の競争は激烈、短期間に成果をだすよう求められるなどで、不正研究・捏造がおきる構造、体質が生まれているようですね。シェーン事件も小保方事件も起きるべくして起きたともいえます。日本政府も科学界も理研も、そういう意識がまだまだ希薄ということでしょうか。犠牲者をひとり血祭りにあげて、幕引きというわけにはいきません。










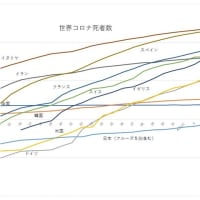









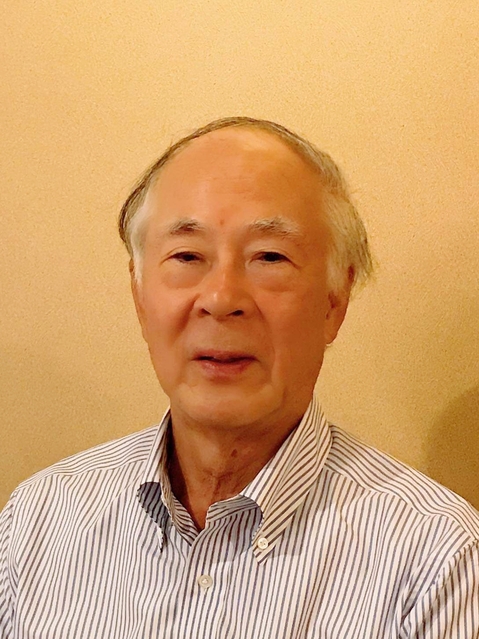

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます