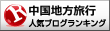坂本龍馬ゆかりの亀山社中跡がある私が住んで
いる町の川向こうに日本初の営業写真館を開
業し、坂本龍馬、高杉晋作など幕末の志士の
写真を撮った上野彦馬をテーマにしたモニュメント
が出来ました、肘置き台(白い壁際にある)の
そばに立つ人を手前にある写真機の上にカメラ
を置いて撮影すると、かつて龍馬が撮った龍馬
の写真と同じ構図になる仕組みになっています
上野彦馬宅跡(上野撮影局跡)
設置されている説明板には次のような記事が
書かれていますので参考にしてみてはいかが
文久2年(1862)上野彦馬はこの地に接する
道路を隔てた北側の地(写真参照)に撮影局
を開業した、わが国最初の営業写真館だった
上野家は代々絵師の家系であったが彦馬は
日本で初めて銀板写真機を輸入した父、俊之
丞と同様に写真に興味を持ち、オランダ人医師
ポンペやフランス人ロシェから写真術等を学び
研究を重ねた、初期の頃のカメラは旧式の箱形
(湿板写真)で露出時間は約10秒その為首押さ
えや胴押さえが利用された、当初は写場もなく
屋根のない小屋が利用された、後にガラス張り
の写場が完成、長崎名所のひとつとなった。
坂本龍馬、高杉晋作、グラバーなど長崎を訪れ
た人たちはこの撮影局で写真を撮ってもらった
彦馬は西南戦争の従軍写真師を務め報道写真
家の先駆けとして評価され日本語の化学の教科
書である(舎密局必携)を著わすなど多大な功績
を残している、この画像のモニュメントは日本写真
の開祖・上野彦馬の功績を顕彰し、上野撮影局で
撮られた龍馬の写真と同じ構図で記念撮影ができ
るように同撮影局の写真機と肘置き台を再現した
ものである。
長崎218年の水がめ・倉田水樋跡
所在地・長崎市伊良林1丁目1-3
新大工町電停から中島川に出るとすぐ右手に
銭屋橋が見える、この橋を渡ると30m川下に
倉田水樋跡の石碑が立っています、これは
1673年に本五島町在の回船問屋倉田次郎右衛門
が私財を投じて造った水源跡である、倉田はこの地
に湧き出す中島川の伏流水と、そこに流れ込む若宮
川の合流点に堰を築き水源地とした
この水は八幡町八幡神社付近まで地上を導かれ
その先は地下1.5mに埋めた水樋により東浜の町
西築町まで導水され更に堰で分岐して末端へ配られ
た、その給水区域は当時の長崎66ヶ町中50ヶ町余
に及び218年間市民の水がめとなった、1891年
(明治24年)本河内高部水源地の給水開始により
その役割を終えた、この水樋は私費を投じて造った
日本初の水道であり、倉田は奉行所から世襲で水樋
支配役に任ぜられ、立山の水道建設にも腕を振るった
画像上クリックで文字が読めるようになります