ぶらり町歩きをしました>大和郡山を。
「奈良ひとまち大学」の授業を受けに行くため、奈良入りした時のこと。
諸般の事情から(?)大阪天王寺を経由して奈良入りしたのですが。
会場は、近なら駅前なので、どこかで近鉄に乗り換えたい。
となれば、JR郡山で、でしょうなあ。
ってことで、郡山で下車。
ホームからは「赤膚焼」の文字が見えました。

初めて意識した(汗)
気がつけば、ワタシ、郡山で下車したことがない。
となれば、ここらへんを歩くってのもいいなあと急遽「郡山探索」に出ることに。
しかし、晴れ女のわたくしとしたことが、
本日も小雨が降ったり晴れたりの天候で、
どーも今年の奈良入り時は雨ばっかりだわ(トホホ)

賣太神社はまた次回
とりあえず近鉄郡山駅方面へ歩いていくことに。
ほんのちょっと歩くと、雰囲気のある神社さんが登場。

高田大神社(駅から歩いてきた道の奥手から撮っています)
村社さん?って感じのたたずまい。
向かって左隣りには釈尊寺というお寺が密着してありました。
この道はJRと近鉄の間に通っている道なので、結構人通りがあります。
そのため昔ながらの商店もたくさんあり、いい感じです。

洋傘直します

開いているようでもあり、休憩中でもあるお店
そうこうしているうちに、外堀公園なる場所へ出ました。

外堀公園
かつてはここが郡山城の外堀だったらしいです。
この横断歩道を手前に歩いてきたら…外堀だった場所が舗装されており、
そこをずんずん進むと何やら気になる文字が。

薬園寺だそうで
薬園で、郡山といえば、薬園八幡神社。
おお、あれってここだったんだ~どこから入れるん?
と西に向かって歩いていくと、ほどなくありました。

薬園八幡神社

標柱
奈良の大仏建立の時代。
宇佐八幡を勧請して奈良の地へお迎えした時、
東大寺へ向かわれる前にお留まりいただいたのが当地。
八幡様は東大寺の地へと向かわれましたが、
そのご分霊をこの地で祀ったのが創祀とのこと。

本殿
とりあえず、パンパンして本日の無事を感謝。
その後、境内をてくてく。

由緒正しそうな燈籠

崩れそうな壁
奥には摂社・末社がたくさんありました。
ふと隣の敷地をみると、墓地。
しかも、立派な鐘楼があるお寺さんらしい。

お隣さんの立派な鐘楼

高いところに鎮座ましますお地蔵さん
これがさきほど見た薬園寺かと思ったら、違う様子。
(こちらは実相寺というらしい)
どうやら、さっきの位置関係から考えて、
本殿へ向かう手水舎の左手にあったこの建物が薬園寺のようです。

これが薬園寺?
なにやらおば様方が掃除をなさっておいでで、
お祭りの前の準備とおぼしき方もいて。
そういえば表のスペースでテントの用意とかしてたなあ。
先ほどは開いてなかったのですが、本殿をお参りして戻ってきたら、
このお寺・薬園寺本堂の正面扉が開いておりました。
おお、これはグッドタイミングなのか?

この珠はなんだろう?
お忙しそうでしたので、声かけるのは遠慮しましたが。
(このお寺は真言宗御室派で、医王山薬園寺というそうで、
その名のとおり、ご本尊は薬師如来だそうです)
ということで、薬園八幡さまをおいとまして、さらに西へ。
向かうと途中大きな道を渡り、源稲荷神社参道の文字を発見。
おお、またまた外せないスポットだ~。
行きます行きます♪
迷い込んだ一画は昔ながらの建物がたくさん。
まっすぐ進めばいい道を、寄り道し、ぐるぐる歩いて、
各所をパシャパシャ写真撮影。

立派な三階建て(しかし室外機が…)

おもむきのある住宅
ここらへんは洞泉寺町といい、その昔、遊郭だった場所なんだとかで。
そういわれてみれば艶っぽいかも。
くるっとまわって、源九郎稲荷さんの前に出てきました。

石柱

鳥居からのながめ
ここは『義経千本桜』の「源九郎狐」ゆかりの神社。

狐さんが一杯
あれこれ見ていたら、神社の方がいらして、オハナシなどして。
「ピエール瀧さんもこられたんですか?」
「はい~、あのとおりの方でね(どのとおりだろ)」
「あ、勘九郎さんも見えたんですね」
「そうそう」
わたし、勘九郎っていうと、平成中村座をたちあげた
18代目・中村勘三郎 (というか、長い事5代目中村勘九郎をやっていた人)
を思い浮かべてしまうんだけど、写真に写っていたのは六代目勘九郎。
ヨメが前田愛ちゃんの勘九郎さんでした。

正面左の写真が勘九郎さんの写真でした
お手植えの木がもう枝ぶりもよかったので、
「すごく育ってますね」といったら、
「最初から大きなものを植えていただいたんです」とのこと。
ははは、確かに襲名して3年ほどですもんね。
あんなにいきなり大きくならないか。

お手植えの木
そこをおいとまして、一路メインルートへ戻り、紺屋町へ。

地中埋め込み案内図

整備された水路
この水路は車に乗っていて見たことがあるから、通ったことはある筈。
県外ナンバーのひとたちは、落ちないようにおっかなびっくり運転してました(笑)
そして郡山といえば、箱本という町内会システム。
それを行っていたのが、ここらへんの町内です(あっさりした説明)

箱本館
写真では見ていたけど、入ったことがなかったから箱本館に入ってみることにしました。
かつて藍染めを生業にしていた屋敷を保存&活用しているところです。

室内の様子
この暖簾の奥の棟では染物の体験もできます。
実際にやっている人もたくさんいました。
(ワタシは見学だけさせてもらいました)
そこでは、なんか独特のにおいがするなあって思ったら、
染に使う染料のにおいだそうで。
(然灰汁発酵建て(てんねんあくはっこうだて)という昔からの方法で仕込むそうです)
今は水道の水を用いて、流しでさらして染料を落としてますが、
昔は店の前に流れていた水路(現在のものより幅広だったらしい)でさらしていたらしい。
それでも自然の染料なので、水路に流しても環境にもやさしかったそうです。
染の体験棟から戻って、今度は母屋の座敷に上がって見学。

座敷の床の間(お軸も金魚なんですよ)
座敷や、床の間には、そこここに金魚。
金魚モチ-フって時節柄、夏っぽくていい感じ。
ここはかなり楽しめました。
昔の器に描かれた和金ってなんてかわいいんでしょ。
そうそう、屋内には例の「箱本」の町内会の決め事を書いて、
各町内で持ちまわったご朱印状のレプリカが展示されていました。
おおう!これ、奈良検定で勉強したアレじゃん?!
最後の最後でテンション上りまくりました。
(へへへ)
そこを出て、水路ぞいに歩いてきたら、すぐ近所に人だかりが出来ていました。
何ごとかと思ったら、「金魚すくい選手権の練習場」でした。
ふと気がつくと、ポスターに金魚すくい選手権。

明日は金魚すくい選手権
おおう、明日は金魚すくい選手権ですか☆

みなさん練習に余念がありません
さて、次はどうしましょうと思ったが、
そうだ、あそこへ、行こう。
今まで一度も行ったことがない春岳院へ。
春岳院は大納言・豊臣秀長(秀吉の弟)の位牌を預かるお寺として、
また、箱本制度の御朱印箱や御朱印文書を寺宝としているお寺として有名…。

春岳院!!
…のはずだったんだけど。
正直、この風貌を見たら「あら」って感じでした。
よくいえば「こじんまり」悪く言えば「地味」
あらあらあら。
現在はコンパクトにまとまっているってことですね。
しかし、そこで一つの発見。
春岳院の前に謎の洋風な白壁の建物を発見。

春岳寺前の謎の洋風建築物
これはなんだ?!

和洋折衷
奥まで見ていってみたら、洋館に接して和風建築。
これぞ、日本っぽいなあって思う建て方だと思いますわ。
せっかくだからってことで、春岳寺のわきの道も歩いて、
ちょっとだけ本堂にも近づいてみました。

春岳寺本堂
わざわざ見に来た甲斐あって、新しい発見が楽しかったです。
さあ、そろそろ奈良へ向かわねばと思って、駅方面へ。
最後の訪問地は、菊屋本店です。
ここの名物は「城の口餅」
秀吉にお出しする菓子を作るように命じられて、
できたお菓子が、粒餡を餅でくるんできなこをまぶした「鶯餅」。
しかし、店が城の入口にあり、「城の口で売っている餅」だからということで、
ひとびとから「城の口餅」と呼ばれ、これが商品名になりました。

菊屋本店
おお、写真や映像では長年見てきたけど、
実際に目にするのは初めて。
(ははははは)
表通りに面してはいないのね。
屋根のたわみが年月の長さをあらわしています。

向かって右手のガラスケースの中はお菓子の型でいっぱいでした
ということで、今回の小旅行(?)は終了。
今回は何の心の準備も無くまわった郡山散歩でした。
以前、近鉄の西側は回ったことあるし、矢田丘陵付近の寺は結構回ったし。
今回のぶら歩きで郡山はだいぶ回れた感じです。
次回はJRの東側の環濠集落など歩く機会があればいいなあと思います。
(それこそ、賣太神社なんかね)
しかし駅前についたら、西友がつぶれていたのにはショック。
ここで買い物して帰ったこともあるのになあ…。
たまに来ると発見がある&新しい発見がある、ちょっと町歩きでした。
「奈良ひとまち大学」の授業を受けに行くため、奈良入りした時のこと。
諸般の事情から(?)大阪天王寺を経由して奈良入りしたのですが。
会場は、近なら駅前なので、どこかで近鉄に乗り換えたい。
となれば、JR郡山で、でしょうなあ。
ってことで、郡山で下車。
ホームからは「赤膚焼」の文字が見えました。

初めて意識した(汗)
気がつけば、ワタシ、郡山で下車したことがない。
となれば、ここらへんを歩くってのもいいなあと急遽「郡山探索」に出ることに。
しかし、晴れ女のわたくしとしたことが、
本日も小雨が降ったり晴れたりの天候で、
どーも今年の奈良入り時は雨ばっかりだわ(トホホ)

賣太神社はまた次回
とりあえず近鉄郡山駅方面へ歩いていくことに。
ほんのちょっと歩くと、雰囲気のある神社さんが登場。

高田大神社(駅から歩いてきた道の奥手から撮っています)
村社さん?って感じのたたずまい。
向かって左隣りには釈尊寺というお寺が密着してありました。
この道はJRと近鉄の間に通っている道なので、結構人通りがあります。
そのため昔ながらの商店もたくさんあり、いい感じです。

洋傘直します

開いているようでもあり、休憩中でもあるお店
そうこうしているうちに、外堀公園なる場所へ出ました。

外堀公園
かつてはここが郡山城の外堀だったらしいです。
この横断歩道を手前に歩いてきたら…外堀だった場所が舗装されており、
そこをずんずん進むと何やら気になる文字が。

薬園寺だそうで
薬園で、郡山といえば、薬園八幡神社。
おお、あれってここだったんだ~どこから入れるん?
と西に向かって歩いていくと、ほどなくありました。

薬園八幡神社

標柱
奈良の大仏建立の時代。
宇佐八幡を勧請して奈良の地へお迎えした時、
東大寺へ向かわれる前にお留まりいただいたのが当地。
八幡様は東大寺の地へと向かわれましたが、
そのご分霊をこの地で祀ったのが創祀とのこと。

本殿
とりあえず、パンパンして本日の無事を感謝。
その後、境内をてくてく。

由緒正しそうな燈籠

崩れそうな壁
奥には摂社・末社がたくさんありました。
ふと隣の敷地をみると、墓地。
しかも、立派な鐘楼があるお寺さんらしい。

お隣さんの立派な鐘楼

高いところに鎮座ましますお地蔵さん
これがさきほど見た薬園寺かと思ったら、違う様子。
(こちらは実相寺というらしい)
どうやら、さっきの位置関係から考えて、
本殿へ向かう手水舎の左手にあったこの建物が薬園寺のようです。

これが薬園寺?
なにやらおば様方が掃除をなさっておいでで、
お祭りの前の準備とおぼしき方もいて。
そういえば表のスペースでテントの用意とかしてたなあ。
先ほどは開いてなかったのですが、本殿をお参りして戻ってきたら、
このお寺・薬園寺本堂の正面扉が開いておりました。
おお、これはグッドタイミングなのか?

この珠はなんだろう?
お忙しそうでしたので、声かけるのは遠慮しましたが。
(このお寺は真言宗御室派で、医王山薬園寺というそうで、
その名のとおり、ご本尊は薬師如来だそうです)
ということで、薬園八幡さまをおいとまして、さらに西へ。
向かうと途中大きな道を渡り、源稲荷神社参道の文字を発見。
おお、またまた外せないスポットだ~。
行きます行きます♪
迷い込んだ一画は昔ながらの建物がたくさん。
まっすぐ進めばいい道を、寄り道し、ぐるぐる歩いて、
各所をパシャパシャ写真撮影。

立派な三階建て(しかし室外機が…)

おもむきのある住宅
ここらへんは洞泉寺町といい、その昔、遊郭だった場所なんだとかで。
そういわれてみれば艶っぽいかも。
くるっとまわって、源九郎稲荷さんの前に出てきました。

石柱

鳥居からのながめ
ここは『義経千本桜』の「源九郎狐」ゆかりの神社。

狐さんが一杯
あれこれ見ていたら、神社の方がいらして、オハナシなどして。
「ピエール瀧さんもこられたんですか?」
「はい~、あのとおりの方でね(どのとおりだろ)」
「あ、勘九郎さんも見えたんですね」
「そうそう」
わたし、勘九郎っていうと、平成中村座をたちあげた
18代目・中村勘三郎 (というか、長い事5代目中村勘九郎をやっていた人)
を思い浮かべてしまうんだけど、写真に写っていたのは六代目勘九郎。
ヨメが前田愛ちゃんの勘九郎さんでした。

正面左の写真が勘九郎さんの写真でした
お手植えの木がもう枝ぶりもよかったので、
「すごく育ってますね」といったら、
「最初から大きなものを植えていただいたんです」とのこと。
ははは、確かに襲名して3年ほどですもんね。
あんなにいきなり大きくならないか。

お手植えの木
そこをおいとまして、一路メインルートへ戻り、紺屋町へ。

地中埋め込み案内図

整備された水路
この水路は車に乗っていて見たことがあるから、通ったことはある筈。
県外ナンバーのひとたちは、落ちないようにおっかなびっくり運転してました(笑)
そして郡山といえば、箱本という町内会システム。
それを行っていたのが、ここらへんの町内です(あっさりした説明)

箱本館
写真では見ていたけど、入ったことがなかったから箱本館に入ってみることにしました。
かつて藍染めを生業にしていた屋敷を保存&活用しているところです。

室内の様子
この暖簾の奥の棟では染物の体験もできます。
実際にやっている人もたくさんいました。
(ワタシは見学だけさせてもらいました)
そこでは、なんか独特のにおいがするなあって思ったら、
染に使う染料のにおいだそうで。
(然灰汁発酵建て(てんねんあくはっこうだて)という昔からの方法で仕込むそうです)
今は水道の水を用いて、流しでさらして染料を落としてますが、
昔は店の前に流れていた水路(現在のものより幅広だったらしい)でさらしていたらしい。
それでも自然の染料なので、水路に流しても環境にもやさしかったそうです。
染の体験棟から戻って、今度は母屋の座敷に上がって見学。

座敷の床の間(お軸も金魚なんですよ)
座敷や、床の間には、そこここに金魚。
金魚モチ-フって時節柄、夏っぽくていい感じ。
ここはかなり楽しめました。
昔の器に描かれた和金ってなんてかわいいんでしょ。
そうそう、屋内には例の「箱本」の町内会の決め事を書いて、
各町内で持ちまわったご朱印状のレプリカが展示されていました。
おおう!これ、奈良検定で勉強したアレじゃん?!
最後の最後でテンション上りまくりました。
(へへへ)
そこを出て、水路ぞいに歩いてきたら、すぐ近所に人だかりが出来ていました。
何ごとかと思ったら、「金魚すくい選手権の練習場」でした。
ふと気がつくと、ポスターに金魚すくい選手権。

明日は金魚すくい選手権
おおう、明日は金魚すくい選手権ですか☆

みなさん練習に余念がありません
さて、次はどうしましょうと思ったが、
そうだ、あそこへ、行こう。
今まで一度も行ったことがない春岳院へ。
春岳院は大納言・豊臣秀長(秀吉の弟)の位牌を預かるお寺として、
また、箱本制度の御朱印箱や御朱印文書を寺宝としているお寺として有名…。

春岳院!!
…のはずだったんだけど。
正直、この風貌を見たら「あら」って感じでした。
よくいえば「こじんまり」悪く言えば「地味」
あらあらあら。
現在はコンパクトにまとまっているってことですね。
しかし、そこで一つの発見。
春岳院の前に謎の洋風な白壁の建物を発見。

春岳寺前の謎の洋風建築物
これはなんだ?!

和洋折衷
奥まで見ていってみたら、洋館に接して和風建築。
これぞ、日本っぽいなあって思う建て方だと思いますわ。
せっかくだからってことで、春岳寺のわきの道も歩いて、
ちょっとだけ本堂にも近づいてみました。

春岳寺本堂
わざわざ見に来た甲斐あって、新しい発見が楽しかったです。
さあ、そろそろ奈良へ向かわねばと思って、駅方面へ。
最後の訪問地は、菊屋本店です。
ここの名物は「城の口餅」
秀吉にお出しする菓子を作るように命じられて、
できたお菓子が、粒餡を餅でくるんできなこをまぶした「鶯餅」。
しかし、店が城の入口にあり、「城の口で売っている餅」だからということで、
ひとびとから「城の口餅」と呼ばれ、これが商品名になりました。

菊屋本店
おお、写真や映像では長年見てきたけど、
実際に目にするのは初めて。
(ははははは)
表通りに面してはいないのね。
屋根のたわみが年月の長さをあらわしています。

向かって右手のガラスケースの中はお菓子の型でいっぱいでした
ということで、今回の小旅行(?)は終了。
今回は何の心の準備も無くまわった郡山散歩でした。
以前、近鉄の西側は回ったことあるし、矢田丘陵付近の寺は結構回ったし。
今回のぶら歩きで郡山はだいぶ回れた感じです。
次回はJRの東側の環濠集落など歩く機会があればいいなあと思います。
(それこそ、賣太神社なんかね)
しかし駅前についたら、西友がつぶれていたのにはショック。
ここで買い物して帰ったこともあるのになあ…。
たまに来ると発見がある&新しい発見がある、ちょっと町歩きでした。










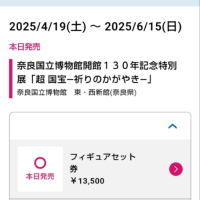















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます