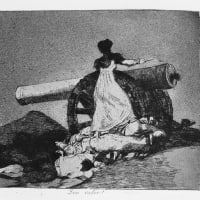いつの間にか九月。暇をみつけてフェルメールを見に行く。8作品が見られるということだったが実際は7作品。以前は「アトリエ」と呼ばれていた「絵画芸術」が作品保護のためキャンセルされたようだ。しかし、七つも鑑賞できることは、私が生きている間はまずないだろう。フェルメールの作品の中では評価の高いものが少ないが、それでもフェルメール。これがほんものだというアウラをひしひし身に感じる。光、色、感触、空気感、生命感らの優れたシニフィアン。息をのむほどの作品である。フェルメールが生きた時代のオランダの絵画は風俗がテーマであったが、そのどれもが道徳的な寓意がシニフィエとして描かれていた。フェルメールも初期はそうだったが、私が思うに「眠る女」から普遍的な美しさを描くようになった。現存する作品目録では60から70ぐらい彼の作品はあるとされるが、消失した多くの作品は初期の宗教画か習作で、継承・保存環境の悪いブルジョワ一般家庭にあったものだろう。

今回はフェルメールに引けをとらないと私が評価しているデ・ホーホが8作品あった。ヘーゲルがオランダの風俗画を見て驚嘆したことは有名だが、日常生活そのものの中に普遍的な美しさを見出したフェルメールたちのメンタリティーは、私たち現代人とそれほど大差ないと思う。
この絵画展で舟越桂の個展を開かれることを知った。もう20年以上前、ガーデンプレースがまだないサッポロビールの倉庫でグループ展があった。横尾忠則が画家に転身し、彼の大作が見られるということで行ったのだが、数ある作品のなかでも、異彩というか時代の流れとは隔絶した具象的な木彫があった。それが舟越桂だった。私は時間を忘れ立ち尽くし、眺めつくし、この作家の非凡な才能に驚くばかりだった。

目黒の庭園美術館での個展は、それまでの舟越にはない鮮烈な造形を見せてくれた。俄かには受けとめれないほどのショックを受けた。両性具有のスフィンクス。ヌードの木彫はこの5,6年ほど彼のモチーフであったが、神話のスフィンクスまで辿り着いた彼の審美的造形力はどこからきているのだろうか。市井に生きる普通の人を対象にした木彫に限りない親しみと、人間の魂のリアルな存在感を感じた私にとって、このスフィンクスをテーマにした連作は安逸に流れるわが凡人の精神に鉄槌を打ち込むものだ。舟越は「芸術家が自分の作品をコピーするようになったら終わりだ」と、自戒を込めてかたっていたことがある。まさにそれを実証するべき新たなアウラを作り出したのではないか。ただ最近、顔の造形がパターン化しているので気にならなくはない。しかし、人間の顔の美しさを極限まで、つまり人種的な差異を超えた美しさを象徴させた表現に他ならないと思う。

この日は、この個展に長くいたので自然教育園にいくことができなかった。残念であった。