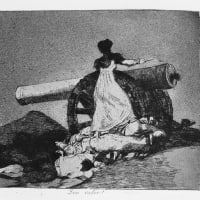お隣の韓国、ムンジェイン(文在寅)大統領の支持率が、低迷期の35%から55%に上昇した。そんなニュースが、コロナ感染騒ぎの渦中に伝わってきた。機を見るに敏の対策が、国民に評価されたらしいのだが・・。実際にはどんな奇策があったのか、と訝しく思っていたところ、最近その一端を知ることができた。
韓国の初動ともいうべきウィルス対策は、PCR検査を迅速かつ広範囲に行ったことで知られる。PCRによる検査態勢は、日本の13倍だというから凄い。
当初、中国に続き世界2位の感染者数だったが、武漢のようなロックダウンはなかった。まず、海外からの入国検査を厳しくして、外からの感染ルートを遮断。国内では、各地にドライブスルー形式のPCR検査を採用した。これらが功を奏し、3月末には事実上ピークアウトしたようだ(感染症ならぬ、心配性が詰めかけて感染が広がったと、茶化した話題もあったけど)。
最近では自主隔離違反者(スマホを家に置いたまま外出)には、リストバンド(GPS付きの移動追跡情報端末)の装着を義務づけた。これも目の付けどころが非凡だ。
(追記:いや、今、不穏な動きが韓国にある。陰性となった感染者が、再び陽性になるというケースが多数現れた。想定外の怖いニュースではないか・・。感染者数推移、その数理モデルのバージョンアップが必要だ。日韓関係がギクシャクしている現在、こうした韓国のデータは入手されているのだろうか? COVID19は油断はできない。)
ともあれ、遺伝子レベルのウィルス感染を判定するPCR検査、韓国は日本よりも充実していたことは確かだ。それは2003年SARSをはじめMERSなどの感染力、致死力の凄さを経験したからだ。シンガポールや台湾も事情は同じで、それ以降PCR検査体制は本腰を入れて整備される。
また、最初に接触した医療従事者が重篤化するという事実、ここにおいてもPCR検査の重要性は認知、徹底され、各国はそのシステムの導入に迷いなく踏み切ったといえる。
日本はといえば、PCR検査は他国に比べれば、その態勢は貧弱だと評価されている。そういえば、WHOの会長からPCRを充実せよと、いちゃもんを付けられたこともあった。ドイツの検査体制のなんと5,6%程度ほどのキャパ、そのお粗末さを指摘されたのだ。なんとしたものか・・。
サーズやマーズ(これらも新型コロナの部類に入る)、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱、ジカ熱などの感染症が世界を震撼させたとき、幸運なことに日本における感染者はゼロだった。それが原因なのか、遺伝子レベルの査定をおこなう煩雑なPCR検査の拡充、人材の育成を渋ったのだ。
それにひきかえ、実際に感染者が出て、そのリスクの深刻さを思い知ったのが、中国(注1)や香港、そして韓国と台湾だった。この時期ぐらいから、スマートフォンはじめ、ICT(情報通信技術)の分野で日本は明らかに後れをとるようになる。
スマートフォンを利用した「濃厚接触者追跡アプリ」は、韓国市民に積極的にダウンロードされた。携帯のGPSを利用して、感染危険エリアを警告するというものだが、たぶん中国のアプリと同様のソフトプログラムだろう、個人が移動する先々のエリアの感染リスクを自動的に緑・黄・赤で判定する。これは不安にさいなまれる市民からすれば、たいへん心強いものだったらしい。(中国のそれは、顔認証と交通移動履歴、さらに購買行動の履歴が組み込まれた、ほぼ完璧な個人情報データ管理を構築させつつある。個人のプライバシーを全く配慮しない、共産党独裁政権を盤石とするパノプティックな監視システムだ)
とはいえ、感染接触を警告するアプリなどは、なぜ日本では開発されないのだろうか? PCR検査システムが充実していないのは前述のとおりだ。感染症に対する研究体制、医療システムも貧弱だといわれる。少なくともアメリカのCDC(国立感染症研究センター)のように自主独立性は保障されず、潤沢な研究資金も予算化されない。
ウィルス感染とたたかうのは、まさに「戦争」だと喩えられる。「敵を知ることこそ必勝の要諦」という鉄則。世界大戦に入る前に、米軍の戦力を正しく分析できたならば、戦争は愚挙そのものだという結果は見えたはずだ。しかし、旧日本軍は敵のデータ収集もなしに開戦に踏み切った。兵力不足、兵站は戦地で調達、その他は精神力で補え! まさに、旧日本軍の「失敗の本質」は、ここにあったのだ。
さてさて、ウィルス検査を疎かにして、ウィルス戦争に勝つことはできない。未知の新型コロナウィルスのデータは、いまどうやって収集されているのだろうか。
先日、落合陽一からの宮田裕章(※参考)という人の存在を知った(News Picks)。昨日(4月15日)、NHKの『クローズアップ現代』に宮田氏は登場した。ビッグデータを解析して社会変革をめざす、そのためのアルゴリズム開発をワールドワイドに進める、気鋭のICT(情報通信技術)学者である。
厚労省の新型コロナ感染対策特別チームのメンバーなのか、この度「ライン」を使ったデータ収集プログラムを開発(指揮?)した。それは、新型コロナ感染を診断する特化アプリで、主に健康チェックを問診形式でおこなう。一週間前に、小生も取り合えずアプリ登録し、健康データを提供したことになる。

▲アプリの初期画面をスクリーン・ショット
このアプリの特長を、自分なりに要約したので、ここに列記する。
●全体の立て付けは、ユーザーが登録した段階で、個別化した情報提供を、適時受けられる双方向通信プログラム。
●現在の体調などの基礎情報、位置情報ログなどのデータを入力すると、個々人に最適化された情報やサポートが受け取れる。
●自身がハイリスク対象者か否か、軽症者か重症者か、医療機関受診のタイミングなども分かる。
●症状があった人へのフォローアップ。定期的にメッセージを送り症状を確認できる。
●医療崩壊を避け、軽症者は自宅でのセルフケア促進。
●体調の変化や周辺の発症状況といった変化を検知し、受診が必要なタイミングを伝える。
●今後データが集積することで、リアルタイムで重症化の予測をしながら、医療資源の振り分けに使うことも可能か。
LINEを使った調査とコンタクトトレーシング(接触追跡)の連動は、プライバシーを考慮して、分けて考えるそうだ。(当面の目標は、LINEユーザーのデータを母集団として、自宅待機者やハイリスク群の実態把握)。
陽性患者以外の人を含めて、社会として有効な施策を打てるのか。今後の予測や対策後に実際にクラスターが解消されたかどうかも分析できるか。課題は大きいが、8300万人を対象にした全国調査という立て付けなので、信用に足るビッグデータを収集できる。
ちなみに、先の『クローズアップ現代』では、ライン登録されたユーザーから、三日連続の37.5度以上の発熱を報告があったのは、3月21日の連休前後で、なんと2万3千人いたとあった! そのすべてが新型コロナの感染者とはいえないが、その後の経緯を考えると、ほとんどが感染者となる。
昨日、厚労省クラスター対策班の西浦博氏は、「対策ゼロならば、重篤者数約85万人、死亡予測はその49%」という試算結果を公表した。海外の流行を基にした試算とのことだが、前述したLINEの感染データ数は反映されているのか・・。机上の分析ではなく、実態調査を盛り込んだ数理モデルで解析してもらいたい。
今日4月16日の夜、都道府県全域に緊急事態宣言が発令された。どうも後手に回っている。さらに、全国民に1人10万円「所得制限なし」の現金給付されるとのこと。どういう狙い、何を期待?
英国が先ほど、「外出禁止令」を3週間先延ばしすると、ラーブ英外相(首相代行)が記者会見した(4/16)。感染拡大の熱量はまだ下がっていないのだ。トランプのピークアウト声明も、願望込みの例のガセかもしれない(投稿後追記)。
(注1):武漢にある「中国科学院武漢ウイルス研究所」、ここはバイオ研究の先端基地で生物兵器の開発研究が専門。以前にも施設管理が杜撰で、ウィルス漏洩が取りざたされた。一方、今回の発生源として疑われた、コウモリのコロナウイルスを研究している「武漢疾病予防コントロールセンター」が、件の海鮮市場の近くにある。それぞれの研究所は離れているが、連携されていることは確かだ。今のところ、真実は分からない。中国が言う「アメリカが持ち込んだ」かも知れないからだ。判断は保留だ。
(※参考):落合陽一◎筑波大学情報学群情報メディア創成学類卒業。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。大学教員、メディアアーティスト、実業家、弱冠33歳だがなかなかの識者だ。
宮田裕章(みやた・ひろあき)◎2003年3月東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。2015年5月より慶応義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授。
落合陽一「Withコロナ時代の日本再生ロードマップ」(期間限定ダイジェスト)