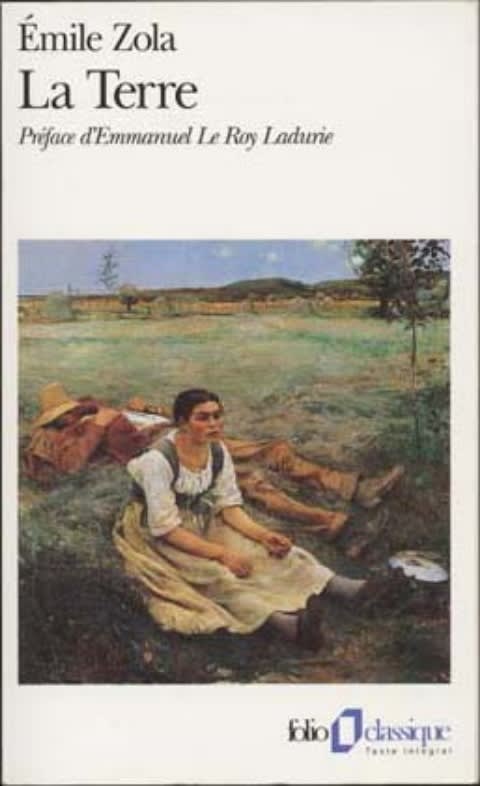
4月末以来の、ゾラの”ルーゴン=マッカール叢書”です。
この「大地」はその第15巻にあたるが、単行本で624頁もある超のつく巨編である。
当時は散々な酷評に巻き込まれたが、時代はそれを許さなかった。
”農村に巣くう因襲と旧弊を取り上げた問題小説で、19世紀フランスの農業を扱ったバルザックの「農民」と並び称される。
土地相続を巡り、農民の貪欲がついには親族殺しにまで発展する残忍で奇怪な過程をテーマに、人間の獣性をえぐり出し、当時のフランス農業が抱えていた諸問題を浮き彫りにした。
「壊滅」「ジェルミナール」に次ぐ、重厚な物語の大作でありながら、露骨過ぎる性描写の為にゾラの弟子たちからも反発を買い、自然主義退潮のきっかけをつくった。
ゾラが描いた黄金の「大地」は、人間を支配する圧倒的な力であり、新しい生命を育む母胎として現れている。その底に脈打つのは生命への信頼であり、ルーゴン=マッカール双書がその結末へ向け、大きく旋回してる事を証した代表作でもある”(SYUGO.comより)
これは残酷を超えてる
というのが、読み終わった後の率直な印象である。
これは小説を文学の領域を超えてる。まるでゾラ自身の本質と本性を熱いまま鋳型に流し込み、そのまま取り出したゾラの等身大の思想と哲学そのものだ。
「居酒屋」よりも残酷で、「ナナ」よりも厭らしく悩ましい。「壊滅」より壊滅的で、「獣人」よりも野蛮で惨たらしい。
いい意味でも悪い意味でも、ゾラの全てを曝け出した作品である。
快楽や平穏や美を追及し、それらに執着するほどに、人類は自ら見出した理想に裏切られ、最後には残酷で残忍になる。
野蛮に成り果て、獣性を帯びた生き物に待ち構えるのは、醜い争いだけだ。そこで流された血は河へと注ぎ、その血と水でパンが作られ、怒り狂った民衆は血のパンにかじりつく。
結果、人類は野生化し、原始社会へと回帰する。
ゾラが唱えるユートピアとは、この素の原始社会を指すのだろうか。全ての思想や信仰、概念や想念が、文明や文化が、唯物や観念が消滅するまっさらな世界。
とにかく、ウンザリする程までに残忍なシーンが最後の最後までへばり付く。
血で血を洗うどころか、残虐が残酷を覆い尽くす。全てが悲惨過ぎる。
確かに、今でも私の田舎の状況は、この頃に比べればずっと良くはなってるけど、本質的にはこれに近い。
農民の土地や過去や慣習に対する執着の根が深過ぎて、些細な事で醜い争いが絶え間なく続く。
これは農村だけの田舎だけの問題でもない。SNSでも、ほんの些細な事で誹謗中傷を浴びせられ、貴重な正論は炎上し、稚弱なデマや陰謀が昨今のネット社会でも渦巻く。
つまり無能が暴走し、無学に歯止めが効かず、古き農耕族の因習に囚われたまま、腐敗し、獣人化し、凶暴化し、死滅する。
これこそが、我ら日本人という農耕族の宿命なのだろうか。
凶暴化した一族と、悲壮で重厚な物語
この「大地」でも、これと同じ様な負のサイクルが延々とブローアップされる中、この悲壮な腐敗と幻滅に何とか歯を食いしばり抵抗する、イタリア遠征からの帰還兵で出稼ぎ農夫のジャンに加え、一族の長老のフーアン爺、それにフーアンの姪でジャンの恋人のフランソワーズ嬢らの孤軍奮闘が延々と続き、悲壮で重厚な物語を支配する。
彼らは決まった様に、凶暴化した一族の犠牲となる。
最初から最後まで飽きずに続く、このおぞましい展開が読者の魂を痛めつけ、良心を蝕む。
特に、フーアンの末弟ビュトーと妻の悍ましい程の土地に対する執着は、この惨劇のエゲツないドン百姓のドラマに、より一層の恐怖を植え付ける。
人間の本性の全てを、この作品の全てを支配する存在でもあリ、この作品の最大のテーマでもある。
とはいえ、この作品の舞台となるボース平野を支える小麦畑群が、ブロンドのテーブルクロスの様に鮮やかに輝き波打つシーンは眩いばかりである。
このローニュ村の壮大華麗な光景こそが、日頃の単調な重労働に疲弊しきった農夫たちを、日常の狂気から救い出してくれる。
全てが、黄金の色彩と壮大な質感を帯びたモネ風の風景画のようで、この印象絵画的なゾラの特異の描写こそが小説の背景となり、この悲壮で陰湿なドラマを支える原動力となる。
最後に(追記)〜神は人類など相手にしない
罪を犯してまでも愛する大地。それは人間のおぞましさや悲惨さを携え、未知の目的に向け、生命を更新していくのだ。
ジャンはもはや大地を耕す気持ちを捨て、フランスの大地を守る為だ。死者は大地の中で眠り、その上に積麦が蒔かれ、麦穂は黄金の輝きを増し、そしてその黄金の大地からパンは生み出される。
寄せられたコメントにあった様に、ジャン•マッカールは善良すぎた。ジャンの支配人で農場主の愛人コニェットと手を組み、農場主と愛人のコニェットを殺害しても、母なる”大地”は全く揺らがなかった筈だ。
事実、コニェットはジャンを求めていた。婚約者フランソワーズをフーアン一族に殺されたばかりのジャンも、一族への復讐と性のはけ口は必要だった筈だ。でないと、ルーゴン=マッカール一族の複雑怪奇な悪のプライドが許さない。
でもこれこそが、ゾラの美しきロマンチシズムの新骨董であり、ゾラの優しさが垣間見える。
大地は空間でもあり、時間でもある。人類の負の歴史も負の空間も、全てを呑み込んで来たのだ。その大地も自然のありとあらゆる災害で痛めつけられ、またそれら自然の恩恵を必要としてきた。
同じように、人類が前進するには時に血も悪も必要なのだ。大地の大らかさに比べれば、人間の不幸や悪事にどれほどの重みがあろう。
神は人間など相手にしない。大地だけが不滅であり、平穏であり、人間が生れ戻っていく母なのだ。










聖なる大地が母親で、荒れ狂う自然が父親で、
それに兄弟喧嘩ばかりする強欲な人間たちの三つ巴の色彩も鮮やかだ
荒れ狂う自然を支える大地ですか
まるで長年連れ添った夫婦みたいですね。
そして、出来の悪い人類という事かな
父なる自然と残酷な人間社会を見てたんだわ
神様もそんな現実をじっと見つめてるだけ
ゾラってやっぱりロマンチスト💘
主人公のジャンマッカールの性格が善良すぎて穏やかなようにも思うが、それと対照的にフーアン一族の悪どく強すぎる個性が、大地の鮮やかな色彩をベースに異質な立体感を絞り出す。
フーアン一族の悪どさがしつこすぎて、ゾラを自然文学を嫌いになった民も多いだろうが、一つの色彩として考えれば悪くない。
最後は、ジャンが善人のまま何を得ることなく愛し続けた農場を去っていくが、通常なら支配人の愛人と手を組み、農場を奪い、支配人と愛人を殺害するくらいの悪どさがあってもバランスは取れてたはずだが。
ということで星4つ
バルザックは貴族やブルジョアの傲慢な性癖を、ゾラは庶民の獰猛な性癖を見事に描き出してます。
結局、現実は指を加えて見つめる事しか出来ないんですかね。最後は悲しかったです。
最後はやはり、ジャンマッカールの復讐劇を期待しました。
でないと、ルーゴンマッカール一族の複雑怪奇な悪のプライドが許さない。
清楚なフランソワーズよりも、淫乱女のコニェットと一緒になってた方が幸せになってたかもしれませんね。
この文言一つに妙に納得しました
私はあり得ない奇跡を待ち、いるはずの無い神に手を合わせております
東日本大震災の時に被災地の老人が泣きながら訴えておりました
『神も仏もあったもんじゃねえ』とね
その時気が付きましたよ
あるとしたら宇宙全体が神だと思っております
しかし象が転んださんのレベルは高いですね・・・
お邪魔しました
見当はずれのコメントでしたらごめんなさい。
ゾラの作品は一貫して、”ああ無情”なんですよ。”神も仏もあったもんじゃない”的展開です。でも不思議と美しい。痛い程に痺れる程に美しい。
でもこれこそがゾラの美しきロマンチシズムの新骨董なんですよね。