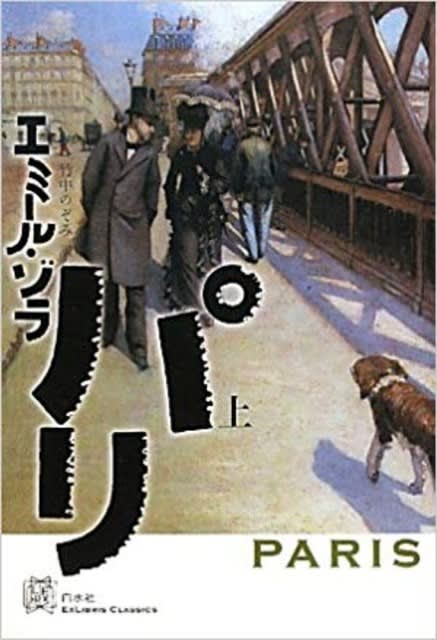
連日の様に、”広島と長崎原爆の違い”ブログにアクセ頂いた方どうも有難うです。
この「パリ」(エミールゾラ著、竹内のぞみ訳)に登場する主人公フロマン兄弟の、兄ギョームが開発する高性能の”火薬爆弾”こそが、爆弾テロや原爆のモデルとなってる(だろう)事は、少し皮肉にもまた驚きにも思える。
”チャーチル、その8”で書いた様に、事実、フランスはドイツに対抗し、両国は世界で初めて原爆の研究を行ってたのだ。
つまり、ギョームが開発した”次世代の火薬爆弾”こそが原爆だと見なすのは、早急すぎるのか?事実、原理的には火薬をウランに変えただけである。
原爆のモデルとゾラが描いたパリ
そこで今日は、”原爆のモデル”の起点となった?「パリ」の紹介です。この記事は、過去にアマゾンに投稿したものですが、誰も読んでくれないので(悲)、大幅に加筆&更新し、ブログにします。
”政治は腐敗し、無政府主義やテロが横行し、ブルジョワが隆盛を極め、労働者は貧困に喘ぐ19世紀末のパリ。
その悪徳と矛盾の町を見下ろす様に、モンマルトルの丘ではサクレ=クール寺院の建設が急ピッチで進められてた。そこに、信仰を失い魂を彷徨わせる神父ピエールがいた。
貧民救済に奔走するある日、彼は男爵邸での爆発事故を目撃する。その現場には何故か?化学者である兄ギョームの姿があった。
「ルーゴン=マッカール叢書」で描かれた第二帝政期以後の、さらに激変した現代都市パリを活写した超大作”
との触れ込みに、ゾラファンなら思わず手が伸びた読者も多いだろう。
この作品の真の主人公は、神父のピエールや化学者のギヨマンではなく、彼らの心情を象徴するが如く、時には絶望的に、時には希望に満ちた様相で描かれる「パリ」そのものだ。
パリという大都市こそが、集団的無意識によって動かされながら、徐々に姿と構造を変えていく象徴なのだ。
飽食と格差の都パリを描いた“予言”の書
巻末の解説にある様に、1898年発刊のゾラの原書は、1908年(明治41年)に飯田旗郎により、翻訳されていた。故に、この”ゾラの予言の書”は、殆ど同時代に日本に伝わった事になる。
更に驚くのは、この翻訳の2年後の1910年に起きた”幸徳事件”を、ゾラはかなりの精度で予言してるのだ。
因みに、”幸徳事件”とは大逆事件の一つで、明治天皇の暗殺を計画したとして、社会主義者や無政府主義者を逮捕•起訴し、死刑や禁固刑判決を下した事件だ。
事実同時期には、米国でマッキンリー大統領暗殺、ポルトガル王国でカルルシュ1世暗殺など、無政府主義者や社会主義者、共和主義者によるテロリズムが多発し、この事件は国内にも大きな衝撃を与えた。
資本主義の発達と民主主義の機能不全で貧富の格差が拡大し、いらだったインテリと民衆の一部が爆弾テロに走るという世紀末パリの状況を描いたゾラの小説は、21世紀初頭の”9-11テロ”までをも予言してた事になる。
主人公は、”迷える”神父のピエール•フロマン(フロマン弟)。真の信仰を求めて聖職者となり、ローマとルルドと2都市を遍歴したが、答えを得られぬまま舞い戻ったパリで、格差の現実に直面し、信仰を失いかける。
そのピエールは、元機械工のサルヴァが不審な行動をとってるのを目撃する。だが驚いた事に、化学者の兄ギヨームとサルヴァが何かを話し合っている現場を見てしまった。
やがてピエールの不安は現実となり、サルヴァはついに直接行動に出て、男爵の馬車を爆弾で破壊しようとするが失敗。代わりに貧しい帽子女工が爆死する。
偶然、爆発現場に居合わせたピエールは、サルヴァの跡を追って負傷した兄を救い出す。ギヨームはピエールの介護を受け、何とか回復する。しかし、弟子のサルヴァが逮捕され、処刑されると、それをきっかけに、あるとてつもない計画を実行に移そうと決意する。
百年前のパリの全貌が明らかに
2010年に、白水社により刊行されたこの作品は、訳者の竹内嬢が解説してる様に、まるで百年前のパリの全貌が明らかになった、「パリ大全」とも言える。
主人公のフロマン兄弟は、腐敗したこの世紀末に憤りを感じ、良心と正義との間で苦悩する。しかし、最後には博愛が科学が労働が、二人に正義と真理を目覚めさせ、兄弟愛を取り戻し、パリを黄金に輝く未来へと導く。
物語の肉付けとして、無政府主義者による爆弾テロ、公開処刑、議会の汚職など、実際過去に起きた実例をモデルにした。
当時、政治的社会的にも多大な影響を誇った新聞界の買収や、ブルジョアの胎動や腐敗を織り交ぜ、実に見事に詳しく細やかに描いてる。
そして、最後に唯一望みを託されたのが、科学技術の急激な進歩だった。事実、1855年から84年の間にパリで開催された4度の万国博は、産業革命が生活にもたらした変化の象徴でもあった。
現代の核兵器?
プロシア軍を壊滅させる為の”大量破壊兵器”として、フランス軍に提供する計画だった、ギョームの発明した新型爆薬。
”現代の核兵器”とも受け取れかねないこの最終兵器のお陰で、ギョームは一時的な狂乱に苛まれ、大聖堂の破壊に使う事を決意し、我を失いそうになる。
しかし弟ピエールが、間一髪でその現場を発見し、兄を説得する。お陰で、この新型爆薬は、小型発動機の動力源として再開発され、人類の平和と労働の為に使われるのだ。
結局、ブルジョアにとって正義とは真理とは金であり、労働者にとっては、富の公平な分配であり、良識ある知識人にとっては、情熱と博愛である。
しかし、極貧層の民にとっては、復讐こそが破壊行為こそが正義なのだ。これは今も昔も全く変わらない。
特に前半は、これら4つの階層の諸々の対立と対比が、実際に起きた様々な歴史的事件をモチーフに肉付けされ、諸々の哲学を展開させ、人間ドラマを家族を巻き込み、壮大なスケールのパリ物語を形作る。
「ルーゴン•マッカール叢書」とは味付けが多少異るが、ゾラのファンなら、無視できない必読の一冊である。
科学か宗教か?正義か破壊か?
前半から中盤に掛け、コッテリとした重々しい展開と、ウンザリする程の哲学論。お陰で、サンシモン、フーリエの空想的神秘的社会主義と、コントにプルードンの無政府主義的実証哲学で、頭が一杯になった。
しかしそれは差し置いて、後半からフロマン兄弟の、特に、弟ピエールとマリーの愛の物語に傾いて行く辺りの、ノスタルジックでメルヘンチックな描写に、少し生温い物足りなさを感じなくもない。
傲慢なブルジョワと腐敗した議会。欺瞞に満ちたカトリック教会と、福音と慈悲に失望し、信仰を失った神父。貧困を背負い、不正義と不平等に中で苦しむもがく労働者。極貧が故に、凶暴化する最下層の浮浪者たち。
そんな中、科学だけが真理と正義を追い求め、泥沼化したパリを救い出そうと孤軍奮闘する。
しかし結果的に、巨悪は滅びず、金と汚職にまみれたブルジョワも議会もカトリック教会も健在なままだ。
倒壊しかかったパリは、科学の進歩と人類の博愛と労働のお陰で、何とか持ち堪えるが。そこに本当の未来はあるのか?
黄金に輝くパリの高揚を未来に託し、この物語は幕を閉じる。しかし、ゾラにしては非常に中途半端に意外な幕切れに思えた。
ドレフェス事件(1894)とゾラの失踪
事実、この後のドレフェス事件(1894)で、ゾラは、軍部を中心とする不正と虚偽の数々を徹底的に糾弾し、逆に名誉毀損で訴えられ、英国に亡命する羽目になる。
ゾラは、いくら科学が進歩し、労働者が公平な分配を、大衆が自由と正義を獲得しようが、地下深くで燻り続ける”国家の腐敗は消す事ができない”事を既に見抜いていた。
結局、彼が思い描く理想郷は、小説の中での淡い幻想に過ぎなかったのか?それとも、何らかの不穏な政治的圧力があったのか?
お陰で、極貧が故に暴徒化し、正気を失い、ブルジョワ邸に爆弾を投げ入れた、民衆の英雄になるべきサルヴァの死は全くの無駄になる。爆弾男の仕返しをしたマチスも100%悪者扱いされ、何とも後味の悪い結末だ。
主観的で身勝手な私めの要望としては、博愛的な科学者の兄ギョームに、パリを見下すあの憎き大聖堂を、新型爆薬で派手に吹っ飛ばして欲しかった。
でないと、サルヴァもマチスも貧困に喘ぐ弱者は報われない。主人公のピエールが兄ギョームの若き婚約者と結婚し、息子を授かり、それでギョーム家が、パリがハッピーエンドというのでは、少し虫が良すぎる。
対立が対立を生む最悪の悲劇
この作品のテーマは、科学とカトリシズムとの対立であり、ブルジョワと労働者との対立であり、同時にギョームとピエールの兄弟の思想の対立でもある。
科学者の執念か?神父の慈悲か?結局、二人とも極貧者の救い難い惨状に憤り、自分を見失ってしまう。
兄は国家に提供する筈の新型爆薬を、カトリック大聖堂を爆破する為に殉教を覚悟する。弟は信仰を捨て、慈善を切り捨て、僧衣を脱ぐ。
兄のかつての婚約者であったマリーと相思相愛になり、生を取り戻したピエールは、大聖堂爆破と共に死のうとする兄を、必死で引き留める。
かつて、兄から生と愛を授かった弟は、今度は兄に生と兄弟愛を授けるのだ。結局、寸での所で爆破を思い留まり、二人は兄弟愛を再確認する。
勿論、自爆テロなんて、ピエールが言う様に、許される事ではないし、科学者なら尚の事だだろう。
それに、爆弾テロが破壊がこの作品のテーマに成り得る筈もない。しかし、博愛に満ちた学者が感情に屈し、破壊行為に身を滅ぼす事に、一種の逆説的な同調を覚える読者は少なくない筈だ。勿論、私もその一人。
別に、”悪の帝王ヴォートランになれ”とは言わない。でも、万が一それができるとすれば、正体不明の”爆弾男”ジャンザンしかいない。彼が兄弟の会話を盗み聞きし、ギョームが果たせなかった大聖堂の爆破を、最後の最後で行使するという、大ドンデン返しの、いきなりの幕切れでも面白かったのでは。
そう思うのは私だけか?










ゾラも非常に複雑な思いでこの小説を書いた。しかし書ききれなかった。その悔しさと虚しさがゾラの失脚に繋がったと思う。
しかし、彼のこの作品は様々な形で、時代の変革において現実となった。この作品は、悲劇と惨劇で終わらせるべきだった。ブルジョアや教会に、等身大の庶民の恐怖を理解させるべきだった。
そうすれば、パリのノートルダムの、その後の歴史も変わってただろうと思うのは、私だけか。
ゾラの死因は、暗殺されたとの疑いもありますね。ドレフュス事件での軍部を中心とした不正と虚偽は、第二次大戦でも当然のごとく繰り返されましたから。
ゾラは政府や軍部の汚職がそのまま国家の腐敗に繋がり、下層市民が暴徒化するのを全て見抜いてたんです。悪の帝王ヴォートランと爆弾男ジャンザンの対比も興味深く映りました。
世の中ってキレイにロマンチックに考えるほど、悪く汚い方向に傾くんですよ。どうしても。穏健派が時には強硬派になり、うまくバランスをとってる間はいいんですが。ロマンも暴走すると、悲しい結果を生む典型かもしれません。ゾラはそういった全てを見通してたんですかね。
『パリ』はゾラが失脚する原因となった作品で、結構力入ってますね。何とか最後にはゾラが目指すユートピアに繋げたかったんですが。感情移入しすぎましたか。
気持ち痛いほど理解できます。そういう私も最下層の民ですから。この作品は私が一番のお気入りですから、自然と感情移入しちゃいます。
ハッピーエンドにするか
バッドエンドにするか
結局、不完全燃焼に終わったから
ドレフェス事件で
とうとう怒りが頂点に達したんだよ
カポーティが『冷血』で
中途半端に終わったよね
そのケースとよく似てるよな
作家とても情熱的な人種なんだ
一つ間違うと狂気に走る
最後はとても口惜しかったです。
バッドエンドにしてたら
ドレフュス事件にゾラが首を突っ込む事もなかったでしょうに。
本当に残念です。