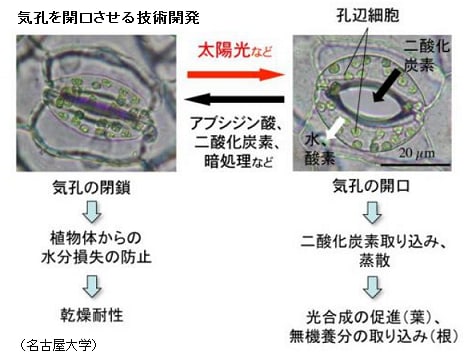宇宙を掃除する計画
スペースデブリ(Space debris)とは、宇宙ゴミのこと。地球の衛星軌道上を周回している人工物体のことである。宇宙開発に伴ってその数は年々増え続け、対策が必要となっている。
「スペースデブリ」の正体は何だろうか?それは耐用年数を過ぎ機能を停止した、または事故・故障により制御不能となった人工衛星から、衛星などの打上げに使われたロケット本体、その一部の部品、多段ロケットの切り離しなどによって生じた破片、デブリ同士の衝突で生まれた微細デブリ、更には宇宙飛行士が落とした工具…などである。
今回、日本の町工場でつくったワイヤー製の漁網で、宇宙のスペースデブリを落とす実験計画が進んでいる。網でそれこそ一網打尽に取り尽くすのだろうか?

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/
参考 Wikipedia: スペースデブリ