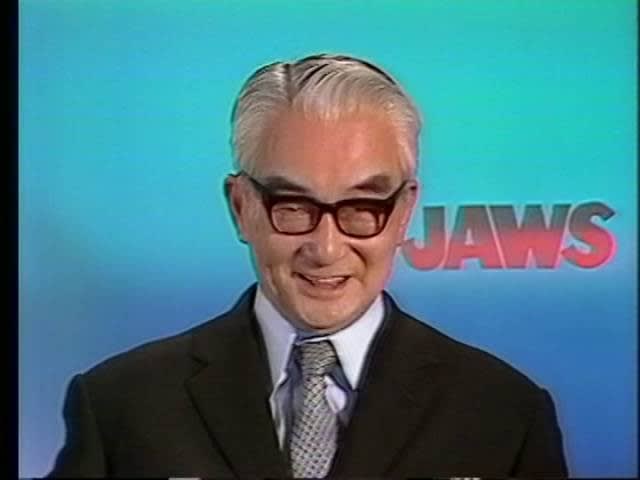<外国映画>
(2)『レイジング・ブル』(80)
ボクサーとして充分な才能があるにも関わらず、何度も何度も過ちを繰り返すジェイク・ラモッタの半生をモノクロームで描く。
破滅的な男の物語といえば、映画小僧にとってはこの映画なのだ。
…………………………………………
<日本映画>
(2)『天国と地獄』(63)
誘拐された「他人の子ども」を救うために大金を出せるかどうかの議論が繰り広げられる前半と、警察機構としてはどうかと思われる「陽動捜査」が展開される後半と。
作劇術を学ぶテキストとしては、これに勝るものはないと思う。

…………………………………………
明日のコラムは・・・
『年末年始特別企画(3) 映画のオールタイム15傑をヒトコトフタコトで語る』
(2)『レイジング・ブル』(80)
ボクサーとして充分な才能があるにも関わらず、何度も何度も過ちを繰り返すジェイク・ラモッタの半生をモノクロームで描く。
破滅的な男の物語といえば、映画小僧にとってはこの映画なのだ。
…………………………………………
<日本映画>
(2)『天国と地獄』(63)
誘拐された「他人の子ども」を救うために大金を出せるかどうかの議論が繰り広げられる前半と、警察機構としてはどうかと思われる「陽動捜査」が展開される後半と。
作劇術を学ぶテキストとしては、これに勝るものはないと思う。

…………………………………………
明日のコラムは・・・
『年末年始特別企画(3) 映画のオールタイム15傑をヒトコトフタコトで語る』