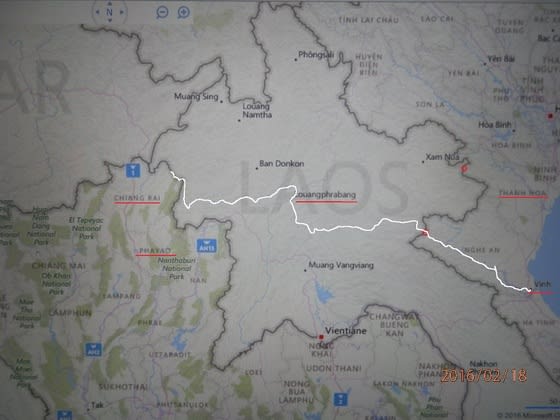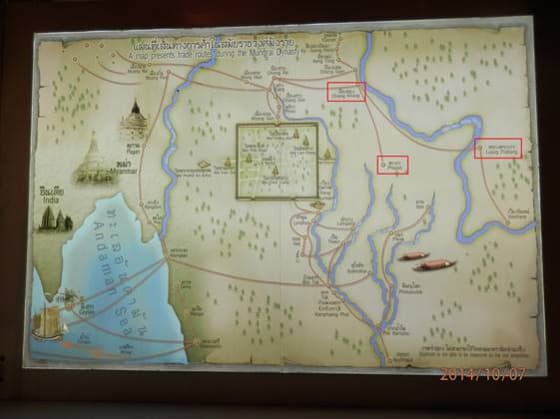次に工房を見学させて頂くと、丁度「打ち刷毛目」の作業中であった。まことにラッキーである。

その黒化粧土が半乾きすると、上の写真のように絵付け用の轆轤にセットし、轆轤をゆっくり回転させながら、スポイトを軽くつまんで白化粧用の泥漿を「の」の字状に絞り出す。そして写真のように刷毛で皿全面に、泥漿を刷毛掛けする。




宮内窯では、胎土が白く黒化粧してからの、打ち刷毛目作業であり上述の手順となるが、小石原皿山の「打ち刷毛目」は、轆轤引き後即白泥漿を刷毛により生掛けし、その手で打ち刷毛目の細工をしている。
その打ち刷毛目の実演がYouTube「小石原焼陶器市、刷毛目実演。」で公開されているので、御覧願いたい。宮内窯と小石原では手順がことなるが、双方共に素焼き後の作業ではない点が共通である。
そこで、先日紹介したサンカンペーンの打ち刷毛目と思われる盤、写真ではあるが見て頂くと下の2点は「打ち刷毛目」であろうとの見解である。



飛び鉋の技法で可能かどうか質問すると、回答できる見識を持たないとのこと、誠実な陶工さんである。小石原や小鹿田皿山の飛び鉋にも、このような放射状の文様を見ないので、これは片切の刃物であろうか?更なる追及が必要である。
<了>