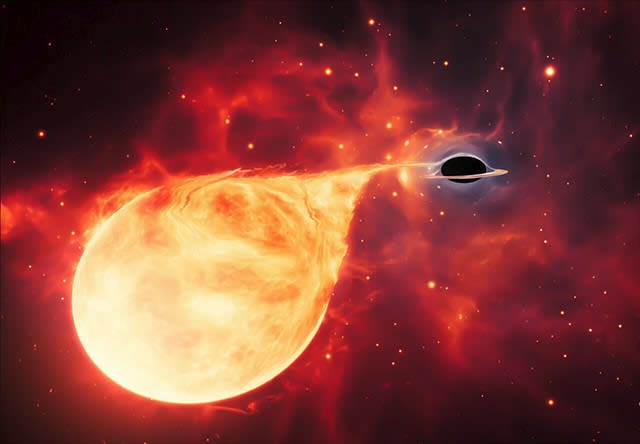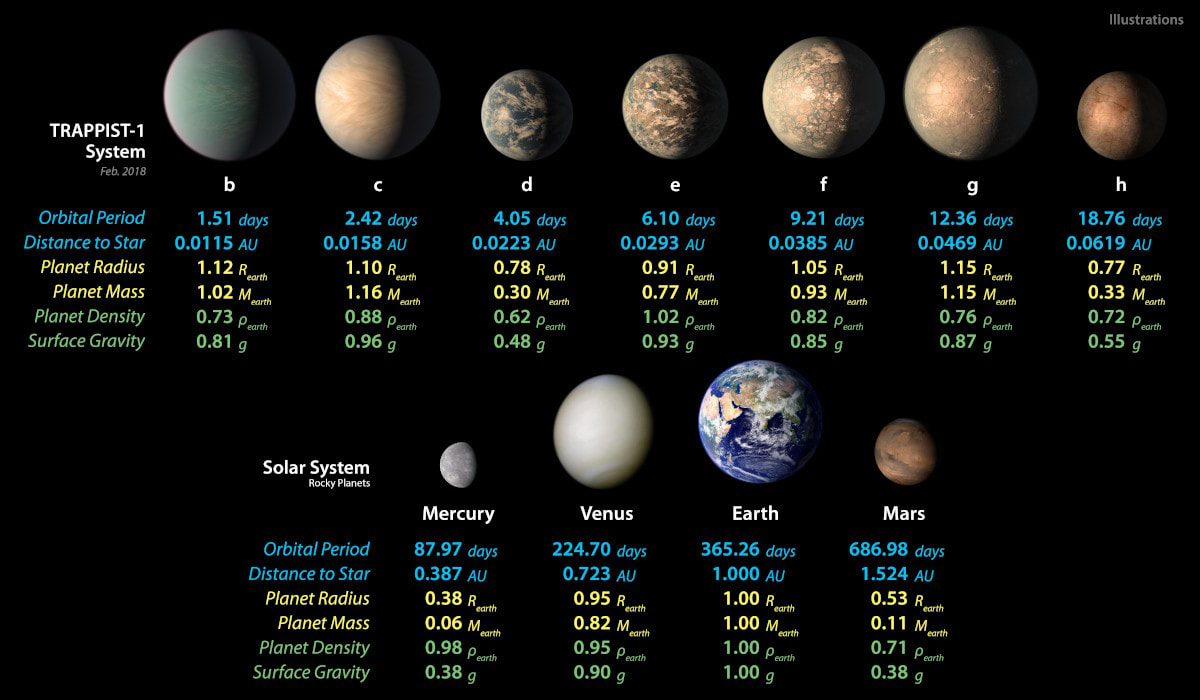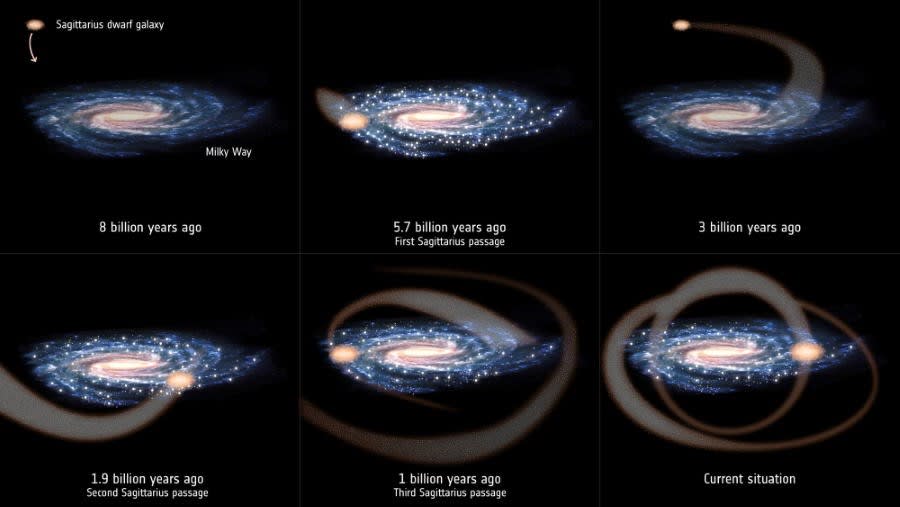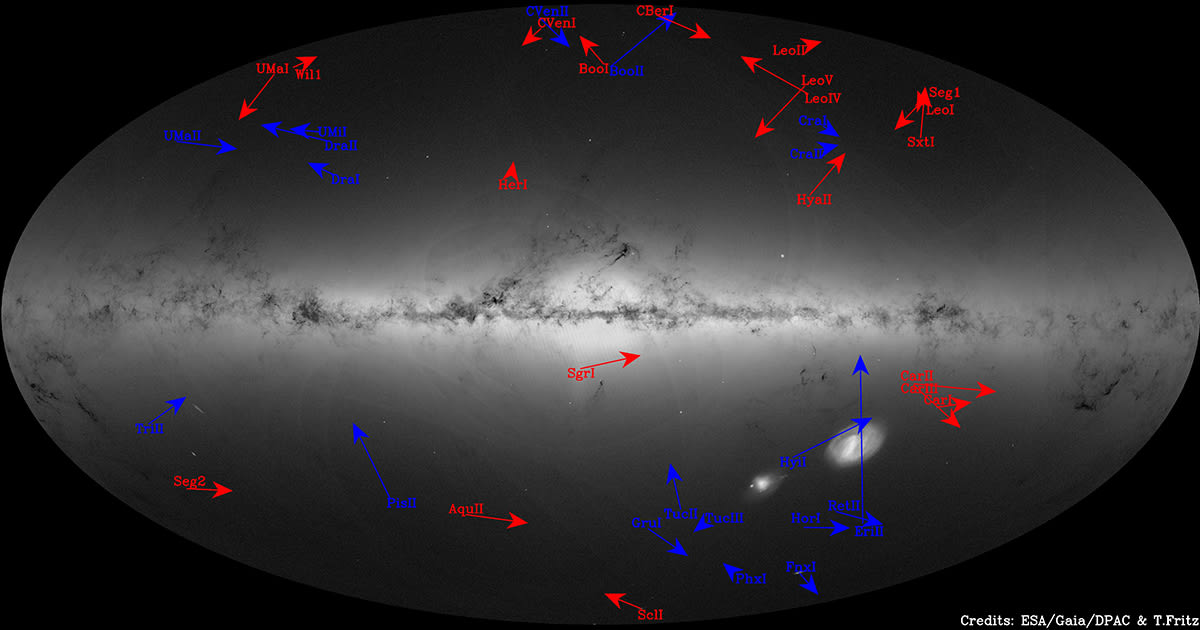都道府県をまたぐ移動の自粛解除が来ました!
梅雨に入っちゃいましたが、これで気兼ねなくツーリングに行けますね~
っということで、過去のツーリングを記事にするのは今回が最後です。
走りに行ったのは1年前の4月27日(土)。
次の日から天気は下り坂… っということで、フラ~っとプチツーリングで朝ご飯を食べてきました。
出発したのは朝の7時。 残念ながらすでに曇り空でした。
今回の目的地は明石港なので、高速は使わず国道2号を西に走っていきます。
1時間ほどで着いたのが、前から行ってみたかった“みなと食堂”さんです。
淡路ジェノバラインの乗り場が目の前にある食堂。 魚の棚商店街にも近いので、ブラブラ歩いて明石焼きを食べるのもいいですよ。
“みなと食堂”さんは創業が昭和15年の老舗の食堂です。
ひとことで言うと、昭和の香りがするこぢんまりとした大衆食堂。
並べてある総菜や壁に貼られたメニューから、港で働く人たちの胃袋を満たしてきたんだなぁ~ っと想像しちゃいます。
さて、店内を一通り見渡したところで朝食の注文です。
明石と言えば真たこの水揚げ日本一! それに鯛や穴子も有名ですよね。
今回は初めてなので、“みなと食堂”さんの名物メニュー“焼き穴子どんぶり”と“明石たこ入だし巻玉子”を注文しました。
まずは、トロトロの玉子でとじられた焼き穴子の丼。
量の割に穴子の香りと味がしっかりとしていて、味付けは少し濃いめでした。
少し変わっているのは、つゆだく状態の明石たこ入りの出汁巻き玉子。
ふわとろなので、玉子焼き(明石焼き)のように崩れやすく、たこの食感がいいアクセントになってました。
どちらも、絶品ってわけじゃないけど、大衆食堂の美味しい料理。
店の雰囲気も含めて、バイクじゃなかったらビールを注文したいメニューでした。
和歌山方面のツーリングだと、和歌山駅近くにある“ねぼけ食堂”さんが朝の7時から営業しています。
淡路島や四国方面へのツーリングでは“みなと食堂”さんが朝7:30から営業しているので、ここで朝食を食べてから目的地に向うのもありですね。
こちらの記事もどうぞ
梅雨に入っちゃいましたが、これで気兼ねなくツーリングに行けますね~
っということで、過去のツーリングを記事にするのは今回が最後です。
走りに行ったのは1年前の4月27日(土)。
次の日から天気は下り坂… っということで、フラ~っとプチツーリングで朝ご飯を食べてきました。
出発したのは朝の7時。 残念ながらすでに曇り空でした。
今回の目的地は明石港なので、高速は使わず国道2号を西に走っていきます。
1時間ほどで着いたのが、前から行ってみたかった“みなと食堂”さんです。
淡路ジェノバラインの乗り場が目の前にある食堂。 魚の棚商店街にも近いので、ブラブラ歩いて明石焼きを食べるのもいいですよ。
“みなと食堂”さんは創業が昭和15年の老舗の食堂です。
ひとことで言うと、昭和の香りがするこぢんまりとした大衆食堂。
並べてある総菜や壁に貼られたメニューから、港で働く人たちの胃袋を満たしてきたんだなぁ~ っと想像しちゃいます。
さて、店内を一通り見渡したところで朝食の注文です。
明石と言えば真たこの水揚げ日本一! それに鯛や穴子も有名ですよね。
今回は初めてなので、“みなと食堂”さんの名物メニュー“焼き穴子どんぶり”と“明石たこ入だし巻玉子”を注文しました。
まずは、トロトロの玉子でとじられた焼き穴子の丼。
量の割に穴子の香りと味がしっかりとしていて、味付けは少し濃いめでした。
少し変わっているのは、つゆだく状態の明石たこ入りの出汁巻き玉子。
ふわとろなので、玉子焼き(明石焼き)のように崩れやすく、たこの食感がいいアクセントになってました。
どちらも、絶品ってわけじゃないけど、大衆食堂の美味しい料理。
店の雰囲気も含めて、バイクじゃなかったらビールを注文したいメニューでした。
 |
和歌山方面のツーリングだと、和歌山駅近くにある“ねぼけ食堂”さんが朝の7時から営業しています。
淡路島や四国方面へのツーリングでは“みなと食堂”さんが朝7:30から営業しているので、ここで朝食を食べてから目的地に向うのもありですね。
こちらの記事もどうぞ