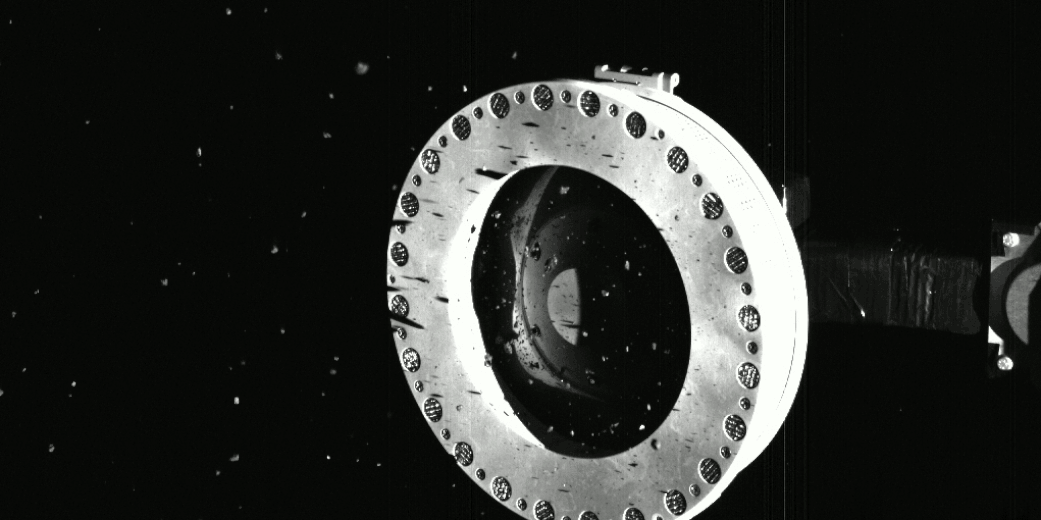2020年12月6日に地球帰還を果たした小惑星探査機“はやぶさ2”。
次の目標天体へ向かう拡張ミッション“はやぶさ2#(シャープ)”の航行中に、およそ半世紀ぶりに黄道光の観測を実施したそうです。
8月22日、内惑星領域における惑星間チリの分布を計測することに成功したことが、東京都市大学、関西学院大学、九州工業大学、JAXAの4者共同で発表されました。
でも、宇宙背景光の観測において最大の不定性要因になっていたのが、前景の明るい黄道光でした。
そこで、この不定性を低減させるため、黄道光の観測を行うことを目指します。
黄道光は、太陽系内に漂う惑星間チリが太陽光を散乱することで、天球上での太陽の平均的な通り道である黄道に沿った領域に生じる淡い光のこと。
黄道光は人間の目には淡い光ですが、宇宙背景光はさらに微弱な光になります。
黄道光を観測することで、太陽系内の最小天体である惑星間チリがどこで形成され、太陽系内をどのように移動しているのかを探ることができます。
惑星や小惑星などの探査とはまた別のアプローチで、太陽系のダイナミックな変化を知ることができるわけです。
黄道光は、惑星間チリによる太陽光の散乱光を視線方向に重ね合わせたもの。
これまでの観測は、主に地球の公転軌道から行われてきたので、手前と奥で散乱された光が重なってしまい、惑星間チリの空間分布を得ることができませんでした。
そのため、チリが太陽系内でどのように分布しているのかを理解するには、地球から離れた様々な場所から黄道光を調べる必要がありました。
それは、惑星間を航行する“はやぶさ2”を用いること。
“はやぶさ2”が小惑星“1998 KY26”へ向かう拡張ミッション“はやぶさ2#”(小惑星への到着は2031年を予定)において、目的地に到達するまで観測装置を温存するのではなく、積極的に活用する“クルージング サイエンス”でした。
この観測は、2021年~2022年にかけて光学航法望遠カメラ“ONC-T”を用いて、太陽からの距離(日心距離)0.7au~1.06auの範囲で実施。
そして、太陽系の内惑星領域で惑星間チリの分布情報を得ることに成功しています。
べき乗則とは、ある観測量が別の観測量のべき乗に比例する関係のこと。
今回の場合は、惑星間チリの個数密度(n)が、太陽からの距離(r)のべき乗則に従う、つまり“n(r)∝r-α”の関係が成り立つことが示され、べき指数を正確に決めることができました(同式のべき指数はα)。
観測されたべき指数が示す惑星間チリの濃度は、惑星間チリの太陽への落下のみを考慮した標準的な理論と比べ、太陽に近付くほど予測より濃くなることを示していました。
この結果が示唆しているのは、惑星間チリの太陽への落下についての新たな物理があるか、地球近傍で惑星間チリが生成されるなどの知られていない天体現象があることでした。
これは、1970年代にNASAの探査機“パイオニア10号”、“パイオニア10号”、“ヘリオスA号”、“ヘリオスB号”が黄道光を観測して以来、約半世紀ぶりの成果。
地球近傍からの黄道光観測では得られない情報で、惑星間を航行する“はやぶさ2”を用いたからこそ達成できた成果といえます。
これを受け、“はやぶさ2”による黄道光観測(及びより発展的な観測)を今後も引き続き継続し、特に2028年に予定されている地球スイングバイ以降は、地球公転軌道の外側(1au~1.5auの範囲)での黄道光観測の実現を目指すそうです。
今回の研究成果は、惑星間チリの研究だけでなく、研究チームがもともと研究対象としていた、黄道光に埋もれた微弱な宇宙背景光を観測するためにも役立つはずです。
今回のメンバーを含む国際研究チームでは、2023年冬に打ち上げ予定のNASAのロケット実験“CIBER-2”や、将来の惑星探査機により、黄道光や宇宙背景光をさらに詳しく観測するそうですよ。
こちらの記事もどうぞ
次の目標天体へ向かう拡張ミッション“はやぶさ2#(シャープ)”の航行中に、およそ半世紀ぶりに黄道光の観測を実施したそうです。
8月22日、内惑星領域における惑星間チリの分布を計測することに成功したことが、東京都市大学、関西学院大学、九州工業大学、JAXAの4者共同で発表されました。
今回の研究成果は、東京都市大学の津村耕司准教授、関西学院大学の松浦周二教授、九州工業大学の佐藤圭助教、同・瀧本幸司支援研究員、JAXA“はやぶさ2”ONCチームらの共同研究チームによるものです。
 |
| “はやぶさ2”での黄道光の観測イメージ。(イラスト:木下真一郎氏(出所:関西学院大・九工大共同プレスリリースPDF) |
惑星間チリが太陽光を散乱することで生じる淡い光
共同研究チームでは、これまでに遠方銀河や初期宇宙から届く微弱な光“宇宙背景光”の観測を通して、初期宇宙での星形成史を探る研究を実施してきました。でも、宇宙背景光の観測において最大の不定性要因になっていたのが、前景の明るい黄道光でした。
そこで、この不定性を低減させるため、黄道光の観測を行うことを目指します。
黄道光は、太陽系内に漂う惑星間チリが太陽光を散乱することで、天球上での太陽の平均的な通り道である黄道に沿った領域に生じる淡い光のこと。
黄道光は人間の目には淡い光ですが、宇宙背景光はさらに微弱な光になります。
黄道光を観測することで、太陽系内の最小天体である惑星間チリがどこで形成され、太陽系内をどのように移動しているのかを探ることができます。
惑星や小惑星などの探査とはまた別のアプローチで、太陽系のダイナミックな変化を知ることができるわけです。
黄道光は、惑星間チリによる太陽光の散乱光を視線方向に重ね合わせたもの。
これまでの観測は、主に地球の公転軌道から行われてきたので、手前と奥で散乱された光が重なってしまい、惑星間チリの空間分布を得ることができませんでした。
そのため、チリが太陽系内でどのように分布しているのかを理解するには、地球から離れた様々な場所から黄道光を調べる必要がありました。
目的地に到達するまで観測装置を活用する“クルージング サイエンス”
そこで、研究チームは効果的な観測方法を考えます。それは、惑星間を航行する“はやぶさ2”を用いること。
“はやぶさ2”が小惑星“1998 KY26”へ向かう拡張ミッション“はやぶさ2#”(小惑星への到着は2031年を予定)において、目的地に到達するまで観測装置を温存するのではなく、積極的に活用する“クルージング サイエンス”でした。
 |
| 黄道光の観測のイメージ。惑星間チリによる太陽光の散乱光を、視線方向の重ね合わせとして見えているのが黄道光。“はやぶさ2”は地球軌道の内側、0.7au~1.0auの範囲を航行している。(Credit: 出所:都市大Webサイト) |
そして、太陽系の内惑星領域で惑星間チリの分布情報を得ることに成功しています。
べき乗則とは、ある観測量が別の観測量のべき乗に比例する関係のこと。
今回の場合は、惑星間チリの個数密度(n)が、太陽からの距離(r)のべき乗則に従う、つまり“n(r)∝r-α”の関係が成り立つことが示され、べき指数を正確に決めることができました(同式のべき指数はα)。
 |
| “はやぶさ2”が観測した黄道光の明るさの日心距離依存性。(出所:関西学院大・九工大共同プレスリリースPDF) |
この結果が示唆しているのは、惑星間チリの太陽への落下についての新たな物理があるか、地球近傍で惑星間チリが生成されるなどの知られていない天体現象があることでした。
これは、1970年代にNASAの探査機“パイオニア10号”、“パイオニア10号”、“ヘリオスA号”、“ヘリオスB号”が黄道光を観測して以来、約半世紀ぶりの成果。
地球近傍からの黄道光観測では得られない情報で、惑星間を航行する“はやぶさ2”を用いたからこそ達成できた成果といえます。
これを受け、“はやぶさ2”による黄道光観測(及びより発展的な観測)を今後も引き続き継続し、特に2028年に予定されている地球スイングバイ以降は、地球公転軌道の外側(1au~1.5auの範囲)での黄道光観測の実現を目指すそうです。
今回の研究成果は、惑星間チリの研究だけでなく、研究チームがもともと研究対象としていた、黄道光に埋もれた微弱な宇宙背景光を観測するためにも役立つはずです。
今回のメンバーを含む国際研究チームでは、2023年冬に打ち上げ予定のNASAのロケット実験“CIBER-2”や、将来の惑星探査機により、黄道光や宇宙背景光をさらに詳しく観測するそうですよ。
こちらの記事もどうぞ