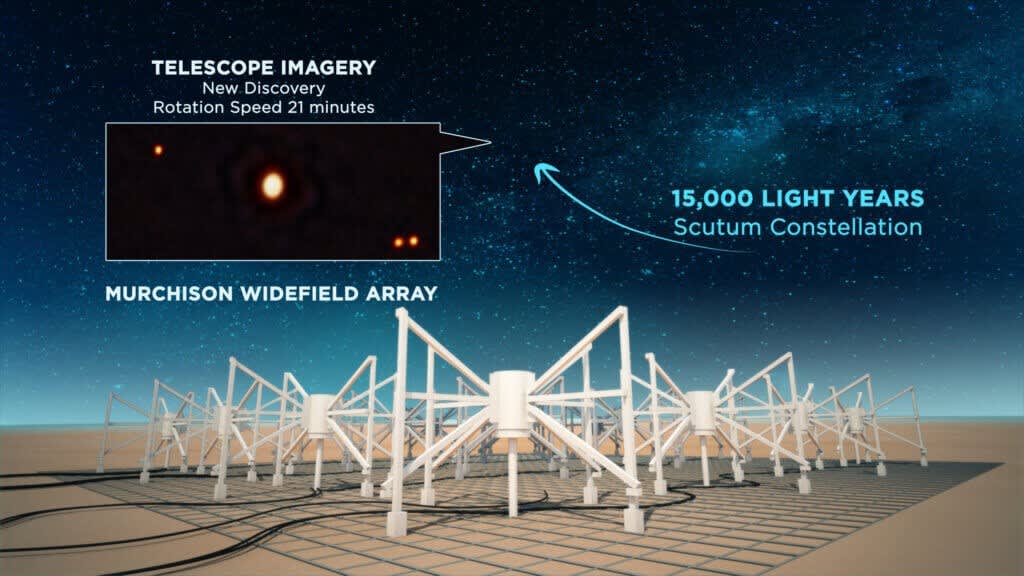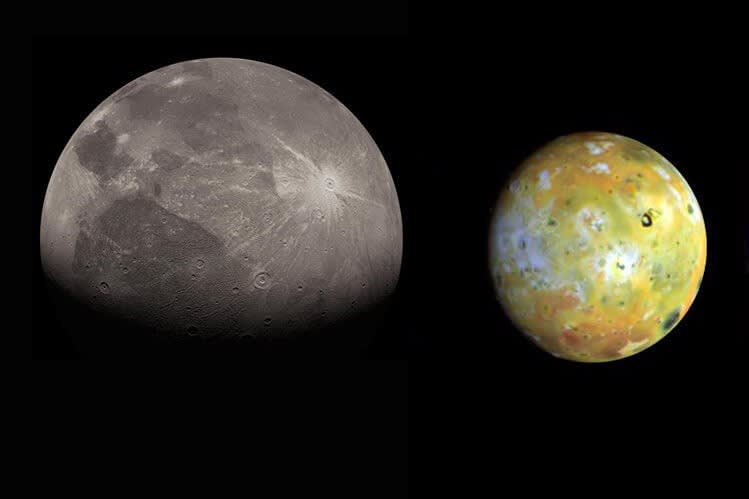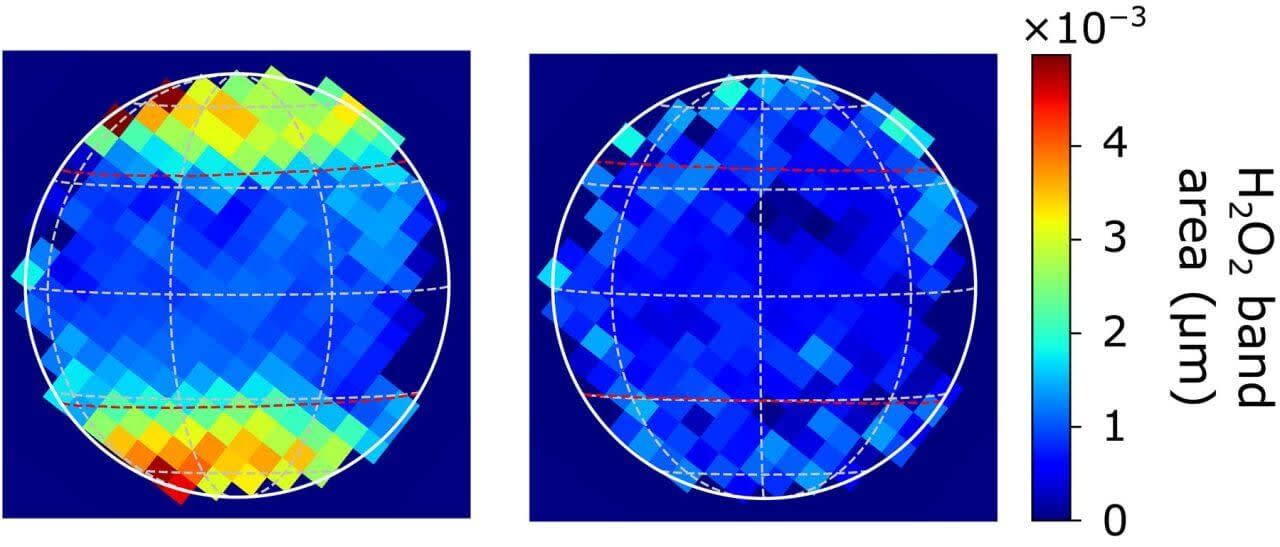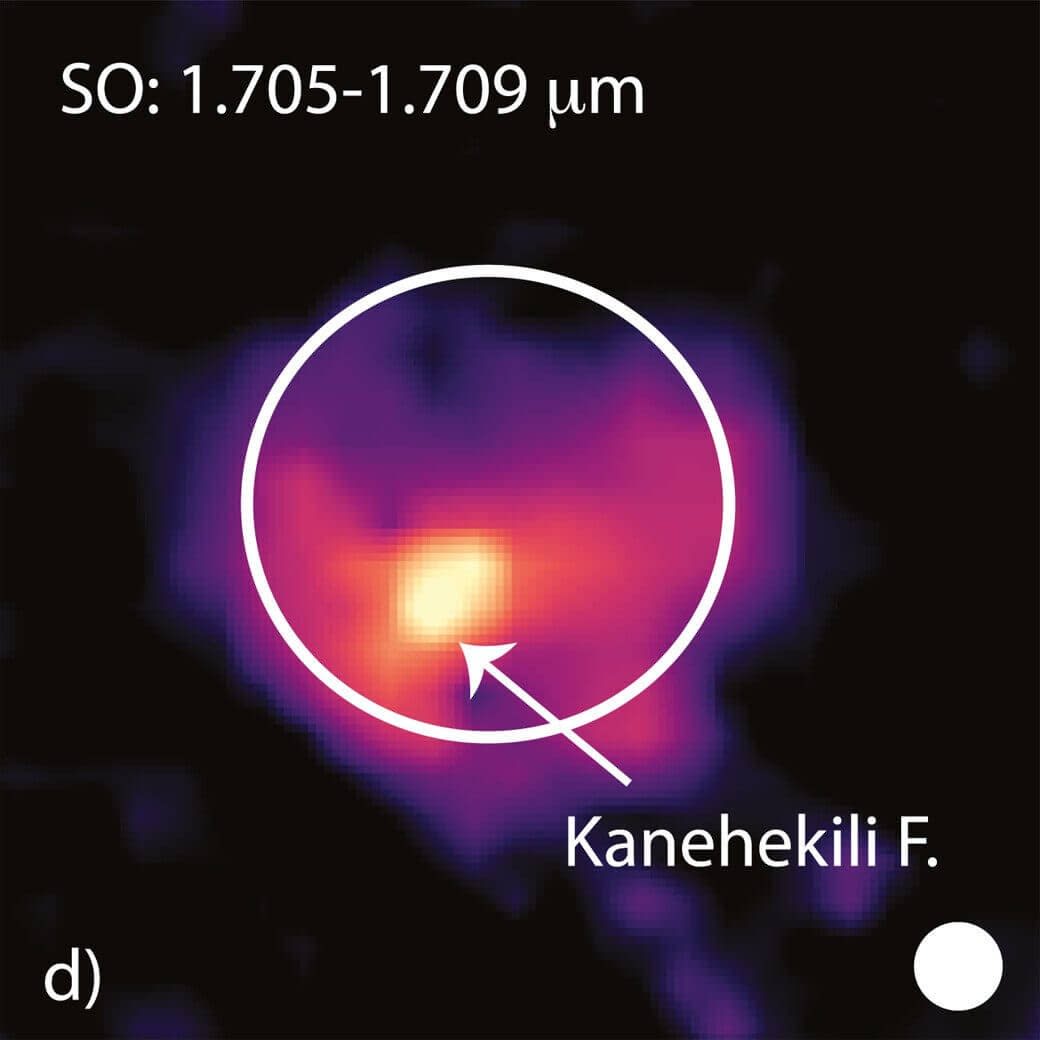植物にとって、風などで横倒しにされた状態が続くのは好ましい状況とはいえませんよね。
なので、植物は速やかに自分の状態を検知し、反応することが知られています。
つまり、植物は重力の向きを検知できる仕組みを持っているということになります。
それでは、重力の向きを感知できない宇宙に持って行った場合には、植物はどう反応するのでしょうか?
この疑問に答えるため、研究チームでは2014年から国際宇宙ステーションで、植物の“シロイヌナズナ”を使った実験を実施してきました。
この研究成果が、2023年7月11日に金沢大学から発表されています。
一般には雑草の範疇に入る植物ですが、科学会では偉大な存在になっています。
それは、“シロイヌナズナ”はゲノム解析が終了していて、遺伝子の働きやタンパク質などについて、全植物中で最も詳しく調べられているから。
このことから、数多くの実験で用いられていて、“4大モデル生物”の1つなどと呼ばれています。
“シロイヌナズナ”は小さいので育てるのに場所を取らないこと、発芽から種を付けるまでの一生が約2か月と短いことなどから、国際宇宙ステーションでの実験にも適していて、数多くの宇宙実験に活躍してきました。
また、ゲノムサイズも小さく、世界中に生息していて地域ごとに分化しているので、遺伝学的な研究でもメリットの多い植物として知られています。
装置内のシロイヌナズナが育ったのは、地球の表面と同じ1Gを再現した環境と、国際宇宙ステーションの微小重力環境(ほぼ無重力の状態)という、重力の異なる2種類の環境でした。
この研究では、植物が細胞膜に持っているイオンチャネル(イオンを通すためのミクロの穴)の1つである“MCA1”に着目。
“MCA1”は、重力の変化の影響を受けるイオンチャネルの1つで、風などで植物が倒れると“MCA1”が開き(細胞膜に入り口ができる)、植物にとって重要なカルシウムイオンが細胞の外から内へと入っていくことが分かっています。
ちなみにイオンとは、いずれかの原子から電子が少なくなった状態、もしくは逆に多くなった状態のことをいいます。
通常、原子は電気的にプラスでもマイナスでもない中性の状態なのですが、イオンはどちらかの電荷を帯びています。
カルシウムイオンの場合、電子を失うのでプラスの電荷を帯びた陽イオンになります。
イオンの細胞への出入りは、神経を伝わる電流を生じさせるなど、人間を含む生命全般の活動において非常に重要なものです。
そこで、今回の研究では、以下の4種類のシロイヌナズナの種子を準備して、国際宇宙ステーションでの実験を行っています。
1.野生そのままのもの
2.MCA1を機能しないように遺伝子に手を加えたもの
3.MCA1自体が光るように遺伝子に手を加えたもの
4.細胞内カルシウムイオンを検出できるようにしたもの(発光試薬“エクオリン”を導入)
実験で確認されたのは、微小重力環境下のシロイヌナズナは自分を支えるために、近くに用意されたメッシュに根を絡みつかせること。
1Gの環境では、このような根の絡みつきは見られないそうです。
シロイヌナズナは重力がほぼない状態を感知し、自分を固定するために根を絡みつかせたのかもしれません。
さらに、4種類用意されたシロイヌナズナのうち、変異体(上記の2~4)の分析から、根の絡みつきはMCA1によって制御されている可能性があることも明らかになります。
MCA1の機能的な役割は完全に解明されているわけではありませんが、伸ばした根の先端が硬いものにぶつかったときにも大切な役割を果たすことが分かっています。
地上で生育する植物は、根を地中へと伸ばしていくときに頻繁に成長方向を変えて土壌中の障害物を避けたり、必要に応じて対象に絡みついたりしますが、それらにMCA1が関わっているのではないかと考えられています。
今後の研究により、重力受容におけるMCA1の機能的な役割が解明されると、重力方向の変化に敏感な植物を作成することができ、その植物は風雨などで倒れても素早く立ち直ることができるはずです。
さらに、MCA1の機能解明という基礎的な研究が穀物生産の増進に貢献できるだけでなく、月や火星といった低重力環境でも元気に育つような植物の品種改良につながると期待されています。
今後の研究により、MCA1のすべての機能が解明されるといいですね。
こちらの記事もどうぞ
なので、植物は速やかに自分の状態を検知し、反応することが知られています。
つまり、植物は重力の向きを検知できる仕組みを持っているということになります。
それでは、重力の向きを感知できない宇宙に持って行った場合には、植物はどう反応するのでしょうか?
この疑問に答えるため、研究チームでは2014年から国際宇宙ステーションで、植物の“シロイヌナズナ”を使った実験を実施してきました。
この研究成果が、2023年7月11日に金沢大学から発表されています。
この研究は、金沢工業大学 応用バイオ学科 辰巳仁史教授を中心とする共同研究チーム、および羽衣国際大学、名古屋大学、JAXAの研究者が進めています。
数多くの宇宙実験に活躍しているシロイヌナズナ
実験に使われた“シロイヌナズナ”は、いわゆる“ぺんぺん草”の仲間です。一般には雑草の範疇に入る植物ですが、科学会では偉大な存在になっています。
それは、“シロイヌナズナ”はゲノム解析が終了していて、遺伝子の働きやタンパク質などについて、全植物中で最も詳しく調べられているから。
このことから、数多くの実験で用いられていて、“4大モデル生物”の1つなどと呼ばれています。
“シロイヌナズナ”は小さいので育てるのに場所を取らないこと、発芽から種を付けるまでの一生が約2か月と短いことなどから、国際宇宙ステーションでの実験にも適していて、数多くの宇宙実験に活躍してきました。
また、ゲノムサイズも小さく、世界中に生息していて地域ごとに分化しているので、遺伝学的な研究でもメリットの多い植物として知られています。
 |
| 国際宇宙ステーションの日本実験棟“希望”で実験のサンプルを確認するJAXAの油井亀美也宇宙飛行士(2015年10月撮影)。(Credit: NASA) |
重力の変化の影響を受けるイオンチャネル
今回の研究では、遺伝子型の異なる4種類のシロイヌナズナの種子と生育培地を国際宇宙ステーションに運び、細胞培養装置で発芽生育させた後、地上に戻して分析が行われています。装置内のシロイヌナズナが育ったのは、地球の表面と同じ1Gを再現した環境と、国際宇宙ステーションの微小重力環境(ほぼ無重力の状態)という、重力の異なる2種類の環境でした。
この研究では、植物が細胞膜に持っているイオンチャネル(イオンを通すためのミクロの穴)の1つである“MCA1”に着目。
“MCA1”は、重力の変化の影響を受けるイオンチャネルの1つで、風などで植物が倒れると“MCA1”が開き(細胞膜に入り口ができる)、植物にとって重要なカルシウムイオンが細胞の外から内へと入っていくことが分かっています。
ちなみにイオンとは、いずれかの原子から電子が少なくなった状態、もしくは逆に多くなった状態のことをいいます。
通常、原子は電気的にプラスでもマイナスでもない中性の状態なのですが、イオンはどちらかの電荷を帯びています。
カルシウムイオンの場合、電子を失うのでプラスの電荷を帯びた陽イオンになります。
イオンの細胞への出入りは、神経を伝わる電流を生じさせるなど、人間を含む生命全般の活動において非常に重要なものです。
そこで、今回の研究では、以下の4種類のシロイヌナズナの種子を準備して、国際宇宙ステーションでの実験を行っています。
1.野生そのままのもの
2.MCA1を機能しないように遺伝子に手を加えたもの
3.MCA1自体が光るように遺伝子に手を加えたもの
4.細胞内カルシウムイオンを検出できるようにしたもの(発光試薬“エクオリン”を導入)
実験で確認されたのは、微小重力環境下のシロイヌナズナは自分を支えるために、近くに用意されたメッシュに根を絡みつかせること。
1Gの環境では、このような根の絡みつきは見られないそうです。
シロイヌナズナは重力がほぼない状態を感知し、自分を固定するために根を絡みつかせたのかもしれません。
さらに、4種類用意されたシロイヌナズナのうち、変異体(上記の2~4)の分析から、根の絡みつきはMCA1によって制御されている可能性があることも明らかになります。
 |
| 国際宇宙ステーションの微小重力環境で発芽生育した約10固体のシロイヌナズナ。長辺が約30ミリの白いメッシュ(長方形)にしがみつくように生育していた。画像はJAXA筑波宇宙センターで撮影されたもの。(Credit: 金沢工業大学) |
地上で生育する植物は、根を地中へと伸ばしていくときに頻繁に成長方向を変えて土壌中の障害物を避けたり、必要に応じて対象に絡みついたりしますが、それらにMCA1が関わっているのではないかと考えられています。
今後の研究により、重力受容におけるMCA1の機能的な役割が解明されると、重力方向の変化に敏感な植物を作成することができ、その植物は風雨などで倒れても素早く立ち直ることができるはずです。
さらに、MCA1の機能解明という基礎的な研究が穀物生産の増進に貢献できるだけでなく、月や火星といった低重力環境でも元気に育つような植物の品種改良につながると期待されています。
今後の研究により、MCA1のすべての機能が解明されるといいですね。
こちらの記事もどうぞ