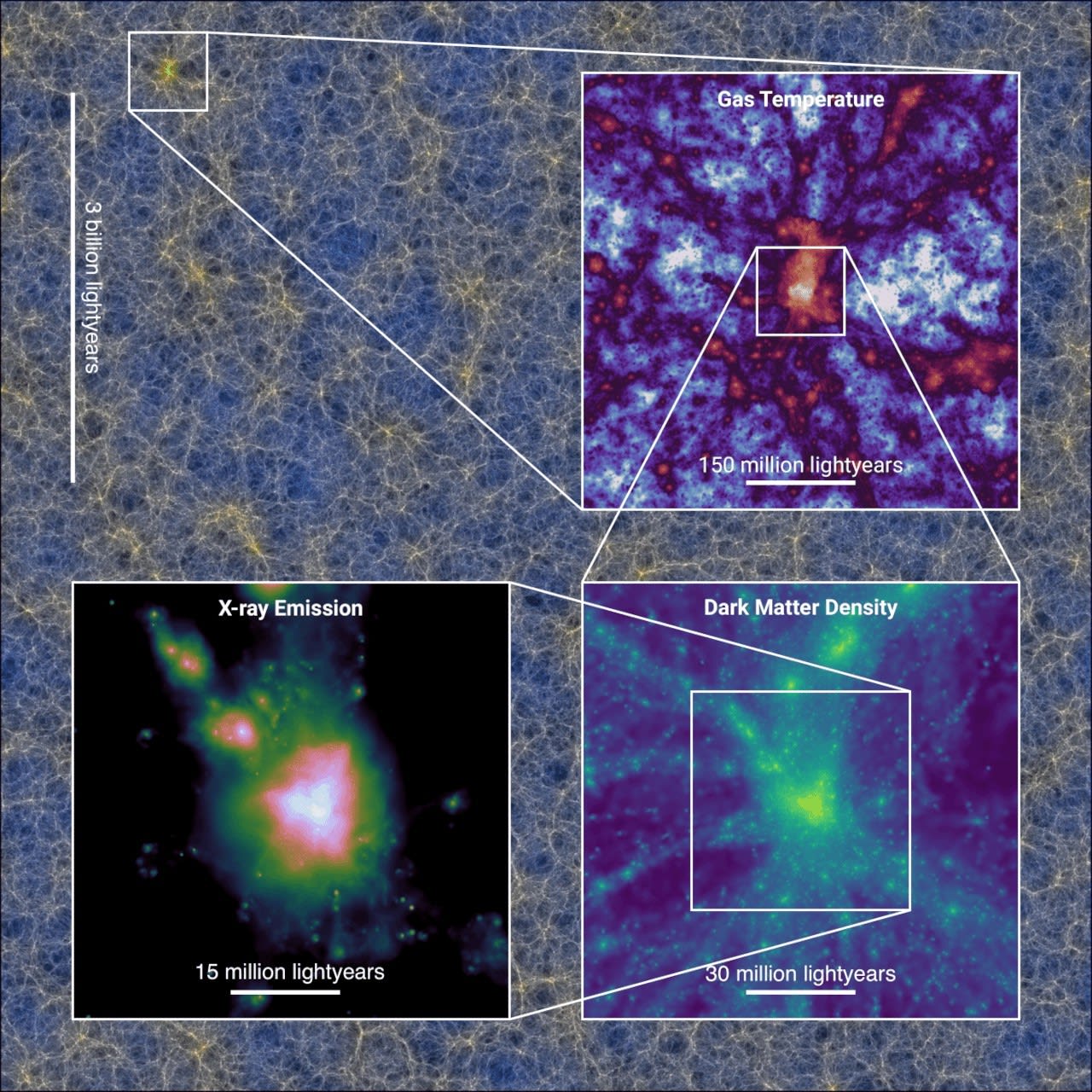火星は地質学的に不活発な惑星ですが、ときどき地震が観測されています。
その起源については、少なくとも8回は隕石の衝突による衝撃であることが判明しています。
今回の研究では、マグニチュード4.7を記録した観測史上最大の地震“S1222a”について、火星を周回している全ての探査機の撮影データを調査し、隕石衝突の痕跡があるかどうかを確認。
でも、それらの画像からは隕石衝突の痕跡が見つからなかったんですねー
このことから、“S1222a”は火星の地殻で発生した地震活動の可能性が高いことが判明。
地質学的に不活発な火星において、これほど大規模な地震が発生したことは興味深い発見になります。
これには、表面が不毛な環境で生命の存在が期待できないという意味もありますが、火星の地質活動が不活発なことを指した言葉でもあります。
直径が地球の半分ほどしかなく表面から水が失われた火星は、内部の熱が地球よりも速く冷めてしまい、地殻を動かすプレートテクトニクスが早期に停止していると考えられています。
このため、地震活動が活発な地球とは異なり、火星の地震は極めて頻度が低いと考えられています。
NASAにとって火星への着陸に成功した8機目の探査機“インサイト”は、火星の地震を高感度でとらえ、内部構造を推定するためのデータを取得することが目標の一つ。
火星の地震を正確に計測した初の火星探査機といえ、2018年から2022年までの4年間で1300回以上の振動を観測してきました。
その多くは隕石の衝突によるものであるとみられ、特に8回は隕石の衝突によることが確認されています。
最も規模が大きいものとしてはマグニチュード4.1±0.2の“S1000a”とマグニチュード4.0±0.2の“S1094b”が知られていて、地震の解析に役立つ表面波が観測されています。
“S1000a”と“S1094b”が隕石の衝突によるものであるという証拠としては、火星を周回している探査機が震源地(震央)に直径約150メートルの新たなクレータを撮影していたことが挙げられます。
2022年5月4日のこと、“S1000a”や“S1094b”よりもさらに大規模な地震“S1222a”が観測されました。
この地震の規模はマグニチュード4.7±0.2で、火星では観測史上最大の地震でした。
“S1222a”は、他の規模の大きな地震と性質が似ているものの、いくつかの異なる点があることも分かっています。
初期の分析結果が示唆していたのは、“S1222a”が1点に衝撃が加わる隕石衝突のような現象が原因ではないこと。
でも、隕石の衝突をはっきりと否定できるほどのものではありませんでした。
もし、“S1222a”が隕石によって発生した場合、予測されるのは直径300メートルほどのクレーターができること。
また、衝突の数時間後には舞い上がったチリによる雲が見られるなど、他の変化も撮影できるはずです。
このような規模の衝突は、100年に1回程度の頻度で起こると推定されます。
火星を周回する探査機のカメラは高解像度なものであるほど視野が狭いので、震源地を撮影していても衝突現場を見逃している可能性があります。
このため、研究で調べているのは、“S1222a”が発生したときに稼働していた探査機全ての画像データでした。
探査機全ての画像データを利用した研究は、今回が初めてのことでした。
HOPE(アル・アマル)(ムハンマド・ビン・ラシード宇宙センター)
エクソマーズ・トレース・ガス・オービター(ヨーロッパ宇宙機関)
マンガルヤーン(インド宇宙研究機関)
マーズ・エクスプレス(ヨーロッパ宇宙機関)
2001マーズ・オデッセイ(NASA)
マーズ・リコナサンス・オービター(NASA)
MAVEN(NASA)
天問1号(中国国家航天局)
徹底的な調査の結果、“S1222a”が発生したとみられる場所に、新たなクレーターや衝突による大気活動は見つからず…
このことは、“S1222a”が隕石の衝突によるものではなく、火星の地殻内部で発生した現象である可能性が高いことを裏付けていました。
“S1222a”の解析は初期段階にあり、まだまだ多くのことが分かっていません。
でも、地質活動が不活発であると考えられている火星で、これほど大規模な地震が発生するというのはとても興味深い発見でした。
今のところ、“S1222a”の震源は深さ18~28キロの傾斜したすべり面を持つ断層であると考えられていて、地殻内に蓄積した力(応力)が解放されて生じたもののようです。
ただ、そのために必要なのは、火星の地殻が場所によって収縮度合いが違うこと。
“S1222a”のような地震は、火星の地殻や内部構造が場所によって異なることを反映した結果であると考えられます。
“インサイト”の運用は終了してしまいましたが、未解析のデータは大量に残されています。
これらのデータや火星を周回する探査機のデータを用いたさらなる研究により、火星やそのほかの惑星の内部構造がより明らかになるといいですね。
こちらの記事もどうぞ
その起源については、少なくとも8回は隕石の衝突による衝撃であることが判明しています。
今回の研究では、マグニチュード4.7を記録した観測史上最大の地震“S1222a”について、火星を周回している全ての探査機の撮影データを調査し、隕石衝突の痕跡があるかどうかを確認。
でも、それらの画像からは隕石衝突の痕跡が見つからなかったんですねー
このことから、“S1222a”は火星の地殻で発生した地震活動の可能性が高いことが判明。
地質学的に不活発な火星において、これほど大規模な地震が発生したことは興味深い発見になります。
この研究は、オックスフォード大学ののBenjamin Fernandoさんたちの研究チームが進めています。
火星で観測された史上最大の地震“S1222a”
よく火星は“死んだ星”と表現されることがあります。これには、表面が不毛な環境で生命の存在が期待できないという意味もありますが、火星の地質活動が不活発なことを指した言葉でもあります。
直径が地球の半分ほどしかなく表面から水が失われた火星は、内部の熱が地球よりも速く冷めてしまい、地殻を動かすプレートテクトニクスが早期に停止していると考えられています。
このため、地震活動が活発な地球とは異なり、火星の地震は極めて頻度が低いと考えられています。
NASAにとって火星への着陸に成功した8機目の探査機“インサイト”は、火星の地震を高感度でとらえ、内部構造を推定するためのデータを取得することが目標の一つ。
火星の地震を正確に計測した初の火星探査機といえ、2018年から2022年までの4年間で1300回以上の振動を観測してきました。
その多くは隕石の衝突によるものであるとみられ、特に8回は隕石の衝突によることが確認されています。
最も規模が大きいものとしてはマグニチュード4.1±0.2の“S1000a”とマグニチュード4.0±0.2の“S1094b”が知られていて、地震の解析に役立つ表面波が観測されています。
“S1000a”と“S1094b”が隕石の衝突によるものであるという証拠としては、火星を周回している探査機が震源地(震央)に直径約150メートルの新たなクレータを撮影していたことが挙げられます。
 |
| 図1.上から“S1222a”、“S1094b”、“S1000a”のそれぞれの地震記録、P波到達を0秒とし、点線がS波到達時間を示している。“S1222a”は、“S1094b”や“S1000a”より大規模な地震のため、加速度のスケールが10倍違うグラフになっている。(Credit: Fernando, et al.) |
この地震の規模はマグニチュード4.7±0.2で、火星では観測史上最大の地震でした。
“S1222a”は、他の規模の大きな地震と性質が似ているものの、いくつかの異なる点があることも分かっています。
初期の分析結果が示唆していたのは、“S1222a”が1点に衝撃が加わる隕石衝突のような現象が原因ではないこと。
でも、隕石の衝突をはっきりと否定できるほどのものではありませんでした。
“S1222a”が火星の地殻で発生した地震活動の可能性
今回の研究では、“S1222a”が隕石の衝突であった場合に予測される火星表面の変化を見つけるため、火星を周回する探査機のデータを調査しています。もし、“S1222a”が隕石によって発生した場合、予測されるのは直径300メートルほどのクレーターができること。
また、衝突の数時間後には舞い上がったチリによる雲が見られるなど、他の変化も撮影できるはずです。
このような規模の衝突は、100年に1回程度の頻度で起こると推定されます。
火星を周回する探査機のカメラは高解像度なものであるほど視野が狭いので、震源地を撮影していても衝突現場を見逃している可能性があります。
このため、研究で調べているのは、“S1222a”が発生したときに稼働していた探査機全ての画像データでした。
探査機全ての画像データを利用した研究は、今回が初めてのことでした。
HOPE(アル・アマル)(ムハンマド・ビン・ラシード宇宙センター)
エクソマーズ・トレース・ガス・オービター(ヨーロッパ宇宙機関)
マンガルヤーン(インド宇宙研究機関)
マーズ・エクスプレス(ヨーロッパ宇宙機関)
2001マーズ・オデッセイ(NASA)
マーズ・リコナサンス・オービター(NASA)
MAVEN(NASA)
天問1号(中国国家航天局)
 |
| 図2.火星を周回する各探査機が観測した火星表面の範囲を示す地図。白い星印が推定震央で、黄色い四角が重点的にクレーターやその他表面の変化を探索した場所を示している。(Credit: Fernando, et al.) |
このことは、“S1222a”が隕石の衝突によるものではなく、火星の地殻内部で発生した現象である可能性が高いことを裏付けていました。
“S1222a”の解析は初期段階にあり、まだまだ多くのことが分かっていません。
でも、地質活動が不活発であると考えられている火星で、これほど大規模な地震が発生するというのはとても興味深い発見でした。
今のところ、“S1222a”の震源は深さ18~28キロの傾斜したすべり面を持つ断層であると考えられていて、地殻内に蓄積した力(応力)が解放されて生じたもののようです。
ただ、そのために必要なのは、火星の地殻が場所によって収縮度合いが違うこと。
“S1222a”のような地震は、火星の地殻や内部構造が場所によって異なることを反映した結果であると考えられます。
“インサイト”の運用は終了してしまいましたが、未解析のデータは大量に残されています。
これらのデータや火星を周回する探査機のデータを用いたさらなる研究により、火星やそのほかの惑星の内部構造がより明らかになるといいですね。
こちらの記事もどうぞ