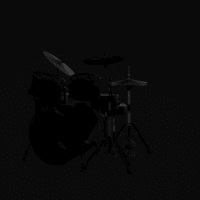以前このブログで、「ラファエル前派の軌跡」という展覧会のことを書きました。
そこでは、ジョン・ラスキンが重要な存在としてクローズアップされていました。
今回は、そのラスキンの経済学について書こうと思います。
これは、昨日書いた消費税の話ともつながってくるところがあり、また、もっと大きな視点でみても、現代世界の経済を考える参考になると思うのです。
ラスキンは、思想家、経済学者、芸術評論家……といったような、なんだか本職がはっきりしないような人ですが、出発点は美術評論家だったようです。
とりわけ、ターナーを評価したことで知られています。
ターナーが出てきた当初、その斬新な画風は画壇から批判を浴び、かのディケンズも批判したといいますが、ラスキンはそこに敢然と擁護の論陣を張ります。
これまでこのブログでは何度も書いてきましたが、新たな表現が登場した時には、たいていの場合激しい批判を浴びてきました。ターナーを擁護したということは、後から振り返れば、ラスキンの先見の明を示すものといえるでしょう。
そして、ラスキンはまた、経済学についても著作を残しました。
彼が経済学の道に足を踏み入れた動機は、ゴシック志向と根を一つにしています。
不均衡、不完全、混沌のなかで雑多なものが調和するゴシックに対して、近代の産業社会は人間にも画一化を迫り、疎外、排除の論理が働きます。イギリス産業革命は、過酷な環境で働く低賃金労働者を大量に生み出すことになり、そのことがラスキンの問題意識を呼び起こしたのです。
近代的な分業体制について、ラスキンは、「分割されたのは、労働ではなく人間だった」といいます。
複雑な作業工程の一部をひたすら続ける単純労働には、創造の喜びなどない。そこでは、人間は歯車の一つでしかない。ラスキンは、そういう非人間的な経済ではなく、人道的経済を主張しました。それが、ウィリアム・モリスの手工業運動につながっていったというのは、以前も書いたとおりです。
そういうわけで、ラスキンの経済学は、正統派の古典経済学を真っ向から否定します。
人間の道義や倫理観といったものが経済学では無視されている――そのことを強く批判し、“生の充実”を主眼とした独自の経済学を展開するのです。
ラスキンは、一般の経済学を「人間はすべて骨格でできていると仮定した無味乾燥な理論」のようなものとして否定します。その理論自体は正しいとしても、前提条件が間違っているので現実に適用することはできないというわけです。
人間は利己心のみで行動するという古典経済学の前提(これには異論もあるでしょうが)が成り立たない場合として、たとえば、ラスキンは『この最後の者にも』の中で次のような例を挙げています。
もし家に堅いパンが一片だけあり、母親と子供が飢餓に瀕しているならば、かれらの利害は同一ではない。もし母親がそれを食べれば、子どもは食べることができない。子どもがそれを食べなければ、母親は空腹をかかえて仕事に出なければならない。しかしながら、だからといって両者の間に「反目」が起こり、両者がその堅くなったパンのために闘い、そして母親が強いために、それを奪って食べるとはかならずしもいえない。
(飯塚一郎訳。中央公論社「世界の名著52」より。以下、引用はこの版による)
経済とは、つねに損得の計算だけで動くわけではない――ということです。
ただ、そこから損得の計算は無意味であるとまでいってしまうのはさすがに行き過ぎだと思いますが……
「全体のパイが大きくなれば貧しい者も豊かになる」という、いわゆる“トリクルダウン理論”も全否定しています。
ラスキンの論旨は明快です。
以下、『この最後の者にも』から、それについて語った部分を引用しましょう。
人々はほとんど常に、あたかも富裕が絶対的であって、ある一定の経済学的な教えに従うことによってだれでも富裕になることができるかのごとく発言し、また書いてもいる。それなのに実際は、富裕は電力のような一種の力であり、ただそれ自身の不均等ないしは反対物をとおしてのみ作用するものである。すなわち、諸君が財布のなかにもっているギニー貨の力は、まったく諸君の隣人の財布にギニー貨が不足していることによるのである。もし隣人がそれに欠乏していなかったならば、それは諸君にとって無益となるであろう。そのギニー貨の有する力の程度は、隣人がそれに対して有する必要ないしは欲望に正確に依存しているのである――それゆえ普通の商業的経済論者の意味において、みずから富裕になる術は、同時にまた必然的に諸君の隣人を貧乏にしておく術である。
すなわち、お金というものは、お金を持っていない人がいてはじめて意味がある。
お金がなくて、お金を必要とする人がいて、はじめてお金はその効力を発揮します。「裕福」とか「貧乏」とかいうのは、そういう相対的な概念なのです。
豊かさとはパイの割合を大きくすることであって、貧困とはパイの割合が小さいということである。パイそのものの大きさは関係ない、ということです。
ということはすなわち、「豊かになる」ということは「貧しい人との間にある資産の差を大きくする」ことであり、ある人が豊かであるためには、そのぶん誰かを貧しくしなければならないのです。
したがって、「誰もが豊かになる」ということは、少なくとも金銭的にはありえません。
そういう意味で、経済学は根本から問題設定を誤っている……ラスキンは、そういうのです。
正統派の経済学は、こうしたラスキンの主張を一顧だにしませんでした。
おそらく、「現実の経済を知らない素人の理想論」みたいな扱いをされてきたんだと思いますが……しかし、それから一世紀半ほどの時を経てみれば、ラスキンのいっていたことのほうが正しかったということなんじゃないかと思います。
古典経済学の理論が現実の経済からかけ離れているという点には、多くの人が首肯するでしょう。
そして、トリクルダウンが実際には機能しないということも、いまでは誰もが実感しているのではないでしょうか。経済学者のスティグリッツなんかも、「トリクルダウンが機能しないことはすでに証明済み」といってます。
なにより、“道義”という概念をまったく考えない金融資本の暴走が社会をむしばんでいる状態は、金融が肥大化するにつれて、無視できないレベルに達してしまっているのではないか。
この21世紀、資本主義経済が行き詰まりをみせるなか、ラスキンの経済学は見直されてもいいんじゃないでしょうか。