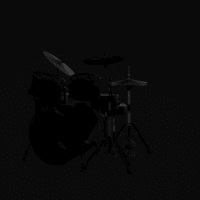今日は2月17日。
安吾忌です。
1955年の今日、作家の坂口安吾がこの世を去りました。
…というわけで、今日は坂口安吾について書こうと思います。
最近このブログの小説カテゴリーでは日本の文豪的な作家を扱っていて、前回登場したのは太宰治。安吾は、その太宰とともにいわゆる“無頼派”の双璧をなす作家であり、そこからのつながりということでもあります。
このブログでは、芥川龍之介も太宰治も三島由紀夫もロックだといってきましたが……もちろん坂口安吾もロックです。
安吾なんか、もう誰がどうみてもロックでしょう。
「日本は負け、そして武士道は亡びたが、堕落という真実の母胎によって始めて人間が誕生したのだ」などというのは、パンクそのものです。
さて、坂口安吾といえば、まず「堕落論」が有名でしょう。
先に引用したのも、「堕落論」の一節。
その「堕落論」を筆頭に、安吾は小説よりもむしろエッセイや評論のほうが注目されがちな印象もあります。
評論の対象は、文学や時事ばかりでなく、興味を持っていた囲碁など多岐にわたり……その一環としてか、安吾は推理小説に関する論考もいくつか発表しています。
坂口安吾と推理小説というのはあまり結びつかいないかもしれませんが、それらの論考を読むと、相当に内外のミステリーを読み込んでいることがわかります。
アガサ・クリスティを第一にあげ、日本のミステリー作家としては横溝正史を高く評価。横溝の怪奇趣味を批判しているところは私としては賛同しかねますが、しかしそこは、怪奇趣味・草双紙趣味を邪魔なものとみてなお高評価される横溝のすごさということなんでしょう。
怪奇趣味を批判する安吾は、ミステリー作品にしばしばみられるペダントリーにも批判的です。
ゆえに、エラリー・クイーンやヴァン・ダインを一定程度評価しつつも、その部分がマイナス点となり、あまりそういうところがないクリスティがよりすぐれているという評価にもつながっているようです。
まあ、そこはよくわかります。私見ですが、クイーンやヴァン・ダインにみられるペダントリーは、文学コンプレックスの裏返しなんじゃないでしょうか。文学界においては、ミステリーということでどこか一段低くみられるようなところがあるのは否定できず……その劣等感から、やたらと古典文学や美術への造詣といったことを前面に押し出そうとするのではないかと。
そこへいくと、安吾の場合はそういう劣等感とは無縁です。
もともと純文学方面の作家であり、そんな背伸びをする必要がなく、またそういうつまらぬ見栄を張ろうとするような人物でもありません。
なので、余計なウンチクを弄したりすることなく純粋に推理ゲームとしてのミステリーを書くことができるというわけでしょう。
そうして書かれた長編が、『不連続殺人事件』ということになります。

多くのミステリー作家と同様、安吾も自作に登場させる名探偵を創作しました。ドイルにとってのホームズ、クリスティにとってのポワロ……安吾探偵小説においては、巨勢博士という人物がそれにあたります。
先述したように、そこで描かれるのは純粋に推理ゲーム。怪奇趣味も、ペダントリーもまったくありません。推理小説の古式ゆかしい趣向として“読者への挑戦”というのがありますが、この作品では、雑誌連載しながらその読者から犯人あてを募るというような企画もやっていました。結果、ほぼ完全に正解の回答が4件よせられたということです。
で、そのミステリーとしてのできはどうなのか。
人様の作品についてあれだけいったからには自分は相当なものを書いたんだろうな……とちょっと意地悪な目線で読んでしまうんですが、これがなかなか堂に入ったものだと感じました。
江戸川乱歩や松本清張も高く評価したということです。
登場人物が多く関係も複雑なんですが、その人物たちの思考や行動をからませつつ明晰なロジックで謎を解明していく手つきには、素直に感心させられました。犯人あて募集に正解が複数寄せられたのも、論理をつきつめていけばきちんと犯人がわかるようになっているというフェアネスへのこだわりゆえでしょう。ほかならぬ安吾自身がそう評しているのは、決してただの負け惜しみではありません。
そこには、安吾独特の感覚が作用しているように思われます。
ここでちょっと大所高所からの話をすると、文学というのはそのときどきの時代にあった思想を背景としている部分があります。
なにも文学にかぎった話ではないでしょうが……たとえば、リアリズム/自然主義という思潮は、“大衆”の発達と民主主義の普及に沿うかたちで発生したものであり、象徴主義はその反動としての帝政や復古王政に対応しているといった具合に。
その観点でみると、ミステリーは実証主義を思想的土台としている、というのが私の文学史観です。19世紀は、実証主義の時代。ミステリーという形式が19世紀半ばごろから勃興してくるのは、まさに実証主義の隆盛と軌を一にしているのです。かの夢野久作『ドグラ・マグラ』において「近代文学の神経中枢とも見るべき探偵小説を読まない奴はモダンたあ云えないぜ」と書かれているのは、まさにこの意味においてでしょう。
で、その実証主義というあまり文学とは親和性の高くない思想を文学に持ち込むことができる作家となったら……これはもう坂口安吾が第一ということになります。
いや……実証主義を文学に持ち込むというのは正確ではありません。
むしろ、両者をはっきりと分離させた。クイーンやヴァン・ダインの陥った罠にはまることなく……逆説ですが、探偵小説専門の作家でないからこそ、余計な要素を排除した純・探偵小説が書けた。
すなわち、旧来の価値観から自由で、機能美を重視する、そんな安吾だからこそ、“ブンガク”ということにとられることなく思いっきり実証主義の方向に振り切って書くことができたのではないか。そんなふうに思われるのです。
“ブンガク”性とミステリーとを完全に切り離していることは、この『不連続殺人事件』のなかにおいて、主人公・矢代の口から語られます。
作家である矢代は、探偵役の巨勢博士を評してこう言います。
我々文学者にとって人間は不可決なもの、人間の心理の迷路は永遠に無限の錯雑に終るべきもので、だから文学も在りうるのだが、奴にとっての人間の心は常にハッキリ割り切られる。
巨勢はもともと文士志望で矢代に弟子入りしてきた人物ですが、いっこうに文才がなく「小説がヘタクソだから、犯罪がわかるんでさア」と嘯きます。
矢代にいわせれば、「彼の人間観察は犯罪心理という低い線で停止して、その線から先の無限の迷路へさまようことがないように組み立てられているらしい」。ゆえに巨勢博士は、「探偵の天才だが、全然文学のオンチ」ということになるのです。
かように、ブンガクとミステリーとは、本質的に相いれない。
それは、はっきりと成文化できるものだけを対象とする実証主義と、成文化できない領域を扱う文学との間には超えられない壁があるためです。
その点を踏まえて純粋にミステリーという方向性を追究しているのが、この『不連続殺人事件』の強みでしょう。
それゆえに、本作はミステリー史上に残る一作なのです。