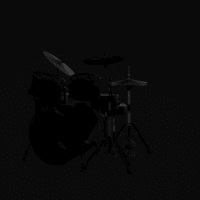今日7月14日は、フランス革命の起こった日です。
フランス革命がどの時点ではじまったかというのは、細かく見ていけば難しいところがあるかもしれませんが、1789年の7月14日、バスティーユ牢獄襲撃をもって革命の火ぶたが切って落とされたというのが一般的な見方でしょう。最近の日付シリーズの流れで、今回はこのフランス革命というものについて思うところを書いてみます。
フランス革命の後には、恐怖政治が行われます。
まあ、たいてい革命の後はそうなるものでしょう。
フランス革命の場合は、ギロチンによる大量処刑や、虐殺事件が起こります。
その点で、革命に批判的な意見も出てくるわけです。
革命といったって、大虐殺を起したじゃないか。それに、延々仲間割れを繰り返してたじゃないか……といった具合です。
私もかつてはそう思っていましたが……ただ、最近はちょっと考えも変わってきました。
たしかに革命後の蛮行はすさまじく、かなり行き過ぎの面があることは否めません。
しかし、強大な権力というのは、そういう行きすぎなぐらいの力でなければ倒せないんじゃないかとも思えるのです。
太宰治に「おさん」という短編があって、そのなかで、7月14日に隣家のラジオから流れてきたフランス国歌を聴いた男が感極まりながらフランス革命について語るシーンがあります。
「バスチーユのね、牢獄を攻撃してね、民衆がね、あちらからもこちらからも立ち上がって、それ以来、フランスの、春こうろうの花の宴が永遠に、永遠にだよ、永遠に失われる事になったのだけどね、でも、破壊しなければいけなかったんだ、永遠に新秩序の、新道徳の再建が出来ない事がわかっていながらも、それでも、破壊しなければいけなかったんだ、革命いまだならず、と孫文が言って死んだそうだけれども、革命の完成というものは、永遠に出来ない事かもしれない、しかし、それでも革命を起さなければいけないんだ、革命の本質というものはそんな具合いに、かなしくて、美しいものなんだ、そんな事したって何になると言ったって、そのかなしさと、美しさと、それから、愛……」
彼が聴いたフランス国歌とは、いうまでもなく、「ラ・マルセイエーズ」。ビートルズのAll You Need Is Loveのイントロに引用されているあの曲です。
この短編を最初に読んだころの私は、ジョン・レノン、そしてボノの歌に、むしろ共感していました。
両者とも、どちらかといえば、穏健的な社会改革を志向していて、革命というような破壊活動には否定的だったと思います。
ただ、それは、革命の経験がある国家だからこそのことなんじゃないかとも思えるのです。
イギリスは、歴史上幾度かの革命を経験していて、アイルランドもイギリスのくびきから逃れるために闘争してきた歴史があります。独立にいたった“英愛戦争”は、革命と呼んでも差し支えないでしょう。
人類の歴史において、まだそういうことをやっても大丈夫な時期があったと思うんです。その時期に、“王殺し”というものを経験しているかどうか。そのことは、国家のあり方に大きくかかわってくるでしょう。
奔流のようなエネルギーで圧政者が倒された――そういう歴史があればこそ、民衆と為政者の間にある種の緊張関係が保たれるのではないか。そうであればこそ、穏健な社会改革という道を選びうるのではないか。
翻って本邦のことを考えると、その“王殺し”の経験がないことが日本の近代史をゆがめてるんじゃないか……そんな気がしています。
先に引用した太宰の「おさん」にしても、結局のところ彼の感慨は不倫という個人的な人間関係に結び付いたものでしかないように描かれています。そうなると、夫氏の道ならぬ恋が心中という結末にいたるように、革命の夢もまた挫折するよりほかないわけです。
もちろんこの現代にあってフランス革命のような革命を起こすことは考えられません。
では、現代日本では社会改革をどう成り立たせるのか……その道は、きわめて困難だということになってしまうでしょう。しかし、いかに困難でもそれをやらないと、この国はもうもたないところにきているんじゃないでしょうか。この10年ぐらいの日本をみていると、そう思えます。