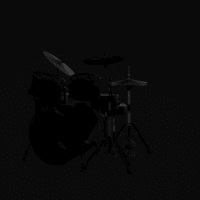遠藤周作の『深い河』という小説を読みました。
1993年発表ですから、最晩年の作です。
読む前は、大作家が晩年に手すさびで書いたような作品かと思っていたのですが……さにあらず。ひょっとすると、遠藤周作が集大成的な意気込みさえ持って書いた作品なのではないかと思えました。
日本人とキリスト教との関係という、遠藤周作がずっと抱えていた問題意識が扱われており、また、少年時代に満州に暮らしていたという人物が登場しますが、ここには著者自身の経歴が投影されているようです。
自身がカトリック教徒である遠藤周作は、信仰を題材にした作品をいくつか書いていますが、この作品では、キリスト教という枠を超えた領域に踏み込んでいます。
この本を読むにあたって私は、以前手塚治虫展で買った『ジャングル大帝』のしおりを使っていたのですが、それがしっくりくるように感じられました。
日本、東洋の価値観と、西洋のキリスト教との葛藤にさいなまれ、宗教の枠を超えた「何か大きな永遠のもの」をもとめる大津の姿は、手塚治虫が描いていたモチーフと重なるところがあるんじゃないか……そう思えたのです。
神は、人の罪さえも活用する、と大津はいいます。
「キニーネを飲むと健康時は高熱を発しますが、これはマラリヤの患者にはなくてはならぬ薬となります。罪とはそのキニーネのようなものだとぼくは思っています。」というのです。
いっぽう、話の後半でマラリヤに感染したと思われる患者が出てくる場面があるのですが、そこでは「今はキニーネは使いませんのよ」というせりふが出てきます。このあたりに、現代社会で精神性が軽視されていることへの批判が込められているのかとも読めました。
ちなみに、タイトルの『深い河』というのは、ゴスペルのタイトルです。
もともとのゴスペルではヨルダン川のことを歌っていますが、この作品では、「河」のイメージがインドのガンジス河に重ねあわされます。「生と死とがこの河では背中を合わせて共存している」という、そういう河です。『深い河』は、この大河ガンジスに託して、宗教の枠をこえた永遠なるものを探求するという意欲作なのです。