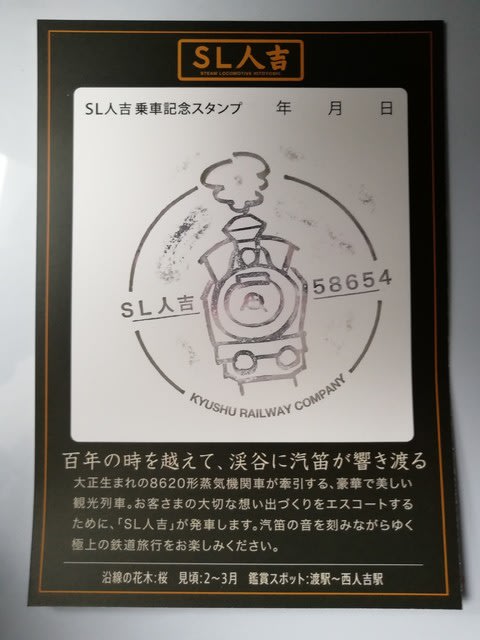以前アマゾンオーディブルに関する記事で、横山秀夫さんの『震度0』を“聴いた”ことを書きました。
ことのついでなので、今回はその『震度0』についてのレビューを書こうと思います。
※極力ネタバレは避けていますが、一部『震度0』終盤部分の展開について書いています。未読の方はご注意を。
この作品では、阪神大震災と時を同じくして起きた事件が描かれています。
警務課長が失踪したというものですが、それが県警本部長の不始末につながっていき、そこから県警内部で主導権争い、派閥争いのようなことが展開していくのです。
横山さんといえば、警察を取材する記者としての経験を生かして警察の内部を描くスタイルで知られていますが、この作品でもそれがフルに発揮されています。
舞台となるN県警の内部で繰り広げられる政治劇は、迫真のリアリティを持っています。
震災で千人という単位の死者が出るなかで、N県警では首脳部が主導権争いのようなことを延々やっています。そのギャップが、どこか恐ろしいような、悲しいような気分になってきます。
一つのキーとなるのが、人事を握る警務部の部長である冬木。
キャリアであり、将来は警視総監をも視野に入れる人物です。
この警務部というのもポイントですね。ふつうのミステリーではまず登場してこないし、出てきたとしても端役にしかならない部署だと思いますが、横山作品では重要な役割を果たしますね。松本清張賞を受賞した「陰の季節」からそうでした。警察という組織内部のことを描くとなると、ここが要になってきます。警務部長の冬木は、人事を掌握する立場から、県警首脳部における政争の軸となるのです。厚遇をちらつかせたり、あるいは、その逆で脅しをかけるようなことをして、人を操る……こうして、本部長や刑事部長と対立し、組織内部に敵味方ができていきます。
ネタバレを避けるために詳細を書くのは控えますが、県警首脳部は、最終的にある種の隠蔽を行なおうとします。これが表に出れば、N県警が大混乱に陥る。警察をやめた後の天下り先もなくなる、キャリの身からすると、そこから先の出世の道が断たれる。だからここは、全員で示し合わせてなかったことにしよう……という話になるのです。もちろん反対する人も出ますが、あんたにも家族がいるだろう、というような言い方で押し切られます。
なんだか汚い大人になっちまったな……というような話ですね。
捜査に出ていく刑事を見送る姿を見て「刑事の背中だった」という刑事部長の述懐が印象的です。自分もかつては、捜査一筋の刑事だった。天下り先の確保なんか考えたこともなかった。しかし、いったん刑事部長という立場になって、その後の天下りが約束されてみると、それを失いたくないという気持ちが出てくる。そうして、政争に明け暮れることになる……
この作品を読んでいて私は、最近相次いでニュースになった隠蔽、改ざんといった類の話を思い出しました。
隠蔽、改ざんを行なっていた各省庁では、たぶん、この小説に描かれているようなことが起きていたんだろうな……と想像します。
上のほうにいる人間ほど、保身を考えるようになる。
そして、これを表に出して自分の立場を失うぐらいなら、死に物狂いで隠蔽しようということになるんでしょう。そのエゴの前では、下っ端の正義感はたやすく握りつぶされます。
しかしこの小説は、それで終わってしまいません。
先述した反対者は、いったんは押し切られますが、そのまま黙ってしまいませんでした。
首脳部が隠し通そうと決めたことを、あきらかにしようとします。彼は本部長室に内線電話をかけますが、話し中です。
「再度、部長会議を」
もし他の誰かがそう進言しているのだとしたら、N県警はこの激震からも立ち直れるに違いない。
そのかすかな希望を示して、物語は終わります。
“自浄能力”とよく言いますが、それは、一個人としての良識だと思うんですね。
それでいいのか、それじゃダメだろ……という。組織を立て直せるのは、組織の論理から独立した個人としての良識しかないでしょう。隠蔽だの改ざんだので揺れている省庁に必要なのは、まさにこの良識だと思います。
※引用部分は、オーディブルの聴き取りによるものです。紙の本での表記は違っているかもしれないのであしからず。










![コンテイジョン [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/510ph%2BH6zJL._SL160_.jpg)