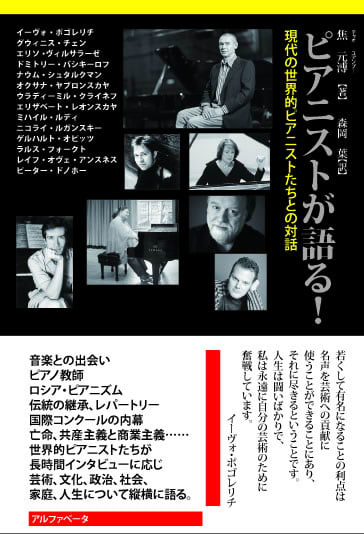10月も下旬となり、今月初めから(正確にいうと4月の予備選から)、ずーっと続いていた第17回ショパンコンクールも、昨日つまり10月21日日本時間で朝8時に結果が発表となりました。
以下公式HPより転載。
1st prize (30 000 €) and gold medal - Seong-Jin Cho
2nd prize (25 000 €) and silver medal - Charles Richard-Hamelin
3rd prize (20 000 €) and bronze medal - Kate Liu
4th prize (15 000 €) - Eric Lu
5th prize (10 000 €) - Yike (Tony) Yang
6th prize (7 000 €) - Dmitry Shishkin
HONORABLE MENTIONS (4000 €) Aljoša Jurinić, Aimi Kobayashi, Szymon Nehring, Georgijs Osokins.
SPECIAL PRIZES
Fryderyk Chopin Society Prize for best performance of a polonaise (3 000 €) - Seong-Jin Cho
Polish Radio Prize for best performance of mazurkas (5 000 €) - Kate Liu
Krystian Zimerman Prize for best performance of a sonata (10 000 €) - Charles Richard-Hamelin
この10月はショパンばかり聴きに聴きたりです。
すべてを聴いたわけでもないですし、じーっと真剣に聴いていたわけでもないですけど、
とにかく、技術的にも、表現的にもなんと難しい作曲家だろうか・・・とあらためて思いました。
正直、聴くのもかなり難しい・・・・・手も耳もでません(笑)。
入賞者は1位と3位が21歳、2位が26歳、4位は17歳、5位は16歳、6位が23歳 ということで、
まさに自分の子供世代の年齢です。
もって生まれたものが大きいとはいえ、この年齢にして、これだけのものを感じ考え表現しているというのは、生きるスピードの違いをも感じます。すごいことです。
一方で彼らがそれなりの天寿を全うするとしたら、これから先の人生、これまでの何倍もあります。
「ある年齢までしか現役でいられない」という世界ではないので、
80~90までずっと演奏し続け、すばらしい音楽家になっていただきたいと心から思います。
それは今回入賞された方々だけでなく、またこのショパンコンクール出場者だけなく、音楽を志すすべての若い方がたに対して思うことです。
そして、こちらもなるべく長い間、彼らの演奏を聴き続けられるように、元気でいなくてはなりません(笑)。
研鑽に研鑽を重ね続けるアーティストの方々をきちんと支え、育む土壌を、年長者として聴衆として作るように努力せねば・・。