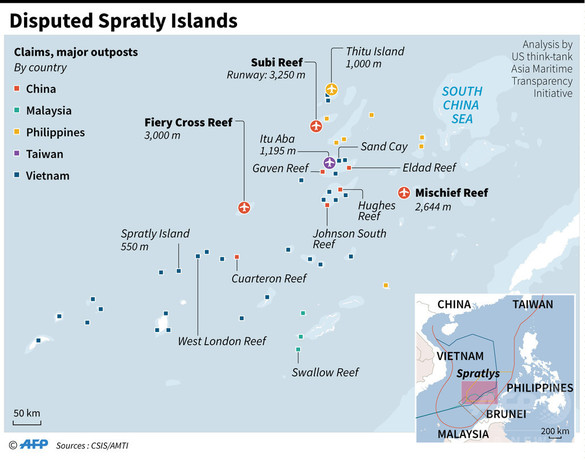須田桃子さんという毎日新聞科学環境部記者が、人工生物の研究最前線を表す本を出版している。その要旨が以下である。。
人類に多大な恩恵をもたらす現代の錬金術か、それとも生命の定義を根源から揺るがすパンドラの箱か――。「生命の設計図」であるゲノムをコンピューター上で設計し、その情報に基づいてDNAを合成したり、改変したりして新たな生物をつくる「合成生物学」の研究が進んでいる。米国のJ・クレイグ・ベンター研究所のウェブサイトに掲載された動画の細長いチューブの中で増殖していく微生物の細胞。そこで細胞分裂を繰り返していたのは、人工的につくられた「新しい生命体」。
「ミニマル・セル」と呼ばれるその細胞は自然界に存在したことがなかった生命体。にもかかわらず、私たちと同じように細胞分裂し、増殖することができる。
この新しい研究領域は「合成生物学」と呼ばれ、その進展は、生命の定義を根源から揺さぶります。
背景には、2003年に完了した「ヒトゲノム解読計画」に伴う、ゲノムの解析技術の進化があります。ゲノムが解読され、コンピューター上のデジタル情報として扱うことが可能になったのです。
例えば、酵母や大腸菌に医薬品や化粧品の原料を作らせたり、藻類の脂質を何倍にも増やしてバイオ燃料を生み出したり。遺伝子組み換え技術やゲノム編集技術など、遺伝子を改変する技術を用いて一部がすでに実用化されています。
米国の生物学者、クレイグ・ベンター氏らのチームが、ミニマル・セル」という新しい生命体を作りだした。
ベンター氏はヒトゲノム解読に最も貢献した科学者の一人が、細菌のゲノムを解析したうえで、生命に必須な最小限の遺伝子だけを選択し、ゼロから人工的に合成したDNAを持つ生物、そのような合成ゲノムを持つ人工的な生命体の作製に、世界で初めて成功したのが「ミニマル・セル」でした。
民間企業セレラ・ジェノミクスをつくってヒトゲノム解読に取り組み、いまは自身が設立した研究所で人工生命を研究するクレイグ・ベンター氏(写真:Shutterstock)
ベンター氏らは、ある細菌のゲノムから生命活動に必要最低限の遺伝子を選択し、さまざまなパターンのDNAを合成。それらを近縁種の細胞に移植して、きちんと分裂が始まるかどうか実験を繰り返しました。
合成したゲノムに少しでも問題(エラー)があると、細胞は分裂できずに死んでしまいます。ベンター氏らは試行錯誤の末、細胞が安定して分裂するために必要な遺伝子群の特定に成功。「生命として機能するために最低限必要なゲノム」を持つ人工細菌「ミニマル・セル」が誕生したのです。2016年のことです。
「ミニマル・セル」は、細胞分裂によって自らの遺伝情報をコピーすることができます。つまり、生命の必要条件の一つを満たした「人工生命体」であると言えるのです。

(図版:ラチカ)
ミニマル・セル・プロジェクトの始まりは1995年。「ヒトゲノム解読計画」の完了より8年も前のことでした。
「ヒトゲノム解読計画」は、ヒトの遺伝情報を「読む」ための試みでした。しかし、ベンター氏は当初から「読んだ後のこと」、つまりヒトゲノムを「書く(合成する)」ことによって人工的な生命体をつくる未来を予見していたのです。
合成生物学は人類にとって有用な生物をつくり出したりする一方、軍事目的などに悪用される恐れもある。
米国滞在中、須田氏は、ベンター氏をはじめ、合成生物学のトップ研究者たちを精力的に取材。旧ソビエト連邦から米国に亡命した微生物学者で、現在はジョージ・メイソン大学教授のセルゲイ・ポポフ氏からは、旧ソ連で医薬品開発の名のもと、合成生物学的なアプローチで生物兵器の開発が行われていたという証言を得た。
冷戦下の旧ソ連では、大規模な生物兵器開発・製造が行われていたことが明らかになっています。ポポフ氏のいた研究所では、さまざまなDNAの断片を作製し、多様な組み合わせで結合させて細菌などの遺伝子に組み込み、自然界に存在しない新しい病原体をつくり出していたと言います。まさに合成生物学的な手法が生物兵器開発に使われていたのです。
すべての科学技術は、人類の発展に貢献するだけでなく、軍事用として活用されうる「デュアルユース性」(軍民両用)を持っています。合成生物学も例外ではありません。
米国の軍部が、合成生物学に強い関心を寄せていると知ったのは、マサチューセッツ工科大学助教のケビン・エスベルト氏とのメールのやりとりがきっかけでした。
彼は2015年に米シンクタンクのウィルソン・センターが発表した「合成生物学の研究資金における米国の傾向」というリポートをもとに「現在、米国の合成生物学研究の大半は軍部から研究資金の提供を受けている」と教えてくれました。
資金を出していたのは、米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)です。DARPAは革新的な新しい技術を生み出す研究機関で、全地球測位システム(GPS)やインターネットの原型となる技術を開発したことでも有名です。

(写真:Shutterstock)
背景には、さまざまな兵器を開発してきた軍事開発拠点としての歴史があります。ベトナム戦争時の枯れ葉剤、また湾岸戦争におけるステルス戦闘機や巡航ミサイルの精密誘導技術の基礎は、すべてDARPA によって開発されたものです。
前出のウィルソン・センターのリポートによると、そのDARPAが、2011年以降、合成生物学研究への出資を劇的に増やしているのです。
「遺伝子ドライブ」で種そのものを駆逐
2014年会計年度には、年間予算の1割に相当する1億1000万ドル(約120億円)を合成生物学研究に対し拠出したDARPA。合成生物学の黎明期の2008年ごろから、既にこの分野で最も優秀な科学者たちへ継続的に研究資金を投じてもいた。
須田氏は2017年1月、DARPAを取材。取材に応じたジャスティン・サンチェス生物技術研究室長は、DARPAの出資目的が「国家安全保障」に根ざしていることを強調し、こう語ったという。
「エボラ出血熱やジカ熱といった自然発生する感染症であっても、その脅威を取り除く技術を持たなければ、安全保障上の課題になる」
DARPAが特に関心を示しているのが「遺伝子ドライブ」です。ある遺伝子が50%を上回る確率で子孫に伝わり、集団の中で連鎖的に広がっていくという、自然界でたまに見られる現象で、遺伝子を効率よく改変できるゲノム編集の技術をうまく使うと、それを人為的に起こすことができると提唱されています。
人為的な遺伝子ドライブは、理論的には、有性生殖で繁殖し、世代交代が速ければ、どんな生物にも適用できます。
例えば、子がすべてオスになるように、ある害虫のオスかメスどちらか一方の遺伝子を改変します。その害虫が交配すると、子はすべてオスになります。この害虫がメスと交配すると、その子はまたオスになる。こうして何世代かを経るうちにメスがいなくなり、結果的にその害虫の集団は消滅します。感染症を媒介する蚊などに有効で、マラリアやエボラ出血熱、デング熱などの撲滅を期待できます。
一方で、生態系への予期せぬ影響や軍事目的での転用も懸念されます。
従来、感染症を媒介する蚊を駆除する場合、放射線の照射で不妊化を施すなど一世代でのみ有効で、種の集団全体に広めることはできなかった。
一方、遺伝子ドライブでは、親から子、子から孫へと目的の遺伝子が100%引き継がれるため、種全体への永続的な効果がある。

(図版:ラチカ)
人為的な遺伝子ドライブの最大の特徴は、特定の遺伝的性質を永続的に次世代へと受け継がせることができる点にあります。それが不妊化の遺伝子であれば、たった一度、遺伝子を改変した個体を数匹放つだけで、理論的には特定の種を絶滅させることもできる。生態系に重大な影響を及ぼす、後戻りできない技術なのです。
例えば、ですが、もしも蚊に遺伝子ドライブで人体に有害な毒素を生み出す能力を導入すれば、強力な生物兵器になります。あるいは、農作物の受粉を担う昆虫を不妊化させる遺伝子ドライブを設計したら、一国の農業を壊滅させられるかもしれません。
DARPAは自らの合成生物学研究が軍事目的であるとは認めていませんし、米国は生物兵器禁止条約の締約国ですから、合成生物学研究がすぐに世界の脅威になることはないでしょう。しかし、私たち人類の未来を左右するような研究の数々が、DARPAの予算をもとに行われているという事実には注意を払うべきだと思います。優秀な研究者たちが、DARPAの上位組織である軍の意向を忖度したり、間接的に研究成果の軍事利用に加担したりしてしまう可能性はゼロではありません。
米国への長期留学で家族と長期間会えないことに不安もあったが、小学生の長女が背中を押してくれて踏ん切りがついたという
生命という概念が変わる
合成生物学で注目される国際プロジェクトの一つに、「ゲノム合成計画」があります。
当初は「ヒトゲノム合成計画」という名称でしたが、このプロジェクトの目的は、決して人造人間を創ることではありません。
あくまでも、人工的に合成したDNAを持つヒトの細胞をつくることを最終目標にしています。2016年に米科学誌「サイエンス」に発表されたプロジェクトの概要によれば、それらの細胞は移植用の臓器の作製や、高い効率性のワクチン・医薬品の開発に応用できる、と主張しています。
一方で、この計画はヒトの創出につながる危険性があると心配する声もあります。計画の発表直後に開かれたある科学イベントでは、若い参加者からこんな質問も出たそうです。「死んでも誰も悲しまない“完全に消費可能な”人間を軍部がつくることを、どうやって止められるだろうか」
コンピューター上で設計した生命をつくる。それはバイオ燃料の開発など素晴らしい恩恵をもたらすかもしれない半面、これまで述べてきたようにさまざまな問題をはらんでいます。
生物を改変することが当たり前になったとき、生命という概念そのものにも変化が訪れるでしょう。ゆくゆくは、ヒトそのものを改変することに、誰も違和感を覚えない時代が来るかもしれません。私たち人類は今、まさにそんな未来の入り口に立っている。1年間の米国取材を通じて、私はそう強く感じました。
思うままに生命を「改変」し、種の進化に「介入」することが、この先、私たちにどのような影響を与えるのか。日本に帰ったいまも考え続けています。
須田桃子(すだ・ももこ)
毎日新聞科学環境部記者。1975年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。2001年、毎日新聞社入社。2006年から科学環境部に所属し、生命科学、再生医療、生殖補助医療、ノーベル賞などを担当。2015年に『捏造の科学者 STAP細胞事件』で大宅壮一ノンフィクション賞、科学ジャーナリスト大賞を受賞。2016年9月からノースカロライナ州立大学遺伝子工学・社会センターに客員研究員として滞在。そのときの調査・研究をもとに、2018年4月『合成生物学の衝撃』を著した。