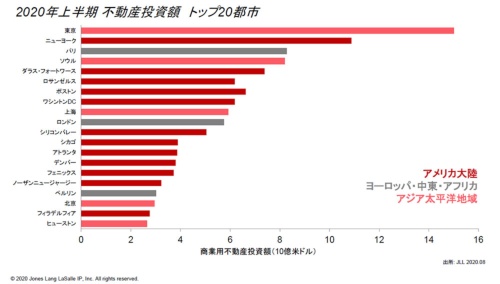中国の輸出管理法が10月17日、全国人民代表大会(全人代)常務委員会で成立し、12月1日に施行される。中国に対して輸出管理の武器を振りかざす米国への対抗措置と明確に規定している。が、日本への影響もありそう。
JETROによる解説::::::::
中国の輸出管理法が10月17日、全国人民代表大会常務委員会において成立した。12月1日から施行される。同法では、管理品目と輸入業者・エンドユーザーについての規制リストを作成し、管理品目やリストに掲載された輸入業者・エンドユーザーに対して輸出を禁止・制限するというかたちで、管理を強化する。
管理品目の具体的なリストは同法成立時点では公表されていないが、同法の総則において輸出管理を適用するものとして「デュアルユース品目、軍用品、核に加え、国家安全と利益の擁護、拡散防止など国際義務の履行にかかわる、貨物、技術、サービスなどの品目」と規定された(注1)。
輸入業者・エンドユーザーの規制リストについても、同法成立時点では公表されていないが、以下の状況が1つでもある輸入業者・エンドユーザーが該当するとされた。
- エンドユーザーあるいは最終用途の管理要求事項に違反したもの
- 国家安全と利益に危害を及ぼす可能性のあるもの
- 管理品目をテロリズムの目的で用いるもの
規制リストに加えられた輸入業者・エンドユーザーに対し、国家輸出管制管理部門は関連する管理品目の取引を禁止・制限するなどの措置をとることができるほか、輸出者は規定に違反して規制リストに加えられた輸入業者・エンドユーザーと取引を行ってはならないとされた(注2)。
同法の企業への影響について、DaWo法律事務所のラッシュフォース弁護士は「米中両国の企業は特に戦略的に敏感な産業分野において、より多くの審査を受けることを想定し、準備をしていく必要がある」と指摘する(「南華早報」10月17日)。
輸出管理法は、商務部が2017年6月に草案を公表して以降、3回にわたりパブリックコメントが実施されてきた。日米欧の主要産業団体は各草案に対して、「再輸出」「みなし輸出」「法の域外適用による責任追及」などの規定があいまいな点などを指摘し、改善要望を行ってきた。
一般財団法人安全保障貿易センターによる同法の解説資料では、「再輸出」規制について「米国式の再輸出規制が下位規則において導入される可能性が高い」と指摘している(注3)。
なお、今回成立した輸出管理法の条文は、49条で構成された原則的な内容にとどまっていることから、環球法律事務所の任清パートナー弁護士は「同法は、関連の法律法規が制定されてから有効に機能する」と指摘する(「環球時報」10月18日)。「再輸出」などが関連法規により、どのように規定されるのか、注視する必要がある。
(注1)管理品目について、草案段階ではデータに関する記述はなかったが、成立した条文においては、「管理品目には、品目に関連する資料などのデータを含む」と規定された(同法2条)。
(注2)「輸出者が特殊な状況下において、規制リストに加えられた輸入業者、エンドユーザーと取引を行う必要がある場合、国家輸出管制管理部門に申請をすることができる」「国家輸出管制管理部門は、実際の状況に基づいて、規制リストに加えられた輸入業者、エンドユーザーを規制リストから削除することができる」などの措置も設けられている(同法18条)。
(注3)同センターのウェブサイトに、輸出管理法に関する解説資料などが掲載されている。
(北京事務所)
(中国、米国)
また、日経ビジネスによると:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
表面的には米国の制度を一見まねているかのようで、今回の対抗措置への批判に対しては「米国も同様で、中国だけではない」と反論するつもりだろう。しかし、後述するように警戒すべき規定が随所に入っている。「運用次第では日本企業にも影響の可能性がある」とメディアは報じるが、事態はもっと深刻だ。運用に透明性がなく、恣意的に行われるのは中国では日常茶飯事だからだ。
中国の「情報戦」には要注意
また、「国家安全保障を理由に中国を規制した国に対する対抗措置で、『目には目を』という趣旨だ」との説明が一部で見られる。そして「日本が中国をそのように刺激しなければ、今までと何も変わらず無関係だ」との解説が流されている。
こうした見方には要注意だ。
中国が最も避けたいのは、日本が米国に同調して中国に対抗する事態だ。米国は対中政策で同盟国に協力を求めようとしている。日本でも、「米国は輸出管理で有志国での連携を提案する」との報道もある。中国が期待しているのは、そうした事態を避けるために、「中国を刺激して怒らせると中国の輸出管理法の餌食になる」と日本の産業界に思わせることだ。
日本の産業界はこうした“揺さぶり”にことのほか、弱い。日本政府に対して「中国を刺激しないように」と、よく言えば「懇願」、悪く言えば「圧力」をかけてくるだろう、と中国は読んでいる。
これこそ、中国が得意とする「情報戦」だ。
今後、“中国専門家”からこうした発言があれば、中国政府によるプロパガンダの影響をまず疑うべきだろう。また日本政府も産業界も中国に“揺さぶられない”よう、腰を据えた対中政策を展開すべきだ。
それでは何が懸念されるか具体的に見てみよう。ただし、規制対象のリストや規制の細則はこれからで不透明なところはある。
羊頭狗肉の輸出管理で、レアアースの輸出制限も
まず法律の目的が異様だ。「国家の安全や利益」となっており、安全保障を超えて非常に広範で要注意だ。もちろん米国も「安全保障」概念を広げてきており問題だが、その比ではない。
前半の「国家の安全」とは、習近平(シー・ジンピン)国家主席が打ち出した「総体国家安全観(総合的な国家安全のあり方)」という概念に基づくものだ。これは軍事だけでなく、政治、文化、社会の安全、さらには資源の安全なども含まれている。
例えば、中国の政治的主張に反するものも「国家の安全」を侵害するものとなる可能性があり、政治的に使える。さらにそこに「国家の利益」まで加えられて、およそ国家のためなら何でもありだ。
各国は国際レジームに参加して輸出管理を行っているが、その際の目的である「安全保障」とは、今回の中国の対抗措置はまるで異質だ。要するにこうした安全保障に関わる輸出管理の国際ルールから、目的からして大きく逸脱しているのだ。日本のメディアが「安全保障の輸出管理」との見出しをつけているが、これは羊頭狗肉(ようとうくにく)だ。
世界貿易機関(WTO)のルール上、国際レジーム参加国が行う安全保障上の輸出管理は21条の安全保障例外によって認められるとされている。ところが中国は国際レジームに参加せず(核兵器関連だけは参加)、国際レジームの目的を逸脱した輸出規制を行おうとしている。規制品目次第では明らかにWTO違反になる。
例えば、「資源の安全」に引っ掛けて、レアアースの輸出制限をする可能性もある。中国は米国による半導体の輸出制限に対抗する切り札はレアアースだと考えている。かつて日本に対するレアアースの輸出制限がWTO違反となったことなど意に介していない。
まず今の段階で、日米欧で連携して「WTO違反の恐れがある」と明確にけん制しておくべきだろう。そして今後、具体的に運用され実害が出てくれば、ちゅうちょせず毅然とした態度でWTOに提訴すべきだ。WTOが機能不全に陥っていて意味がないとの指摘もあろう。しかし長い目で見て、ルール重視の旗は降ろしてはいけない。
公然と域外適用を掲げる
「域外適用」を明確に打ち出したことも深刻に捉えるべきだ。
国内法を海外にまで適用する域外適用は国際法違反である。しかし米国は長年、域外適用を武器に他国を従わせてきた。ルール違反でも市場、通貨、軍事力を背景に実行する能力のある超大国による「力の論理」がまかり通っていた。
このように米国の専売特許であった「域外適用」を、米国に対峙する自信をつけた中国が打ち出し始めたのだ。今年6月施行の香港国家安全維持法も、海外における外国人の発言も国家転覆罪に問われる恐れがある。そしてこれを言論統制だけではなく、経済活動にまで広げたのが今回の輸出管理法だ。
こうして米中二大国が力を背景に容赦なく他国を自国の判断に従わせようとする。米中以外の第三国は、相反する二大国の域外適用で“股裂き状態”になる。これぞ「パワーゲームの世界」だ。これまでの「ルールによる国際秩序」が音を立てて崩れる、深刻な危機だ。
日本をはじめ、そうした力のない国々にとって身を守るすべはルールしかない。
日欧などのミドルパワーの国々による連携で、何とか国際的なルールにてこ入れをしなければならない。有志国による国際ルール作りが急がれるゆえんだ。これについての詳細は別稿で述べることにする。