5月2日国立新美術館で第86回国展をみた。いつも大量の作品が展示されているので、回る順番に悩む。今年はセザンヌ展、エルミタージュ展も同時にやっていたのでスペース縮小かと思ったらとんでもない。セザンヌやエルミタージュは1階、2階のごく一部で、ほぼ全館国展だった。

いつもとあまり変わらないが、1階の彫刻、絵画、3階の版画、工芸、2階の絵画、写真の順に回った。スペースでいうと全体の6-7割が絵画だ。
1階の入り口には、梅原龍三郎(洋画)、平塚運一(版画)、千野茂(彫刻)、濱田庄司(陶芸)、吉川富三(写真)の5人の10個の目の写真が展示されていてちょっとびっくりする。国展のパンフにも「先達の紹介」が特筆されているが、それを拡大して展示したような光景だった。いずれも国画会の各部門の先駆者である。
いつも物量に圧倒されるが、今年は少し楽に回れた。それは人物や人間をテーマにした作品が多かったからだ。人間をテーマにしたものが多いのは、昨年の3.11事故発生の衝撃があると思った。
たとえば、絵ハガキを横30枚、タテに25枚並べ(4m×4mくらいの大きさ)、そこには顔や風景が描かれ「原発」「福島」「除染」といった文字が読み取れる。また「楽園への歩み」というタイトルで、小学校低学年のランドセルを背負った男の子の後ろ姿と手前に爆発したような工場の作品があった。まさに福島原発1号機の爆発跡にみえた。また遺体が4-5体横たわっているような作品もあった。
彫刻はそういう目で見なかったが、たとえば関谷光生「受容する心」は悲しみを耐え忍ぶ老人のようにみえた。
モデルと画家をテーマにした作品は、ピカソに限らず昔から多くある。しかしここでみたのはキャンバスの中のモデルの顔を塗りつぶしふてくされている画家、そして不安そうな顔で画家を見つめるモデルである。たしかにこんなことは現実に起こりそうだが、まさにひとつのドラマである。
昨年に比べるとアニメ風の絵は少なかったが、しかし猫耳少女の絵があった。
昨年も「未来のスターだ!若手作家の挑戦状」という若手育成の企画展をやっていたが、絵画部は、今年も「新しい眼 若手作家の挑戦状」を開催していた。昨年は30歳以下の作家29人だったが、今年は40歳以下37人だった。少し門を広げたわけである。

ところで工芸だが、やはり織を中心にみたのは変わらない。たまたま会場に入ったのが13時前で、20人くらいの女性グループが作品の講評のようなことをしていた。なんだろうと思ったら、毎年初日のこの時間に、織、染、木彫、陶磁器などのグループに分かれ講評を行っているそうだ。すると作家の方が多いのだが、偶然出会ったのは染のグループでほぼ全員女性だった(注 陶磁器は男性もたくさんいた)。先生が批評し、作者が制作の動機や苦心した点を語る形式だったが、かなり厳しい注文も飛び出す。「花はていねいに描きこんであるが、鳥の形がもうひとつだ」「広がりすぎて印象が散漫になる」「地色が重い」などである。
・・・たんなる抽象的な印象批評でないからよいのかもしれない。あるいは厳しいことを言ってくれる人はそうはいないので、これこそ勉強になるのかもしれない。
しかし「来年(次作)に期待している」などと評されると、どんな気持ちがするのだろう。
「グレーの色を出すのは難しい」「色を重ね合わせるときは、色が濁るので、単色のときに比べるとパーセントを落としたほうがよい」など、なるほどと思うことが多い。もっともこちらが実制作するわけではないので、役に立たないのだが。
その他「アイロンをかけてピシッと伸ばす」「柄合わせが難しい」「色がしっかり入っていない」、これは糸の芯まで染料が通り、生地の裏まで色が通るという意味だそうだ。説明しながら生地を裏返していたのでよくわかった。そうでないとやがて色がハゲてくるそうだ。技術的な話だが、たしかになあと思った。

宮平初子さんの作品(左)
織のほうは時間不足とエネルギー切れで鑑賞がちょっと手薄になってしまった。毎年楽しみに見させていただく人間国宝・宮平初子さんは、ことしはベージュの着物でなく藍地手縞「鳥とメービチ」という作品だった。上品な作品だった。
その他、杉浦晶子「春の海」、川村成「春の庭」、山下健「想春」などが印象に残った。陶芸では大皿、たとえば黄瀬戸大皿(松崎健)に目がいった。
なお、この日見たなかで最も衝撃的だったのは「月に鬼が笑う」という写真の作品だった。青空なので昼間なのだが、鬼瓦の上に白い月が出ている写真だった(写真部はなぜか作品の撮影禁止になっている)。
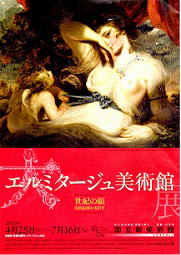
☆せっかくなので帰りに「エルミタージュ展」をみた。エルミタージュはサンクトぺテルブルクにある美術館で、もとはロマノフ朝の王宮だった。「ペョートル大帝の間」「黄金の客間」などの部屋があり、金とシャンデリアでいっぱいの貴族趣味の建物である。ソ連時代によく生き残ったと思う。

いつもとあまり変わらないが、1階の彫刻、絵画、3階の版画、工芸、2階の絵画、写真の順に回った。スペースでいうと全体の6-7割が絵画だ。
1階の入り口には、梅原龍三郎(洋画)、平塚運一(版画)、千野茂(彫刻)、濱田庄司(陶芸)、吉川富三(写真)の5人の10個の目の写真が展示されていてちょっとびっくりする。国展のパンフにも「先達の紹介」が特筆されているが、それを拡大して展示したような光景だった。いずれも国画会の各部門の先駆者である。
いつも物量に圧倒されるが、今年は少し楽に回れた。それは人物や人間をテーマにした作品が多かったからだ。人間をテーマにしたものが多いのは、昨年の3.11事故発生の衝撃があると思った。
たとえば、絵ハガキを横30枚、タテに25枚並べ(4m×4mくらいの大きさ)、そこには顔や風景が描かれ「原発」「福島」「除染」といった文字が読み取れる。また「楽園への歩み」というタイトルで、小学校低学年のランドセルを背負った男の子の後ろ姿と手前に爆発したような工場の作品があった。まさに福島原発1号機の爆発跡にみえた。また遺体が4-5体横たわっているような作品もあった。
彫刻はそういう目で見なかったが、たとえば関谷光生「受容する心」は悲しみを耐え忍ぶ老人のようにみえた。
モデルと画家をテーマにした作品は、ピカソに限らず昔から多くある。しかしここでみたのはキャンバスの中のモデルの顔を塗りつぶしふてくされている画家、そして不安そうな顔で画家を見つめるモデルである。たしかにこんなことは現実に起こりそうだが、まさにひとつのドラマである。
昨年に比べるとアニメ風の絵は少なかったが、しかし猫耳少女の絵があった。
昨年も「未来のスターだ!若手作家の挑戦状」という若手育成の企画展をやっていたが、絵画部は、今年も「新しい眼 若手作家の挑戦状」を開催していた。昨年は30歳以下の作家29人だったが、今年は40歳以下37人だった。少し門を広げたわけである。

ところで工芸だが、やはり織を中心にみたのは変わらない。たまたま会場に入ったのが13時前で、20人くらいの女性グループが作品の講評のようなことをしていた。なんだろうと思ったら、毎年初日のこの時間に、織、染、木彫、陶磁器などのグループに分かれ講評を行っているそうだ。すると作家の方が多いのだが、偶然出会ったのは染のグループでほぼ全員女性だった(注 陶磁器は男性もたくさんいた)。先生が批評し、作者が制作の動機や苦心した点を語る形式だったが、かなり厳しい注文も飛び出す。「花はていねいに描きこんであるが、鳥の形がもうひとつだ」「広がりすぎて印象が散漫になる」「地色が重い」などである。
・・・たんなる抽象的な印象批評でないからよいのかもしれない。あるいは厳しいことを言ってくれる人はそうはいないので、これこそ勉強になるのかもしれない。
しかし「来年(次作)に期待している」などと評されると、どんな気持ちがするのだろう。
「グレーの色を出すのは難しい」「色を重ね合わせるときは、色が濁るので、単色のときに比べるとパーセントを落としたほうがよい」など、なるほどと思うことが多い。もっともこちらが実制作するわけではないので、役に立たないのだが。
その他「アイロンをかけてピシッと伸ばす」「柄合わせが難しい」「色がしっかり入っていない」、これは糸の芯まで染料が通り、生地の裏まで色が通るという意味だそうだ。説明しながら生地を裏返していたのでよくわかった。そうでないとやがて色がハゲてくるそうだ。技術的な話だが、たしかになあと思った。

宮平初子さんの作品(左)
織のほうは時間不足とエネルギー切れで鑑賞がちょっと手薄になってしまった。毎年楽しみに見させていただく人間国宝・宮平初子さんは、ことしはベージュの着物でなく藍地手縞「鳥とメービチ」という作品だった。上品な作品だった。
その他、杉浦晶子「春の海」、川村成「春の庭」、山下健「想春」などが印象に残った。陶芸では大皿、たとえば黄瀬戸大皿(松崎健)に目がいった。
なお、この日見たなかで最も衝撃的だったのは「月に鬼が笑う」という写真の作品だった。青空なので昼間なのだが、鬼瓦の上に白い月が出ている写真だった(写真部はなぜか作品の撮影禁止になっている)。
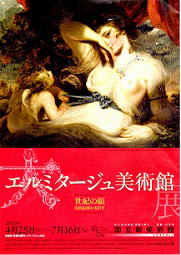
☆せっかくなので帰りに「エルミタージュ展」をみた。エルミタージュはサンクトぺテルブルクにある美術館で、もとはロマノフ朝の王宮だった。「ペョートル大帝の間」「黄金の客間」などの部屋があり、金とシャンデリアでいっぱいの貴族趣味の建物である。ソ連時代によく生き残ったと思う。
























